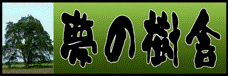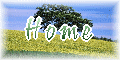
三 年
その夜、俺は三年ぶりに古ぼけたビルの懐かしい階段を地下へと急いでいた。
この街に住んでいた時は二晩と空けずに通い詰めていた店『Bar ROADSIDE』だ。
マスターはおそらくは五十代前半くらいだろうか。
無精髭がそうとは見えないくらい渋い、いわゆるチョイ悪オヤジという言葉がピッタリな感じで
黙っていればかなりなイケメンなのだが、<相好を崩す>という言葉があるけど
まさにそんな風で、一言話を始めると途端に人懐っこい笑顔が全開になって
そのギャップが何ともマスターの人柄に於いても良い味を醸し出していた。
しかも、歳の割にはけっこうなマッチョ体型で
それをわざと見せつけるかのようにいつも店のロゴ入りの白いTシャツを着ていた。
大きな声では言えないけど、御多分に漏れず?
その手の体型の人に有りがちな<おネエ系>的要素も時折り顔を覗かせたりしていて
まぁでも、そんなことも常連客を引き付けるマスターの魅力のひとつにはなっていたんだと思う。
このマスターだが
常連客の間では『マスターは元高級官僚だった』という噂がまととしやかに語られていた。
いつだったか、一度マスターに訊いてみたことがあった。
「マスター、本当なの?」
「さぁね。忘れたよ。」
マスターは意味有り気に答えたもののその真偽はついに解らずじまいだった。
ただ、俺の送別会の時だったか・・・マスターはこんな話をしてくれたことがあった。
転勤が決まった時、俺は正直落ち込んでいた。
会社の仲間はみんな「係長に昇進するんだから栄転だ。おめげとう!」って言ってくれたけど
そんなことよりも俺は単純にこの街を離れたくなかったのだ。
長年住み慣れた街。学生時代からの友達がたくさんいる街。この店がある街。
新しい生活への不安もない訳ではなかったが
それ以上に青春時代を共に過ごしたこの街を離れることで
自分が今まで大切にしてきたものを全て失うんじゃないかという畏れを感じていたのだ。
漠然としたものではあったのだが。
「行くの止めようかな・・・」
酔ってそう言う俺にマスターは店の名前の由来を話してくれた。
「ねぇ、真ちゃん。『ROADSIDE』って名前どう思う?」
「えっ? うん、良い名前だと思うよ。」
「どんな風に?」
「どんな風って・・・」
もちろん、単語の意味は解ってはいたもののマスターがそこに込めた想いまでは解ってなかった。
「『ROADSIDE』ってね。通りに面しているお店なんかもそう言うけど
『道端』とか『路傍』って意味なんだよね。あっ、それは解ってるよね? 失礼、失礼(笑)」
「まぁ・・・」
「『道端』ってどう? 真ちゃんならそこで何をする?」
「するって?」
「メインストリートをずっと歩いて来た真ちゃんには難しいかなぁー?」
意地悪い言い方でマスターが言った。
もちろん、それが本意ではないことは解っていたけど、その時の俺は少しムッとして答えた。
「そんなことはないよ。」
それに構わずにマスターは続けた。
「『道端』ってさ。疲れたら休む所なんだよ。
道端に座り込んでボーっとするのも良いし、道端に咲いている花を眺めるのも良い。
人間ってさ、ロボットじゃないからね。歩き続けていると疲れるじゃない?
休息が大事なんだよ。心にも身体にももちろんね。
そういうのが次につながるエネルギーになると思うんだ。
俺なんかも良くやってたなぁー、勤めていた時にね。
疲れ果ててボロボロになってさ。どうしようもなくなったらね。
道端や土手に座って、ただ何時間もボーっと空を眺めてたりする訳よ。
で、雲なんかを見てたらさ。曇って色んな形に変わるじゃない?
それが面白くて、ホント何時間も何時間も見てたよ。
気が付いたら夕暮れになっていて慌てて職場に戻ったなんてね、あったなぁー。」
「・・・」
「まぁ、俺の場合はそれでもどうしようもなくなってさ。
ホント、疲れる世界だったんだよね。
足の引っ張り合いとか上司にゴマ擦ったりしてどんどん昇進していく奴らを見てるのが嫌でさ。
何て言うか、人間を止めたくなる前に仕事を辞めたんだ。
で、俺は応援をする側に回った訳。
だから、ここでは誰がどんな愚痴を吐いても俺は止めない。
時には『そうだ、そうだ!』なんて言ったり、時には聞いてないフリをしたりなんかしてさ。
疲れたらさ、好きなだけ休んでいけば良いんだ。
ここを愚痴の姥捨て山にしても良いからさ(笑)」
「・・・」
「だから真ちゃんもさ。疲れたと思ったらいつでも帰っておいでよ。」
そんなマスターが<居る>この店が俺は大好きだった。
そして、マスターの他には女の子が一人。
常連客の下世話な下ネタにも明るく冗談で返すような快活で朗らかな女の子で
<飲み屋の女の子>と言えば偏見になるかもしれないけど、それを恐れずに言うなら
およそ女を売り物にしていない、むしろ女にしておくのがもったいないくらいサバサバとしていて
良く笑うその表情は屈託がなくて常連客の誰からも間違いなく愛されていた。
「留美ちゃんってさ。
こんな<道端>に咲かせておくのがもったいないくらい良く出来た子だよね。」
酔ってそういう俺に留美ちゃんは笑顔で言った。
「あら、ホント? 嬉しい! ねぇ、マスター、聞いた?
私ってとっても可愛いんですって!」
「あれっ? そこまで言ったっけ?」
思わず苦笑いの俺。
「真ちゃんの心の声が聴こえたー。ねぇ、マスター?」
留美ちゃんの言葉に内心ドキッとする俺。
マスターは憮然として答えた。
「『こんな道端』で悪かったね。」
「いや、こんな素敵な花を咲かせるのは立派な道端だからこそだよ。
ホント、ホント。ねぇー?」
慌ててフォローしようとした俺に留美ちゃんがトドメを刺した。
「ほら、やっぱり素敵って言った!
でも、実際は私が咲いていてあげてるんだけどね。
でなきゃ、こんなむさ苦しい所にミツバチさん達はせっせとやって来ないわ。」
「あれ? ミツバチさんって・・・もしかして俺のこと?」
「ウフフ。」
ドヤ顔の留美ちゃんを前に男二人は苦笑するしかなかった。
でも確かに、留美ちゃんがいるお蔭でこの店はそれなりに繁盛をしていたのだと思う。
道端に咲く一輪の花。それが留美ちゃんだった。
みんなは『留美ちゃん』と呼んでいたがそれが本名なのかどうかは知らなかった。
ただ、俺も留美ちゃんのファンの一人だったこと、それも間違いなかった。
例え、ミツバチの一人としか思われていなくなって
楽しいひと時を過ごさせてくれる花があるならそれで良いって
きっと、他のミツバチさん達もそう思ってたのに違いなかった。
「こんばんは」
そう言いながら店に入って行くとマスターがきりっとした目を大きくして
驚いたようにまじまじと俺と見ると
やがて、あの頃と同じようにとびっきりな笑顔になって
俺に向かって逞しい両手を大きく開いて言った。
「おー、真ちゃんじゃない! こんな所に急にどうしたんだい?」
「こんな所って・・・あはは、マスターのお城でしょ?」
俺は思わず苦笑した。
「あはは、そうだった。さぁ、こっちにどうぞ。
カウンターのこっちがお気に入りだったね。」
マスターは笑顔で俺を<いつも>の席に促した。
「真ちゃん、何年ぶりだい? まだA市にいるのかい?
今日は出張かい? そういや、もう結婚したのかい?」
「あはは、マスター。その前に飲み物を注文したいんだけど。喉がカラカラでさ。」
「あー、そうだった! で? いつものやつで良いのかい?」
「ハイボール・・・」
「薄めね?」
マスターはニヤリとしてウインクをしてみせた。
ハイボールを待つ間、俺はおしぼりで手を拭うと周りを見渡した。
「今日は静かだね。常連さんはまだなの? そういや、留美ちゃんは?」
一瞬、マスターの顔が曇った。
「寿退社ってやつ?
だよね、あんなに気立ての良い子だもの男は放っておかないよね。」
「なら、良いんだけどね。」
ハイボールを俺の前に置きながらポツンとマスターが言った。
「えっ? どういうこと?」
「留美ちゃんね・・・亡くなったんだ・・・」
「えっ? いつ? どうして?」
「一昨年の八月。そういやもうすぐ三回忌だわ・・・」
深く溜め息をつくとマスターがゆっくりと話し始めた。
「あの子ね。乳がんだったんだ。
この店で働き始める前からそうだったみたいでね。
気付かなかった? あの子、片側の乳房を取ってたの。
飲み屋の女の子みたいな胸の前が空いた服も絶対着てなかったでしょ?
昔は髪も長くて可愛かったのに、それからはずっと髪もショートカットにしててさ。
逆に男を・・・何て言うか、わざと寄せ付けないみたいにね。」
「えっ、でも。留美ちゃんはいつも笑顔で俺達に接してくれてたよね。
他の常連さんにも分け隔てなくさ。」
「その<分け隔てなく>ってのがね。
つまり<特定の男を作らないよ>っていうことだったんじゃない?」
「でも、それなら何でこんな仕事を・・・あっ、ごめん。」
「ううん。彼女ね。親友の一人娘さんだったんだけどね。
病気になる前は普通に昼間の会社に勤めていたんだけど病気で勤められなくなってね。
でも、人と接する仕事が好きだから働かせてくれって頼まれてね。
俺も乳がんってのは留美ちゃんが亡くなってから親友に聞かされたんだけど。
もしかして、留美ちゃんにとっては
<人と接する>というのは自分の生を確かめる手段だったのかもね。
或いは、ひと時でも病気を忘れる為だったのかも知れないね。
でもまさか、そんな病気だったなんてね・・・」
「そんな・・・」
俺はショックでそれ以上は言葉も出てこなかった。
「それからお店はごらんの通り、火が消えたみたいになってね。
常連さんにも留美ちゃんファンは多かったからね。
いつの間にか一人来なくなって、二人来なくなって。
あー、それでもね。こんな店が良いって言ってくれる人だっているんだからね。
俺のこの抜群のスマイルとお上品な下ネタがさ。」
そう言うとマスターは豪快に笑った。
でも、俺にはマスターが無理に笑顔を作っているように見えた。
もしかしたら、忘れたかったことを俺がここに来たばかりに
又、思い出させることになったのかもしれない。
「マスター、ごめん・・・」
「何が?」
「いや・・・俺が来なきゃ思い出さなくても済む話だったのかなぁーってさ。」
「何をバカ言ってるのさ。大歓迎だよ。
もし真ちゃんが来てくれなかったら今夜のお客はゼロだったかもしれないんだから。
言ってみれば真ちゃんはお店の救世主? なんてね。」
そう笑うとマスターは冷蔵庫からビールを取り出すと栓を抜いてグラスに注いだ。
そしてそのグラスを俺の方に向けると言った。
「乾杯しよっか。真ちゃんとの再会に。そして・・・留美ちゃんの想い出に。」
「・・・」
「何よ? そんなしょぼくれた顔はしないの! 留美ちゃんに笑われるよ。」
「そうだね・・・乾杯。」
俺も飲みかけたハイボールのグラスを持つと黙ってマスターのグラスと合わせた。
「でも、それならそれで教えて欲しかったな。
せめて葬儀には出たかった・・・」
「留美ちゃんがね。言わないでくれって。」
「えっ? どうして?」
「真ちゃんが転勤をしてやっと一年経ったかどうかって時だったから
きっと、気を遣ったんじゃない?」
「そんな・・・」
「そうだ! 忘れるとこだった。ちょっと待ってて。」
そう言うとマスターは奥の控室に引っ込んだがすぐに又、戻って来た。
その手にはピンクの可愛い封筒があった。
「何?」
「うん、これね。留美ちゃんから預かってたんだ。真ちゃんがいつか来たら渡して欲しいって。」
「手紙?」
「さぁ・・・開けてみたら?」
封筒の中から一枚の写真が出てきた。
この店で俺の送別会をやった時のもので俺と留美ちゃんが仲良くツーショットで写っていた。
思い出した。
いつもは「ヤダー!」とか言ってお客さんの肩を叩くことはあっても
冗談でも腕を組んだり手を繋いだりしなかった留美ちゃんが
あの夜は珍しく酔っていたのかずいぶんと俺に突っかかってきて
挙句に半ば強引に腕を組んだツーショット写真を撮らされたのだ。
もちろん俺は嬉しかったのでされるがままだったが妙に照れくさかったのを覚えている。
俺が写真をジッと見ているとマスターが声をかけてきた。
「どれどれ、ちょっと見せて。」
マスターにその写真を渡すとまじまじと写真と俺を見比べながらポツリと呟いた。
「なるほどね。」
「えっ? 何が?」
「何がって・・・真ちゃんってもしかして国宝級に鈍い人?」
「そんなこと・・・」
「ありそう。」
マスターはそう言うとニヤリと笑ってみせた。
「いや、そんなことはないよ・・・たぶん。」
「あるね。きっと今までも何人もの女に冷たい仕打ちをしてきたんだろうな。
影で泣いている女がたくさんいるのに
本人がそれに気が付いていないところが一番の罪だね。」
「まさか。」
俺は大袈裟に首を振って否定した。
「送別会だったからでしょ。お別れのサービスみたいな?」
それを聞かずにマスターは呟いた。
「本当に最後になっちゃったんだね・・・でも、幸せそう。」
「・・・」
「留美ちゃんね。真ちゃんが好きだったんだよ。」
「えっ? まさか。」
「ほらね。全然気がついてない。」
マスターはヤレヤレと言ったポーズで笑ってみせた。
「だって・・・そんな素振りなんて無かったよ。」
「そりゃそうだよ。自分の抱えている病気のことを考えたらさ。
もし真ちゃんだったらどうする?
自分が治らない病気で、好きな人がいたらそれでも告白する?」
「いや・・・出来ないよ。」
「でしょ? そっか、だから真ちゃんには知らせたくなかったんだね。」
マスターはゆっくりとビールを一口飲むと続けた。
「薄々は感じていたんだけどね。
真ちゃんが来ないと妙にそわそわしてたし
真ちゃんが帰った後は何だか寂しそうだったんだよね。
今にして思えば、そうだったのかな? なんて思うんだけどね。
でも、その時はそれが本当に真ちゃんなのか誰だったのか
今ひとつ確信の持てないところもあってさ。
あの子、普段は明るくてテンションも高めなんだけど
時々ね、何か沈んでいるというか、疲れているというか。
そんな時もあったものだからさ。
それに、お互いに大人だし、縁があれば結ばれるものだって思ってたんだ。
もっと、強引にでも真ちゃんとくっつけちゃえば良かったのかなぁー
もしかして、国宝級に鈍いのは俺の方だったのかもね。」
「そんな・・・」
マスターはカウンターの引き出しから手帳を取り出すとパラパラめくっていた。
そして、その指を止めると俺の方を見て言った。
「再来週の日曜日さ。三回忌の法要があるんだけど、真ちゃんどうする?」
「俺? 行きたいけど・・・良いのかな? 俺なんかが行って。」
「もちろんよ。留美ちゃんのお父さんも喜ぶと思うよ。
留美ちゃんが真ちゃんのことを話してたとしても
話してなかったとしても、そんなことを気にする奴じゃないからさ。
でも、手帳とか確認しなくて良いの?
後になって<やっぱり予定が入ってた>なんて言ったら
留美ちゃんが悲しんで化けて出るかもよ。」
「あはは。
お蔭さんでうちの会社は休日に社員を働かせるほどブラックじゃないから。
あっ、でも・・・もう一度留美ちゃんに会えるんだったら
化けて出られた方が良いかな?」
「そんなことくらいで化けて出る訳ないじゃん。
留美ちゃんはそんな子じゃないよ。」
「何だよ、マスターが先に言ったくせに。」
「あはは、ごめんごめん。そうだったっけ。」
しばしの沈黙が二人を包み込んでいた。
それぞれがそれぞれに同じ想いに耽っていた。
マスターは黙ってグラスを拭いていた。
俺は煙草を吸いながら目の前のグラスをただ見つめるでもなく見つめていた。
「そういや、誰も来ないね。」
店の入り口を見ながら俺はポツリと呟いた。
「みんな気を利かせたんじゃない?」
グラスを拭きながらマスターは応えた。
「優しいね。みんな、優し過ぎるよ、みんな・・・」
自分の口をついたその言葉と共に込み上げてきた或る種の感情に
俺は溢れてくる涙を止められなかった。
時計の針が一時を回った頃、俺はマスターと再来週の約束をして店を出た。
ビルの階段を上りながら俺は考えていた。
三年。それは長い月日なのか? 短い月日なのか?
三年経っても何も変わらないものもある。
しかし、人の人生が変わるには十分な時間でもある。
そこにいるはずの人がもうこの世にすらいなくなっていたのだから。
それでもマスターの人柄は何も変わっていなくて
そこに流れていた時間も三年前と変わらず優しい時間だった。
まるで三年前から時が止まっていたかのように。
「俺を待っていてくれたのかな?」
ふと、そんな言葉が口をついた。
そして多分、そうなのかもしれないと思った。
もし、そうならこれから又、俺達の時間は動き出すのだろうか?
何事も無かったかのように。
いや、それは違う。
失くしたモノを埋める為に時間は動き出すのだ。
埋められないモノ、埋められるモノはあるにしても
それでも時間を動かしていかなければならないのだ。
それが生きていくということなのだから。
そして、ひとつ心に思った。
今までは忙しさに振り回されて脇見すらする余裕もなかったし
道端に何があるのかさえ考えたこともなかったけど
これからは道端に咲いている花にもきっと気が付くことが出来るんじゃないかと。
そうやって生きていくことが自分らしく生きていけることにも繋がっていくんじゃないかと。
「留美ちゃん、ありがとう。」
俺は胸ポケットにしまった留美ちゃんとの写真に手を当ててそう呟いた。