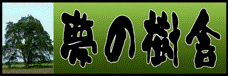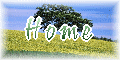
六等星でも照らせるもの
「ねぇ、さっきから何を一生懸命に切ってるの?」
「これ? 何に見える?」
「カラフルな紙」
「もう!」
琴美は浩司の言葉に思わず苦笑をした。
「他には?」
「カラフルな偽札?」
「浩ちゃん、職業間違えたよね。
営業マンよりお笑い芸人さんの方が向いてるんじゃない?」
そう言うと、琴美は今度は面白そうに笑った。
「失礼だなぁ〜 仕事だってちゃんと真面目にやってるよ。
で? ヒントは?」
「ヒント? そうねぇ〜 『星』『願い事』と、きたら?」
「星・・・願い事? 分かった! じゃ、カラフルなピノキオ!
『星に願いを』ってピノキオの歌だろ?」
「あはは。 浩ちゃん、本当に漫才でもやれば?」
「良いかもね〜 でも、残念ながら漫才って一人じゃ出来ないんだよな。
何なら、夫婦漫才でもするか?
琴美がさ。こんなに大きな真っ赤なリボンを頭につけてさ。
ド突き漫才とか良くない?(笑)」
浩司は頭の前で両手で大きなリボンの形を作ってそう言った。
「止めてよ。子供達が泣くわ」
「いやいや、一躍学校の人気者間違い無しだって」
「けっこうです。今でも十分人気者ですから」
「あら、そうだったんだ? それは知らなかったわ〜」
「目の前の人は全然私の魅力を分かってないんだわ。
見る目が無い人って嫌よね〜」
「魅力ぅ〜? 確かに、魅力的なバデーではあるけどね」
「バデーって何よ?」
「ボデーにはちょっと足りないんだな。
『ボ』のちょっと手前。バビブベボみたいな(笑)」
「まぁ、失礼ね! 何が足りないですって?」
「まぁ、その。 ほれ、その色気っつうかさ。
セクシーっつうかさ」
「小学校の先生に色気を求めないでよ、もう!」
「あはは、冗談だよ。 それ短冊だろ? 七夕の」
「ピンポーン♪」
「で、何をお願いする気なの?」
「私じゃないわよ。 明日、七夕でしょ?
子供達と一緒に学校で飾るのよ」
「あー、忘れてた! そっかぁ、明日は七夕かぁ〜
何か、懐かしいよね。
そういや、昔はお願い事をたくさん書いたっけな」
「たくさん?(笑) で、浩司少年はどんなお願い事をしたの?」
「ガンダムのプラモだろ? それから・・・ゲームとかさ。
後はねぇ〜 中森明菜のCDとかかな」
「へぇ〜 ちゃんと少年してたんだね?」
「何だよ、それ?(笑) 俺はいつだって健全な少年さ」
「健全な少年って何よ?」
「健全な少年らしい清い心をいつも持っている・・・とか?(笑)
でも、今の小学生って何をお願いするのかな?
琴美の生徒達って一年生だったよな?」
「うん。そうねぇ〜 何だろう? 明日が楽しみだわ」
「それこそ、健全な子供らしい願い事を書いてくれりゃ良いけど
金持ちになりたいとかさ。
プラダのバッグが欲しいとか書かれた日には担任としてどうよ?(笑)」
「まぁね。あながち無い話でもないかもね。
今の子ってけっこう現実的だったりするから」
「現実的・・・か。
今の時代ってさ、小学生だってパソコンや携帯とか当たり前に使ってるだろ?
色んな情報が垂れ流し状態で氾濫してるけどさ。
情報を自分で取捨選択出来るなら良いけど
ちゃんと判別も出来ない子供の内に変に毒されて耳年増的に情報通になってさ。
精神だけ大人と同じになってるって言うよね」
「そうね。それって本当は親がきちんと教えなきゃならない事だと思うけど
親自体がそれを出来ないのに、子供に何でも与え過ぎている気もするわね」
「俺達の親の時代は『一億総中流』なんて言葉があったそうだけど
今は物だけ豊かになって心は何処かに置き去りのままになってるのかもなぁ〜」
「そうね。私も他人の事は言えないかも知れないけど
大人に成り切れていない大人が親になってる。そんな親も多いわ。
もちろん、親だけじゃなくて先生もなのかも知れないけど」
「そうだね。オヤジが良く言ってたけどさ。
甘やかされて育った子供が親になってるから子供の躾け方も分からない親が多いって。
例えば、電車やバスなんかでも、騒ぐ子供を注意するのに
『怖いオバチャンに怒られるから止めなさい』とかさ。
オバチャンに怒られるから騒いじゃダメって話じゃないよね。
公共の場でのマナーとかルールなんだから。
ひどいのになると、子供が公共の場で騒いでいても止めもしないとかね」
「子供が騒いでいるのを注意したら逆切れされて文句を言われるとか聞くわね」
「うん。そういや、琴美の学校にはモンスターペアレントなんていないの?」
「そうね〜 私のクラスではまだそんな親御さんはいないけど。
でも、4年生のクラスの先生が悩んでいたわ。
『なんで家の子は九九が出来ないんですか?』とか
『なんで家の子の嫌いな物を給食で出すのか?』とかね。
今は給食なんかでも、無理矢理食べさせる事はしないんだけど。
でも、全員の好きな物ばかり出すなんて無理よね。
先生同士の飲み会なんかになると
何処そこの先生がノイローゼになったとか
突然退職したとか、そんな話も良く聞くわね」
「ん〜 先生受難の時代なのかね」
「そうとばかりも言えないけどね」
「どうして?」
「先生にも問題はあると思うの。
向いてる向いてないとか、子供達に対する情熱とか・・・
ううん、最初はみんな情熱を持って先生になったと思うの。
でも、今って色々な制約があるのよ。
何かあると、すぐに親が文句を言うし。
親がクレームをつけると教育委員会が黙ってないでしょ?
そうすると、結局先生も出世に響くし
結局、事無かれ主義みたいな感じになっちゃうのよね」
「運動会でも順番はつけないとか、騎馬戦は危険だからしないとか
カッターやナイフで鉛筆を削ったら指を怪我するから禁止だとかさ。
発表会の劇じゃ主役が何人もいるとか、いつからそうなったんだろうね」
「そうね。でも、私達の頃もそうだったじゃない?」
「まぁね」
「子供達って本当はすごくキラキラしてるの」
「うん」
「勉強の得意な子、絵の得意な子、歌が上手な子、運動が得意な子。
それから、とても面倒見の良い子とかね。
みんな良いものを持っているの。
それを伸ばしてあげるのが教育だと思ってた」
「うん」
「でも、理想と現実は違うのよね」
「違うって?」
「えぇ。例えば、授業中に急に立って歩きまわる子だとか
おしゃべりを止めない子。悪戯をする子。
そんな子がいたらどうする?」
「そりゃ、注意するだろ?
集団生活のルールを教えるのも先生の仕事じゃん?
良い事をしたら褒める。逆に悪い事をしたら叱る。
それは親の仕事でもあるけど、先生の仕事でもあるよね」
「そうなんだけど・・・でも、下手に子供を叱れないの」
「どうして?」
「親がね」
そう言うと、琴美はふと溜め息を漏らした。
「そっか。親だって叱ると怒るの区別もつかない親もいるんだろうしね。
それが出来ない親に限ってうるさいんだろうな」
「そうなのよねぇ〜
でも、先生でも敬語の使い方も知らない先生もいるけどね」
「敬語? 先生が? まさか?」
「いるのよ。若い先生なんだけどね。
例えば、学校行事で父母にお手伝いを頼む事もあるじゃない?
そんな時に、父母の前で校長先生が挨拶をするとするでしょ?」
「うん」
「普通は父母に校長先生を紹介する時は何て言う?」
「そりゃ、『校長の何々が挨拶をさせて頂きます』とかでしょ?」
「そうよね。
でも、普段子供達の前で話すのと一緒で
『それでは校長先生からご挨拶をして頂きます』って平気で言うの。
普通の会社ならお客様に自分の会社の社長を紹介する時って
社長に対して敬語は使わないでしょ?
『社長さんから』とか『ご挨拶』とか言わないよね?」
「そりゃそうだよ。
サラリーマンにとって唯一社長を呼び捨てに出来るのがお客様の前だからね。
後は飲み会の愚痴大会の時とかもだけどさ(笑)
『あのバカ社長は何にも分かってない!』とかね」
「あはは。それは聞かなかった事にしてあげるわ」
「そりゃ、どうも(笑)」
「確かに未熟なままで先生になっちゃった先生もいるわ。
こんな私でさえビックリしちゃうような先生って実際にいるのよ。
思うんだけどね。
お医者さんにはインターン制度があるでしょ?
法学生が裁判官や弁護士になる時には司法修習制度もあるし」
「あぁ、そうだね」
「でも、子供達の人格の基礎を作るべき一番大事な時期を預かる先生には
学生の時に2週間くらい実習があるだけ。
もちろん、厳密にはそれだけじゃないけど。
それで大学を卒業して、学校に赴任した途端にすぐに
親や周りの先生達から『先生』なんて呼ばれたら
普通の人ならそれだけで勘違いしてしまうよ」
「『自分は先生なんだ。もしかしたら偉いんじゃないか?』なんてね」
「まあ、それは極端にしても、それに近いものは私も感じた事があるの。
学校の先生って、ある意味じゃ医者や裁判官より大事な仕事だと思わない?
この国の未来を担っていく子供達に一番影響を与えてしまうかも知れないのよ。
学校の先生になるにしても、何年かの社会人経験だとか
海外青年協力隊みたいなボランティア経験だとか
色々な社会をちゃんと何年か体験した上で先生になる資格を与えるとか
そんな制度も必要なのかも」
「そうだね。学生を卒業して一般の会社に入ったら
ただの平々で一人前になるにも何年も勉強したり
努力をしたりしなきゃならないものな。
それが先生一年生も先生。経験豊富な先生も同じ先生ってのは違うかもね。
でも、そう言う事って先生方の口から上がって来ないと
なかなか現実にはならないんじゃない?
組合が強そうだから、なかなか大人しく賛成はしないだろうけど」
「国会議員や官僚と同じね。
自分達の立場の事になると不利になるような事はしないと思うし」
「確かに、学校や先生の制度を変えるのって
そんな簡単じゃないかも知れないけどさ。
でも、若手の先生の中から問題提起をしていくのって大事なんじゃない?
仮に、そこまで変える事は出来なくたって
先生一人一人が『誰の為の学校なのか?』って事を考えたらさ。
きっと、少しづつでも変わっていくさ」
「そうね」
「とりあえずは、現状は今の制度の中でどうやったら子供達の為になるのか?
人生の先輩として、子供達に何を伝えて上げられるのか?
そして、子供達の心に何を残せるのか?
それを考えるのが琴美達の仕事だと思うよ。
琴美が一人一人の子供達と誠実に向き合っていけば必ず子供達の心に何かを残せるさ」
「そうね・・・」
「まぁ、言うは安しってとこかな?」
「うん・・・ あっ、ちょっと待ってて。今、コーヒーを入れてくるわ。
喋り過ぎて何だか喉が乾いちゃった」
そう言うと琴美は立ちあがって台所に向いかけた。
「じゃ、俺はビールでも飲むかな」
「ビール?」
その言葉に反応したかのように浩司の方に振り返ると
琴美は目を細めて浩司を少し威圧するように睨みながら訊き返した。
「今夜はビールですか?」
「あっ、いや・・・もちろん、発泡酒だよ」
「よろしい! ちゃんと倹約しなきゃね」
「おいおい、それ先生の口調になってるよ(苦笑)」
「あらっ、そうだっけ?」
琴美はとぼけたような素振りでペロっと舌を出すとそう言って笑った。
「琴美ってさ〜 普段は優しいんだけど、時々きつくなるんだよな。
結婚したら間違いなく尻に・・・ボソボソ」
「えっ? 何か言った?」
「い、いや、別に。ただ琴美の生徒達が羨ましいと思ってね。
こんな美人の先生なら俺ももっと勉強したのに・・とか?」
「もう! 嘘ばっか。浩ちゃん鼻が伸びてるよ」
浩司は慌てて鼻を押さえて言った。
「俺はピノキオかい?」
「ちっともカラフルじゃないけどね(笑)」
浩司と琴美が初めて会ったのは大学一年生の時。
学部は違ったが、同じテニスサークルの新入生同士だった。
お決まりの新入生歓迎コンパで先輩達の注いでくれた酒を断れずに
浩司は注がれるままに飲み続けた。
しかも、その頃はまだ自分の酒の定量すら分かっていなかった時だ。
これまた、お決まりのコースで浩司は見事に酔い潰れたのだった。
それを介抱してくれたのが琴美だった。
そして、これまたお決まりのように二人はそれをキッカケに付き合うようになった。
あれからもう10年近くになる。
『お決まり』繋がりみたいな縁で安直に付き合い始めた二人だったが
多少の紆余曲折も有りながらも、それでも着実に愛を育み続けていた。
卒業後、浩司は地元で普通に就職をして今は小さい会社ながら営業係長を任されていた。
琴美は隣町で小学校教師になった。
時々、ボランティアで近くの子供達を集めてやっている読み聞かせの会を手伝っていた。
琴美の面倒見の良いところは昔からちっとも変っていない。
「琴美が先生って言うのはまさに天職なんだろうな」
浩司は心からそう思っていた。
「えっ? 何か言った?」
琴美はコーヒーカップをテーブルに置くとイスに座り浩司の方を向くと訊いた。
「いや、別に。ちょっと昔の事を思い出してた」
「昔って?」
「琴美と初めて会った頃の事」
「へぇ〜 ねぇ、どんな?」
浩司は発泡酒のリングプルを開けてひと口飲むと言った。
「俺が新入生歓迎コンパで酔い潰れてさ。
そのお陰で今があるだろ?」
「そのお陰でって何よ? 私がちゃんと介抱してあげたお陰でしょ?」
「あれってさ。俺じゃなくても介抱した?」
「さぁ〜 どうかなぁ〜」
琴美は悪戯っぽく笑ってみせた。
「おいおい、こんな時は嘘でも『あなただったからよ』って言うのが
”彼女”の優しさだろ?(笑)」
「彼女ね〜 もうだいぶ長いよね?」
「そうだな。 10年ひと昔って言うけど
それで言ったら、もうひと昔前からの付き合いになるもんな」
「誰のお陰?」
「あはは。はいはい、琴美さんのお陰でございます」
「よろしい!」
「だから、それ先生口調だってば」
「だって、先生だも−ん♪」
「ま、確かに間違いは無いけどさぁ〜
でも、何も俺の前でまで先生やらなくても・・・」
「えっ? 何? 発言は手をちゃんと上げてからね」
「おいおい、何だか、本当に漫才になってきてないか?(笑)」
「あはは」
「全くもう」
「そう言えばね」
「うん?」
「さっきの続きみたいになるけど」
「うん」
「咲子、覚えてる?」
「あぁ、確か・・・高校の先生をやってるんだろ?」
「そう。 で、いつだっけなぁ〜
卒業して、2〜3年・・・かな。
咲子から連絡が有って会ったのよ」
「うん」
「その時にね、咲子に訊いたの。
咲子って昔から子供が好きだったから
てっきり私と同じ小学校の先生になると思ってたの。
それが高校の先生でしょ?
『どうして高校の先生になったの?』って」
「うん」
「そしたら咲子ね。
『小学生の時の教師の対応は、
この先の子供の心の成長に大きく作用するの。
そんな大切な時期の子供と接するには、私の器は小さ過ぎるから』って言ったの」
「へぇ〜 それ凄い話だね。
そこまで考えて、先生を選ぶなんて凄いよ」
「私なんか、そこまで考えていなかった」
「普通、そうでしょ。
でもさ。 そんな人にこそ、本当は小学校の先生をやって欲しいよね。
自分の事よりも、そこまで生徒の事を思えるなんてさぁ〜
そんな先生ってどれだけいるんだろ?
そんな人が先生だったら、生徒達は幸せだと思うな」
「うん。そうね」
「いや、琴美の生徒も十分幸せだと思うよ」
「あら、ついでにどうもありがとう」
「いや、そんなんじゃないよ。本当にさ。
琴美と言い、咲子さんと言い、そんな先生ばかりだったらって思うよ。
俺にはまだ子供はいないけどさ」
「本当はいたりして?」
「おいおい、止めてくれよ。
琴美に覚えがないならいる訳ないだろ?」
「覚え? ん〜 いつ? あの時?」
「おいおい、マジで答えるなよ(笑)」
「ごめんね。 なかなか会う時間が作れなくて」
琴美が神妙な面持ちで言った。
「あぁ、分かってるって。
琴美が一生懸命なのは分かってるよ。
今は子供達に一生懸命なんだろ?」
「うん。 でも、浩ちゃんにはいつも甘えてばっかだね。
きっと、寂しい想いもさせてるよね?
せっかく、車で二十分くらいの隣町に住んでいるのに
会えるのはせいぜい月に一〜二回くらいだし。
私・・・全然、良い彼女じゃないね。 ごめんね・・・」
「何を今更(笑) そんな事、気にしちゃいないよ」
「でも・・・」
「おっと。 それ以上は無し! 分かってるって言っただろ?」
「うん・・・」
「月に一回だって、年にしたら十二回じゃん。
それこそ、七夕の織姫と彦星なんか年に一回だからね。
それだって、雨が降ったら会えるかどうか分からないんだろ?
それから見たら俺達なんて幸せだよ」
「・・・」
琴美は浩司の言葉に黙って頷いていた。
「でもさ。 今って良い時代になったよな。
会えなくたって、スカイプがあるお陰でさ。
こうして顔を見ながら話が出来るじゃん」
「そうだね」
「考えたら、スカイプって俺達にしたらさ。
七夕に出てくる『カササギ』みたいなもんだよね?
会えない時間を、こうして橋渡ししてくれてるんだからさ」
「そうね」
「ただ・・・」
「何?」
「こうやって顔が見えてるからさ。
パンツ一丁で股間をボリボリかきながら電話は出来ないよな?
だらしない恰好で画面に現れたら琴美に幻滅されちゃうだろうし」
「ぷっ。 お願いだからそれだけは止めてね」
「はいはい、頑張ります(笑)」
「えー!? 頑張らないとできないの?」
「いやいや(笑)」
「もう! でも、ホント。 こうして浩ちゃんの顔が見られるだけでも嬉しい」
「おっ、珍しく可愛い事を言ってくれますな?」
「珍しくは余計です!」
「あはは。 でも、出来ればさ」
「出来れば?」
「うん。 ただの電話の時より、こうして顔見られるのは俺も嬉しいんだけどね」
「うん」
「ただねぇ〜 琴美に触れられないのが残念だわ。
これも、もっと科学が進歩したらスカイプみたいなTV電話でも
お互いに触れられるようになるのかな?」
「あはは、そうだね。 でも、そうなったら会わなくても良くならない?
私、そんなのは嫌だな」
琴美はそう言うと頬を少し赤らめた。
「確かに、そうだね。
久しぶりに会った時の感激も愛おしさもドキドキもなくなっちゃうよね」
「うん」
「おっと、もうこんな時間だ」
見ると時計は十二時を回っていた。
「そろそろ寝る? 明日も早いんでしょ?」
「そうね。 もうそろそろ寝るわ」
「うん」
「ねぇ、浩ちゃん。 今度はいつ会えるかな?」
「それは琴美次第でしょ?」
「そうね・・・ ごめんね」
「だからぁ〜 それは良いって」
「うん。 ごめんね」
「ほらぁ〜」
「あっ」
琴美は舌をペロッと出して笑った。
浩司もそれにつられて思わず笑った。
実際には会えなくても
こうして顔を見ながらその日の事をお互いに話し合ったり
何て事はない他愛もないお喋りをしながら過ごすこんな時間が
今の二人にとってはそれだけで幸せな時間だった。
「明日の夜は晴れると良いな。 せっかくの七夕だから。
彦星もきっと今頃はドキドキしながら眠りについてるだろうな」
「織姫もよ、きっと。 明日はきっと会えるよね」
「そうだね。 そう思うよ。 いや、必ず・・・かな」
「うん。 そうだと良いな」
「大丈夫、きっと会えるさ。 さてと、それじゃ、俺達も寝ようか?」
「そうだね」
「うん。 それじゃ、また明日の夜にね」
「うん。 待ってる。 仕事、頑張ってね」
「おう。 ありがとう」
「車の運転も気をつけなきゃダメだよ」
「あぁ、分かってる」
「それから・・・」
「おいおい、キリがないよ(笑)」
「あはは。そうだね」
「じゃ、おやすみ」
「はい、おやすみなさい」
琴美の映像が消えるのを待って
浩司はスカイプを切るとパソコンシャットダウンさせた。
消えていくパソコンの画面。
こうして一日、一日が刻まれていく。
浩司は窓際に立ってカーテンを少し開けた。
寝静まった街の上には満天の星空が拡がっていた。
「この調子だと、明日の夜は彦星と織姫もデートが出来そうだな。
じゃ、俺もあやかって願い事でも書いてみるかな」
そう言って、浩司はカーテンを閉じると
プリンターの所に行きカラー用紙を一枚取り
居間のテーブルの前に座るとカラー用紙を丁寧に折り始めた。
「たぁなぁーばぁーたーさぁーらさらぁー・・・あれ? 笹の葉だっけ?」
うろ覚えの七夕の歌を口ずさみながら、一人で苦笑をしては
今度はハサミを入れて数枚の短冊を切った。
「さてと、何て書こうか・・・」
七夕の夜。
琴美は学校が終わってアパートの部屋に戻ると
パソコンを開いて昼間子供達と撮った七夕の写真を選んでいた。
明日の学級通信に載せる為だ。
「ん〜 どれが良いかな・・・ これは?
でも、やっぱりこっちかな」
子供達が短冊に真剣に願い事を書いている写真。
一生懸命に手を伸ばして短冊を柳の枝に下げようとしている写真。
そんな子供達の何枚もの写真を見比べながら
思わず昨夜の浩司との会話を思い出して笑みがこぼれた。
「それにしても、子供達の願い事が普通で良かったわ。
男の子はサッカー選手、女の子はお花屋さんやケーキ屋さん。
ウルトラマンやプリキュアなんて子もいたし
やっぱり、一年生は一年生よね。
このまま純粋に育ってくれたら良いんだけどなぁ〜」
そんな事を思いながら写真を選んでいった。
「良し、こんなところかなぁ〜 後は、通信に入れる文章よね。
ん〜 どうしよう・・・」
そこにスカイプの着信が入った。 浩司だ。
「あらっ、今夜は早いわね」
「よぉ。 こんばんは」
「こんばんは。 早いわね。 もう仕事は終わったの?
あれっ? もしかして、車の中?」
浩司の背景には車の後部座席が映っていた。
「あぁ、仕事が長引いていてさ。
今、車の中でクライアントが戻ってくるのを待ってるんだ」
「大変ね。 ご苦労さま。 でも、それじゃ長話は出来ないわね」
「まぁね」
「もし、仕事に戻るなら、何も言わないで切っちゃっても良いからね」
「うん。 ありがとう。 琴美は? もう終わり?」
「今ね、今日撮った七夕の写真を選んでいたの。
早速、明日の学級通信に載せようと思って」
「そっか。 でも、先生って大変だね。
勤務時間だけが仕事じゃないもんな?」
「まぁね。 学校だけじゃ終わらないのよ。
何だかんだとやる事が多くって」
「うん。 ご苦労さま。 で?」
浩司が意地悪そうな顔をして笑っている。
「何が?」
「いや・・・ほらっ、昨日、話してたじゃん?
子供達はどんな願い事をしたのかなって思ってさぁ〜」
「あらっ。 残念でした! 浩ちゃんの期待に応えるような子はいなかったわよ」
「何? プラダのバッグとか?(笑)」
「えぇ。 うちの子供達は誰かさんと違って健全に育ってますからねぇ〜」
「誰かさん? 誰かさんって誰だろ? きっと、俺の知らない人だな、うん。」
「どうかしら?」
そう言いながら琴美は浩司をジーっと見つめた。
「よせよ。 照れるじゃん」
「あはは。 やっぱり、分かってるのね。 浩司クン、偉いわぁ〜(笑)」
「あはは、そりゃどうも(笑)
で? 琴美は何か書いたの?」
「えぇ、もちろん!」
「へぇ、なんて?」
「子供達の夢が叶いますようにってね。
これは・・・まぁ、表向きだけどね」
「表向きって、あぁ〜た。 まさか、裏では子供を虐めてるんじゃないよね?(笑)」
「そんな、まさか!」
「あはは。 分かってるよ」
「当たり前よ。 子供達の前で個人的な願い事なんか書ける訳ないでしょ?
そう言う意味よ」
「そりゃま、そうだね。 じゃ、ホントの琴美の願い事は?」
「これ♪」
そう言うと、琴美は一枚の赤い短冊をカメラの前にサッとかざしてすぐに隠した。
「おいおい、それじゃ見えないよ」
「良いのよ」
「良くないよぉ〜 ねぇ、見せてよ」
「いやぁ〜よ」
「お願いしますだ! 織姫様ぁ〜」
「まぁ〜 そのうち、浩ちゃんが忘れた頃にね」
そう笑いながら琴美はウインクをしてみせた。
「いつの話だよ(笑)」
「えへへ」
「ねぇ〜 見せてくれよ」
「ふふ、だぁ〜め!」
「おーい! 琴美さぁ〜〜〜ん」
「なぁに?」
「おいおい、『なぁに?』じゃないでしょ?」
浩司は思わず苦笑をした。
「やれやれ、今年の織姫様はなかなか手強いぞ」
「そうよ。 女は毎年強くなるのよぉ〜」
琴美はドヤ顔で
画面に映っている浩司の鼻を人差し指で、ちょんと突いて見せた。
「そうか、分かった。
実はさ。 俺も短冊を書いたんだよね。 これっ!」
浩司もカメラの前に青色の短冊をサッとかざした。
「えっ、何?」
「見たい?」
「見たい、見たい♪」
「えー? 嫌だよ。 琴美だって見せてくれなかったしさぁ〜」
「もう、意地悪!」
「意地悪さんはどっちかなぁ〜?
お兄さんは誰かさんの真似をしているだけなんだけどなぁ〜」
そう言いながら、ニヤニヤしながら仕返しとばかりに
カメラの前で青い短冊をヒラヒラ振って見せた。
「見える?」
「見えない!」
琴美はふくれっ面で言った。
「じゃぁさ。 『せぇ〜の』で見せ合う?」
「・・・うん。」
「あらっ、渋々ですかい?」
「もう〜」
「あはは。 じゃ、『せぇ〜の』でいくよ。 良い?」
「OK♪」
「良し。 じゃ、せぇ〜の!」
琴美は声に合わせてカメラの前に短冊をかざした。
浩司は短冊を見せてはいない。
「あっ、ひどぉ〜い!」
琴美は慌てて短冊を後ろ手に隠した。
そして、浩司に訊いた。
「見えた?」
浩司はニヤッと笑って言った。
「バッチリ♪」
「もう、やだぁ〜 サイテー!」
琴美は両手で顔を覆って泣いている。
「ひどい・・・」
「おいおい・・・ 琴美?」
「・・・」
「もしもぉ〜し!」
「・・・」
「嘘だよ。 字が細かくて全然見えなかったんだよ。
ホントだよ! ごめん、ごめん!」
「・・・」
「琴美? ごめん・・・本当にごめん!」
浩司はカメラの前で何度も頭を下げてみせた。
「本当にごめん!」
恐る恐る顔をあげた浩司。
そこには画面の中で面白そうにニヤニヤ笑っている琴美の顔が見えた。
「仕返しよ」
「あっ、それはないよぉ〜」
今度は浩司が泣きそうになった。
「もぉ〜 頭にきたぞ!」
浩司がそう言うと、突然スカイプが切れた。
「あっ、浩ちゃん? ・・・どうしよう? 怒らせちゃった・・・?」
琴美は慌ててスカイプで浩司を呼び出そうとした。
でも、何度呼び出しをしても繋がらなかった。
「浩ちゃん・・・ そんなつもりじゃ・・・」
琴美は慌てて、携帯を手に取ると浩司の携帯に電話をかけた。
「浩ちゃん・・・ 出て、お願い。 こんな夜にこんなケンカは嫌よ・・・」
携帯の呼び出し音が鳴り続けたが浩司は出なかった。
と、その時。 突然、玄関のチャイムが鳴った。
「もう、こんな時に!」
琴美はチャイムを無視しながら携帯が繋がるのを千秋の思いで待っていた。
玄関のチャイムもそれに負けずに鳴り続けていた。
「もう、いい加減にして!」
琴美は呼び出し音が鳴り続けている携帯を耳に当てたまま玄関に走った。
「こんな時間に誰?」
「俺だよ」
浩司の声だ。
「えっ!?」
琴美は思わず絶句した。
「お・れ・!」
「浩ちゃん? どうして?」
琴美は慌てて玄関のドアを開けた。
そこには紛れもなくスーツ姿の浩司が立っていた。
「じゃーん」
浩司は例の青い短冊を琴美の前に差し出した。
「俺の短冊も琴美のと一緒に飾ってくれよ」
「えっ? えっ? もしかして・・・さっきのホントに見えていた?」
「あぁ」
浩司はそう言うとニッコリと微笑んだ。
「でも、この短冊は今、書いたんじゃないよ。
昨夜書いたのを持って来たんだからさ」
「ホント?」
「あぁ、ホント」
「浩ちゃん・・・」
そう言うが早いか、琴美は浩司に抱きついた。
浩司も琴美を抱きしめると、髪を撫でながら言った。
「琴美。 今じゃなくても良いからさ。 琴美の仕事が落ち着いたら結婚をしよう」
「はい」
琴美の部屋のソファに並んで座っている二人。
琴美の入れたコーヒーの香りが優しく二人を包み込んでいた。
琴美はコーヒーカップを両手に包むように持ちながら
ひと口啜るとカップをテーブルに置いて、それから浩司の方に向き直ると訊いた。
「でも、ホントに良いの? また、待たせちゃうよ?」
「あぁ。 もう慣れてるから」
「ごめんなさい・・・」
「あはは。今更何を(笑)」
「・・・」
「琴美が一番納得出来るようにしたら良いさ。
時間はまだまだタップリとあるだろ?」
「私ね。浩ちゃんが思うような良い先生じゃないかも知れない。
私自身がまだまだ立派な人間じゃないし
先生だなんて威張れるような事もまだ何も出来ていない・・・」
「うん・・・でも、良くやってる方だとは思うけどね。
いつも『子供達が一番』って言ってるじゃん?
それが何より先生として大事な事だと思うよ」
「ううん。いつも迷ってばかりで、いつも自問自答しているの。
『これで良いのかな?』
『今日はちゃんとみんなの話しを聞いてあげられたのかな?』
例えば・・・
『真菜ちゃんは今日はいつもより元気が無かったけどけど
私は気付いていたのに、忙しいからって話を聞いて上げられなかったな』とか。
家に帰って寝る時なんか、毎晩のように自己嫌悪しちゃう・・・
『ダメだなぁ〜私って』なんてね。 そんな事ばっかり・・・」
「うん。 でも、仕方ないよ。
40人からの生徒がいるんだろ?
毎日、全員の顔色を伺って、『何かあったのか?』とか無理だよ」
「でも、私は子供達みんなの先生なのよ」
「そりゃそうだけど・・・」
「確かにね。 私は先生としてもまだまだ半人前。
満月でさえ、ベガのような一等星でさえ地上全部を照らすのは無理なのに
六等星のような私なんかじゃ40人みんなを照らすなんて出来ないわ」
琴美はテーブルの上に置いていた自分の書いた赤い短冊を手に取ると
それを天井のシーリングライトにかざしながら話しを続けた。
「それは分かっている・・・
でもね。たった一人でも困っている生徒がいたら
私がその子の為に何かをしてあげたいって思うの。
私がその子をちゃんと照らしてあげたいって思うの。
それくらいは私にでも出来るかなって・・・」
「うん。 それで良いんじゃないかな。
六等星にだって照らせるモノはきっとあるよ」
「うん、そう信じている。
だからね。 そう自信が持てるようになるまで
もう少しだけ時間をください」
「あぁ、了解だよ! でもさ、今夜のこの時間だけは俺にくれよな?」
「うん」
琴美はそう頷くと頬を赤らめて少し俯いた。
重なり合う二つの影を優しく見守るように
窓の外、夜空にはベガとアルタイルがひと際輝いていた。
今夜は七夕。
えっ?
二人が書いていた短冊の言葉ですか?
実は私もずっと気になっていたんですよね。
それでは野暮を承知で、ちょっと失礼をして・・・どれどれ?
テーブルの上に仲良く並べられた赤と青の二枚の短冊。
その短冊にはそれぞれこう書いてあった。
「琴美と結婚が出来ますように。 絶対、幸せにする! 浩司」
「いつか、悪い彼女を卒業して浩ちゃんの良いお嫁さんになりたい。 琴美」