
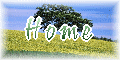
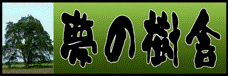
Dear My Christmas
「クリスマスが嫌いな子供なんているのかな?」
街路樹を飾る色とりどりのイルミネーション。
ショーウインドウに飾られたクリスマスカラーのオブジェ。
街を流れるクリスマスソング。
もし自分が独りぼっちだとしたら街行く誰もが自分より幸せに見える季節。
もし自分の今が幸せだったら街行く誰よりも幸せを感じられる季節。
それがクリスマスだ。
「いるわけないか。
だよなぁ~ 俺なんかも楽しみだったもの。
クリスマスの朝、目が覚めたらさ。
枕元に・・・あれっ?」
並んで歩いていた千春の表情が沈んでいるように見えた。
「どうした?」
「ううん」
笑顔で否定をした千春の顔は作り損ねた作り笑顔のようだった。
「なんか変だぞ?」
「そんな事ないよ」
正人は千春の顔をまじまじと見つめた。
「止めてよ。そんなマジな顔・・・正人らしくないよ」
「俺だって真面目な顔くらいするさ。
特におまえの事になったらさ」
「あはは、正人。変だよ。おかしい!」
そう言って千春は何事も無かったかのようにケラケラと笑った。
正人と千春は高校の同級生だった。
正人は野球部の四番でクラスでも学校でも目立つ存在ではあったが
どちらかというとその頃にしては珍しく硬派で
野球以外にはさして興味も持っていなかった。
千春は吹奏楽部だったが、大人しい性格が災いしてか
クラスでもそれ程目立つ存在では無かった。
当然、クラスメイトという事以外は
特に親しいという事も無く卒業を迎えた。
そんな二人が付き合う事になったのは
今年のお盆時期にあった高校の同窓会の時だった。
高校を卒業して銀行で働き始めて四年。
薄らとではあるが化粧をし小綺麗なワンピースを着た千春は
控えめは相変わらずではあったが
それでも同級生の女子の中でもひときわ輝いていた。
「おい、あれ誰だ?」
千春を指して訊く正人に同級生の男子の一人が答えた。
「あいつは千春だよ。
覚えてない? 吹奏楽部でクラリネットを吹いてたろ?」
「千春? 千春って宇野千春か?
確か・・・そうそう!
三年の冬休みにお父さんが事故で亡くなったっていう」
「あぁ、それであいつは進学を諦めて銀行に勤めたんだよな」
同窓会の二次会はカラオケボックスだった。
店に入る時、正人はタイミングを見計らって千春の隣に座る事に成功をした。
歌い出しはクラスでもムードメーカーだった吉田だ。
一曲目からフリを交えながら大熱唱をし
歌い終わると吉田がみんなに向かって言った。
「良し、紅白歌合戦にしようぜ!
じゃ、次は女子な! さっ、誰が行く?」
「じゃ、私行っちゃう!」
当時からノリの良かった真弓が手を挙げた。
「おー、もう酔ってるのか?
出ました、真弓の行っちゃう! いやぁーん」
身悶える格好をしながら吉田は真弓にマイクを手渡した。
「バッカじゃないの?」
笑いながらマイクを受け取ると真弓もノリノリで歌い始めた。
「あはは、すごいねみんな。圧倒されるよ」
さりげなく正人は隣の千春に声をかけた。
「川田君も負けていられないよ。
何を歌うの? 私、入れてあげる。
ねぇ、デンモク貸して」
千春は向かいに座っていた女子に声をかけた。
それより驚いたのは正人だった。
「宇野だよね? 俺の事、分かるの?」
「えっ? もちろんよ。女子の憧れだった川田君。
さっき、隣になって焦っちゃった。
まだドキドキしてる」
照れくさそうに笑った千春がますます可愛く見えた。
盛り上がった二次会も終わりカラオケボックスの外では
みんながそれぞれにグダグダと終わらない話を続けていた。
「みんなすごかったな」
正人は千春に話しかけた。
「ホント、高校の時より確実にパワーアップしてるよね。
でも、川田君の歌も良かったよ。
けっこう渋い選曲だったよね。
高校時代を思い出したわ」
「すまんね、働くようになってから忙しくてさ
最近の歌を覚えるヒマがなくってさ」
「いや、褒めてるつもりだったんだけど・・・」
千春は申し訳なさそうな顔をした。
「あはは、今度までには新曲を覚えておくよ」
「うん、楽しみにしてるね。
私、同窓会どうしようかと思ってたんだ。
みんな大学を出て社会人になってさ。
私なんか大学の話は分からないし話が合うかなって」
「そんな事は関係ないよ。
こうして会えばみんな高校生だもん」
「そうね。来て良かった」
「ねぇ、宇野」
「何?」
「俺達、付き合わないか?」
「えっ?」
突然の正人の告白に千春が明らかに強く動揺をしている様子が見えた。
「ごめん。こんな流れじゃ軽過ぎるよな。
それにもう恋人くらいいるよね?
ごめん。忘れてくれ」
「忘れない・・・」
「えっ?」
今度は正人が驚く番だった。
千春は改めて正人を見ると言った。
「良いよ」
恋人と初めて過ごすクリスマス。
それは恋人達にとっては特に特別な一日だ。
一ヶ月後に控えたクリスマス。
それは正人と千春にとっても
付き合い始めてから初めて迎えるクリスマスだった。
当然、正人は力が入っていてあれこれと計画を練るのだが
何を言っても千春はのらりくらりと曖昧な返事しか返さなかった。
仕事を終えた二人はいつものカフェで待ち合わせていた。
「千春、イブの夜は仕事は何時頃に終わる?」
コーヒーを一口飲むとカップをテーブルに置いて正人は訊いた。
「んー、まだ分からないよ。銀行はクリスマスとか関係無いし」
アイスティーのストローをかき混ぜながら千春は答えた。
「そうだけどさ。でも、早めに予約をしておかなきゃ良いレストランとか取れないよ。
ねぇ、レストランは何処が良い?
やっぱりイタリアンかな? うん、少なくともクリスマスに中華はないな」
「良いよ、レストランなんて別に。
正人の部屋で私が何か作るよ」
「それじゃいつもと同じじゃん?
何か特別感が無いよ」
正人は『又か』と言う体で口を尖らせた。
「じゃ、プレゼントは? プレゼントは何が欲しい?」
「良いよ。一年目の給料なんだから無理はしないで」
「いやいや、そうだけどさ。
千春の誕生日とクリスマスだけは特別な日だし
何もって訳にはいかないよ。
それにほらっ、少しだけどボーナスだって出るしさ」
「貯金しておきなよ」
「それはちゃんとしてるよ。
まぁ、偉そうな事をいえる程じゃないけど・・・
ねぇ? クリスマスだよ」
正人は千春を見て言った。
有無を言わせない強い視線で。
「・・・」
千春は答えなかった。
しばしの沈黙が二人の間に横たわっていた。
「せめてプレゼントくらいはさせてくれよな。
一緒に過ごす初めてのクリスマスなんだからさ」
「ありがとう・・・でも、ホントに・・・」
千春が言いかけた言葉を遮って正人は声を上げた。
「いや、良くないよ!」
「シー、皆に聞こえるよ」
千春は人差し指を立てて自分の唇に近づけると
こっそりと覗き込むように周りを見渡した。
「あっ、ゴメン・・・つい。
でもさ。ディナーはいらないプレゼントもいらないじゃ
俺はどうしたら良いんだい?
千春にただ喜んで欲しいだけなのにそれもダメなのかい?」
千春は困ったような顔をして俯くだけでそれには答えなかった。
正人は一人納得出来ずにいてそれに続けるべき言葉を探しながら窓の外を見ていた。
『何で千春はこうも拒むんだろう?』
せめてその理由が知りたかった。
二人の間に流れていた重苦しい空気を何とか振り払いたくて正人は言った。
ただそれは千春が一番困る言葉だったらしい。
「ねぇ? 教えてくれないか? どうして・・・」
その言葉に顔を上げて千春は笑顔を見せると言った。
それは明らかに無理をして作った笑顔だった。
その証拠に千春の瞳は今にも涙が溢れそうに潤んでいた。
「ゴメンね。そろそろ帰らなきゃ。
お母さんに今夜は早めに帰るって言ってあるから」
「あっ、じゃとりあえず出ようか。駅まで送るよ」
「ううん、ここで良い。それじゃ又、連絡をするね」
「あ・・・あぁ」
そそくさと千春は席を立つと一度も振り返らずに店のドアを開けた。
その後ろ姿を見送りながら席を立てずにいた正人は
やおら気が付くと慌てて会計を済まして店の外に飛び出した。
だが、街を行き交う人の群れがあるだけで千春の姿はもう何処にも見えなかった。
「やはりまだ気にしているのか・・・」
店の前で立ちすくんでいると後ろから声がした。
振り返ると4~50代くらいだろうか?
紺色のスーツに年代には似つかわしくないような
少し派手目のオレンジ色のレジメンタルタイ。
その上から黒いコートを着た中年の紳士が立っていて
偶然だろうか千春が去ったであろう駅に向かう道を眺めていた。
正人は思わず声をかけた。
「あの・・・千春の事をご存じなんですか?」
すると、その紳士は驚いたような顔をしてこっちを見た。
「あの、違っていたらごめんなさい。
今、彼女を見送っていたところだったもので。
いや、それは正確じゃ無いな。彼女が去ったであろう方向を・・・
ん、何を言ってるんだ俺は?」
紳士は微笑むと言った。
「ちー・・・いや、千春ちゃんね?
昔からのちょっとした知り合いなんだ。
そうそう、このネクタイ私にはちょっと派手だろ?
実はね、千春ちゃんからのプレゼントなんだ」
「ホントですか? じゃ、親戚の方とか?」
「まぁ、そんなところかな」
「そうだったんですか。
あの・・・俺、いや僕は川田正人と言います。
あの、高校時代の同級生で千春・・・
いや、千春さんとお付き合いをさせてもらってまして・・・
あっ、付き合うと言ってもまだ半年も経っていないんですけど・・・」
「あはは、君は良い子だね。素直な好青年だ」
「あっ、ありがとうございます」
しどろもどろな正人に紳士は笑顔で応じてくれた。
正人はふと、さっき紳士が言っていた言葉を思い出した。
「そう言えば、さっき何か言ってましたよね?
『まだ気にしているのか?』みたいな。
それってどういう意味なんですか?」
紳士は顎に手を当てると少し考えて、それから千春の父親の事を話し始めた。
「千春ちゃんのお父さんが亡くなっているのは知っているのかな?」
「えぇ、詳しくは聞いてはいませんが。あの・・・あまり喋りたがらないので」
「うむ。そうか・・・そうかも知れないな」
「ちー、クリスマスプレゼントは何が良い?
まだ店はやってるかな?
何か見て行こうか?」
受験生にはクリスマスも正月も関係ない。
クリスマスイヴの夜八時。
迎えに行った千春の塾の帰りの車内でお父さんは言った。
「ねぇ、お母さん。
今年のクリスマスプレゼントはジョニーズのコンサートDVDが良いな」
「ちーちゃん、あなた受験生なんだよ。
判ってる? クリスマスも何もないでしょ?
大学に受かったら、ちゃんとお祝いしてあげるから
今は勉強だけ頑張りなさい」
「ちぇっ」
そうは言ってもクリスマスは別だ。
千春は口を尖らせた。
サンタさんはもうとっくに信じてはいないけど
でも、クリスマスプレゼントはクリスマスにもらってこそプレゼントであり
子供にとってクリスマスの夜はそれだけ特別な夜なのだ。
それは高校生になったって同じだ。
いくら普段は子供扱いされる事を嫌っていたとしても
クリスマスとなれば話は別なのだ。
ジョニーズは千春が吹奏楽の次に愛して止まない今や日本一のアイドルグループで
ファンクラブの会員でさえコンサートチケットを取るのは至難の業と言われていた。
ましてや地方に住んでいたらコンサートなど夢の又、夢だった。
せめてコンサートDVDを観る事だけが唯一の出来る楽しみだったのだが
そのDVDも高校生に取っては簡単に買える値段でもなかった。
誕生日かクリスマスでもなければねだる事も出来ないのだ。
そんなお母さんとのやり取りを聞いていたお父さんが
塾に迎えに行った帰りにこっそりと千春に訊いたのだ。
「ちー、プレゼントは何か良い?」
でも、その時の千春は
家で待っているお母さんの顔がチラついていて
それを心の中でかき消すようにそっけなく答えた。
「今はいい」
「そっか、そしたら今度街に出た時にでも何か買ってやるよ。
お母さんに内緒でな」
お父さんは助手席の千春をチラッと見るとそう言ってほほ笑んだ。
その二日後だった。
お父さんは仕事中の交通事故で還らぬ人となった。
運転中にスマホを操作していた相手の車が反対車線をはみ出して
お父さんの運転する車に正面から突っ込んで来たのだ。
グシャグシャに潰れた車の助手席の足元には赤いリボンの付いた包みが転がっていた。
それは数日前に千春がお母さんにねだっていたアイドルのコンサートDVDだった。
もし、お父さんがDVDを買いに行かなかったら
事故には遭わなかったんじゃないのか?
千春は人知れず自分を責めた。
その事もあったのか、お父さんが亡くなった事で
家計の心配もあって千春は進学をせずに就職をした。
勉強が手につかなかった事ももちろん大きかったのだが
それよりも心に抱えた傷が大き過ぎたのだろう。
お母さんは学費の心配はしなくて良いと言ってくれてはいたが
それを許せない自分がいたのだ。
「そんな事が・・・」
「あれから千春ちゃんにとってクリスマスが哀しい日になってしまったんだ。
可哀想に・・・」
正人は言葉を失くした。
「ちーのせいじゃないのに・・・」
男はぽつりと呟いた。
その言葉に気付かずに正人は今までの千春と事を思い出していた。
初めてのデート、初めての千春の誕生日、それ以外でもお互いに仕事が忙しくて
1ヶ月ぶりにデートをした夜とかは
ちょっと無理をしてイタリアレストランを予約したり、ささやかながらプレゼントも用意した。
そして、千春は本当に嬉しそうに笑顔を振りまいてくれた。
だから、当然初めて一緒に過ごす事になるクリスマスも
それ以上豪華にとは出来ないまでも、少しでも千春に喜んでもらいたかった。
今では千春の笑顔を見るのが正人にとっては何よりかけがいのない喜びになっていたのだ。
だが、ことクリスマスのプランに関しては
千春の態度は正人の予想をはるかに裏切るものに終始していた。
正人がいくら千春に訊いても千春は曖昧に言葉を濁したり話をはぐらかせたりするばかりで
ただ、言いようの無い不満が溜まるだけで正人はその理由がまるで理解出来ないでいた。
その理由が今夜ふとした事から解明される事になった。
理由を知ってしまった以上、もう千春に対する心のモヤモヤも失せたし
ましてや知らん顔は出来ないと思った。
「でも、何て声を掛けたら良いんだろう?」
ふと見ると男はただ静かに立ち尽くし千春が去ったであろう方向に視線を向けていた。
正人は男に声を掛けた。
「あの・・・」
男は急に我に返ったように半分驚いたような顔で正人を見た。
「あぁ、すまない。ちょっと考え事をしていたようだ」
「はい、僕もです」
「そうか。何だか似たもの同士みたいだね」
男はそう言うと無理をして作ったような、そして何処か寂しそうな笑顔を見せた。
正人はふと『何処かで見た事がある笑顔だな』と思った。
すると男は改めて正人を正視すると真顔で訊いた。
「君は・・・正人君と言ったね? 君は本当に千春ちゃんの事を愛しているんだね?」
「はい。もちろんです!」
正人も男の目を真っ直ぐに見返して言った。
「キレイな良い目をしている。君なら千春ちゃんを変えられるかもしれないな」
「はい。何とかしてあげたいです。でも、どうしたら良いのか・・・」
「うん。もしかしたらずっと長い時間だけしか千春ちゃんを変えられないのかもしれない。
もしかしたら時間でさえも千春ちゃんを変えられないのかもしれない。
それは私にも判らないけど、でも今、私は真っ直ぐに人を見る事の出来る
君のその純粋な心に掛けてみたいと思っている。
千春ちゃんは今こそ真実を知らなきゃならない。
そうしなきゃ千春ちゃんはいつまで経っても哀しいクリスマスを迎え続けなきゃならない。
それは不幸だとは思わないかい? 私は千春ちゃんに幸せになって欲しいんだ。
クリスマスだけじゃなく他の他愛もない普通の日でさえもね」
「・・・」
正人は自分でも驚くほど素直に、そして真剣にさっき会ったばかりの男の言葉に聞き入っていた。
それだけの男の想いが今、正人にはビシビシと伝わっていた。
一呼吸置いて柔らかな口調に戻ると男は訊いた。
「真実が真実として相手に伝わる為には何が必要か判るかな?」
「どれだけ真剣に伝えられるか・・・ですか?」
「うん。でも、それは一番じゃ無い」
「じゃ、どうしたら?」
「どれだけ相手に信頼をされているのか。そこに尽きると思うんだ。
信用だけじゃ弱い。信頼なんだよ。判るかい?」
「信頼・・・ですか?」
「あぁ、そうだ。愛でも信用でもない。
どれだけ信じても絶対に相手に裏切られないという信頼。
どうだい? その意味で、君は千春ちゃんに信頼されていると思うかい?」
「それは・・・そこまでの自信はまだありません。
でも、僕は千春を信頼しています」
「そうなんだ。実はそこが一番大事なんだよ。
それを聞いて安心したよ。
正人君、今度千春に会ったら今夜の話をしてもらえないだろうか?
お父さんが亡くなったのは決して千春ちゃんのせいじゃないという事を」
「でも、あなたは千春とは近しい方なんですよね?
その時の事情を知らない僕よりはあなたの方が相応しいんじゃありませんか?」
「そうだね。私も出来るなら自分の口からちゃんと千春ちゃんに伝えたいんだけどね。
でも、訳が有って今は千春ちゃんの家族とは疎遠になってしまっているんだ。
今更、ノコノコと出て行ったって端っから信用すらされるとは思えない」
「そうですか・・・判りました。千春に話してみます。
因みに、千春のお母さんとかも知らないんですか?」
「あぁ、多分ね。なんせ突然だったからね」
「じゃ、どうしてあなたは知っているんですか?」
正人はふと浮かんだ疑問を男にぶつけた。
男は少し考えるように視線を通りに向けた。
「電話をね。そう、事故の前日に電話をもらったんだ。
アイドルのDVDだっけな。駅前の店に行ったら売り切れだったらしくてね。
それで何処か他の店を知らないかってね。
駅からは少し離れているんだけど1件、知っていた店を話したらすぐに電話が切れてね。
その30分くらい後だったかな。又、電話が来たんだ。
買えたってね。そりゃ嬉しそうに話してたよ。
中年の男がアイドルのDVDだなんて恥ずかしかったなんて言いながらもね。
だから、あのDVDは事故の当日に買ったものじゃないんだ。それは間違いない」
そう言うと、それから男は又、正人に視線を向けると強く言った。
「だから、あの事故も千春ちゃんのせいなんかじゃないのさ。
事故の事は忘れろと言うのは無理かも知れないけど少なくとも気に病まなくても良い。
千春ちゃんは千春ちゃんの幸せを掴んで欲しい。
それだけを心から願っている男がいる。
それを君から伝えて欲しい。頼むよ」
そう言うと男は頭を下げた。
「でも、何て話したら・・・僕なんかが言っても信じてもらえるでしょうか?」
「もし、千春が信じなかったら、こう言って欲しい。
『千春の小学校の入学式のお祝いに
千春が欲しがっていた大きなテディベアを買ってくれたオジサンから聞いた』ってね。
実はぬいぐるみにしてはあまりに高価だったから妻にも内緒でね。
千春ちゃんにもおじいちゃんから買って貰ったって言えって言いくるめたんだ」
「それで判りますか?」
「千春ちゃんが君を信頼していたらね」
そう言うと男は優しく微笑んだ。
正人は心に強く決心をすると答えた。
「判りました」
「うん。ありがとう。君ならきっと大丈夫だ。
それじゃ、私はここで失礼するよ。ちょっと約束があってね」
「はい。ありがとうございます」
男は軽く会釈をすると駅とは反対の方に歩いて行った。
そして、本当に消えるように街行く人並みの中に紛れたかと思うとすぐに消えて行った。
その夜、正人はずっとベッドに横たわりながら真っ黒な画面のスマホを眺めていた。
何度も電話をしようとは思いながら、千春の電話番号を押せずにいたのだ。
『なんて切り出したら良いんだろう?』
言いたい事や言うべき事は十分に判っている。
でも、突然電話をして『千春のお父さんの事故は千春のせいじゃない』
そう言ったところで素直に信じて貰えるとは思えなかった。
『やっぱ、唐突過ぎるよな・・・』
確率は極めて低いけど仮に話の流れでたまたまお父さんの話になったとしても
だからと言って、事故の原因がどうとか言う話には出来ない。
取って付けたように話をしたって、せいぜい同情で言っていると思うに違いない。
そう思うと、なかなか電話が出来なかったのだ。
溜息も何度目だったろうか。
時計の針が深夜を指した時、突然メールの着信ランプが光った。
「あっ、千春だ!」
正人は慌てて起き上がるとスマホを立ち上げてメールを読んだ。
<正人、今日はごめんね。気を悪くしてるよね?
今度、時間のある時に必ず話をします。でも、少し時間を下さい。
愛しています。千春>
正人はすぐに千春に電話をした。
コールが1度鳴ったと思ったらすぐに千春が電話に出た。
「千春・・・」
そう言う正人に千春は申し訳なさそうに答えた。
『ごめんね。起こしちゃった?』
「いや、起きていたよ。何か眠れなくってさ」
『ごめん・・・』
「違うんだ。考え事をしていたんだ。
いや、今夜の事じゃない。今までの色んな事・・・
俺、千春の事が好きだ。すっごい好きなんだ」
『何よ、取って付けたみたいに。でも、嬉しい』
「クリスマスはさ。一緒に居られたらそれで良いよ。
俺のボロアパートでも千春が良いならさ。
ディナーもプレゼントもどうでも良い。
だから、話したくない事は無理して話さなくても良いよ。
いつか、聞いて欲しいなって思ったら話してくれたらそれで良いよ。
思ったんだ。クリスマスは何処で過ごすかよりも誰と過ごすかの方がずっと大事なんだって」
『ありがとう・・・』
電話の向こうの千春の声は涙ぐんでいるように聞こえた。
正人は<真実>を話すタイミングを完全に失ったと思った。
でも、今はまだそれで良いようにも思えた。
男との約束を破るつもりではない。
ただ、今はまだ<その時>ではない・・・そう思ったのだ。
『正人?』
「ん? あぁ、ごめん。聞いているよ」
『何も言ってないよ』
「あぁ、そっか」
正人はそう取り繕うと笑った。
電話の向こうで千春が続けた。
『もし、もし良かったらね。クリスマスイブは家に来ない?』
「千春の家に?」
『うん。正人の事をお母さんに話したらね。
お母さんが<クリスマスに二人っきりはふしだらだから家に連れて来なさい>って言うの。
今まで、正人のアパートに泊まった時だってそんな事は言った事はなかったのにね』
そう言う千春は楽しそうに笑った。
『きっとね。お母さん、正人に会いたいのよ』
「俺に? 品定めをされるのかな? それとも取り調べ?
<お前は本当に千春を愛しているのか?>とか?
<愛しているなら証拠を見せろ!>とか?」
『うふふ、まさか。でも、もしそうだったら正人は何て答える? それとも逃げ出す?』
「まさか! お母さんの目の前で千春にキスをするよ。
どれだけ愛し合っているのか見せつけようよ」
『いやよ、そんなの。恥ずかしいわ』
「あはは、そんな事するか! 俺の方が恥ずかしいわ」
『でも、何かあったのかな? 急に言い出したのよ。<正人君を連れておいで>って』
「千春の事が心配なんだよ。何処のどんな馬の骨と付き合っているのかね」
『でも、今まではそんな事は一度も言った事が無かったのよ。
誰だろうと、もう大人なんだから自己責任で付き合いなさいって言ってたのに』
「タイミングかもね」
『タイミング? 何?』
「いや、何でもないよ」
正人はふとさっき会った男の顔が浮かんだ。
『どうしてだろう?』
クリスマスイブの夜。
正人は早めに仕事を切り上げると駅前のケーキ屋に寄って
予約をしていたデコレーションケーキを受け取ると千春の家に急いだ。
駅から五つ目のバス停で下りて
二日前に千春と会った時に渡された手書きの地図を見ながら方向を定めた。
「こっちかな」
辺りは住宅街のせいか駅から少ししか離れてはいないのに
クリスマスイブの夜まだ7時だというのに通りを歩いている人もほとんどいなかった。
皆、もうそれぞれの<場所>でクリスマスを楽しんでいるのかな?
そんな事を何となく考えながら地図の通りに歩いていた。
コンビニの角を曲がり、古い赤提灯がぶら下がっている小さな居酒屋の前を抜けると
その先に目印の理髪店のサインポールが見えた。
この角を曲がるとすぐ左手にある4階建てのマンションの2階が千春の家だ。
マンションの前まで来ると正人は2階を見上げ、ひとつ大きく深呼吸をした。
初めて訪れる<彼女>の家は
誰だって緊張をするものだが正人とて例外ではなかった。
正人はマンションの入り口のガラス扉に映った自分を見てネクタイの曲がりを直し
それから髪を二~三度撫でてから意を決したようにその扉を開けた。
「いらっしゃい、正人!」
玄関を開けるといつにも増して抜群の笑顔で千春は俺を迎えてくれた。
「メリークリスマス! お邪魔するね」
俺はそう言って手に持っていたクリスマスケーキを千春に手渡した。
両手に抱えたケーキを左の小脇に抱え直すと千春は右手で正人を引き寄せ軽くキスをした。
「おいおい、マズいよ」
ここは正人のアパートではなく千春の実家だ。
いつになく積極的な千春に正人は少しドギマギしていた。
「オホン!」
「えっ? お母さん、イヤだぁ-、もう!」
開いていた居間の戸の向こうでお母さんが腕組みをしながらニヤニヤと二人を見ていた。
そして言った。
「そんな所じゃなんでしょ? さぁ、入って」
母娘揃っての奇襲攻撃に先制パンチ。
まさにそんな状況に
正人が初めてお母さんに会った時に言おうと練習していた言葉は全て吹っ飛んでいた。
玄関を上がり正人がコートを脱ぐとすぐに千春が手を出してそれを受け取ると
丁寧にコート掛けに掛けた。
「あっ、ありがとう」
「どうぞ。狭い所だけど」
千春に促されて居間に入るとテーブルの上には豪華な料理が所狭しと並べられていた。
「凄い豪勢な料理だね。でも、何人分?」
そう言って千春を見ると千春は横目でお母さんの方を促した。
「あっ、いけね。オホン」
正人はひとつ咳払いをすると絨毯の上で正座をしてお母さんの方を見た。
「あの、今夜はお招き頂いてありがとうございます。
俺・・・いや、僕は千春さんと・・・」
正人が言いかけた途中でお母さんは笑顔でそれを遮った。
「良いのよ、そんな堅苦しい挨拶は。我が家の家訓にはないから」
そう言ってお母さんは笑った。
「正人さんね? 千春から良く話は聞いています。凄い良い人だって」
「いえ、そんな・・・とんでもないです。僕の方がいつもお世話になってまして」
正人のそんな言葉にも構わずお母さんは続けた。
「千春の母の美智子です。皇后陛下と同じ名前、凄いでしょ?」
「はぁ」
正人が戸惑っていると千春が助け船を出した。
「ねぇ、お母さん。いつまで正人をそんな所に座らせておくつもり?」
「あら、いけない! さぁさ、こっちに来て座ってちょうだい。
いやぁねぇー全く気が付かないもんだから。ごめんなさいね」
「いえ」
この母にしてこの千春在りか?
お母さんの話のスピード、展開にも千春は負けていない。
「さぁ、正人。こっちに来て座って。ジャケットはソファにでも置いておいて。
後でハンガーに掛けて置くわ」
千春はそう言うと正人の腕を取ってテーブルの正面に招いた。
豪華な料理が並んだテーブルを三人で囲んだ。
千春がシャンパンの栓を抜くと正人とお母さんに注ぎ、それから自分のグラスにも注いだ。
「何か、嬉しいわね。こんな賑やかな食卓は久しぶりよね。
いつもは千春と二人か千春がいないと私一人だから」
お母さんがしみじみと言った。
千春がシャンパンの入ったグラスをお母さんの目の前にかざすと乾杯の催促をした。
「はいはい。えーっと。正人さん、ようこそ我が家へ。
大した物は何も無いけど、ゆっくりしていってね」
「はい」
「それじゃ、正人さんと千春と、ついでに私の為に乾杯-!」
「お母さん、クリスマス!」
「あら。じゃ、そういう事で乾杯!」
お母さんは舌をぺろっと出して笑った。
「乾杯-!」
「乾杯!」
「正人さん、たくさん食べてね。
食べてきって貰えないとお正月まで我が家の食卓は残り物になっちゃうから」
「お母さん!」
「あっ、はい。頂きます。それにしても凄いご馳走ですね」
「お母さんが昨夜から腕によりをかけて頑張ってたからね」
「あれ? 千春は?」
「私は味見と配膳担当なの」
千春はそう言って笑うと舌をぺろっと出した。
やっぱり似た者母娘だと正人は思ったが、むしろそれが微笑ましかった。
「じゃ、正人さん。ゆっくりしていってね。
全部食べていってね。残したら罰金が高いわよー
あっ、ケーキだけは少し残しておいてね」
お母さんはそう言ってテーブルを立ち上がると居間の隣の部屋に入っていった。
隣の部屋からお鈴をならす音が二度聞こえた。
するとすぐにお母さんは部屋から出て来たがその腕にはハンドバッグが抱えられていた。
「お母さん? 何処かに行くの?」
「えぇ、言ってなかった? これからテニスサークルのメンバーとクリスマスよ。
お食事と二次会は又、カラオケかな。それから何処に行こうかなぁー。
若い人は若い人同士、オバサンはオバサン同士よ。
そうそう! 正人さん、何なら泊まって行って良いわよ。
きっと朝まで帰らないから。それじゃね。そうそう、戸締まりだけはよろしくね」
お母さんはそう言うと鼻歌を歌いながら居間を出て行った。
正人と千春は呆気に取られてお母さんの後ろ姿を見送っていた。
正人は目の前のテーブルいっぱいに並べられたご馳走を改めて一瞥すると訊いた。
「ねぇ、これって何人分?」
「決まってるでしょ? 正人、一人分よ」
千春はすましてそう言うとグラスのシャンパンを飲み干した。
「ねぇ? お母さん、俺達に気を遣ったのかな?
だとしたら、悪い事をしたなぁ-」
「まさか。正人を家に呼んだらって言い出したのはお母さんなのよ。
でも、変なのよね。あの夜、帰ったらお母さんが珍しくボーっとしてソファに座っていたの。
最初、ただいまって言っても返事もしなかったのよ。
で、二度目にただいまってお母さんの耳元でわざと大きな声で呼んでみたらね。
そしたら急に我に返ったように私を見ていきなりよ。正人さんを呼んだらって言ったの。
何だったんだろう? 変よねー。なのに自分はハイ、さよならみたいに出掛けちゃって」
「それっていつの事?」
「いつだっけ? あっ、そうそう! この前、いつものカフェで正人に会った後よ」
「あの後で? んー、何だろう?」
「何?」
「判らない・・・」
「何よ。もったいつけて」
「そうじゃないよ。何か引っかかってるんだけど・・・それが何か判らないんだ」
正人の心の中で見えそうで見えない<何か>がモヤモヤとなって答えを隠していた。
後、ひとつ何か<ピース>が埋まれば、それは見えてくるような気がしていたが
今の正人にはその手がかりさえも知る由もなかった。
「あっ、そう言えば」
正人は急に大事な事を思い出した。
「何?」
「いや、全然関係無いんだけどさ」
「何?」
怪訝そうに千春は訊いた。
「そう言えばさ。俺、まだお父さんに挨拶してない。
お父さんの仏壇があるんだよね? さっき、お母さんが出がけにお鈴を鳴らしていたよね?」
「うん、でも後で良いよ。ご飯まだ途中だし。食べてからで」
「でも、思い出した時に挨拶しておかないと何だか落ち着かないよ。そっちの部屋?」
「そうだけど。でも、そんな事を気にするお父さんじゃないよ」
「いや、俺が気になるんだ。ちょっと挨拶をさせてもらっても良いかな?」
そう言うと正人は立ち上がった。
千春も渋々立ち上がると隣の部屋の戸を開いて中の電気を点けて仏壇の斜め前に座った。
正人はネクタイの緩みを直しジャケットを羽織ると一礼をしてその部屋に入った。
それから仏壇の前に正座をし、ろうそくに火を灯し線香を点けると二度お鈴を鳴らした。
そうして正人は仏壇の前で静かに手を合わせた。
「はい。もう良いでしょ? いきなりできっと、お父さんもすごい緊張しているわ。
そろそろ解放してあげましょ」
あまりに真剣に手を合わせている正人を見て、そう言って千春は笑った。
「いや、そんなつもりじゃ・・・」
その時、ふと仏壇の斜め上に掛けられていたお父さんの遺影に目をやった正人は我が目を疑った。
「えっ!?」
「どうしたの?」
「これ・・・この人がお父さん?」
「えぇ、そうよ。どうして? そんなに私に似てない?」
「いや・・・そうじゃなくて・・・」
遺影に写っていたのは紺色のスーツに年代には似つかわしくないような
少し派手目のオレンジ色のレジメンタルタイを締めた<あの時>の紳士だった。
「そんな事って・・・」
正人は混乱していた。
『どうして、あの時の人が遺影に? それじゃ、あの時に俺が会った人は?』
「ねぇ? どうしたの?」
「えっ? あっ、あぁ・・・」
千春の声に正人は我に返った。
混乱の中で正人がそこに見つけた<答え>
だが、その答えを受け入れるには正人の頭の中は全く整理されていなかった。
むしろ余計に混乱をするだけだった。
「正人。ねぇ、正人ってば。変よ?」
尋常じゃ無い正人の様子に千春は怪訝な顔を見せた。
「ねぇ、千春。このネクタイって他の人にも贈った?
例えば、お父さんとお揃いで誰か伯父さんとか」
「ネクタイ?」
「あぁ。お父さんが締めているオレンジ色のネクタイだよ」
「これ? ううん。でも、どうしてこれが私が贈ったネクタイだって知ってるの?」
「やっぱり・・・」
「やっぱりって?」
「いや・・・」
そう言ったきり正人は黙り込んだ。
何度考えても、何をどう考えたとしても
その混乱の正体を整理する為には、いや、整理させる為に出せる答えはひとつしかなかった。
正人は大きく深呼吸をすると千春を見た。そしてゆっくりと語りかけた。
「ねぇ? 信じられないかもしれないけど。いや、俺だって信じられないんだけどさ」
「何? 急にどうしたの?」
「いや、ちょっと待ってくれないか・・・上手く説明が出来ない」
「何よ、ひとりで何を言ってるの? 判るように言って。正人らしくないわ」
正人はひとつ溜息をついた。
正人には何をどう言えば良いのか検討もついていなかった。
だが今、正人には判った事があった。
どうして今夜ここに来たのか? 来る必要があったのか?
そして、どうしてお母さんが正人を呼んでおきながらさっさと退席をしたのか?
お父さんとお母さんが正人に託したかった想いとは?
後はもう、あの人が言った言葉を信じるしかないと思った。
<千春ちゃんが君を信頼していたらね>
正人は改めて大きく息を吸い込んで深呼吸をした。
そして千春を真っ直ぐに見つめると静かに話を始めた。
「ねぇ。多分、こんな話は信じて貰えないと思う。
だけどね。俺が話し終わるまで黙って聞いていて欲しいんだ」
千春は正人の真剣な眼差しに答えるように畳の上で座り直した。
「実はね。この前、あのカフェで千春と別れた後でお父さんに会ったんだ」
「えっ? 誰って言った?」
「この遺影に写っている人。つまり君のお父さんだったんだと思う」
「そんな事! 有り得ないわ!」
千春には突然の正人の言葉は悪い冗談にしか聞こえなかった。
「質の悪い冗談は止めて! 正人だって怒るわよ」
千春は一気に立ち上がると強い口調で正人を諫めた。
「判ってる。俺だってつい今までそんな事は思いもしなかったんだ。
千春。座ってとりあえずは俺の話を最後まで聞いてくれよ」
合点がいかない様子を見せながらも千春は又、その場に座り直した。
正人はあのいつものカフェで千春と別れてからの男とのやり取りを
一言、一言、正確に思い出しながら千春に話し始めた。
話を聞きながら千春は何かを堪えるように膝の上に乗せた拳を強く握っていた。
正人は千春の目を一心に見つめながら精一杯の真剣さで男が話した内容を
そして男がどうしても千春へ伝えたかったと正人に託したあの想いを話した。
「だから、お父さんの事故は決して千春のせいなんかじゃなかったんだよ。
それをどうしても千春に伝えてくれとお父さんは俺に言った。
そして千春には幸せになって欲しいんだとね。
クリスマスだけじゃなくて他愛の無い普通の日も」
正人は男が託した想いを話し終えても尚、千春の目に必死で訴えかけた。
二人の間に重い沈黙の時間が流れた。
しばしの沈黙の後、先に口を開いたのは正人だった。
「さっきね。遺影のお父さんを見て、それがこの前の人だと判った時に全部繋がったんだ」
「・・・」
「きっと、いや、もしかしたらだけどね。
お母さんの夢枕にかどうかは判らないけど、きっとお父さんが同じように現れて
お母さんに俺に話をしたような事を話したんじゃないのかな? なんてね。
そしたら、急にお母さんが俺を家に呼んだ事も理解出来る気がするんだ」
「ひどい!」
膝の上に乗せた拳を更に強く握ると俯いた千春の目からは大粒の涙が止めども無く溢れた。
「千春・・・」
正人は千春を引き寄せると強く抱き締めた。
だが、それに構わずに千春は泣きながら正人に抗議をした。
「嘘! みんな嘘ばっかり! 正人もお母さんも嘘ばっかり!
どうせ、お母さんと相談してそんな話をでっち上げたんでしょ?
ひどいよ、みんな・・・ひどい・・・」
「千春! 違うよ」
正人は千春の両肩に両手を掛けると千春の目を見て否定した。
「違う。信じてくれ。千春の事を想う人はたくさんいたって千春を陥れよう何て人はいない。
そうだ! その人はこうも言っていたんだ」
千春は頑なに心を閉ざすかのように流れる涙も構わずにいっそう目を強く瞑った。
「千春。小学校の入学式のお祝いを覚えてる?
その人はこうも言ったんだ。もし、千春がどうしても信じてくれなかったら
千春の小学校の入学式のお祝いに
千春が欲しがっていた大きなテディベアを買ってくれたオジサンから聞いたって言ってくれって。
それって、お母さんに怒られるから
お父さんがおじいちゃんから買って貰った事にしなって言ってなかった?」
その言葉に反応するかのように千春は顔を上げた。
「嘘でしょ? 本当にお父さんだったの?」
千春は驚きを隠せないでいた。
「そんな事・・・そんな事って・・・」
「やっと信じて貰えたかい? お父さんの事故は千春とは関係なかったんだ。
だから、これ以上気に病んでいつまでも哀しみばかり背負っていたらお父さんが悲しむよ」
「やっぱりひどい・・・」
「えっ? だからそれは・・・」
「お父さん、やっぱりひどいよ・・・
正人の所やお母さんの所にだけ現れてどうして私のところには一度も現れてくれなかったの?
私、何度も何度も夢でも良いから出てきて下さいってお願いしていたのよ。
なのに、一度も・・・夢にも出てきてくれなかった・・・」
「それは、お父さんが本当に千春を愛していたからじゃないのかな?
今の千春の前にお父さんが現れても千春を苦しめるだけだと思ってたんだと思うな。
だから、千春が呵責の念から解放されて自分から幸せを掴む気持ちになったら
きっといつか、お父さんは千春に会いに来てくれるよ」
「お父さん・・・会いたいよぉ。もう一度、夢の中でも良いから会いたいよぉ・・・」
そう呟くと千春は泣きながら正人の胸にしがみついた。
正人はそんな千春を誰よりも愛おしいと思った。
そして、見上げたお父さんに誓った。
『千春を必ず、絶対に幸せにします』
その夜、正人の腕の中で千春は夢を見た。
小学校の入学式の後、こっそりとお父さんと一緒におもちゃ屋に行って買ってもらったものの
自分より大きなテディベアを『抱っこ出来ない』と泣いてお父さんを困らせたよね。
小学校六年の運動会でお父さんと一緒に走った二人三脚、転んだ私を最後は抱えてゴールしたね。
あの時は恥ずかしかったんだよ。でも、嬉しかった。
クリスマスプレゼントに必ず添えてあったお父さん手書きのカードには
『Dear My Christmas』と書いてあったけど、幼かった私にはその意味は判らなかった。
でも、今はお父さんの愛がすごく良く判る。少しは大人になったのかな私。
そうだ。中学の時は反抗期でいつも困らせていたのにお父さんは嫌な顔ひとつ見せなかったね。ごめんね。
不安だらけで迎えた高校入試の朝、緊張していた私を下手なオヤジギャグ連発で笑わせてくれたよね。
高校合格が決まった日は三人じゃ食べきれないくらい大きなケーキを買って帰ってきたっけ。
あの日はなんかいつもよりすごい早く帰って来たよね。
私がふざけて『こんなに早くて会社クビになったの?』って言ったら
『クビになったくらいじゃこんなに早く帰って来ない』なんておどけてた。
吹奏楽部のコンサートや塾の送り迎え、その合間に交わした他愛もない会話。
考えたら、あの頃はいつも無愛想な受け答えしかしてなかったね。本当にごめんね。
私、どんなに大きな愛に包まれていたんだろう?
あの頃は思いもしなかった。
それでも、お父さんはいつもたくさんの愛で見守ってくれていたんだ。
それは今でも変わっていなかったんだね。
どんなに謝っても悔やんでもお父さんはもう帰っては来ないけど
でも、お父さんはきっと判ってくれているなんて又、甘えても良いかな?
今の私にとっての『Dear My Christmas』それは正人です。
お父さんに負けないくらい大きな愛をくれる人。
もちろん、クリスマスだけじゃなく、ごく平凡な普通の日でも。
正人ならお父さんともきっと良い親子になれたんだろうな。
お父さんもそう思ってるでしょ?
いくつもの想い出がその夜に限っては部屋中に溢れてもまだ足りないくらいたくさんたくさん溢れ続けた。
フラッシュバックした想い出の次に現れたのは
みんなに祝福をされてウェディングロードを歩く正人と千春の幸せそうな笑顔の姿だった。
そして祭壇の一番前で二人を見守っていたのはハンカチを握り締めて涙ぐんでいるお母さんと
その隣で静かに微笑んでいるお父さんの姿だった。
『お父さん・・・ありがとう』
正人の温かな腕の中に包まれながら千春の目には幸せの涙が光っていた。