
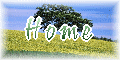
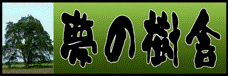
星のクロスロード
普段は見知らぬ電話番号からの電話なんて絶対に取らない俺だったけど
あの夜、12時過ぎに疲れ切って帰宅をして
スーツを着たままでベッドに倒れこむように爆睡をしていた俺は
つい無意識で明け方に着信したその電話を取ってしまった。
「もしもし・・・」
俺の頭は全く働いていなかったが身体が勝手に反応をしたんだろう。
『ねぇ? どうしても別れなきゃダメ?』
耳元のスマホの遙か遠いところで聞えてきたのは
泣きながら問いかけてくる女の声だった。
『ねぇ? タカシ、聞こえているんでしょ?
答えてよ、ねぇ?』
他人の痴話ゲンカに首を突っ込むほど俺はお人好しじゃない。
まして、俺は疲れて切っていたのだ。
「良いんじゃない、別に」
寝惚けていた俺は適当な返事をした。
とにかく早く眠りに戻りたかったのだ。
『ホント? タカシ、良いの?
すぐ行くわ! ねぇ、これから行って良い?』
「好きにすれば?」
そう言って俺は電話を切るとスマホをベッドの足下に放った。
出来るだけ自分の耳元からスマホを遠ざけたかったのだが
寝惚けていた俺にはそれが精一杯の抵抗だった。
久しぶりの休みだったのだ。
俺は目覚ましすらかけずに目が覚めるまで寝ていようと決めていた。
そんな俺を叩き起こすかのように突然、スマホは派手な音楽を鳴らし始めた。
「誰だ? こんな時間に・・・部長なら絶対に電話にでないぞ・・・」
無視を決め込んでいたがスマホの着信音は何度鳴っても一向に諦めなかった。
「もう!」
足下に転がっていたスマホを半身だけ起こして何とか手探りで探し当てて
着信音をやっとの思いで止めると俺は布団を頭から被った。
すると又、すぐにスマホは鳴り出した。
「何時だよ・・・いったい・・・?」
枕元の目覚ましを見ると朝の7時を過ぎたところだった。
止めても止めても何度もスマホは鳴り続けた。
「何だ? 急用か?」
渋々、スマホの画面を見るとその電話番号は見知らぬものだった。
「何だよ、間違い電話じゃん・・・もう、いい加減にしてくれ」
それでもスマホは鳴り続けた。
どうやら、間違いだと言うことを相手に伝えない限り
鳴り止んではくれないようだ。
俺は受話ボタンを押した。
すると聞こえてきたのは見知らぬ女の声だった。
『あなたは誰よ? いったい何の恨みがあってあんな適当な事を言ったのよ!』
はぁ? まるで言いがかりだ。
「ちょっと、あなたは誰にかけてるんですか? 番号間違ってますよ」
『あなた、明け方の人でしょ?』
明け方? そういえば、夜中に誰かの電話を取った気がする。
だが、寝惚けていた俺に判るはずもなかった。
そんな事にかまわずに電話の向こうで女はしゃべり続けていた。
『あなたが良いって言ったから私は彼の部屋に行ったのよ!
そしたら、どうしたと思う?』
どうしたもこうしたも俺には知った事ではない。
『玄関のチャイムを押したら知らない女が
バスローブ一枚で出てきて
<あんた誰? あー、元カノってあんたね?
何してんだが知らないけどこんな夜中に迷惑な女ね。
そんなんだからフラれるのよ。バッカじゃない>
そう言って私を見て嘲笑ったのよ!』
「それは・・・まぁ・・・ご愁傷様・・・」
『あなたねー、ご愁傷様だなんてどうせ他人事だと思ってるんでしょ!』
って、言うか。他人事だしね。
『何? 何か言った?』
「えっ? い、いや・・・」
こいつは読心術師か?
「で、俺にどうしろと?」
『謝ってよ』
「えっ?」
『・・・』
スマホの向こうから言葉にならない嗚咽が漏れる<音>が聞こえていた。
「おい・・・何だよ、泣いてるのか?」
『・・・』
「おい・・・ねぇ。ちょっと君。落ち着いて話をしよう」
もう、いったいどうすりゃ良いんだよ?
泣きたいのはこっちだよ。
休みの日にいきなり電話で起こされて、やれ謝れだのって。
しかし、どうもこれじゃ収まりがつかないらしい。
それだけはしっかりと感じ取れた。
「判った。ごめん。俺が無神経だったよ。ホント、ごめん・・・」
『・・・』
今度はダンマリか?
と、思った瞬間だった。
『バカ! バカバカバカバカバカ、バカ!』
そう叫んだかと思うといきなり電話が切れた。
お陰ですっかり目が覚めてしまった。
「ったく、何時だよ?」
スマホの時計を見ると朝の7時半にもなっていなかった。
「まだ、こんな時間か・・・よし!」
俺は寝直すと決めた。
こんな目覚めの悪い置き方じゃせっかくの休みの朝が台無しだ。
俺はもう一度布団を頭まで被ると目を瞑った。
しかし、あの女の言葉が耳の奥で何度も繰り返し聞こえてきた。
『謝ってよ』
その言葉を遮るように俺は更に強く目を瞑った。
しかし、目を強く瞑れば瞑るほどその声は鮮明になるばかりだった。
どのくらい俺はその言葉と格闘をしていただろう?
やがて、諦めがため息となって俺の口からはみ出した。
「最悪の朝だ!」
俺はしぶしぶベッドから這い出した。
目覚めの悪い朝から始まる一日はろくな事が無い。
それを地で行くかのようにその日は最悪な一日だった。
とりあえず、朝飯を食べに行こうと決めて洗面所で歯を磨き
続けて髭を剃ろうとしたがシェービングフォームが空だった。
洗面所の引き出しを探したが、やはり買い置きは無かった。
そりゃそうだ。一人暮らしなんだから俺に買った覚えが無いなら
それは無いに決まっている。
しかたなく、ハンドソープで髭を剃る事にしたが
どうにもシェーバーの滑り心地が悪くて
そうこうしている内に口の周りがヒリヒリし出した。
やっぱりかと思ったが案の定
口の周りの2~3カ所から血が滲んでいるのが鏡越しに見えた。
「まぁ、これくらいなら絆創膏を貼るまでも無いかな?
出掛けるまでには血も止まるだろうし」
ヒリヒリする口の周りを擦りながらも
こんな事は良くある事で今朝のあの忌まわしい1件とは関係無いだろう。
そう言い聞かせている自分がいた。
「止めてくれよ」
自分で自分に言い聞かせるように俺は呟いた。
それから新聞を開き、テレビでニュースを観ながら少し時間を潰した。
休みにいつもブランチを食べに行くカフェがオープンをするのは10時。
「後、15分くらいして出掛けたら丁度良い時間だな」
マンションを出て空を見ると快晴で何処までも青空が広がって見えた。
寝起きは最悪だったけど、これで少しは気分も晴れるだろうと思った。
6月、初夏の風が気持ち良かった。
マンションの前の歩道をしばらく歩き
途中の公園を横切りながら進むと緑の芝生も木々も活き活きとして見えた。
それから駅の方に向かって10分も歩けば目的地だ。
俺は足を早めた。
と、やがて店の前に立つと店のドアには張り紙があった。
A4のコピー用紙にパソコンで打たれた文字は無情にもこう書かれていた。
<本日、都合により休みを頂きます。又のお越しをお待ちしております。店主>
「マジか・・・」
だんだん、何か嫌な予感がしてきた。
「あの女のせいだ」
八つ当たり? そうでもしなきゃ何処にもぶつけようがないじゃないか。
「それよりも、何処に行こうか?
あぁ、そういや今来る途中でやってたカフェがあったっけ。
とりあえずはそこに行くか」
来た道を10分くらい戻るとその店はあった。
確かに開いているし、中を覗くと数人の客の姿も見えた。
俺は昔からカフェでも床屋でも飲み屋でも<ここ>と決めたら浮気はしない性分だ。
随分、昔からの一種のトラウマかも知れないし
単に自分勝手な気の回し過ぎかも知れないんだけど
経験上、どんな店でも店の不文律だとか常連贔屓とかあったりして
初めて入る店は何かと変な気を遣ったりして落ち着いた事がなかったのだ。
しかも、初めての店には当たり前だけど必ず当たり外れがある。
当たりばかりだと良いのだが、えてしてそうは上手くはいかないものだ。
一度外れに当たると、新しい店を開拓しようと思ってもそれが億劫になる。
「までも、仕方ないか」
俺は覚悟を決めて店のドアを開けると空いている席を探して店の中を見渡した。
すると店員は空いている4人掛けの席があるにも関わらず
俺を向かい合わせの2人席、しかもイス席へと導いた。
俺は2人掛けのソファ席にゆったりと座るのが好きなのだ。
しかし、今日の俺は新参の外様みたいなものだ。
俺は敢えて逆らう事を止めて大人しくその席についた。
それからメニューを決めて店員を目で探した。
が、店員は常連らしき客との話に夢中なようでこちらには気にも留めていないようだった。
「すいません」
俺は軽く手を挙げ店員を呼んだ。
しかし、店員は話に夢中でこちらには気が付いていない。
何分か待ったが一向に注文を取りに来る気配が無かったので
俺は仕方なく席を立つと店員の方に歩いていった。
「すみません。ピザトーストとアイスコーヒーを下さい」
店員はそれに応えもせず何事も無かった風でマスターにオーダーを告げた。
良くある話と言えばそれまでだが、その時点で俺の気分は最悪になっていた。
しかも、出てきたアイスコーヒーには既にミルクとガムシロップが入っていた。
俺はコーヒーはアイスもホットも絶対にブラックなのだ。
カフェではそれらは別々に出てくるものだと思っていたのは
単なる俺の思い込みだったのか?
俺は店員が愛想もなくテーブルに置いたピザトーストを急いでガッツくと
甘過ぎるアイスコーヒーを一口だけ啜って早々に店を出た。
間の悪い日というのがあるとしたら、それはまさしく今日なのだろう。
それから気分転換にと入った映画館では
隣に座った若いカップルのお喋りが煩くて俺はスクリーンに集中出来なかった。
本人達は声を潜めて喋っているつもりだったんだろうけど
声を潜めれば潜めるほど隣にいると会話が気になってしまうものだ。
エンドロールもそこそこに映画館を出ると突然の夕立が俺を襲ってきた。
人生一番の最悪な日とも思えた1日だったが唯一の救いは明日も休みだということだ。
俺は何もかも忘れようとベッドに潜り込んだ。
そして、羊の数を数える間もなく俺は深い眠りについた。
ふと気付くと何処か遠くで電話の鳴る音がしていた。
「こんな夜中に電話をする奴もいるもんなんだな」
俺には関係無いと決めつけて俺は又、眠りにつこうとしていた。
だが、その電話の音は鳴る度にだんだんと近くに聴こえてきた。
鳴っているのが自分のスマホだと気付くまでにそう時間はかからなかった。
「ふざけるな!」
そう叫ぶと俺は画面も見ずに着信を切ってスマホをベッドのマットレスの下に押し入れた。
だが、それで大人しくなるような素直なスマホではなかった。
スマホは俺のモノでありながら、それは俺のモノだけではないという事か?
しかも、小さく微かに聞えてくる着信音というのは
それはそれで耳には煩いものだ。
仕方なく手探りでマットレスの下からスマホを探し当てて
俺は表示されている電話番号を確認した。
何となく見覚えの有る電話番号に嫌な予感がした。
<あいつ>だとすると恐らくはこちらが電話を取るまで諦めないだろう。
しばし考えあぐねた末に電話を取るとそれは案の定だった。
「なんだよ。又、文句か? いい加減にしれくれないか?
確かに俺が悪かったよ。でも、真夜中の電話だったし寝惚けてたんだ。
謝れと言うなら何度でも謝るさ。だから、せめて明日にしてくれないか?
今日は朝から色々な事が立て続けであって疲れているんだ。
話は明日、ゆっくり聴くから頼むよ」
『眠れないの・・・』
今にも消え入りそうなか細い声が聞えた。
「えっ?」
『眠れないの・・・』
そんな事を突然俺に言われても、だからって俺にはどうしようもない。
第一、この女が何処に住んでいるのか? どんな女なのか?
何ひとつ判ってはいないんだから。
しかし、その理屈が通用するとも思えなかった。
俺がお人好しだって事はもう、この女にはバレバレなんだろう。
どうやら、ここは観念するしかなさそうだと思った。
俺はベッドから起きて座り直すと女に話しかけた。
「判ったよ。どうやら、その責任の一端は俺にもあるようだ。
そういう事だろ? なら、話を聞くよ」
『・・・』
しかし、女は何も応えなかった。
ただ、微かに嗚咽が聞えているだけだった。
困り果てた俺は諭すように続けた。
「眠れない時はかえって無理に寝ようとしない方が良いよ。
そうだ、何かさ。何かない?
温まるようなホットミルクとかさ、ココアとか飲んでみたらどうだい?」
『・・・』
「それじゃさ。何か・・・こう、心が穏やかになるような音楽とかさ。
イージーリスニングとか・・・そう、好きな映画音楽とかさ。
あっ、でも・・・映画のワンシーンなんか思い出したら
感動とか興奮も思い出して余計に眠れなくなるかな?」
『・・・』
「まぁね。そんな気分じゃないか。
実際、俺なんかも眠れない時は音楽よりも
高校の時の数学の教科書なんか開くと一発で爆睡してるけど・・・
って、そんな面白くないか」
『・・・』
「ふゥ・・・さてさて?
姫は何を所望されておるのやら?
寝ている姫を起こすのは得意なんだけどなぁ~
でも、姫を寝かせ付ける手立ては得意じゃないんだよなぁ~
そうだ、ちょっと待ってくれる?
安眠方法、安眠方法・・・と。
今、パソコンを立ち上げたからさ。
ちょっとググって見るから・・・えーっと、何々?」
『ありがと』
電話の向こうからか細い声が聞えてきた。
「えっ? 何?」
『おやすみなさい』
「えっ? おい! 何なんだ、いったい?」
今度は俺の眠気が覚めて、しばらく寝付けなくなったのは言うまでもない。
それから毎晩、決まって夜中の0時を過ぎた頃彼女から電話が入った。
しかし、相変わらず電話は掛けてくるくせに彼女は殆ど何も話さなかった。
ただ、黙って俺がアレやコレや話すのを聞いているだけで
適当な時間が過ぎた頃<おやすみなさい>とだけ言って電話が切れる。
そんな事の繰り返しだった。
「さんざん人に話をさせておいて又、これかい?
待てよ、これもあいつ流の嫌がらせなのか?
そうだとしたら何て陰湿な女なんだ!
そうだ! あいつは俺が焦って色々な事を喋っているのを
きっとニヤニヤしながら聴いて面白がっているに違いない。
もう止めた! 電話を掛けてくるならいくらでも掛けてくれば良いさ。
明日は一言罵声を浴びせて絶対すぐに切ってやる!」
そうだ。そうしようと俺は決めた。
なんせ、こんな調子で電話が切れた後も俺はなかなか寝付けないでいたのだ。
もう1週間も付き合ったんだ。もう禊ぎは済んだはずだ。
これ以上は俺だって身体が持たない。
第一、こんな事は俺の精神衛生上にだって百害あって一理無しだと思った。
次の夜も午前0時を過ぎた頃、彼女からの電話が鳴った。
俺はひとつ軽く咳払いをするとおもむろに電話に出た。
「もしもし」
『・・・』
やっぱり今夜もダンマリのようだ。
「なんだい、今日もやっぱりダンマリかい?
嫌がらせなら、もう十分だろ?
君の狙い通りに俺はここ1週間毎晩寝不足だよ。
謝れと言うなら、今夜ここで何百回でも謝るからさ。
だから、これっきりにしてくれよ」
すると彼女は予想外の言葉を口にした。
『ひどい・・・』
そうとだけ言って電話は切れた。
怒っていると言うよりは、どう聞いても涙声のように聞えた。
「ひどい? 俺が?」
予想外の反応に予想外に戸惑っている俺がいた。
「全く・・・どうすりゃ良いんだよ?」
そんな言葉を呪文のように頭の中で繰り返して
結局、俺はその夜もただ寝不足を積み重ねてしまった。
俺は何気なく壁の時計に目をやった。
時間はもう深夜の0時半を差そうとしていた。
毎晩のように訳の分からない電話が来て
その度に俺はどう対処して良いのか判らないまま
それでも何とか対処しなきゃと自分なりに一生懸命に対応をしてきたつもりだった。
相手に理解を求めようと言う気持ちももちろんあったけど
結局、彼女の意図は未だに全く分からない。
「単に嫌がらせや憂さ晴らしだけで、こんなに電話って出来るものかな?
しかも、見知らぬ相手に。それにしても・・・」
俺は又、時計に目をやった。
スマホの時計でも確認をしてみたが、やはり0時はとっくに過ぎていて
時間はもう1時になろうとしていた。
「今夜はもう来ないのか? やっと諦めてくれたんだろうか?」
そうなら、それで良いと思った。
だが、これで寝不足が解消されるとも思わなかった。
何故なら、もう既に<違う>事を考え始めていたからだ。
今夜に限って急に電話が来なくなった理由。
何か急用が出来たのか?
それとも単に気が済んだのか?
「いや、それは無い・・・かな」
俺は昨夜の電話の切れ方が気になっていた。
「ひどい? あれは何だったんだ?」
そして俺はもうひとつ<違う>事に気が付いた。
あんなに鬱陶しいと思っていた深夜の電話だったはずなのに
来なければ来ないで彼女からの電話を待っている自分がそこに居たのだ。
そして、ちょっとしたすれ違いから長年付き合っていた恋人と
中途半端な気持ちのままで別れた時のような妙なモヤモヤ感にも似た
そんな複雑な気持ちになっている自分に気が付いた。
<いっそ、嫌いになったとハッキリと言ってくれた方がすんなり受け止められる。
でも、中途半端なままだといつまでも引きずってしまうかもしれない>
付き合っていた訳でもないどころか何処の誰かも良く判らない彼女に対して
抱く気持ちにしてはおかしな気持ちだと自分でも判ってはいた。
でも、今の俺はまさにそんな気分の中にいた。
だが、次の夜も、その次の夜も彼女からの電話が来る事はなかった。
「交差点で出会い頭に事故に遭ったようなものだったんだ」
俺は自分にそう言い聞かせて彼女の事はもう忘れようと決めた。
「いや、交わるべき交差点にすら俺達は立ってはいなかったんだ」
それから3週間が経とうとしていた夜。
今まさに寝ようとしている俺を引き留めるかのようにスマホが鳴った。
俺は慌てて電話を取った。
「もしもし」
『・・・』
俺はスマホの画面に表示をされている電話番号を見た。彼女だ。
「もしもし? しばらくだね。元気にしてたかい?」
恋人どころか友達でもないのに、その言い方は変だとは思ったが
他に気の利いた言葉が浮かばなかった。
「あれから少し時間も経ったし、君も少しは落ち着いたかな?」
それには応えずに彼女は言った。
『彦星と織り姫・・・今夜はきっと逢えたね。
天の川がキレイに見えているもの』
「えっ? 何?」
俺は思わず聞き返した。
『今夜は七夕だよ』
「えっ? あぁ・・・そうだっけ?」
俺は壁のカレンダーに目をやった。なるほど確かに今日は七夕だ。
「すっかり忘れていたよ。そっかぁ、七夕か」
『ねぇ? そこから星が見える?』
「星? さぁ・・・ちょっと待って」
俺は立ち上がると窓の所に行ってカーテンを開けた。
確かにキレイな星空だった。
どれが何の星かなんてのは判らなかったけど
窓の外に広がる夜空にはたくさんの星が煌めいて見えた。
「あぁ、見えてるよ。すごいね。こんなに星が煌めいているんだ」
俺は窓の外を見ながら独り言のように呟いた。
『切ないよね』
「えっ? 何が?」
『だって、愛し合っているのに1年に一度しか逢えないんだよ』
「うん、そうだね。でも、逢えるだけ未だマシなんじゃない?
お互いに生きているから逢えるんだし、お互いに愛が冷めずにいるから逢えるんだからさ」
『でも、そんなの辛くない?』
「辛さよりも愛の方が強いって事なんじゃない?」
『あなたはどう?』
「何が?」
『そういうの我慢出来る方?』
「そうね・・・判らないな。なんせ、そんな経験が無いんで」
『うふふ。正直なのね』
「あぁ、俺はいつだって正直で小心者で
しかもすこぶる付きのお人好しだと思うよ。
自分でも時々嫌になる事がある、こんな自分にね」
『あら、そうなんだ? 小心者かどうかは知らないけど
でも、あなたが良い人だというのは良く判ってる』
「それはありがたいね」
俺は自虐的に答えた。
その言い方は何か自分でもすごく嫌だと思った。
彼女もきっとそれを感じたに違いない。
彼女の応えはなかった。
俺は焦って話題を変えようとした。
「ところで君は何処で織り姫と彦星を見ていたの?」
『部屋よ』
良かった。どうやら話を続ける気はまだあるみたいだ。
「恥ずかしながら、俺は星には全く詳しくないんだよね。
天の川ってどっちの方に見えるの?」
『東の空よ。何となくでも見てると3つの目立つ星が見えない?』
「目立つ星? あぁ、あれかな? 他よりは一際煌めいている気がするけど」
『あなたが見ているのが同じなら
それが夏の大三角形と言われているベガとアルタイルとデネブで
その内のベガが織り姫でアルタイルが彦星。
そして、その間に何となく細かな星が川のように伸びているのが見えない?
それが天の川よ』
「ん-、何となく見えるような見えていないような・・・
あぁでも、何となく判る気がする。アレかな?
でも、君は随分と星には詳しいんだね?」
『中学程度の理科の知識よ』
「理科? そう言えば、何かそんなのも習った気がするけど。
までも、我が家は根っからの文系家系だったから理科には疎いんだよね。
理科と数学の教科書は睡眠導入剤だと思ってたしさ」
『うふふ。面白い事を言うのね』
「そうだね。こんなロマンチックな夜には相応しくないけどね」
『そういう意味で面白いって言った訳じゃないけど』
「あはは。でも、ホントにキレイだ。
こんなにマジマジと夜空を見たのって何年ぶりだろう?
君には感謝だね」
『あらっ、今夜は嫌がらせ電話だって思ってないの?』
「そんな事・・・いや、正直に言うと前はそう思ってたよ。
いつも決まって寝る頃に電話を掛けてくるくせに
それでいて、特に何か言う訳でもなかったじゃない?
女の無言電話ほど男にとって怖いものは無いんだよ」
『うふふ。随分と経験豊富なようね?』
「いやいや。でも、内心穏やかじゃ無くってさ。
しかも、俺はとても無言に耐えられるタイプじゃないし
とりあえず、何か喋らなきゃみたいな感じでさ。
ほら、さっき小心者だって告白したじゃん? まさにそれだよ」
『あら、さっきのは告白だったの?』
そう言って電話の向こうで彼女は笑った。
初めて聴いた彼女の笑い声だった。
俺はベッドの所に戻るとそこに腰を下ろした。
そして軽く咳払いをひとつしてから改まって彼女に話しかけた。
「ねぇ? 随分と久しぶりの電話だったけど今夜は何かあった?
良かったら話くらい聞くよ」
『ありがとう。でも、特に何がって訳じゃないわ。
ずっと自分なりの前の事を整理してたの。
あー、最初の電話の原因になった件ね』
例の彼の件ね? とは、敢えて言わなかった。
否定されても肯定されてもそれはそれで何かあまり聞きたい話でもなかったから。
「で、やっと落ち着いたのかな? 良かったじゃん」
『そうね。でも、そこでひとつだけ気にかかる事があって・・・』
「何?」
『私、あなたに随分な事をしていたんじゃないかって』
「まぁ、否定も肯定もしないでおきましょうか」
俺はワザとそんな持って回った言い回しをして笑ってみせた。
『本当にごめんなさい』
「いや、そんなに改まれると・・・ねぇ?」
と、いったい誰に同意を求めているんだかはともかく
急に愁傷な言い方をされるとかえって返す言葉に困るというものだ。
『あなたが本当に優しい人だというのは良く判ったわ。
普通ならあんな電話にあそこまでの対応はしてくれないもの』
「ホント、何でだろうね? 俺も自分で良く判らないよ。
実際、罵声を浴びせて思いっきり電話を切ってやろうと思った時もあったんだ。
でも、心の中ではそう決めていたのに出来なかった。
俺が部類のお人好しだから? いや、そんなんじゃない<何か>
そう、何かがあの時の俺を操っていたのかもね」
訳の分からない事を思いながら俺は自分の言葉に苦笑した。
それに対して彼女は予想外に真剣に応えた。
『運命・・・的な?』
運命という言葉を聞いて、俺はあの時の自分の対応に妙に納得が出来た気がした。
「運命か・・・どうなるのが運命なのかはまだ判らないけど。
もし、運命というのが何かしらの悪戯をしたのだとしたら
その結果というのは何かしら起こるのかもしれないね。
例えば、それが今夜だとか。
それが七夕の夜というのはちょっと出来過ぎな感はあるけどさ」
『そうね。そこまでいくと陳腐な三流小説みたいかもね』
「あはは、そうだね」
俺はそう言うと笑った。
それに対して彼女は至って真剣に話を続けた。
『私も思ってたの。
<どうして、この人はいつもこんなに一生懸命になってくれるんだろう>って。
あなたが言うように普通ならガチャンと切ってそれでおしまいよね?
あなたが言ったように、いくらお人好しだったとしても、それだけじゃ1週間もは無理よ。
で、考えた中でふと思いついたのが<運命>って言葉だった。
随分、突拍子もない答えだって思ったわ。そんなのある訳ないとも。
でも、確かめたいと思った。それで思い切って電話をしたの。
図々しいのは十二分に判ってはいたんだけど・・・』
「でも、お互いにそんな風に思ってたんだとしたら
俺達は同じ事を考えて、同じ結論を出して、それを今確かめようとしてる。
そういう事だよね?」
『もし、私達が今、運命という交差点の向こうとこっちに立っているんだとしたら
その交差点を渡って巡り会うのか?
それとも、何も無かったようにただ通り過ぎてしまうのか?
確かめてみたい』
「うん。同感だね。でも、どうやって確かめる?」
『そうね・・・どうしたら良いんだろ?』
「人間ってさ。けっこうその場の雰囲気で流されちゃうよね?
だから、例えば今日でも明日でも会って確かめるとかなったら
俺なんか特にだけど君に会ったら絶対その場で抱き締めてしまうと思う」
『いきなり? 顔も知らないのに? 好みのタイプじゃなかったら?』
そう言って彼女は笑った。
俺は至って真面目に続けた。
「もし、君が本当に運命の人だとしたらきっと君は俺のタイプだよ」
『わー。無責任』
「だって、運命ってそういう事だろ?」
予想外に自分の口から放たれたキザな言葉をかき消すように俺は言った。
『じゃ、私があなたのタイプじゃなかったら運命じゃなかったって事ね?』
「君にとってもね」
『じゃあ、こうしない?
来年の七夕の夜にあなたの街の駅前で一番高いビルの前で会いましょう。
それでもし、出会えたらそれが運命だわ』
「来年? もし、出会えなかったら?
そもそも住んでる場所もお互いに知らないんだから。
その可能性の方が遙かに大きいよね?
それとかもし、その間に別な人が好きになって付き合う事になっていたら?」
『それが運命なんだわ』
「解った。じゃ、ヒントも無しで時間も決めないんだね?」
『運命に任せましょ』
そんな事があったものの、それが本当に<実現>をするとはとても思えないでいた。
そもそも何でそんな話になったんだっけ?
話の流れ・・・そう、単にその場の流れでお互いに酔狂話をしただけだったのかもしれない。
いつしか季節も変わる頃にはそんな<約束>も日々の忙しさに紛れて忘れていた。
その夜、仕事が終わって帰宅のバスに乗る為に駅前に向かって歩いていたら
先月駅前に新しく出来た17階建てのホテルの前に七夕飾りが立っているのが見えた。
朝もここと通ったはずだけど気が付かなかったのは電飾が点いてなかったせいかもしれない。
俺はふと足を止めてそのホテルをマジマジと見上げた。
ホテルの壁面にはオープンの大きな垂れ幕が屋上から吊り下げられていた。
<17階のラウンジからは市内最高層からの夜景が広がり
貴方だけの大人のひと時を演出いたします!>
「へぇ-、このホテルが市内で一番高いんだ?」
何気なく呟いた後で俺はあの<約束>を思い出した。
「そっか、明後日は七夕か・・・」
その場に立ったまま俺はしばし考えた。
「彼女はこのホテルが新しく建った事を知っているんだろうか?
ここが市内で最高層だと言うなら一年前の時とは状況は変わった訳だし・・・
いや、それよりも彼女がこの街に住んでいるのかさえ疑わしいよな?
話の流れであんな<約束>をしたけど、やっぱりただの酔狂だったに違いない。
運命なんて、そう何処にでも転がってる訳じゃないもんな」
半ば諦めて俺は又、歩き出した。
でも、何かに後ろ髪を引かれた気がして俺は振り返るとそのホテルの最上階を見上げた。
その日は昼間から半ば落ち着かずに仕事をこなしていた。
気もそぞろとはこういう事を言うんだろう。
1年前の<約束>には今でも半信半疑だった。
と、言うか、あんないい加減な話がそもそも約束だったのか?
何度も否定的な意見で自分自身を言いくるめてみた。
どうせ当たらないと思って宝くじを買った時でさえ
ここまで否定はせずに少しは夢を見たりも出来た。
しかし、どう考えても宝くじで見れるほどの夢には及ばないと思った。
何かで読んだが宝くじで一等が当選する確率は250万分の1なんだとか。
それと比べても二人が出会える確率はその何万分の1、いや、それ以下だと思った。
「でも、たまにはそんな酔狂に付き合うのも悪くはないかな? どうせ、帰り道だし」
期待はしないでおこうと思った。
でも、こんなドキドキするのも本当に久しぶりだった。
「そんな気持ちを思い出せただけでも良かったじゃないか」
仕事が終わるとそう自分に言い聞かせて俺は例のホテルに向かった。
駅前まで来ると、その手前にあるアーケードの商店街にもたくさんの七夕飾りが立っていて
この町の何処にこんなに人がいたんだろうと思うくらい行き交う人々もいつになく多かった。
その人並みをかいくぐるように歩きながら俺はその先に見えるホテルを目指した。
ホテルの前は小さな広場になっていて幾つか置かれたベンチには何組かのカップルや
スマホを見ながら座っている若い女の子やらサラリーマン風の若い男もいた。
他はと見渡すとホテルの入り口付近にも人待ち顔の数人の男女が立っていた。
「さて、困ったぞ。もし、仮に、本当に彼女がいたとしたって
これじゃ、誰がだれなんだかサッパリ解らないな」
とりあえず俺は、立っている女性を一人一人観察してみる事にした。
「この子は・・・いや、こんな若い感じじゃなかったよな。
あっちの子は・・・うん、ちょっと派手目だし、多分違うよな」
電話の声でしか知らない彼女。
俺は自分なりにイメージを膨らませた。
多分に期待を込めてだったが。
「そう、髪はセミロングかな。目は・・・うん、どうかな?
話してた感じでは少し勝ち気な感じだったから、切れ長?
それとも、気まぐれな猫目ってところかな?
とすると、髪はセミロングじゃなくてショートカットっぽいのかな?
服装は・・・うーん・・・OLっぽい感じだったから
もし、来るとしたらやっぱりスーツかな? それも黒とか」
色々とイメージをしてみたものの、結局これといった確定事項には至らなかった。
「そうだよな。声だけだもんな。解る訳ないかぁー」
そうこうしている内に見渡すとさっきまでいた女性達はみんな待ち人と出会えたのか
辺りにはすっかり誰もいなくなっていた。
「さてと、どうするかなぁ-」
俺は空いたベンチに座ると手を頭の後ろで組んで目の前のホテルを見上げた。
と、そこに一人の女性が声を掛けてきた。
「隣、空いてますか?」
「えっ? あぁ、空いてますけど」
俺の返事を聞くか聞かないかのうちに、その女性はベンチの隣に腰を掛けた。
しかし、その女性は特に何かを話しかけてくる訳でもなく
俺は妙な空間に紛れ込んだ時みたいな居心地の悪さを正そうとひとつ咳払いをして座り直した。
その際にチラリと横目で彼女を見た。
髪はセミロングで、声を掛けられた時に見た感じだとけっこう目はパッチリとしていたようだ。
白いブラウスに淡いモスグリーン系のカーディガンとクリーム色っぽい膝丈のフレアスカート。
どう考えても電話の彼女のイメージではなかった。
でも、ひと目見ただけだったが俺の好みにはドンピシャだった。
『まぁでも、そんな都合良くはいかないよな』
そんな事を考えていると彼女が話しかけてきた。
「こんなホテルが出来てたんですね」
「そうだね。先月オープンだったらしいよ」
前を向いたまま俺は答えた。
「ここって、この辺で一番高いんですか?」
「どうなんだろ? 泊まった事はないから解らないけど」
「えっ? うふふ、料金じゃないですよ」
その笑い方に俺は思わず彼女をガン見してしまった。
聞き覚えのある笑い方だったからだ。
「えっ? もしかして、あの・・・変な事を聞いていい?」
「何ですか?」
「あの、もしかして・・・君って電話の?」
彼女は俺の方を向くとニコニコしながらも平然と答えた。
「今頃解ったんですか?」
「えっ? えっ? なんで? 君は俺がそうだと解ってたの?」
「えぇ、さっきひと目見た時にすぐ解ったわ」
「なんで?」
驚く俺に彼女はまたしても平然と答えた。
「だって、私のタイプだったから」
「で、今に至る・・・なんてね」
俺は照れ隠しに目の前にあったコーヒーを一気に飲み干した。
長い話にコーヒーはスッカリ冷めていたが何となくほろ苦さも思い出させるような味がした。
「へぇ~ すごぉ~い! そんな奇跡ってあるの?
ロマンチックだわ! ねぇ、それでどうしたの?」
娘が目をキラキラさせて話に食いついてきた。
「どうもこうもないよ。これでおしまい」
「ダメよ! もっと詳しく話を聞かせて!」
「いいよ、もう。恥ずかしいし」
多分、俺は娘の前では見せた事がないくらい赤面をしていただろう。
こんな話をし出した事に少し後悔をしていたくらいだ。
しかし、娘は一歩も引かない。
「そこまで言って終わりなんて殺生というものだわ!
ねぇ、それからどうしたの?」
「どうもこうも、結婚してお前が生まれたんだよ」
「そんなの解ってるわよ。結婚した時の話が聞きたいの!
ねぇ、それからすんなりと結婚したの? 紆余曲折とか何もなかったの?
結婚してからは? やっぱりケンカとかした?」
矢継ぎ早に質問を繰り出す娘。
「だから。もういいって。勘弁してくれよ」
俺はソファを立ち上がって、その場を逃げだそうと試みた。
だが、一変して神妙な顔つきに戻った娘を見て俺は又、ソファに腰を下ろした。
そして努めて静かに娘に話しかけた。
「そんなに迷ってるんなら結婚、止めたら?」
「もう! 他人事だと思って」
そう言ってむくれた顔はまさに妻に瓜二つだと思った。
「他人じゃないけどな」
冗談めかして俺は答えた。
「当たり前でしょ! あーでも、ホントどうしようかなぁ-」
「でも、ちゃんと考えて決めたんだろ?」
「そりゃそうだけど」
「なら、自分を信じたら良いんじゃない?」
「でも、色々と進んで行く毎に何かね、だんだん現実が重たくなってきた」
そう呟くと娘は怠そうにため息をついた。
「不安は誰だってそうさ」
「お父さんの時もそうだった?」
「まぁ、そりゃね。出会いが出会いだっただけにね」
「でも、ロマンチックじゃない? まさに運命だった訳でしょ?
それに比べたら私達なんか平凡でつまらないわ」
娘は会社の先輩と春先に結納を済ませて来月には結婚を控えている。
最初はルンルン気分でアレやコレや楽しそうに話をしてくれていたが
ここのところ、どうも気分が停滞気味になっているようだった。
いわゆるマリッジブルーというやつなんだろうけど
さっきみたいにため息をつく事が多くなっていた。
「ねぇ? お父さんとお母さんの時ってどんなだったの?
出会いは? どうして付き合う事になったの?」
そんな話から少しでも娘の気持ちが前向きさを取り戻すキッカケにならないかと思って
今まで娘に話してなかった昔話をして聞かせる事になったのだった。
もし妻が生きていたら、もっと良い相談相手になってやれていたかもしれないが
今の俺にはそんな昔話を聞かせる事くらいしか思い浮かばなかった。
俺は娘の顔を改めて見つめると努めて平静に言った。
「人生に平凡なんて事はないさ」
「あるわよ。私達がそうだもの。
同じ会社の同じ係の先輩で私が入社をした時から何かとお世話になっていた彼だったけど
まさか、こんな手近の人と結婚をする事になるなんて想像もしてなかったわ」
「まさか、王子様が白馬に乗って迎えに来るなんてのを信じてた訳じゃないよな?」
「それはないけど・・・でも、何かもう少しドラマみたいな出会いがあったりとかさ。
お父さんの話を聞いてたらメッチャ羨ましかったわ。私もそんなのが良かったな」
娘はそう言って口を尖らせた。
「あはは。でも、出会いってさ。
本当はどんな出会いだって、それは運命の糸に導かれた特別な事なんだよ」
「それはお父さん達がそうだったから言えるのよ。私達なんて平凡なだけだわ」
「本当にそうかな?」
「そうよ」
「例えば、そうだな・・・すごく大きな紙を用意したとしよう。
で、横に100本の線を書くとするだろ?
それから適当に何十本も何百本も縦線を入れていく。
そして出来たアミダクジの右と左からお互いに好きな線を選んで
その線の通りに進んで
それでもし、真ん中でお互いの線がぶつかったとしたら凄くない?
それが運命だって信じられるだろ?」
「それはね」
娘はそう言いながらも納得はしていないように見えた。
俺は話を続けた。
「お父さんとお母さんが結婚をしたからお前が生まれた。
もし、お父さんの結婚相手がお母さんじゃなかったら
もし、お母さんの結婚相手がお父さんじゃなかったら
生まれた娘にお前と同じ名前を付けたかもしれないけど
それはお前じゃない。解るかい?」
「うん」
「もし、お前が高校受験をした時に
もっとレベルの高い高校を受験して合格していたら?
逆にレベルを落として違う高校に行っていたら?
多分、お前が行った大学だって違っただろうし
就職先だってきっと今とは違っていたよな?
彼だってそうさ。
全く違う街で生まれて違う環境の中で育って
そして、その時その時で色々な選択をしてきて
その結果、今の彼があってお前と出会う事が出来たんだ。
まさに、さっきのアミダクジと同じだろ?」
「・・・」
「もし、どちらかが途中の何処かで違う選択をしていたら
お前と彼とは出会えていたと思うかい?」
「それは・・・まぁ・・・」
「それこそが運命以外の何物でもないって証拠だよ」
「でも、まだこれからどうなるか解らないよね? お互い様だけど」
「まぁ、確かにこの結婚がお前のゴールだと言う保証もないけどね。
でも、良いじゃないか。
もし、彼が最終的な運命の人じゃなかったとして
いつか別れる事になったって、それこそが運命で
もしかしたら、その経験をした上で出会う次の人が本当の運命の人かもしれない。
言い換えれば、本当の運命と出会う為に必要だった順路みたいな、とかね。
そんな事が待っているとしたって、そりゃ不思議ではないさ。
でも、誰もが死ぬ時じゃないとそんな事は解らない」
「そうだけど・・・」
娘はまだ納得をしていないようだった。
「解らない事に悩んだってしょうがないだろ?
なら、受け入れるか受け入れないか
それを自分で決めて先に進めば良い。
人生の交差点なんて数え切れないくらいあるんだし
そこで誰と出会うか誰と別れるか何処に進むかどっちに曲がるか
それを決められるのは自分だけだよ」
「まぁね」
「で、どうなんだい? 彼は運命の人だと思う?」
「・・・解らないよ」
「だよな? 良いじゃん、今はそれで」
「お父さんはどうなの? この先、誰かと結婚をするの?」
「さぁな・・・運命の出会いがあればするかもしれないし
もう、そもそも運命の出会いなんか起きないかもしれないけどさ。
もし、お父さんが運命の人と再婚をしたらどうする?」
「多分・・・嫌だ。お母さんが可哀想・・・」
「うん。そうか、可哀想か。でも、お母さんなら何て言うかな?」
「・・・多分、良かったねって言うかも・・・」
「もし、もしだけどね。
お父さんがこの先、運命の人に出会って結婚をしたとしても
だからと言って、決してお母さんが運命の人じゃなかったとは絶対に思わないよ。
お前という娘に出会わせてくれたんだから。
他の誰でもない、お前にね」
妻が亡くなって、もう5年になる。
娘の就職も決まり、卒業を控えた春先くらいから少し体調を崩して
しばらく微熱が収まらない日が続いていた。
病院に行けよと言う俺の言葉にも「風邪だから大丈夫」と言って妻は耳を貸さなかった。
俺も年度末を控えて仕事が忙しい時期でもあり妻の「大丈夫」と言う言葉を鵜呑みにしていて
そんなに深刻な状態だとは夢にも思っていなかった。
今思えば、娘の大事な時期だと一人で無理をしていたのかもしれない。
それだけが今も残る後悔だった。
体調がすぐれないまま、それから1ヶ月後
ようやく病院に行った時にはもう既に遅くて「後、もって3ヶ月」だとの宣告を受けた。
急性白血病、それが妻の病名だった。
社会人になって初めて貰ったささやかなボーナスで娘は妻にお揃いのスカーフを買った。
妻の大好きなヒマワリの柄の黄色いスカーフを選んだのは黄色が幸運の色だとされていたから。
奇跡を祈る娘の想いがそこには込められていたのだろう。
そのスカーフの入ったピンクのリボンが掛けられた小箱を抱えて会社帰りに娘が病室に駆けつけた時
娘の顔を見るなり最後の気力を振り絞ってだったと思うが、精一杯の笑顔で妻は娘に言った。
「ありがとう。あなたに会えて私は本当に幸せだったわ」
そして、妻は静かに息を引き取った。
「早いね」
居間の壁に掛けられた家族3人が幸せそうに笑っている写真を見ながら娘はポツリと呟いた。
娘がまだ中学の頃だったろうか。東京に家族旅行に行った時の写真だ。
壁には娘の幼稚園の頃、小学校時代、中学とそして高校時代の頃のそんな写真が幾つか飾られていた。
「そうだな」
俺もそう言うとソファから立って娘と並んで写真を見た。
「懐かしいね、これ」
娘が小学生の頃にキャンプに行った時の写真を指さして言った。
「あぁ。夜、お前がトイレが怖くて行けなーい、漏れるーとか騒いで泣いたよな?」
俺は湿っぽくなるのが嫌でわざと意地悪く娘に向かって言った。
「もう、変な事は思い出さなくて良いの!」
案の定、娘はむくれて見せた。
「あっ、これは海に行った時だ」
「そういや、いつの間にかお前はお父さんより泳ぎが得意になってたよな?」
「えっへん! 夏休みにお母さんにプールで特訓してもらったのよ」
「そっか、お母さんは泳ぎが得意だったっけ」
「中学の時は何とか中のミス飛び魚だって言ってたわ」
「へぇ-、それは初耳だ」
「お父さんでもお母さんの知らない事ってあるんだね?」
「そりゃそうだよ。夫婦だって知らない事はお互いにたくさんあるさ」
「そんなもの?」
「あぁ、そんなものさ。でも、それで良いんだと思うよ。
付き合って解る事、結婚してから解る事。そんな事も確かにあるけどね。
でも、それでもお互いの全部を知り尽くす訳ではないけど、それが又、良いんだよ。
全部、何から何まで解ってたら逆につまらないと思わないか?」
「私は彼の事は全部知ってたいな。良いところもそうでないところも」
「それは何十年の経ってからで良いんだよ。
若い頃は些細な事でぶつかるもんさ。でも、そうやってお互いを解っていくんだ。
全部解ってから始めるんじゃない。解り合おうとして始まるんだよ」
「ふぅーん。今夜のお父さんは話が深いね。初めてかな? こんな話をするのって」
「かもな」
「そっかぁ、解り合おうとして始めるのか」
「それって、運命だかより大事だと思わない?
むしろ、そうやってだんだんとお互いが運命になっていくんじゃないのかな?
初めはきっと単なる偶然に過ぎない出来事なんだ。
そんな偶然を幾つも幾つも重ねていって
それを更に運命に変えていくのは、やっぱりお互いの想いなんだと思うよ」
「うん。そうだね。そうかも」
「そうさ」
「何だか彼の声が聞きたくなってきた。ちょっと部屋で電話してくるね」
「なんだ、ここですりゃ良いじゃん?」
「嫌よ。お父さんだって娘が彼とイチャイチャ電話をしてるの聞きたくないでしょ?」
「イチャイチャする気か?」
「当たり前でしょ。私達、結婚するのよ」
そう言った娘は
さっきまで結婚を悩んでいた娘と同一人物かと思うくらい晴れやかな表情に変わっていた。
「そりゃ、ごちそうさま。どうぞご勝手に」
俺はそう言ってバイバイと娘に手を振ってみせた。
居間を出てドアを閉めかけた娘はふと振り返ると言った。
「そう言えば、明後日って七夕だったわよね?
お父さん、久しぶりに七夕飾りを飾ってよ」
「面倒くさいよ」
「昔は飾ってくれたじゃない」
「それはお前が小さかった頃の話だろ?」
「私がお父さんの為に短冊に願い事を書いて上げるから」
「いいよ、別に。ってか、本当はお前が書きたいんだろ?
『彼と幸せになりますように』とかってさ」
「そんな事は書かないわよ。十分幸せですから」
「あら、随分さっきまでと違うじゃん? じゃ、何て書いてくれるんだ?」
「お父さんが2番目の運命の人に出会えますように」
そう言って娘は悪戯っぽく笑った。
思わぬ言葉に俺は苦笑いをするしかなかった。
「やっぱり、お前の娘だな」
壁に掛けられた妻の写真を見て俺がそう呟くと
「うふふ。当たり前でしょ」
そう言って妻が微笑んだように見えた。