
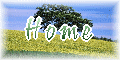
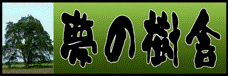
星にリボンを
仕事帰り。
夕暮れの堤防沿いのサイクリングロードを私はいつものように自転車を走らせていた。
七月とは言え、
この時間になると昼間の暑さも落ち着きをみせ頬に当たる風は幾分涼やかだ。
晴れた空は青から蒼へ、そしてそれが藍に変わる頃
その下にグラデーションで広がる夕焼けのオレンジ。
闇に押されて次第に小さくなっていくオレンジと入れ替わりに
川の向こう岸とこちら側に徐々に拡がっていく街の灯り。
やがて灯る一番星。
そんな夕暮れの風景を眺めながら自転車を走らせる帰り道。
私はこの風景に出会う為に毎朝他の人より一時間は早起きをして
バスも電車も使わずに自転車を漕いで通勤をしているのだ。
ビルの谷間に沈む夕焼けもそれなりに美しい。
でも大きな空いっぱいに拡がる夕焼けの美しさには敵わない。
もし、この風景に敵うものがあるとしたら
それは故郷の空だけかも知れない。
私はこの風景にかつて故郷で見ていた風景を重ねているんだろうな。
望郷とかホームシックではない。
むしろ、この風景を見ることで私は仕事で疲れ切った心と身体を癒している。
故郷の温かさに包まれながら・・・そう、そんな感じなのだ。
私の名前は小島千里。
『せんり』と書いて『ちさと』と読む。
小さい頃は父も母もおじいちゃんもおばあちゃんも
もちろん友達も誰もが『ちーちゃん』と呼んでくれた。
幼いなりにけっこう気に入っていたのだ。
中学の頃だったか、一度父親にお父さんの由来を訊いたことがあった。
「ねぇ、おとうさん? 『千里(ちさと)』ってどうして付けたの?」
「うん、名前か?
お父さんもお母さんもこの町で生まれてここでの生活しか知らないんだ。
いや、これは不満じゃない。
お父さんもお母さんも満足しているさ。
この町で生まれてお母さんに出会えたし結婚をしてお前が生まれた。
それがお父さんとお母さんの幸せだった。
でも、お前が産まれた時に思ったんだ。
じゃ、この子は将来どうなるんだろう?ってな」
「うん」
「親の勝手かもしれんが、お前にはもっと広い世の中を見て欲しいと思った。
将来、大人になって例えお前が千里離れて遠くに行ったとしても
お父さんとお母さんはいつでもお前と繋がっているし
いつでもお前のことを見守っていたい。
『千里』の『里(り)』は長さの単位ではあるけど
もうひとつは『古里』の『さと』だ。
つまり千里離れたとしても始まりはお前の生まれたここと言う訳だ。
お前がどんなに遠くに行ったとしてもお前が帰れる場所はいつでもここにある。
それを忘れて欲しくなくてさ。
それでどうしてもお前の名前に『里』の字は使いたかったんだ。
つまり、どんな時だってお前と繋がっているってことをお前が忘れないようにな。
・・・まぁ、そんな色々な想いを込めてさ」
「うん」
私はちょっと感動していた。
と、お父さんはそれをすぐに台無しにしたのだ。
「なぁ〜んてな」
そう言ってお父さんは笑ってみせた。
「えっ? 何?」
「あはは。すまん、すまん。今のは後付けだ」
「えっ? ひどーい! けっこう感動したのに!」
「すまん、すまん」
そうは言ってごまかしたけど、後になって考えると
それは父親特有のテレだったのかもしれないと思った。
名前の由来を語っていた時のお父さんの表情は
娘の贔屓目じゃなくたって深い愛情に満ちていたのだから。
小さい頃、白い紙やノートさえあれば好きで良く絵を描いていた。
絵と言うには稚拙でむしろ単なるマンガだったのだが
みんなが褒めてくれたので
私はすっかりその気になって将来はマンガ家になりたいと思っていた。
でも、だんだん大きくなるにつれ
絵が上手いだけじゃマンガ家にはなれないことを悟った。
つまり、物語を創造する斬新な発想力とそれを具体化する為の構成力。
そこに登場するキャラクター。
真剣に考えれば考えるほど自分には無理だと考えるようになっていったのだ。
それでもやはり絵を書くのは好きだった。
高校を卒業すると私はデザイナーになる為に東京の専門学校に進んだ。
北海道からだと千里とまではいかなかったが
奇しくも父親の言っていた通りに私は故郷を離れて暮らすことになったのだ。
卒業後はそのまま東京の中堅デザイン会社に就職をし
そろそろ八年目に入ろうとしていた。
独身のアラサー女、二十八歳。
このお盆が過ぎたらいよいよ二十九歳になる。
今日の私は疲れ切っていた。
と、言うよりは自己嫌悪・・・そう言った方が正しいのかも知れない。
いつもと同じ夕暮れの帰り道。
いつも以上にきれいな夕焼けを見ながら自転車を走らせても
爽やかな風を頬に受けてもちっとも心は晴れやかにならなかった。
出るのは溜め息ばかりだった。
「何なんだろう? 私って・・・」
つい先日のこと。
この秋に行われる子供向けのイベントのポスター作製の依頼があった。
クライアントの意向はこうだ。
<子供が喜ぶようなマンガっぽい可愛い絵を大きく配置して
職業体験イベントの楽しさが良く伝わって
尚且つ、子供の興味を引くような謳い文句の入ったカラフルで目立つポスター>
「小島、これ今週中にやってくれないか?
マンガはお前の得意分野だろ?
頼むぞ、けっこう大事なクライアントなんだ」
「あっ、はい」
上司の加藤課長はそう言って私の肩をポンと叩くと
鼻歌を歌いながら自分の席に戻って行った。
何でも言えば簡単に出来ると思っている加藤。
上手く行けば当然自分の手柄になる訳だし
ダメならそれは部下のせいにすれば良いんだから気楽なものだ。
加藤課長は元々は営業畑専門でデザインのことなんててんで解ってはいない。
ただ、前任の課長が体調を崩して退職をしたので
急きょ先月からデザイン課を任されることになったのだ。
なのでデザインに関するアドバイスは一度も無かった。
もっともプロのデザイナーにアドバイスを出来るほどの
経験も知識も無いに等しいのだから
ある意味それは当然過ぎるほど当然のことだった。
古参のデザイナーの中には早くもバツマークを付けている者さえいた。
それでも上司は上司だ。
こちらもプロだし、言われたことには全精力を注ぐのだ。
それがプロとしての誇りだった。
「で、何だって?」
私はクライアントの作成した意向書に改めて目を通した。
「なんだこれ?」
二〜三回サラッと目を通した後で
私は意向書をデスクの上に放り投げると
頭の後ろで手を組み回転イスを右へ左へゆするように回した。
「どうした? ブランコをわざとゆすって拗ねている子猿みたいな顔だぞ」
隣の席の山崎がニコニコしながら声をかけて来た。
山崎はこの道四十年の超ベテランデザイナーで
その存在は業界大手事務所のデザイナー達からも一目置かれている。
普通の会社なら定年はとうに過ぎているだろうが
今でも現役バリバリのデザイナーである。
私の師匠であり、相談相手。
山崎にしてみれば私は危なっかしい手のかかる孫みたいなものだろうか。
時にはその柔和な顔からは想像できないくらい激しく叱られもしたし
私が落ち込んでいる時は何も言わず飲みに連れて行ってくれたりと
入社以来何かと面倒を見てくれていた。
「どうせ北海道から出て来たまだまだ半人前の子猿ですから。
すいませんね。可愛くなくて」
「いやいや、子猿はけっこう可愛いぞ」
「んー、微妙です」
私は山崎と顔を見合わせて笑った。
「これ」
「ん?」
山崎に意向書を手渡すと時々何かを考えながら丁寧に目を通していた。
「ふむ」
私は山崎の持っている意向書を横から覗き込むように言った。
「それ」
「ん?」
「もう既にクライアントの頭の中にはガチガチのイメージが出来上がってますよね。
それも、いかにも大昔の子供向けーみたいなの」
「だね」
「じゃ、自分で書けよって感じだわ」
「おいおい、それじゃ俺達は失業だよ」
「あはっ、確かに。でもなぁー なんかつまんない」
「そこを何とかアイデアを絞って
クライアントを喜ばすのが俺らの仕事だろ?」
「そうなんですけどー」
「俺達は・・・」
山崎が言うのを遮って私が続けた。
「『俺達は芸術家じゃない。
クライアントの意向を最大限に形にするのが俺達の仕事だ!』
でしょ?」
「なんだ、解ってんじゃないか」
「もう何百回も聞かされましたから」
「なら、頑張れ」
「はーい」
「だが、気を付けろよ。簡単なものほど実は難しい」
「どういう意味ですか?」
「んー、こればっかりは教えてもどうにもならないんだ。
まぁ、お前なら出来るさ。
よしんば、一度は大きく躓いてみるのも良い。若いんだから」
「えっ?」
「いや、こっちの話だ」
「はぁ・・・」
「子供向けのイベントかぁー。
じゃ、やっぱりイラストは小学生くらいの男の子と女の子かな?」
私はデスクに向かうとペンタブレットを使い
思い浮かぶままに子供のイラストを幾つも描いていった。
前を指差す笑顔いっぱいの子供。
警察官の制服を着てパトカーに乗っている子供。
ファーストフードの店員さんのようにニコニコしながらおじぎをしている子供。
描いては削除をし又、描いては削除をして
数時間経っても結局パソコンの画面は真っ白なままだった。
何だかしっくりこない。
何を描いても陳腐なものに思えた。
「そもそも、子供が喜ぶような可愛いマンガっぽい絵って何?
イベントって職業体験だよね?
じゃ、働く車とか・・・あっ、そうそう! 大工さんとかコックさんの絵とか?
んー、ダメだ・・・全然浮かばない。
簡単なものほど難しいってこういうこと?」
真っ白なパソコンの画面を見ながら私はずっと頭を悩ませていた。
「山さん、もう帰っちゃったしなぁー」
私は又、両手を頭の後ろで組むとイスを左右に揺らした。
「なんだ、もう煮詰まっているのか?」
驚いて振り返ると買い物袋を手に持った山崎がニコニコしながら立っていた。
「山さん!」
「ほら、差し入れだ。どうせこんなこったろうと思ってな」
山崎は手に持っていた買い物袋を袋ごと私に差し出した。
「でも、何だな。この時間のコンビニって弁当とか売り切れが多くってさ。
ほとんど何も残ってないんだな。
すまんな。アンパンとジュースだ。
アンパンと牛乳なら刑事の張り込みみたいで面白かったんだけど
お前は北海道人のくせに牛乳が苦手だったよな?」
「あはっ、山さん。ありがとう。
『くせに』は余計だけど。
北海道人だってみんなが牛を飼っている訳じゃないですよ」
「あはは、イメージだよ。
北海道と言えば澄み切った青い空と広い大地。
どこまでも真っ直ぐに伸びた道路。
その両脇には緑の牧草地と放し飼いされた乳牛・・・ってな」
「それと熊と蟹と鮭でしょ?」
「他に何がある?」
「ありますよー、いーーーっぱいです!」
私はわざと大袈裟に両手を広げて言った。
その時、ふと思いついた。
「そっか、イメージだ!
私は言葉のイメージに囚われ過ぎていたんだ。
山さん、ありがとう!」
私はペンを握るとすぐさまタブレットに向かってイラストを描き始めた。
山崎がいつの間にか帰っていたことにも気が付かないまま。
それから三日間でポスターを仕上げた。
「うん、我ながら良い出来だよね」
出来上がったポスターを何度も見ては私はウンウンと頷いてニヤニヤ。
「やったじゃん!」と私はご満悦だった。
それくらい快心の出来だったのだ。
早速プリンターでA3判に縮小印刷をすると隣の山崎に見せた。
「山さん、どう?」
山崎はポスターを受け取るとしばらくじっと見ていた。
私は椅子を転がして山崎に近寄るともう一度訊いた。
「どう? けっこう自信があるんだけどなぁー」
すると山崎は予想外な答え方をした。
「んー、ポスターとしては悪く無い。
むしろ良い出来だと思うよ。
後はまぁ、課長がどう判断をするかだな」
その加藤課長のオーケーをもらい
翌日、課長と営業さんと私の三人でクライアントの会社に向かった。
「すみません。お待たせをしました」
そう言ってクライアントの担当者が応接室に入って来た。
一通りの挨拶と世間話の後で課長が私に向かって言った。
「小島君、ポスターをお出しして」
「あっ、はい」
私はゲラ刷りの入った茶封筒を担当者に手渡した。
「ほぉ、楽しみですね」
担当者が笑顔で茶封筒からゲラ刷りのポスターを取り出した。
と、ポスターを見ている担当者から笑顔が消えて行った。
「どうでしょう? 良い出来だと思うんですが」
課長がご機嫌を伺うような口調で担当者に尋ねた。
私はドキドキする気持ちを抑えながら担当者の言葉を待った。
担当者はポスターをテーブルの上に置くと
軽く一息ついてからこちらを見据えるとゆっくりと判決を下した。
「確かに、ポスターとしては良い出来だと思います。
でも、残念ながらこちらの意向があまり良く伝わっていなかったようですね」
会社への帰り道。
不機嫌な課長を筆頭に誰もが無言だった。
私は必死に涙を堪えながらダメ出しされた理由を考えていた。
ふと、奇しくも山崎と担当者が同じことを言っていたのを思い出した。
<ポスターとしては良い出来だ>
ポスターは悪くない?
じゃ、何が?
良い出来なら良いじゃない!
何がいけないの?
私の頭の中は最早グシャグシャだった。
「小島ーーー! ちょっと来い!」
会社に戻るなり私はすぐに課長のデスクに呼び付けられた。
「バカヤロー! お前、何年この仕事をやってんだ?
俺に恥をかかせやがって!
えっ? この始末、どうすんだよ?
お前の代わりなんていくらでもいるんだからな。
やる気がないならとっとと田舎に帰っちまえ!」
「すみません・・・」
私はそう言うのがやっとだった。
怒られるのには慣れているつもりだった。
だが、それ以上に自分に対する悔しさに涙が溢れた。
そこに課長が追い打ちをかけた。
「へっ! 泣けば良いと思ってるのかよ!
これだから女は困るんだよ。
もう良い! 行け!」
席に戻った私は机に伏したまま、溢れてくる涙を何度も堪えようとしていた。
でも、涙の蛇口が壊れたかのように涙を止めることは出来ないでいた。
「どうした?」
外から戻って来た山崎が声を掛けてくれた。
でも、私は答えられなかった。
「そうか、ダメだったのか・・・」
察したように山崎が優しく言った。
「まぁ、そんなこともあるさ。
あまり気にするな。
この商売は腕よりもクライアントとの相性みたいなこともあるしな」
私は涙を拭いながら山崎に訊いた。
「山さん・・・ 何が悪かったの?
山さんも言ってたよね?
『ポスターとしては良い出来だ』って。
あれって、どういう意味?
良い出来なら良くないの?」
「んまぁ・・・そうだな」
山崎は席を立つとコーヒーサーバーの所に行き
ふたつのカップを持って戻って来た。
そして、私にひとつを手渡すと優しく微笑みながら話を続けた。
「俺がいつも言ってる言葉、覚えているよな?
『俺達は』ってやつだ」
私は無言で頷いた。
「それが全てだよ。それだけだ。
今回のクライアントの意向はどんなだった?
芸術的なポスターを望んでいたのか?
大人が見て感心をするようなポスターだったか?
若者の気を引くようなポスターだったのか?」
「違う・・・」
私は俯きながら小さな声で答えた。
そうだ。その通りだ。
私は端からクライアントの意向書を陳腐なものだと軽く見ていたのだ。
そして、思い上がった私は自分の力を誇示するかのようなポスターを作った。
私は何を思い上がっていたんだろう?
何を焦っていたんだろう?
何に恐れていたんだろう?
働き始めてもうすぐ八年。
しかも、来年には三十歳になる。
早く一人前にならなきゃという焦り?
何も結果らしい結果を残せずに三十歳を迎えることへの恐れ?
その先に待っているであろう人生へのおぼろげな不安?
「山さん、もしかしてこうなるの解ってた?」
山崎は優しく答えた。
「いや、俺は神様じゃない。そんな予言は出来ないよ。
でもな。長年の勘っていうのかな。
お前が一人前になるためには必要な試練なんじゃないかと。
漠然とだが、そんな風にも思っていたのも事実だ」
「『簡単なものほど難しい』・・・ですか?」
「まぁな。でも、お前なら乗り越えられるさ」
そんなこんながあって
目一杯落ち込みながら帰り道の自転車を漕いでいたら突然メールの着信音が鳴った。
自転車を停めて、ポケットからスマホを取り出した。
見ると出張に行っているはずのタカシからだった。
<やっほー! 今日も快食快便してるかい?
今、札幌だよーん。
ススキノのネオンが俺を待ってるぜい(むふ)
おぉーっと、待っているのはススキノのお姉ちゃんだけじゃないぜ。
カニ、イクラ、ラーメン、ジンギスカーン!
何? 羨ましい? わっはっはー。
お土産は北海道の空気だ! 楽しみにしておけよー!!!>
いつもながらのノー天気なメールだった。
でも、これでけっこう根は真面目で仕事も頑張っていたし
何より優しかったので
私が落ち込んでいる時もこんな明るいタカシに救われることも多かった。
でも、今日だけは違っていた。
いつもなら『バカなやつ』と笑って許せることも
今は落ち込んでいる気持ちを余計に助長させた。
それだけに今日はいつになくカチンときたのだ。
「なんて無神経な奴!」
もちろんタカシはこっちの事情なんて知る由もない。
だが今の私にはそんな解りきったことを許せる気持ちの余裕すらなかった。
ついマジ切れした私は『絶対別れてやる!』
そう返信しようと心に決めた。
と、その時。
堤防の下の家の庭先にキラキラ光るものがあった。
「何だろう?」
良くみるとそれは柳の枝に飾ったいくつもの短冊だった。
その内の金銀の短冊が夕日に反射をして光っていたのだ。
ふと、スマホのカレンダーを見て気が付いた。
七月七日。
「そうだ。今日は七夕だったんだ。あっ!」
私は思い出した。
十一年前の七月七日の夜。
私が高校三年の時に病気療養中だったお母さんが亡くなった。
今日がその日だったことを。
「あー、今日はお母さんの命日じゃん!
何をやってるんだろ、私って。こんな大事なことを忘れていたなんて・・・」
私はすぐさま自転車を漕いで堤防を下るとバス通りに出て自販機を探した。
「あった!」
私はお母さんの好きだったサイダーを二本買うと又、自転車を漕いで堤防に戻った。
そして自転車を停めると堤防の草むらに腰を下ろした。
缶のサイダーのリングプルを開けると座った横に置いた。
そしてもう一本を開けると私はそれを一口飲んだ。
「あぁー、サイダーって昔と変わらないね」
私はお母さんに話しかけた。
「ごめんね。お母さん。すっかり忘れていたよ。
ダメだね。だから仕事も失敗するのかな?
私だけ何だか変わっちゃってるのかもね・・・」
川面に夕日が揺れながら光っていた。
そして、その向こうに灯り始める街の灯り。
そんな景色を眺めながら小さい頃のことを思い出していた。
「ローソクだーせ、だーせーよ。だーさないとひっかくぞ・・・」
小さい頃、町内会の子供会が中心になって七夕の日にそうみんなで歌いながら
子供達は町内の家々を回ってはお菓子をもらって歩いていた。
(注)道南の一部を除いて北海道の七夕は月遅れの八月七日。
だが、本当にローソクなんてくれようものなら大ブーイングものだった。
子供達の目当てはあくまでもお菓子だったのだ。
「クスッ」
私は思い出し笑いをした。
「そう言えば、向かいのオバサンは
わざと意地悪く最初は本当のローソクを出してきたっけ。
そして私達がもじもじしているのをニコニコ楽しそうに見ては
『ほらっ』って言って後ろ手に隠していたお菓子をくれたんだ。
懐かしいなぁー」
そう呟いて私は又、ひと口サイダーを飲んだ。
「そうだ! 五年生の時だっけ?
新しい浴衣を買ってくれたよね。嬉しかったなぁー。
それまでは従姉妹のお姉ちゃんのお下がりばかりだったから
自分のを初めて買ってもらった時はホントに嬉しかった。
そう、そしてお母さんが結んでくれた黄色いリボン・・・
ずっと私のお気に入りだったんだよ。
あの頃が一番幸せだったのかなぁー」
「ちーちゃん、ちょっと来てごらん」
居間で宿題をしていたら隣の和室からお母さんの呼ぶ声がした。
「なぁーに?」
すぐに走って行き和室に入るとお母さんがニコニコしながら座っていた。
「おいで」
そう促されて私はお母さんの前にちょこんと座った。
「はい、これ。 どう?」
目の前に置かれたのは新品の浴衣だった。
白地に赤と青の朝顔が描かれていた。
側には黄色い帯と黄色い鼻緒の下駄も一緒に置かれていた。
「わぁー、可愛い!」
「気に入ってくれた?」
「これ私の?」
「そうよ。今度の七夕の時に着させてあげるね」
「わぁーい! お母さんありがとう!」
それから七夕の日まで毎晩私は枕元に畳んだ浴衣を一揃い置いたまま寝た。
ある夜、私は起きると浴衣が失くなっている夢を見た。
慌てて飛び起きた私はすぐに電気を点けて枕元の浴衣を確認した。
「あぁ、あった! 良かった。夢だったんだ」
そして、ホッとすると又、私は眠りについた。
そんな夢を見てしまうくらい私は本当に嬉しかったのだ。
七夕の日(実際には八月七日)
私は朝起きると浴衣を持って居間に行った。
待ちきれなかったのだ。
「あら、どうしたの? 早いわね」
時計は朝の六時だった。
「ねぇ、これ着たい」
「えー? まだダメよ。だって回るのは夕方でしょ?
一日ずっとそのかっこうでいる訳?
汚したらどうするの?
それに、もう少ししたらラジオ体操に行くんだよ。
浴衣じゃ体操が出来ないでしょ?」
「えー、つまんない。体操・・・行かない」
「なら浴衣も無しよ」
「そんなぁー」
私は半べそをかいた。
そして、待ちに待った夕方になった。
私は台所仕事をしていたお母さんをチラッと見て言った。
「ねぇ、お母さん?」
お母さんは神妙な顔の私に気付いて笑顔になると手拭で手を拭きながら居間に来た。
「はいはい。じゃ、こっちにおいで」
お母さんの後について和室に入ると衣紋掛けに浴衣が掛けてあった。
浴衣を着付けてもらった私は有頂天になって
何度もクルクルと右へ左へ回りながら得意満面の笑顔でお母さんに尋ねた。
「ねぇ、どう? 似合う?」
「えぇ。良く似合ってるわ」
ニコニコしながらお母さんもそう答えた。
「あっ、そうだ!」
そう言うとお母さんは箪笥の真ん中の引き出しを開けて何かを取り出した。
「せっかくの浴衣だし、髪を後ろに束ねたらこれで結おうか?」
それは帯と同じ色の黄色いリボンだった。
「うん!」
考えると帯も下駄の鼻緒もリボンもみんな黄色だった。
でも、その時はそんな事はちっとも気にならなかった。
自分の浴衣が着られる。
それだけで私は大満足だった。
お母さんが亡くなる何日か前のこと。
私は学校が終わるといつものように病院にお見舞いに行って
そして、いつものようにその日学校であったことをお母さんに報告していた。
「そっか。夏休みが終わったら進路のことも決めなきゃね」
「うん。まぁねー」
「ちーちゃんはどうしたいの?」
「んー。迷ってる。
お父さんはとりあえず大学に行けって言うけど・・・
ねぇ、お母さん。私ね、デザイナーになりたいの!
だから専門学校に行った方が近道だと思うんだけど
でも、その為にはどうせなら東京の専門学校に行きたいんだ。
レベルの高い所で勉強をしたいの!
ねぇ、どう思う?」
「そうね。ちーちゃんの人生だもの。ちーちゃんの思うようにしたら良いわ」
「でも、お父さんが・・・デザイナーなんてそんなに甘くないんだから
とりあえずは大学に行ってしっかり勉強をしてからにしたらって」
「うふ。お父さんらしい真面目な考え方よね?」
「真面目なのは良いんだけど、お父さんは堅過ぎよ」
私はふくれっ面で答えた。
「ごめんね。ちーちゃんの大事な時に傍にいつもいてあげられなくて」
お母さんは申し訳なさそうに言った。
「ううん。そんなことない。
それにね。何だかんだ言っても私、お父さんのことも大好きだし。
これからもしっかり話をしてみるわ」
「そうね」
「うん。だからお母さんも早く治してよ。
二対一なら絶対お父さんなんか撃破よ!」
「まぁ、物騒な言い方」
「えへっ」
二人は顔を見合わせながら大きな声で笑った。
「あっ、そうだ。これ覚えてる? この前、お父さんに急に持って来たの。
『どうだ? 懐かしいだろ?』って言って置いて行ってくれたのよ。
何年ぶりに見たかしら。私もビックリしたんだけどね。
良くお父さんも覚えていたもんだわ」
そう言うとお母さんはベッドの脇の引き出しから見覚えのあるモノを出して見せた。
「あっ、それ!」
それは初めて買ってもらった浴衣を着せてもらった時に
後ろに束ねた髪を結んでくれたあの黄色いリボンだった。
「わぁー、懐かしい! まだ取ってあったんだ?」
歓喜の声をあげながら黄色のリボンに頬ずりしていた私を
嬉しそうにお母さんは見ていた。
ふと我に返ると私はお母さんに訊いた。
「そう言えば、浴衣の帯も下駄の鼻緒も、そしてこのリボンもみんな黄色だったよね?
ねぇ、どうしてだったの? お母さんの好きな色だったから?」
「そうね。それもあるわ。
黄色って明るい色よね。向日葵とか太陽とかのイメージでしょ?」
「うん」
「何かね、黄色って見ているだけで心が弾んでくるようなそんな気持ちになるの。
だから、昔から黄色が大好きだったの。
それでね。いつ頃だったっけなぁー
そうねー、ちーちゃんくらいの頃かな。
図書館で黄色に関する事が載っている色々な本を読んだの」
「うん」
「例えば、そうね・・・
イギリスでは黄色は身を守る為の色とされていたりね。
それで黄色いネクタイとか黄色いハンカチとかを身に付けるの。
時が経ってアメリカに渡ると今度、黄色いリボンは
戦場にいる愛する人の無事を祈り
無事な帰還を願うシンボルになった・・・とかね」
「へぇー、そうなんだ?」
「昔の歌だけど『幸せの黄色いリボン』とか
日本の映画でも『幸せの黄色いハンカチ』とかあったりね」
「あっ、その映画は知ってるわ。
家にDVDがあるよね?」
「そう。お父さんもお母さんもこの映画が大好きだったの」
「そうなんだー 私も今度観てみようっと」
「んー、ちーちゃんはどうかなぁー?
もう少し大人になってから観た方が良いかもよ」
「ひどーい! 私だってもう十分大人です!
ご飯だって洗濯だってちゃんとしてるよ。
もちろん、お父さんの分もね! えっへん!」
「あらあら、それは失礼しましたね」
そう言うとお母さんは笑った。
その時、私はお母さんの私への深い愛情を改めて知った。
そして又、お父さんのお母さんへの深い愛情も。
お父さんもお母さんの完治を祈り
そして無事に退院出来る日が来ることを心から祈っていたんだ。
残念ながら黄色いリボンの願いも叶わずに
その数日後にお母さんは亡くなった。
私が東京の専門学校に旅立つ朝。
既に会社に出かけていたお父さんの書置きと一緒に
キレイにアイロンがかけられた
あの黄色いリボンが食卓テーブルの上に畳んで置いてあった。
<これを持って行け。
お母さんがきっとお前をいつも応援してくれるはずだから>
お母さんの形見の黄色いリボン。
「お父さん、ありがとう。お父さんも応援してね。
私達家族は離れたっていつもみんな一緒だから」
私は荷物を持って玄関に出ると振り返って誰もいない居間に向かって叫んだ。
ぽろぽろと落ちてくる大粒の涙を止めることも忘れて。
「お父さん、お母さん、ありがとう! 行ってくるからね!」
私はそんなことを思い出しながら
土手の上に座ったままでだんだんと灯りを増していく向こう岸の街を見ていた。
気が付くと空にももうたくさんの星達が煌めき始めていた。
「そうだ。お父さんにも電話をしておかなきゃ」
私はスマホでお父さんの携帯を呼び出した。
数回の呼び出し音の後でお父さんが出た。
「おー、千里か? どうした? 何かあったのか?」
「何かないと電話しちゃダメ?」
私はついぶっきらぼうに答えてしまった。
お父さんも前だとどうしてだろう?
いつも変な意地を張ってしまう。
可愛げのない娘。
「あはは。そんなことはないさ。嬉しいよ」
いつもと変わらない優しい声でお父さんは答えた。
「ごめんね・・・」
「なんだ急に? どうした?」
「今日・・・お母さんの命日だったよね。
私、すっかり忘れていた・・・」
「あはは。そんなことか?
良いさ。お前だって忙しいんだ。気にすることはない。
今日、仕事を抜け出してお母さんのお墓に行ってきたよ。
もちろん、お前の分もちゃんとお参りをしておいたからな。
もっとも、そのお蔭でまだ会社に居残りだけどね」
「あっ、ごめん! まだ仕事中だったんだ?」
「あぁ。でも、みんな帰っちまったからな。
大丈夫だ。これが終わったらお父さんも帰るよ」
「そっか。無理しないでね。
お父さんだっていつまでも若くないんだから」
「おいおい、それは失礼だぞ。
お父さんはまだまだバリバリの現役だからな。
何年後か?何十年後か知らんけどさ。
孫の顔を見てお母さんに報告をするまでは元気でいるさ」
「あはは。じゃ、ずっと結婚しないでいたら
お父さんもずっと元気でいてくれるんだね?」
「おいおい、それは止めてくれ!
お父さんだって人間なんだから限界と言うものがだな・・・」
「止めて!」
私はつい大声で怒鳴ってしまった。
お父さんの限界(死)のことなんか聴きたくは無かったのだ。
「そんな弱気なことなんて言わないでよ・・・」
私は涙声になっていた。
「すまん、すまん。だが、心配するな。
お父さんは元気だし、ちゃんとやっているよ。
お前はとりあえずは自分のことだけに一生懸命になれば良いさ」
「ありがとう・・・」
「あはは、泣くな! お母さんも悲しがるぞ」
「うん・・・」
「本当にそれだけか?
何かあった訳じゃないのか?」
「うん。それだけだよ。お母さんの命日を忘れていて電話もしなかったから」
「そっか。それなら良いけど」
「来月ね。お盆には休みを取って帰りたいと思ってる。
もう二年も帰ってないし・・・
親不孝な娘だけどいつまでもお父さんとお母さんの娘でいさせてね」
「あぁ。当たり前じゃないか。
でも、忙しいなら無理はしなくても良いんだぞ。
大事な時なんだろ?
人間てな、頑張らなきゃならん時は何を放っても頑張らなきゃならんのだ。
それがお前にとって今なら余計なことは考えなくたって良いさ」
「うん、ありがとう。でも、大丈夫。頑張って休みを取れるようにするから」
「そっか」
「うん。それじゃ又、決まったら電話をするね」
「あぁ。解った」
「お父さんも無理はしないで。それじゃ、おやすみ」
「あぁ、おやすみ」
「うーーーーん!」
私は土手の上に両手を伸ばして寝転がった。
頬を撫でる風が気持ち良かった。
久し振りにお父さんの声を聴けて
さっきまで落ち込んでいた気持ちがすっかり晴れた気がした。
「わぁー! キレイな星ー!」
見上げると夜空には数えきれないほど無数の星達が煌めいていた。
七夕のせいか今夜は天の川もいっそうキレイに見える。
「良いなぁー、織姫と彦星は年に一度のデートかぁー。
それなのに、あのバカは札幌だしさぁー」
私はふとさっきのタカシのメールを思い出した。
「そうだ! 絶交メールを送るんだった!」
私はスマホを取り出すとタカシのアドレスを出した。
しばらくスマホの画面を見た後で私はそのままアドレスを閉じた。
「まぁ、良いっか。あのバカはそんなくらいじゃ治らんし。
それに私くらいしか相手をする可憐な女性もいないだろうしさぁー
ボランティアっての? 仕方ないよね」
私は一人で笑い声を上げた。
近くに歩いている人がいたらきっと気味悪がったに違いない。
「ねぇ。お母さん。私達のこと・・・どう思う?」
満天の夜空を見上げると私はお母さんに話しかけた。
その時、星のひとつがキラリと光った気がした。
「お母さん。ありがとう。やっぱりお母さんともまだ繋がっているんだよね?」
私はそう言いながらその光った星にジェスチャーでそっとリボンを結んだ。
黄色いリボンを思い浮かべながら。
帰り際に私は閉店寸前の花屋さんに駆け込みミニひまわりを一輪買った。
部屋に戻ると白いチェストの上のお母さんの写真の前に
その一輪挿しにしたミニひまわりを飾ると目を瞑って手を合わせた。
「お母さん、忘れていてごめんね・・・」
それから冷蔵庫の中の有り合わせで簡単に食事を作って食べた。
独り身の食事なんてそんなものだろう。
手間を掛ければ掛けるほど出来た料理は何だか虚しい気がしていた。
「食事と言うよりは単なる給油みたいな感じ?」
私は自分で思い付いた比喩に苦笑いをした。
食事の後片付けもそこそこにシャワーを浴びて
上がった後、タオル一枚を巻いたままソファに寝転がってテレビを観ていた。
これが一方では独り暮らしの気軽さだ。
寂しくはないと言えば嘘になるけど
この気楽さは時に何者にも代えがたいものだって気もしていた。
「こんな風に揺れる気持ちの中で気が付けばいつしか三十歳も過ぎていくのかな?」
二十代と三十代の境目。
その先には何が待っているんだろう?
その時、私はどうなっているんだろう?
「さぁて、明日も仕事だし。そろそろ寝ようかなぁー」
私はテレビを消して立ち上がるとひとつ伸びをした。
その時、テーブルに置いてあったスマホにメールが着信した。
見るとタカシからだった。しかも添付ファイルのみで本文は無い。
「なぁに? ススキノのお姉ちゃんとのアホ写真なら今度こそ絶交だからね!」
私は添付ファイルをクリックして開いた。
と・・・私は我が目を疑った。
「えーーーー!? なんで? ねぇ、なんで? なんで?」
確かにそこには酔っぱらって真っ赤な顔ではしゃいでいるタカシのアホ面があった。
だが隣に一緒に写っていたのは<お姉ちゃん>ではなかった。
「お父さん!? な、なんで? なんでお父さんと一緒なの?」
そう、タカシと一緒に写っていたのは間違いなくお父さんだった。
しかも、かなり酔っぱらっているのだろう。
真っ赤な顔の男同士で頬をくっつけて二人とも大きな口を開けて笑っている。
タカシのアホ面はともかく
こんなにはしゃいだ顔のお父さんは見たことがなかった。
しかし、問題はそんなことではない。
どうしてタカシとお父さんが一緒にいるのかということだ。
と、そこに又、メールが着信した。
<いやぁー、驚いた? 俺も!(笑)
ススキノに行こうと思ってたんだけどお前の家が急に見たくなってさ。
で、住所を頼りに家を探してたんだけど夜だし解らなくてね。
うろうろしてたら、そこに偶然通りかかったのがお父さんでさ。
もう、超ビックリだったわ!
で、訳を話して・・・と、言ったって
いきなりお前と付き合ってますと言っても信じてもらえないだろうからさ。
お前とツーショットの写メを見せた訳。
あー、ごめん!
つい、間違ってお前とキスしている自画撮り写メも・・・見られちゃった(汗)>
「なっ、何をバカやってんのよ!」
<で、『とにかく入れ』って言われてさ。
いやぁー 俺はてっきり殴られるかと思ったんだけどね。
そしたらビールを出してきてくれて・・・
その一時間半後がこれ(笑)
すっかり意気投合しちゃってさ。
ホント、お前に似合わずさばけた良いお父さんだわー。
おっと、メンゴメンゴ!
でね。今夜はお前ん家に泊まらせてもらうことになったから。
お父さんがどうしてもって言うもんだからさぁー。
『千里の部屋が空いてるから好きに使え』なんてね>
「冗談でしょ! 止めてよ!」
<てな訳で、今夜はお前のベッドを借りるから、ヨロチクびー!>
「嘘でしょ!」
青天の霹靂とはまさにこういうことを言うのだろう。
私はすぐさまタカシに電話を入れた。
多分、ホンの数秒だったに違いないのだけれど
その間にも私のボルテージは目一杯上がっていた。
プルルル、プルルル・・・
「おー、千里? どうした?」
平然とした態でタカシは答えた。
「どうしたもこうしたもない! なんでタカシが家にいるのよ!」
「あー、そんなことか」
「そんなことって・・・良く平然と言えるわね!」
「それはさっきのメールで説明したじゃん。
そういうことだよ」
タカシが平然と答えれば答えるほど私はどんどん過熱していった。
「とにかく、早く帰ってちょうだい!」
「無理だよ。お父さんももう寝ちゃったし俺もベッドの中だし」
「ベッドって・・・」
「あぁ、お前の。けっこう可愛い趣味してたんだな」
電話の向こうにタカシのニヤニヤした顔が浮かんで
私は目の前のそれを思いっきり振り払った。
「他には? 何も見てないわよね?
勝手に何処でも開けたら承知しないからね!」
「他にもって? 何かあるのか?」
しまった! 墓穴を掘った?
「別に見ちゃいないよ。見せたいものがあるなら見てやるけどさ」
「なっ、そんなものある訳ないでしょ!」
「お前の勉強机って何っての?
アンティーックぽいってかカントリーっぽいってかシックで良いね?
これってお父さんとかお母さんが選んだのか?
子供の趣味とは思えないけど」
「えっ? 勉強机・・・まさか、引き出しを開けてないわよね?」
「引き出し?」
「あんたね! 日記なんか見たら絶対殺すからね!
タカシを刺して私も死ぬから!」
「日記? ほぉー」
あっ、しまった! また?
「もう・・・」
私は床にへたり込むとソファに向かってスマホを投げつけた。
なんか今日の私はいつもの私じゃない。
タカシへの怒りと言うよりはそんな自分自身への漠然とした怒りだったのかも知れない。
ソファに転がったスマホから微かにタカシの声がした。
「おーい、どうした?」
私は膝で歩きながらソファの元まで行くとスマホを手に取った。
「おーい、千里ー!」
「もしもし・・・」
「おー、何かにぶつかったような音がしたけど大丈夫か?」
「なんでもない・・・」
「そっか、なら良いけど」
「・・・」
「やっぱ、何か変だぞ」
「何が?」
「何がって・・・いわゆるひとつの勘とでも申しましょうか」
「何それ? 誰のモノマネよ? バッカみたい」
「へぇへぇ。どうせね。
あっ、そうだ! 一応、お前に言っておかなきゃな」
「何を?」
「俺さ。さっきお父さんに約束をしたんだ。
来月のお盆には必ずお前を連れて来るからってさ。
もし、お前が休めないとか何とか言っても
俺が責任を持って引っ張ってでも連れて来るからって。
だから、お前もそのつもりでいろよ」
「な、何を勝手なことを言ってるのよ?
しかも何? 私を連れて来るって・・・誰の家だと思ってるの?」
「あはは。それはまぁ、言葉のあやだよ。
でも今日、お前のお父さんに会えた。
やっぱり思った通り、いやそれ以上に素敵な人だったよ。
となるとさ。
ここはやはりお前を産んでくれたお母さんにも
ちゃんと挨拶をしておかなきゃさ。
お盆には一緒にお墓参りに連れて行って欲しいんだ。
お前とお父さんと一緒に」
「タカシ・・・」
「だから、そのつもりでいろ」
「・・・」
「ん? どうした?」
私はスマホを握り締めながらボロボロ泣いていた。
やはり今日の私は変だ。
涙の蛇口が完全に壊れてしまってる。
「おーい! おーい? おぉーーーーい!」
「・・・」
「えっ? 何? 何だって?」
「泣かせるなよ」
「えっ?」
「だから・・・泣かせるなっての!
私はここに独りなんだぞ。
こんな気持ちにさせて・・・どうしろって言うのよ?
タカシに責任取ってもらいたくても・・・いないしさ・・・」
「ごめん・・・」
「何で謝るの?」
「だって・・・」
「バッカじゃないの?」
「何だよ、それ?」
「バカ・・・」
「お前なぁー」
「・・・」
「えっ? 何? 聴こえない」
「アイシテル・・・」
「えっ? えっ? 何だって? もう一度?」
「バカ・・・」
「いや聴こえなかったんだって。何て言ったんだ?」
「別に」
「いや今、お前は何だかすごく大事なことを言った!」
「言ってない」
「いや言った!」
「良いよ。とにかく私のベッドを汚さないでよ!」
「何だよー? 人を汚物みたいにさ。怒るぞ!」
「うふふ。お父さんによろしくね」
「えっ? おお、任せとけ」
「じゃ、私は寝るから。こっちに帰って来たら連絡ちょうだいね」
「んー、何だかすごくごまかされた気がする・・・」
「そんなことないよ。じゃあね」
「はいよ。お土産楽しみにしとけよ」
「空気だけじゃ嫌よ」
「あはは、やっぱこの手は無理か? よし、解った。ちゃんと買って帰るよ」
「うん。ありがと」
「じゃあな、おやすみ」
「おやすみ」
私はスマホをテーブルの上にそっと置くと窓のところに行きカーテンと窓を開けた。
夜風が頬に気持ち良い。
「織姫と彦星のデートは上手くいっているかな?」
見上げた夜空にはいつもの東京の空では見られないくらいキレイな天の川が見えていた。
「二人がもっともっと、そしていつでも傍にいられますように」
そう願いながら私はジェスチャーで天の川にリボンを結んだ。
もちろん黄色いリボンだ。