
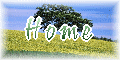
星の巡り
良く、星の巡り合わせが良いとか悪いとか言うけど
考えてみると、俺の今までも決して良いものではなかったように思う。
もちろん、全てが悪いことばかりではなかったけれど
何故だか覚えているのはやはり良くないことの方が多い。
小学校時代。
引っ込み思案だった俺に何かにつけて声を掛けてくれていた担任の先生。
はつらつとした、そして何より笑顔が素敵な若い女性の先生だった。
休み時間に独りで本を読んでいると、先生が来て前の席に後ろ向きで座ると
「何を読んでいるの? 先生にも読んで聞かせてよ」
とか言ってくれて、恥ずかしかったけど俺は一生懸命に物語を読んで聞かせた。
俺の拙い読み聞かせを先生は笑顔で頷きながら聞いてくれていた。
お陰で、それからますます本が好きになって国語の成績も上がっていった。
それでも引っ込み思案だけは治らずに
昼休みの校庭でみんなが手繋ぎ鬼をしていた時も
みんなの輪に入れずに校庭の隅でポツンと立っている俺を見つけて
そして俺の手を引くとみんなのところに連れていて仲間の輪に入れてくれた。
それから、こんなこともあった。
風邪を引いて休んだ時は放課後になると
俺がそれを好きなのを知っていてくれたのか、その日の給食の揚げパンと
その日の授業の内容をまとめたノートをわざわざ自宅まで届けてくれた。
俺はそんな先生が大好きで、ずっと先生が担任だったら良いのにと思っていた。
しかし、二年生の三学期。先生は隣町の小学校に転勤になった。
先生が最後にかけてくれた言葉は
「弘樹君、いつまでも本を好きでいてね」だった。
訳もなく溢れる涙の意味をその頃の俺にはまだ知る由もなかった。
淡い、仄かな恋心。今思えばそれが俺の初恋だったのかも知れない。
中学になると俺の引っ込み思案もいくらかは治っていたけれど
特段、何かに目立つ訳でもなかった俺は
相変わらず休み時間には独りで本を読んで過ごしていた。
或る日、クラスの悪友達が体育館の裏で煙草を吸っているところに
俺が偶然通りかかった時、間の悪いことに指導係の先生も見回りで通りがかり
悪友達がダッシュで逃げる寸前に手渡された煙草を持っていた俺は
ただ呆気に取られたまま何の言い訳も許されずに二週間の停学になった。
そのことが響いたのか俺は第一志望の高校に落ちて
滑り止めの私立高校にやっとのことで滑り込んだ。
そうして始まった高校時代。
第一志望じゃ無かったからというのは言い訳に過ぎなかったろうが
部活に熱中するだとか勉強に集中するだとかもなく
何となく漠然とした気持ちのまま怠惰に毎日が過ぎていくだけだった。
将来の目標どころか現実すら目を開けて見ようともしていなかった。
そんなところに良い運気などくるはずもないということにさえ
今思えば、あの頃は気が付いてはいなかったのだろう。
或る時のこと。
各クラスから必ず生徒会役員の立候補者を出すというのが高校の伝統だった。
とは言え、みんなそんな役にはなりたがらず
当然のごとくクラスの中では押し付け合いが起きた。
良くある話ではあるが、たまたまそんな時に風邪を引いて学校を休んだ俺が
生徒会長に立候補させられる羽目になった。
勉強が出来るとか、スポーツが得意だとか、カラオケが上手いとか
人目を引くような、そんな特技などあろうはずが無い俺は
人気者どころか学校の中でも全く目立つ存在ではなくて
もちろん後日、必死に固辞ををしたのだったが欠席裁判の有罪率は高い。
少しは責任を感じていたのか仲の良かったクラスメイトが推薦人になってくれて
かろうじて何とか選挙運動のかっこうは付けられたものの
よりによって候補者の立ち会い演説会の時
徹夜で考えた演説原稿を何処かに置き忘れて頭が真っ白になった俺は
うろたえた結果、自棄になってただ自分の名前を叫んで演説会の持ち時間が終了。
せめてクラスに戻った時にでもクラスメイト達が
俺の不出来を揶揄してでもくれていたら良かったのだが
余程俺を気の毒と思ったのか
誰もそのことには触れず、それがかえって俺の中でトラウマとなってしまった。
大学時代も正直、あまり思い出したくはないことばかりだった。
バイト先が初めての給料日の前日に潰れて店主は夜逃げをし
結局、一ヶ月間のバイト代がパーになったこともあった。
バイトと言えば、一般教養のクラスでたまに顔を合わせる奴が
割の良いバイトがあると誘ってきて
「何、簡単なアンケート取りだよ」と誘われるままに付いていくと
そこは怪しげなマンションの一室だった。
愛想の良い二十代後半くらいの人に一通りレクチャーを受けたが
それはアンケートにかこつけて高価な物を売りつけるという類いの商売だった。
”商品”が売れないとなると日毎に良かった愛想が厳しい口調へと変わって行った。
「売れないならお前が買い取れよ。なぁに、金のことなら心配するな。
俺が良い金貸しを紹介してやるよ。
それが嫌なら死ぬ気で売って来い、ほらもう一度行って来いよ!」
そう言われたのを幸いに俺はマンションを出て、そのまま逃げ帰った。
大学の授業に行っても俺を誘った奴から逃げ回るようにしながら数日が経った時
クラスの噂でそいつが警察に捕まったという話を聞いた。
運が良かったのか悪かったのか?
ともあれ、前科者にだけはならずに済んだようだった。
こんなこともあった。
初めて付き合った彼女に三日でフラれたのだ。
何のことは無い。
相手の浮気が原因で別れたらしいが、俺と付き合っていることを知った元彼が
平謝りで謝った結果、彼とよりを戻すことにしたんだとか。
ちなみに、彼女の元彼は俺達のゼミの先輩だった。
人は自分のモノが他人に取られたと思うとよほど悔しいと思うらしい。
結局二人は半年もせずに別れて彼女はやり直したいと言ってはきたが
俺はそこまでお人好しにはなれなかった。
遅まきながら、少しは勉強をしなきゃと思い始めたのも
或いは、そんな色々がキッカケだったのかもしれない。
やる気を出すと運気も変わるのだろうか?
就職活動をしながら続けていたバイト先で俺は美里と出会って付き合い始めた。
美里は隣町の短大に通う二年生で、やはり就職活動中だったことから話の共通点も多くて
色々とお互いに相談しあっているうちに良いなと思うようになったのだ。
それから俺は卒業までには卒論も無事に提出をし何とか単位も全部取れて
大企業とまではいかないが地元ではそこそこ名前の知れた会社に就職をすることが出来た。
美里も同じ町の信用金庫に就職が決まった。
二十七歳、入社五年目の頃にはいつしか俺もいっぱしの社会人となっていた。
同期の中には早々と主任に昇格をする奴が出てき始めていて
そういう俺自身も同期へのライバル心から仕事に没頭をする毎日を送っていた。
しかし、その頃からだろうか?
学生時代から付き合っていた恋人、美里とも
仕事を理由に合う間隔がだんだんと離れていった。
俺としては早く一人前になって美里と結婚をしたいと思っていた。
その為にも少なくとも同期には負けたくなかったし
『将来の為にも今はがむしゃらに仕事をして成果を出す』
その一存しか頭には無かった。
だが、それも全ては美里の為。
自分にそう言い聞かせて俺は仕事漬けの毎日を送っていた。
三十歳前には係長になって美里にプロポーズをするつもりだったのだ。
そして、それは美里も解ってくれていると思っていた。
七月六日は美里の誕生日だった。
その夜、俺は美里の為に超有名な高級ホテルのレストランを予約していた。
やれ三つ星だとか四つ星だとか、そんなことは俺には良く解らなかったが
SNSを見ると予約の取れないレストランとして有名な店らしかった。
美里もきっと喜んでくれるに違いないと思っていた。
そして案の定、次々と運ばれてくる豪華なフレンチに美里も終始ご機嫌だった。
やがて、コースの締めのデザートとコーヒーが運ばれてきた。
「どう? 満足した?」
俺は美里の満足げな笑顔に向かってバカみたいに得意げに訊いた。
「えぇ、とても美味しかったわ。弘樹にしては上出来よ。
でも、良くこのレストラン予約取れたわね。
半年先まで予約で一杯だって、もっぱらの評判なのよ。
何でもシェフがフランスでも賞を取った人なんだって」
美里はそう良いながらケーキを頬張っていた。
「そりゃ良かった。これでも一応頑張ったんだぜ。美里の為にさ」
俺はコーヒーを啜りながら答えた。そして何の気なしに続けた。
「明日は七夕だね」
「そうね。まるで織女と牽牛みたいな私達にはピッタリな季節よね」
意に反し美里はため息交じりにそう答えた。
「いやいや、それ以上は会っているよ」
「じゃ、この前はいつだった?」
美里は俺の顔を覗き込むようにして訊いた。
「この前? えぇーっと・・・先月、いや先々月になるんだっけ?」
俺は美里の顔を見ながら、申し訳ないといった心地で答えた。
「ブッブー! 四月の頭よ。ゴールデンウイークだって弘樹は出張で居なかったし。
あれ、本当に出張だったの?」
「当たり前じゃないか! でも、こうして同期では二番目に主任になれたし。
美里、見てろよ。俺さ、絶対三十前には同期で一番に係長になってやるからさ」
「仕事、仕事かぁ-。良いわね、男は。
仕事、仕事って頑張って偉くなってくけど待ってる女はただ歳を取っていくだけ」
「そんなことはないよ。俺だって、何が何でも仕事が命って訳じゃないさ。
早く良い給料を貰えるようになって美里と結婚したいって頑張ってるんだぜ」
「それは解るけどね。でも、それを解らない私もいるのよ」
美里は再びため息をつくと窓の外に広がっている夜景を見た。
心ここに在らずといった風にも思えた。
俺は話題を変えようと話を切り出した。
「それは俺も悪いと思ってる。本当だよ。でも、もう少し待っていて欲しいんだ。
そうだ。ねぇ、夜景のキレイな最上階の部屋を取ってあるんだ。
今夜くらいは二人っきりでゆっくり過ごそうよ」
美里は俺の方を向くと愁傷な面持ちで言った。
「ごめんね。この後、用事があるの。友達と約束をしてる」
「えっ? なんで?」
驚いた俺を尻目に美里はとどめを刺した。
「私、もう待つのも疲れちゃった。逢いたい時に逢えないのって恋人じゃないよ。
ごめんね。弘樹は悪くない。それは解ってる。
でも、しょうがないの。これで終わりにしましょ」
その翌日は朝から散々だった。
取引先から急なクレームが入って、その対処に追われた俺は
一日中あっちこっち走り回って頭を下げたり謝ったりでクタクタになっていた。
何とか素早い対応で一応クレームは収まったものの
仕事が終わったのは終電も間近な頃になっていた。
急いで向かった駅で電車を待っていると
何処かの駅で人身事故が有ったとかで間に合うはずだった電車が止まった。
駅前ではタクシーを待つ人の列は何十にもなっていて
いつになったら乗れるか検討も付かないくらいだった。
「仕方ない、歩いて帰るか。一時間も歩けば何とか帰れるかなぁー
途中、何処かでタクシーが来たら止めれば良いしな」
どのくらい歩き続けただろうか。
重い足取りで歩いていた俺に追い打ちを掛けるような突然の土砂降りの雨。
ずぶ濡れになりながら俺は道すがらのビルの軒先に駆け込んだ。
「参ったな。いつまで降るんだ?」
雨空を見上げながら俺はぼやいた。
天気予報は一日中晴れのはずだったから当然、傘なんて持ってはいなかったのだ。
その時だった。
「ミャア」
「えっ?」
思いも寄らぬ鳴き声に驚いて声のした方を見るとそこには先客がいた。
軒先の隅が暗くて気が付かなかったのだが
一匹の痩せ細った黒猫が俺に何かを訴えるように又、鳴いた。
まだ若い猫に見える。
しかもオッドアイというんだったか、右目と左目の色が違っていた。
「へぇ、お前。変わってるな。何処の魔法使いに飼われているんだい?」
つい、そんな言葉が出てしまうほど不思議な輝きの瞳に見えたのだ。
「ミャア」
「何だよ、どうした?」
俺は屈むと猫の頭を撫でながら訊いた。
猫は答えない代わりに屈んだ俺の足下に何度も頭をすり付けた。
「困ったなぁ-。懐いてくれるのは嬉しいんだけど
でも、お前を連れて帰る訳にはいかないんだよ」
猫は聞えていない風で俺の足下で寄り添うように香箱座りをした。
「寒いのか? そっか、濡れているもんな。
少しでも温まるんなら、もう少しそうしていろよ」
最初は雨の音で聞えなかったのだが、確かに猫は喉を鳴らしていた。
やがて雨が上がると俺は立ち上がった。
猫は俺を見上げるとひと声「ミャア」と鳴いた。
俺はまた屈むと猫の頭を撫でながら言い含めるように呟いた。
「ごめんな。俺のアパートじゃ猫は飼えないんだ」
良く見ると猫には首輪が付いてはいなかった。
「そっか。お前、帰る家も無いのか?
でも、困ったなぁー。やっぱりお前を連れて行けないよ」
とは言え、いつまた雨が降るかも知れない。
考えあぐねた末に
俺はリュックからパーカーを取り出すと濡れていた猫をくるんで
胸元に抱えると帰り道を歩き始めた。
「良いか? 今夜だけだぞ。
明日、もし晴れたら何処かもっと良い場所を探しに行けよ」
判っているはずはないのだが猫は「ミャア」と返事をするように鳴いた。
それから安心したのかパーカーにくるまれたまま猫は目を瞑った。
猫を胸元に抱いているといっそうゴロゴロと喉を鳴らす音が感じられた。
人を和ませるような温かな音だと思った。
猫を抱えてタクシーに乗る訳にはいかないと
改めてアパートまで歩いて帰る覚悟を決めたのだが
独りじゃ無いと思えただけで何だか気持ちは軽くなったように感じていた。
小一時間も歩いただろうか。
アパートの前まで来ると抱えていた猫は急にムクッと頭をもたげると
「ミャア」とひと声鳴いて俺の胸から飛び降りた。
そしてそのまま、まるで俺の部屋が二階だと判っているかのように
一気に階段を駆け上がっていった。
「おい、待てよ! おい!」
俺も慌てて猫を追いかけて階段を駆け上がった。
そして階段を上りきって部屋の前を見ると
そこには猫を抱えた美里が鳩が豆鉄砲を喰らったような顔をして立っていた。
「えっ? 美里? どうして?」
驚いたのは俺も同じだった。
俺の問い掛けに我に返って美里が答えた。
「あっ、あぁ。急にゴメンね。部屋のカギを返しに来たの。
スペアが無いと困るだろうと思って・・・」
「こんな時間に? そんなのいつでも良かったのに。
それより寒かったろ? 部屋に入っていれば良かったのに」
それには答えずに美里が言った。
「あっ、この猫ちゃん、知ってる?
何か階段で音がしたと思ったら急に猫ちゃんが飛びついて来て・・・」
見ると猫は美里に大人しく抱えられたまま目を瞑っていた。
雄か雌か気付かなかったが、どうやら奴は雄のようだ。
ここまで喉を鳴らす音が聞えてくる。
しかも、俺が抱いていた時よりも心地良さそうな喉の鳴らし方に思えた。
「あぁ、さっき知り合ったんだ。けっこうイケメンだろ?」
「うふふ、そうね。可愛い」
美里はそう言うと抱えていた猫に頬ずりをした。
「そうだ、丁度良かった。そいつを連れて部屋で待っててくれないか?
そいつ、お腹を空かせてると思うからコンビニでエサを買って来るよ」
「そうだったの。これも何かの縁ね」
俺は美里に猫との出会いの顛末を説明した。
「そうなんだけどね」
猫を見ながら俺は呟いた。
猫は買ってきたエサをがっつくように夢中で食べていた。
よほど、お腹を空かしていたに違いない。
その様子を楽しそうに見ながら美里は言った。
「で、この子。飼うことにしたの?」
「いや、無理だよ。ここじゃ飼えないしね。
かと言って、放って置くわけにも行かなかったしさ」
「弘樹らしいね」
「えっ? 何が?」
「いつもそう。自分のことより、いつも相手のことだったね。
しかも、後のことは考えずにさ」
「そうだっけ・・・ごめん」
「謝ることはないよ」
猫を眺めながら美里は呟いた。
そして俺を見ると悪戯っぽく笑いながら言った。
「どうせなら飼っちゃえば?」
「おい、よせよ。無理だよ。大家に知れたら俺が宿無しになっちまう」
「そしたら・・・」
美里は言いかけて止めた。
「そしたらって?」
「ううん、何でもない。
そっか、お前も行くとこがないんだね。そっか・・・」
「お前もって、美里は帰る部屋があるだろ?」
「うふふ。可笑しい。言葉尻を逃さないのは相変わらずだね」
「えっ? そうだっけ?」
「もちろん、帰る部屋はあるわよ。でも、行く場所をひとつ無くしちゃった」
「・・・」
行く場所? それはここのことを言っているのだろうか?
それとも、何処か行くはずだった場所のことだったのか?
俺は返す言葉を見つけられずにいた。
お腹がいっぱいになって満足をしたのか、エサを食べ終えると
猫は勝手に俺のベッドに上がり込むとそのまま布団の上で丸くなった。
どうやら今夜のねぐらを”ここ”と決めたようだ。
衣食足りて礼節を知るなんて言うが、どうやらそれは猫には関係ないらしい。
別にお礼を言われたい訳ではないけど猫はお腹が満たされて眠たくなったら寝る。
猫は寝子とは良く言ったものだ。
猫が嫌いな人にとっては、そういうところが気ままとか自分勝手に映るんだろう。
でも、猫好きにはそんなところも魅力に見えたりするに違いない。
じゃ、人間はどうなんろうか?
猫は確かに気ままだし、行動も自分勝手かもしれない。
だけど、猫はそれを人間に押しつけている訳ではない。
人間が勝手に猫を見て好きだとか嫌いだとか言っているだけだ。
俺は美里とのことを思い出しながらそんなことを考えていた。
「美里・・・」
「ん? 何?」
「俺、あれからもずっと考えていたんだけどさ。
確かに、俺は自分のことしか考えていなかったかも知れないなってさ。
いつだって俺は美里のことを一番に考えているんだって。
そう口では言いながら・・・つまり、なんて言うかさ。
でも、それって俺の独りよがりってか、単なる押しつけでしかなかったのかな?
とかね・・・」
「判ってるよ。弘樹の気持ち。私のことを本当にいつも思ってくれてた。
だけど、判っている自分とそれでも寂しいと思う自分がいたの」
「うん・・・」
「私も考えてた。弘樹のこと。
自分勝手は私の方だってことも本当は判ってた」
「いや、そんなことはないよ」
「ううん。だから謝らなきゃって思ったの。
思ったら・・・気が付いたらここに来ていた・・・
もう手遅れかも知れないけど、なんか今日じゃなきゃって」
「美里・・・いや、謝らなきゃいけないのは俺の方だよ。
美里。今度からは一緒に考えよう。何をするんでも、何でもさ」
「うん。そうだね。
きっと、頭の中だけで考えるから変な結論しか出せないんだよね。
だから、一緒に考えれば良いんだよね。自分だけで考えてないで」
「きっと、俺達に足りなかったのってそれだったのかもね。
それをあいつは教えてくれたのかも・・・考えるキッカケを・・・」
そう言いかけてベッドを見ると、そこに猫の姿はなかった。
「えっ? 何処へ行ったんだ?」
俺は布団をめくって、そこにいないと判ると次に屈んでベッドの下を探した。
美里も慌てて「猫ちゃん」と呼びながら洗面所や台所の隅を探していた。
所詮はワンルームのアパートだ。猫の隠れる場所だって、そうはない。
にも関わらず、何処に行ったのか? 結局、猫の行方は判らなかった。
「外は?」
言うと俺は窓の方へ駆け寄った。
しかし、窓のカギは閉まったままで、猫が出られる隙間すらなかった。
「えっ? 何処に行ったんだ? さっきまでそこにいたよね?」
俺は美里に確認をしたが、美里はただ頷くだけだった。
「こんなことってある? そうだ、押し入れは?」
押し入れを開けてはみたが、そこにも猫が隠れられる場所は見つからなかった。
長い沈黙が続いた。
雨宿りで駆け込んだビルの軒下で確かに俺はオッドアイの黒猫に出会った。
そして、猫をパーカーにくるんで抱えたまま俺はここまで歩いて来た。
そして美里と再会をした。猫はエサを食べてから確かにベッドの上で丸くなっていた。
つい、少し前までは。
「そうだ、エサは?」
見ると、エサを入れていた小皿がそのまま床に置かれていた。
「そうだ。確かに猫はいたんだ。でも・・・それじゃ何処へ?」
キツネにつままれるとは言うけど猫につままれるなんて話は聞いたことがない。
「何処へ行っちゃったのかしら?」
心配そうに美里も呟いた。
しかし、探すべき場所は他にはなかった。
「ちょっと外も見てくる」
そう言うと俺は部屋を出てアパートの周りをくまなく見て回った。
「おーい、猫ちゃん」
夜中だ。大声で叫ぶ訳にもいかない。
「しまった。どうして名前くらい付けてやらなかったんだろう?」
俺が部屋に戻ると美里は駆け寄って来た。
「どうだった?」
俺は黙ったまま首を横に振った。
部屋に戻った俺は何の気なしに美里のバッグに目をやった。
「えっ?」
「どうしたの?」
怪訝そうに美里が訊いた。
俺は美里のバッグを手に取ると思わず呟いた。
「そんな・・・まさかね・・・」
美里のバッグにぶら下がっていた黒猫のマスコット。
良く見てみると、その黒猫の目もオッドアイだった。