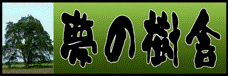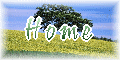
君のシアワセ
何も起きない事が幸せなんだよ。
もし、
辛い事や哀しい事がひとつも起こらないなら良い事だっていらない。
平凡で良い。平凡が良い。
何も無い毎日がただ繰り返してくれるなら、それで幸せだよ。
それが母の口癖だった。
もしかしたら、そう自分に言い聞かせていたのかも知れない。
でも『それにしては』とも思っていた。
それくらい母は何があっても動じる事も無く
いつも穏やかな笑みを浮かべていた。
まるで修学旅行先の京都のお寺で観た菩薩様のように。
父は私が物心がついた頃には既に定職にもついていずに
毎日朝から冷酒を飲み、たまに日雇いに出たと思ったら
その日は帰らずに真っ直ぐに競馬場に向かうか、
そうでなければ麻雀荘に入り浸っていた。
そして何日も帰って来なかった。
当然、家計は苦しくて母はクリーニング店のパートの他に
夜は幾らにもならない内職を遅くまでやっていた。
それでも母は愚痴ひとつこぼす訳でも無く、
私を普通に高校に通わせ、修学旅行にも行かせてくれた。
或る日、私は母に言った。
「私、明日からバイトをするよ。友達に頼んで決めて来たんだ。
私だって、もう高校生なんだし、少しはお母さんを助けてあげたいの」
すると、予想外の事を母は口にして私を強い口調で窘めた。
「生意気な事を言うもんじゃない。お前の仕事は何だい? 勉強をする事だよ。
バイトなんか断っておいで。そんな暇があったら勉強しなさい」
後にも先にも、私が母に窘められたのはこの時だけだった。
それはきっと母のプライドだったのだろう。
事実、自分がどんなに襟首のよれた服を着ていても
私にはもちろん安物ではあったけどいつも新品の服を着せてくれていた。
私が高校を卒業し、地元の会社に就職をして五年が過ぎた頃に父が突然倒れた。
幸か不幸か(私にはその時、そうとしか思えなかった)
父は一命を取り留めたが半身に麻痺が残り車イスの生活を余儀なくされた。
ただ、本当に幸いだったのは
父の酒はますます増えていったが、決して母にも私にも暴力を振るわなかった事だった。
半身が不自由だとは言え、全く動かない訳ではない。
良く、酔うと見境なく暴れては暴力を奮う男の話は聞いてはいたけど
私の恐れなど見事に肩透かしをくったかっこうだった。
その分、父は以前より無口になった。
感情さえも失くしてしまったかのように。
そんな父を母は当たり前のように甲斐甲斐しく世話をし
いつも笑顔で父に語りかけていた。
与えても与えても何も返される訳では無い。
親が子に与える愛は無償の愛だと言う。
夫婦、いや・・私にとってはまともな夫婦とは思えなかった母と父の間にも
そんな愛が存在していたのだろうか?
その時の私には知る由も無かった。
そんな生活が十年続いた。
私はとうに三十歳を過ぎていたが、ずっと独身を通していた。
「誰か良い人はいないのかい?」
時折り、母に言われるその一言が私の気持ちを責める時もあったが
(もちろん、母がそんなつもりで言った訳では無い事は解っていた)
私には母と父を見ていて”幸せな結婚”など思い描けなくなっていたのだ。
こんな私にでも付き合いを求めてくる男性がいなかった訳では無い。
職場の先輩は人柄も良く、仕事も出来たし後輩にも慕われていた。
結婚をしたら家庭的な夫になるのかも知れないと思いながら
それでも一歩先に踏み出せなかったのは私が結婚に対して臆病になっていたからかも知れない。
取引先の人からは良く見合い写真を見せられた。
銀行員、公務員、何処かの会社の社長の息子さんetc
どの人も父なんかとは比べ物にならないくらい
(父と比べる方が間違っていたのだろうけど)
真面目そうで、朝からお酒とかギャンブルとかとは無縁な感じの人ばかりだったが
誰もがみんな私とは住む世界が違う住民のように思えた。
結婚に対して臆病になっていたと言うよりも
むしろ、私には母のように強く振る舞える自信が無かったのだと思う。
そんな或る時、父が再び倒れてそのまま還らぬ人となった。
葬儀が滞りなく終わり、白い布に包まれた箱を抱えて私と母は家に戻った。
狭いアパートの居間の隅に白い布をかけた小さなテーブルを置き
そこに父の遺影と位牌、そして父の入った箱を置くと母は遺影に向かって手を合わせ
そして静かに肩を震わせて涙を流した。
「お母さん、終わったね」
私は台所に行きコンロにやかんをかけた。
そして、台所のテーブルのイスに腰掛けると溜まっていた新聞に目を通し始めた。
すると突然
静かな部屋にお湯の沸いた事を知らせるピーッと言う音が響いて私は慌ててコンロの火を止めた。
葬儀疲れで私もボーっとしていたようだ。
肩の荷が降りると、それと引き換えに虚無感がやってくる。
気持ちの良い気だるさなら歓迎したいところだったが、そんな良いものじゃ無かった。
『やれやれ』
自分をひとつ奮い立たせて
それから茶箪笥から茶筒と急須と湯呑を二つ取るとお茶を入れた。
「お母さん、お茶が入ったよ」
しかし、母はそれには答えなかった。
「お母さん・・・?」
母はいつまでも父の前を動こうとはしなかった。
「お母さん、少し休みなよ。お母さんまで倒れちゃうよ」
「いっそ、その方が良かったよ。お前の為にも・・・」
「お母さん、何を言うの!」
「ごめんよ・・・」
「何が『ごめんよ』よ? お母さんは何も悪く無いよ」
溢れるほどの涙・・・そんなものはドラマや小説の中の描写に過ぎないと思っていた。
だが、今の私はまさにその通りだった。
私と母は抱き締め合いながらいつまでも泣いていた。
お互いに「ごめんよ」「ごめんね」を繰り返して。
「お母さん、お父さんと結婚をして幸せだった時ってあったの?」
夕食の片づけをしながら私は母に訊いた。
まるで、それは愚問だとばかりに笑顔を取り戻した母は答えた。
「あぁ、ずっと幸せだったよ」
「ずっと? まさか!
だって、あんなにお酒ばかり飲むわ、ギャンブル三昧で
ろくに家にいないばかりか、一度だって稼いだお金を入れた事があった?
お母さんがどれだけ苦労していたかも、きっと知らないまま死んでいったんだわ」
「そうかも知れないねぇー でも、それで良かったんだよ」
「お母さん、お人よしも過ぎるよ」
「そうかい?」
母はいつもの笑顔でまるで他人事のように答えた。
「優しい人だったからねー」
「えっ? 誰が?」
「お父さんだよ」
そう言うと母は小さな祭壇に飾った父の遺影を愛おしむように見た。
母はどうしてそこまでキッパリと言い切れるのだろう?
私の知る限り、父が母に優しかった事なんて一度たりとも無かったのだ。
「それが証拠に、確かに家にお金は入れなかったかも知れないけどね。
あれだけギャンブルに現を抜かしていたけど借金だけはこさえなかったでしょ?
そう言う人なんだよ」
「ねぇ? いったい何処でお父さんと知り合ったの?
どうしてお父さんと結婚をしたの?」
私は母に訊かずにはいられなかった。
「そんな昔の話は・・・」
そう言いかけて母がフッと笑みを浮かべた。
「お父さんの前で嘘は付けないねぇ」
それからゆっくりと話し始めた母の話は私には衝撃的な内容だった。
「私は高校を卒業してからも仕事も決まらずにブラブラしていたんだよ。
そんな時、バッタリ会った高校時代の友達に誘われて・・・『パーティがある』ってね。
なんて事は無い。シンナー吸ったりさ、おかしな薬をやったりね。
あの頃の私はどうにかしていたんだね。
仕事も決まらず、家には居づらかったし。
まぁ、私の親はそんな事をガミガミ言う人じゃなかったけど、それが逆に辛かったんだよ。
で、お決まりのようにズルズルと転落の一途ってのかい?
万引きをやったり、カツアゲをやったり、どうしようも無い不良だったね。
そんなある時、街で高校時代の担任にバッタリとね。
それがお父さんだったんだよ。
お父さんは真剣に私に諭したけど、あの時の私には何も聞こえていなかったのさ。
それから何日かして仲間の居る所にお父さんが来てね。
私を抜けさせようと言い合っている内に揉み合いになって・・・
仲間の一人が持っていたナイフを出して・・奪い合っている時・・・刺してしまったんだよ、仲間を。
私は怖くなってすぐに逃げたんだ。ひどい女だよね?」
「それで?」
私は固唾を飲んで尋ねた。
「それから、どれくらいだったろうかね。
風の噂でお父さんがあの後、学校をクビになって
しかも、傷害で刑務所に入ってるって聞いたんだ」
「・・・」
「五年・・・だったかな。
お父さんが釈放されたって聞いて、居ても立ってもいられなくてね。
謝ろうと思ってアパートに尋ねて行ったんだ。
そしたら何て言ったと思う?」
「何て言ったの?」
「私に一言の文句を言う訳でも無く、嫌味を言う訳でも無くってさ。
一言『俺の撒いた種だ。お前には関係無いから早く帰れ。そして、もう来るな』
そんな事を言われたってね。
私だけ関係無いみたいな顔は出来ないだろ?
それから毎日、押し掛けてやったよ。
お父さん、あの頃から日雇い仕事みたいな仕事ばかりでさ。
無理も無いよね、刑務所なんか一度入ってしまったら定職なんかつけやしないよ。
だから、お父さんが出かけている時は勝手に部屋の掃除をしたり食事を作ったりね。
そんな事をしている内に、私も家に帰るのが面倒になってしまってさ」
そして、まるで愉快な昔話を思い出したようにクスッと笑って言った。
「そのまま押し掛け女房になったのさ」
母は当たり前のように父の祭壇の前に布団を引くとそのまますぐに静かな寝息を立てた。
無理も無い。通夜から葬儀が終わって今に至るまで一睡もしていなかったのだ。
今夜は母はどんな夢を見るのだろう?
嘘でも良い、それこそ夢でも良い。
せめて今夜だけは母に父との笑顔の想い出を見させてやって欲しいと願った。
そんな母の寝息を聴きながら私は眠れずにいた。
さっき聞いた母と父の話を思い出していたのだ。
そこには私の知らない母と父がいた。
当たり前の話だが、子供にとっては母と父は初めから母と父だったのだが
二人にとっては決してそうでは無かったのだ。
初めは懺悔だったのか? 同情だったのか?
しかし、やがてそれが確かな”愛”になった後ではどうでも良い事だったのだろう。
その時、母は確かに幸せだったのだから。
それから一年後。父の一周忌を見届けた後で母は父の後を追うように亡くなった。
一人ぼっちになった私はそれから毎日、版で押したように
ただ、会社とアパートの往復に明け暮れた。
会社帰りにたまに立ち寄るのも駅前のスーパーくらいだった。
一人で食べるモノなんてたかが知れている。
少しの野菜と小さなパックの肉とか魚とか、せいぜいそんなものだ。
それすら面倒になると惣菜売り場を覗いた。
スーパーの惣菜売り場では七時を過ぎると五十円引きとか百円引きとか
運が良ければ半額のシールが貼られる。
ただ、半額のシールが貼られる頃にはほとんど選べる程の惣菜は残ってはいなかった。
ある夜、スーパーの惣菜売り場を物色していると。ふいに後ろから声を掛けられた。
「えっ? あっ! 増井さん」
「やぁ、優子さん。こんばんは。心配していたんだよ。元気だったかい?」
「え、えぇ。お蔭様で何とか少し落ち着きました」
「そうか、そりゃ良かった」
「あっ、そう言えば・・・父の時も母の時もわざわざご焼香頂いていたのに
何のお礼もしないままで済みませんでした」
私は増井さんに深々と礼をした。
「いや、良いんだよ。さぁ、こんな所でなんだ・・頭を上げて」
「は、はい。増井さんはお使いですか?」
「えっ? あぁ・・・まぁね。
実は私もね。先週、女房の四十九日を済ませたところなんだ」
「そうなんですか!? それは・・知らなかったとは言え失礼しました。
どうしよう? 私、ご葬儀にも・・・」
「いや、良いんだ。身内だけでひっそりと済ませたからね」
「そうだったんですか・・・あっ、今度、失礼じゃなかったらお宅に焼香にお邪魔させて下さい」
「いや、良いんだよ。そんな気にしないで」
「いえ、ぜひ。こんなご無礼をしていたら母に叱られますから」
次の日曜日。私は増井さんのお宅に伺って焼香をさせてもらった。
増井さんの奥さんの祭壇は父のそれとは大違いで
カサブランカだろうか? 白い大きなユリとか淡いブルーやピンクの可愛い花々で飾られていた。
「済まなかったね。こんな立派な花まで頂いて、逆に申し訳ないよ」
「いえ・・・」
増井さんの奥さんの祭壇に飾られている花々を見てしまうと
私の選んだ花が安っぽく見えて思わず恐縮してしまった。
「さぁ、こっちへ」
増井さんは私を居間のソファに手招くとコーヒーをテーブルに置いて又、お礼を繰り返した。
「せっかくの休みだったろうに、わざわざ来てもらって済まなかったね」
「とんでもありません。増井さんには昔から何かとお世話になっていたのに」
「私は何もしてないよ」
「いえ・・・そう言えば。昔は良くお見合い写真を頂きましたよね?
それなのに私ったらワガママばかり言って」
「あはは、そんな事も有ったかな」
「はい、済みません」
「あはは、もう良いよ。そんなにかしこまられるとこっちが恐縮しちゃうなぁ」
「でも、どうして私にばかりお見合いの話を?
あの頃は他にもたくさん女子社員がいたのに。
やっぱり、私って見るからに行き遅れそうでした?」
「えっ? そんな事はないよ。
そうね・・・娘と名前が一緒だったからかな。
確か、優しい子で『優子』さんだったよね?」
「はい。じゃ、娘さんも?」
「あぁ。十五歳で亡くなってしまったけどね」
「そうだったんですか・・・」
「だから、優子さんには娘の分も幸せになって欲しかったんだ。
まぁ、勝手に余計なお世話をしていただけだけどね」
そう言って増井さんは照れたように頭を掻いた。
突然の言葉に私は返す言葉も見つからなかった。
「あっ、コーヒーが冷めるよ。飲んで、飲んで。
こう見えても私は昔、喫茶店のマスターに憧れていてね。
コーヒーには少々うるさいんだ。
もちろん、ガミガミと飲み方がどうとは言わないけどね」
増井さんはわざとおどけてウインクをして見せた。
コーヒーを飲みながらひとしきり世間話に花を咲かせた。
得意先の増井さんとしか知らなかったが
話をしてみると実に趣味の幅も広くて、意外な面もたくさん垣間見えた。
ふと私はいつも疑問に思っていた事を訊いてみたくなった。
「増井さんは幸せな人生でしたか?
幸せって何だと思います?」
「どうしたの? 何か有った?」
「そうですね。有ったと言えば有り過ぎたし、無かったと言えば何も無さ過ぎました」
「そうですか・・・ あっ、どうです? もう一杯?
そうそう! そう言えば確か・・・良い貰い物が有るんですよ」
増井さんはそう言うと中座をして台所に行ったかと思うとクッキーの缶を持って戻って来た。
「これこれ。けっこう美味しいんですけどね、一人じゃ食べきれないんですよ」
そう言って私に缶を開けてクッキーを勧め、
それから自分も向かいのソファに座り直すと口を開いた。
「そうね。幸せか・・・難しい質問ですね。
人によっても違うし、感じ方も人それぞれだしね。
幸せの尺度って言うのかな。
そもそも、幸せに<絶対>って無いじゃないですか?
これがこうなら絶対に誰もが幸せだ、なんてね。
愛する事に幸せを感じる人、愛される事で幸せを感じる人。
お金があれば幸せだと言う人もいれば、お金より愛が大事だって言う人もいるよね。
仕事に生きがいを見出す人もいれば、家族円満が幸せだと言う人もね。
平凡な生活が幸せだと言う人、スリルがある生活じゃ無きゃ生きていると実感出来ない人。
本当に様々なんだ。
何処の何を以って幸せだと思うのか?
例えば、周りの誰から見てもほぼ満点の人がいたとしたって
たったひとつの欠点が自分にはどうしても許せないと思ったらアウトだよね?
他の人にしたら、『なんで、それくらい』と思う事でも許せないものは許せないよね。
逆に、周りの誰もがほぼ百パーセント『あいつはダメだ』と言ったって
自分にとって響くものがひとつでもあれば、自分にとっては大事な人ってなる。
そもそも、幸せって他人が決めるものじゃなくって、自分が感じるものなんだからね」
「まさに、母にとっては今のお話がそのままだったかも知れません。
あの、少し聴いてもらっても良いですか?」
増井さんと話をしているうちに
『この人になら聴いてもらいたい。この人なら真剣に聴いてくれるに違い無い』
勝手にそう思うようになっていたのだ。
私は、私の知っている母と父の事。
それから、母から聞いた私の知らなかった母と父の事を全て隠さずに増井さんに話した。
「んー、壮絶な話だね」
話を聞き終えた増井さんは残っていたコーヒーを一気に飲み干すと深くひとつ溜め息をついた。
「比べてはいけないんだろうけど、私にはお母さんのような生き方は出来ないだろうと思ったよ。
話を聴いていてね。私は自分は何て幸せだったんだろうと思った、正直に言えばね。
でも、その反面・・・何て言うかな? お母さんが羨ましくも思ったんだ」
「羨ましい? 母が・・・ですか?」
「うん。羨ましかった。いや、お父さんが・・・かな?
いや、きっとどっちもだな」
「どっちもですか?」
「信じられない?」
「えぇ」
「そうかな? 今の優子さんが一番良く解っているんじゃない?
確かにね。お母さんはいつも、どんな時でも笑顔を絶やさなかったって言ったよね?
それは菩薩様の慈悲の笑みのようだったと」
「はい。それくらい凄いと思ってました」
「うん。そうだったろうね。
仮に、それが菩薩様の慈悲の笑みでは無くて
そうね・・笑顔を続ける事でしか自分を保てなかったとしても・・・
一度でも、泣いてしまうと全てが崩れてしまうからと自分に言い聞かせていた笑顔だったとしても
だからって、それを続けられるのは並大抵の事では無いよ。
それは或る意味、<愛>以外の何物でも無かったんじゃないかな?
それをお母さんは必死になって守ろうとしていたんだと思うな」
「・・・」
「私はもうすぐ五十六歳だ。
多分、優子さんのお父さんやお母さんの年代とは十歳も離れていたかどうかだろうね。
でも、私が例えその歳に追い付いたとしたって、お二人のようにはなれないと思う。
それくらい濃密な人生だったんじゃないかな。
それだけ、お母さんの愛は深かったはずだよ。そして、それ以上にお父さんの愛もね」
「父の? そんな事は絶対ありません!」
私はつい感情的に言い返してしまった。
「あんな父なんて・・・私はいつも大嫌いでした。一度だって好きになった事はありません」
「優子さん、落ち着いて。
人ってね、相手への愛が深ければ深いほど
それが形に出来ない時に自分の不甲斐なさと言うのかな。
自分への憤りとか言うか・・・自分を責め立てるものなんだよ。
それに耐え切れなくなると現実逃避をする。
他人から見れば、それはただの逃げにしか見えないだろうけど
それは一種の・・・そう、自己防衛の本能みたいなものなんだよ。
多分・・・優子さんのお父さんのようにね。
それをある人はダメな奴だとか、不器用だとか言うかも知れない。
でもね、私は思うんだ。それだけ真正直過ぎたんだとね。
多分、優子さんはお二人を身近に見過ぎていたから
感情的な見方しか出来なくなっていたんじゃないかな?
無理も無い。それだけ苦労もして来たんだろうし・・・」
そんな事は増井さんに言われるまで思っても見なかった。
父が母を母以上に愛していた?
にわかには信じられなかった。
それを簡単に信じるには、余りに失くしたものが多過ぎたのだ。
でも・・・
もし、増井さんの言う事が正しかったとしたら?
私の心は大きく動揺していた。
「優子さんはいくつになるのかな?」
その言葉にふと我に返った。
「えっ? 私ですか? 今年で四十二歳です」
「そうですか。じゃ、今度は私から質問をしましょう。
優子さんの幸せって何でしょうね?」
「私の・・・幸せ・・・ですか?」
「はい、優子さんの幸せです」
「それは・・・」
答えにならなかった。
父を亡くし、母を亡くし、少なくともこれ以上に失うものは無かった。
毎日が会社とアパートの往復。
アパートの部屋にいると誰とも話す事もなく、多分・・・独り言も言わず。
ただ、さざ波すらも立たない毎日。
特に趣味も無く、欲しいものも無く、食べたいものも無い。
これでも私は生きていると言えるんだろうか?
何も疑問に思わなかった事が、今こうして増井さんと話していると不安をかき立てた。
「結婚はどうです? 考えた事は一度も無かったんですか?」
「結婚・・・ですか?」
「えぇ」
「父が生きていた頃は結婚どころでは無かったです。
第一、あんな父を結婚相手やご家族に紹介できる訳も無かったし」
「それでも、本当に好きな人がいたなら駆け落ちをしたって良かったじゃないですか」
「そんな事まで頭が回っていませんでした」
「そうですか。いやね、別に結婚は女性の幸せだなんて決めつけるつもりは無いんですよ。
仕事をバリバリやっていて輝いている女性だって今は多いですからね。
さっきも言いましたが、幸せって人それぞれなんですよ。
心が決めるものなんですから、決まった形だって無いんです。
でもね。自分なりの幸せって必ず有るはずなんです。
想像した事はありませんか? 自分が幸せになっている姿を」
「・・・無いです」
「そうですか。じゃ、こうしましょう。これから見つけるんです。
四十二歳なんて、女性の平均寿命からしたら未だ半分以上、人生は残っているんですよ。
このまま何もせずに、何も望まずに生きるなんてもったいないじゃないですか。
そう思いませんか?
優子さんの幸せ・・・きっと見つけられますよ」
増井さんはそう言うとにこやかな笑みを浮かべた。
「それで、それから君はどうしたの?」
それまで黙って話を聴いていた慎二が口を開いた。
「まず、毎日の通勤経路を変えたわ。
朝はバス停ひとつ分を歩いて、その先からバスに乗るようにしたの。
帰りは、駅の反対側に一度出てからグルッと遠回りをして歩いて帰った」
「へぇー」
「そしたらね。景色がまるで違ったの。私の知っている街じゃ無いみたいだった」
「うん。それで?」
「それからね。お風呂で身体を洗う順番を変えた」
「へぇー それは又、思い切ったね(笑)」
「そうよー 習慣って案外変えられないものなのよ。
でも、やった。
それから、ついでにそれまで持っていた服も下着も全部棄てたの」
「Rebornだね」
「そうね。そんな感じだった」
優子はアパートの部屋の窓際に歩いて行くとカーテンを左右に開けた。
優子の住んでいる街の灯りの遥か向こう側に超高層ビル群の灯りが見えた。
「昔は・・・別世界だったな」
「何が?」
慎二も窓際に来て優子と並んで外を見た。
「あの高いビル。ううん、あそこのマンションの灯りも、そう・・この隣の家の灯りも。
ぜーんぶ、別世界だった」
「今は?」
「うふふ。今は同じ世界よ」
そう言うと優子は慎二の腕に寄り掛かかった。
「増井さんには感謝しなくっちゃ」
「そうだね。俺達の縁結びの神様だからね」
慎二は増井の会社の後輩で四十八歳、やはり数年前に奥さんを亡くしていた。
男の子が二人いるが、二人共もう独立して暮らしていた。
そんな慎二に優子を紹介したのが増井だったのだ。
「でも、君のシアワセがこんな俺で良かったのかな?
再婚だし、金持ちじゃ無いし、自分で言うのも何だけど決してハンサムじゃ無いし、万年係長だし」
「じゃ、あなたの幸せはこんな私で良かったの?
手近なところで済ませ過ぎたとか思ってない?」
「あはは、そんな事は無いさ。
青い鳥を探していたら、たまたま近くにいた・・・シアワセってそう言うもんでしょ」
「メーテルリンクね? じゃ、私がミチルであなたがチルチルね?」
「いや、残念ながら、そこは童話と一緒じゃ困るところだな」
「えっ? どうして?」
「あはは、兄妹じゃ結婚出来ないだろ?」
「うふふ。そうね、それは困るわ。
ねぇ? チルチルとミチルが最初に行ったのは『思い出の国』だっけ?」
「えー? そうだっけ? 良く覚えてないな」
「確か、こうよ。死んだはずのおじいさんとおばあさんにそこで会うの。
そしたら、おじいさんがね。
『人は死んでも、皆が心の中で思い出してくれたなら、いつでも会う事が出来るんだよ』
そう言うのよ。
私、今すぐにでもお父さんとお母さんに会いたいな」
「優子・・・」
「そしてね。あなたを紹介するの。
『お父さん、お母さん。この人が私のシアワセです』ってね」
母が父を深く愛していた。それは解るとして父も又、母をそれ以上に深く愛していた。
そんな増井さんの言葉も二人が亡くなった今となっては確かめようも無いけど
あの瞬間、私は救われた。その事だけは確かだった。
だから私は今までの全てを受け入れる事が出来たし、それが有ったから私は変われたのだと思う。
先の事は解らない。
解らないけど、それで良いのだ。
ささやかでも、今ここに私のシアワセが確かに在るのだから。