
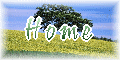
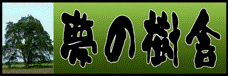
迷 い 星
勤続三十年という事で
会社から一週間のリフレッシュ休暇をもらった事もあり
野暮用ついでに俺は久しぶりに故郷に戻った。
十年前に父親を、そして三年前には母親を亡くして
もう戻る事もないと思っていた故郷だったが
実家の土地を買いたいという人がいるという連絡が
仲介を頼んでいた不動産屋から入ったので
その手続き等もあったし
何より、お盆を二ヶ月後に控えて久しぶりの墓参りもしたいと思っていたのだ。
故郷に帰るに際して地元の友人には連絡をしていたので
その夜は友人達と繁華街の居酒屋に集まった。
高校の同級生で今でも一番親しい友人の晃とその奥さんの有希。
そして、高校時代に晃と通っていた喫茶店で親しくなり
それ以来付き合いの続いている智宏と奥さんの優子。
そして、早めに店じまいをして駆けつけてくれたその喫茶店のマスターの祐二さん。
何故か当時喫茶店でバイトをしていた真美ちゃんもいた。
何と今はマスター婦人なんだとか。
歳も確か十五歳はマスターより下だったはずだ。
「ところで、どうなんだよ?」
タバコに火を付けながら晃が訊いてきた。
「何が?」
その質問の意味を解っていながらトボけたフリをして俺は返した。
「何がじゃねぇよ。結婚だよ、結婚!」
「あぁ」
「あぁって。お前ねぇー、結婚する気はないのかよ?」
「いや、別に。縁があればいつだってするさ」
「確か、二十年前も同じ事を言ってたよな? 十年前もだけど」
「そうだっけ?」
「お前ねぇ-、他人事じゃないんだぜ。解ってる?」
「そうは言ってもなぁー。
でも、いくら結婚をしたいって言っても一人じゃ出来ないしさ」
「理想が高過ぎるんじゃないですか? 和也さん、モテそうですもねぇー」
焼き鳥を頬張りながら真美ちゃんが口を挟んできた。
「そんな事はないよ」
「ダメですよぉー、適当なとこで手を打たないとぉ。
私みたいに、ねぇ?」
真美ちゃんはそう言うと悪戯っぽく笑って祐二さんを見た。
「適当なとこで手を打ったのは俺だよ。
誰だっけ? 酔ったフリをして俺に無理矢理キスをしてきたのは?」
お返しとばかりに祐二さんが真美ちゃんに言った。
「ひどーい! アレはマスターがしたそうにしてたからですよぉー」
「まぁまぁ。痴話ゲンカは帰ってからにしましょ!」
笑いながら有希が二人をなだめた。
「でもホント、不思議よね。うちの人と違って優しいしハンサムなのに」
晃の顔を見ながら有希が言った。
「おいおい、それはどういう意味だよ?」
「そういう意味よ」
「意味が解んないんだけど」
晃が口を尖らせた。
「いやぁーねぇー 自分を知らないって怖いわぁ」
「すまんね。それが解ってりゃお前とは結婚してないよ」
「あら、ねぇ? 聞きましたぁ、奥様?
どの口が言ってるのかしらねぇ-?」
有希が隣の優子の膝をチョンと叩いて答えを促した。
「それ私が答えるの?」
優子が苦笑しながら有希に訊いた。
「えぇ、言って差し上げたら?
『結婚前の浮気がバレた時に泣きながら土下座までして
もうしません、もうしませんって謝った後で
有希さんに結婚をせがんだのは晃、お前だろー?』ってね」
すまし顔で有希が答えた。
「おいおい、いったいいつまで俺は十字架を背負わされるんだよ?
もう何十年経ってると思ってる? いい加減に時効にしてくれよぉー!」
「だって面白いんだもん」
「あのなぁー ・・・もう!」
どう言っても勝ち目のない晃はグイッと一息でビールを飲み干した。
「はい、これで私の387連勝ね、やったぁー!」
有希はわざと大袈裟に万歳をしてみせた。
「なんでいっつもこうなるんだよ?
今日はみんなで和也を攻めるんじゃなかったのかよ?」
「なんで和也クンを? そんなひどい事、私ぃ出来なぁーい。
私は和也クンの味方だしぃ」
「おいおい、お前こそ、どの口が言ってるんだよ?
和也が来る前は『今度こそ絶対に和也クンを結婚する気にさせる』
とか言ってたくせに」
「このク・チ。女の口はいっぱいあるのよ」
有希が笑いながら人差し指を自分の口に当ててみせた。
「お前なぁー」
相変わらず何を言っても漫才に聞こえるくらい息もピッタリの仲の良い夫婦だ。
結婚をしてもう三十年近く経つというのに昔と全く変わっていない。
今年のクリスマスの頃には息子さん夫婦に待望の赤ちゃんが産まれるんだとか。
きっと二人共、良いじーちゃんとばーちゃんになるに違いないと思った。
二人を見ながらそんな事を考えていると今度は優子が話をぶり返してきた。
「ねぇ。和也さんって、もしかしてこっち系だった?」
右手の甲を左の頬につけてオネエポーズで優子が言った。
「マジかよ?」
智宏が俺の顔をマジマジと見た。
「な、訳ないよ」
俺は思わずマジレスをしてしまった。
「じゃ、どうして? 別に童貞を守ってるって訳でもないだろ?」
智宏が言うと女性陣がザワついた。
「キャー! 和也クンって童貞なの?」
「あーん、もう少し早く知ってたら私が奪ってあげたのにぃ-」
「おいおい、お前ら酔っ払ってんじゃねぇーよ」
晃が笑いながら言った。
それに被せて更に智宏が言った。
「あっ、童貞はないか? 彼女いたもんな。じゃあ、なんで?」
俺は立て続けに振られる質問攻めに苦笑をするしかなかった。
「ねぇ、そう言えば・・・」
晃の顔を伺いながら急に真面目なトーンで有希が言った。
「今更、こんな話を言って良いのか判らないけど」
晃は黙って頷いた。
それを見て有希は言葉を続けた。
「美奈子ちゃんね。一昨年に離婚したのよ。
ご主人のDVが理由だったみたい。
今は信金時代の経歴を買われて商工会議所で働きながら
娘の真奈ちゃんと二人で駅裏のマンションに住んでいるわ」
突然、出てきた美奈子の名前に俺は思いっきり動揺をした。
「なぁ、どうせ毎日朝から晩まで就活をしてる訳じゃないんだろ?
きっと気分転換にもなると思うし、何より人助けだと思ってさ。
週に二~三日で良いから、ちょっと手伝ってくれないか?」
もう三十一、二年前の事だ。
卒業前に就職が決まらなかった俺は
地元に戻って一年間就職浪人をしていた時に
晃の誘いでとあるボランティアの手伝いをする事になった。
そんな或る日、その日の仕事が終わって帰ろうとしていた時だった。
「山崎さん? 山崎さんって高梨さんの友達でしたよね?」
そう言って声を掛けてきたのが菅原美奈子だった。
「えっ? あぁ、そうだけど」
菅原美奈子の第一印象はセミロングの髪が似合う明るい子だった。
実際、笑うと目尻が下がってクシャクシャな笑顔になるんだけど
それが又、嘘なくらい可愛かった。
人伝に聞いた話だと歳は俺より二つ下で地元の信用金庫に勤めているらしい。
ボランティアでは同じ班になる事はなくて
あまり話した事も無かったけど俺はしっかりチェックだけはしていたのだ。
その美奈子から俺に話しかけてきたのだ。
俺はちょっとドキドキしながらも努めて平静さを装って聞き返した。
「何?」
聞き返す俺に美奈子は少しためらいながら口を開いた。
いつも遠くから見ていた笑顔ではなくむしろ神妙な面持ちだったが
そんな顔も又、素敵だと思った。
「すみません。いきなりな話なんですけど・・・
あのぉ、私の友達の有希が高梨さんの事を好きらしくて。
で、私『いつも傍にいるんだからチャンスはあるでしょ?
思い切ってアタックしたら?』って言ってたんですけど。
でも、いざとなるとなかなか高梨さんに言えなかったみたいで。
で、私。なんとかしてあげたいなって・・・
で、その・・・高梨さんに・・・訊いてもらえませんか?
有希はシッカリ者だし、料理なんかも得意で・・・えーっと・・・
そう! でも、他人の面倒見は良いくせに自分の事になるとからっきしで
とにかく良い子なんです! だから、その・・・」
「晃?」
俺は内心ちょっとガッカリしたけど、まぁ現実はそういうもんだろう。
「有希さんって・・・あぁ、晃と同じ班のショートカットの子だっけ?」
「はい、傍で見ていても二人は良い感じに見えるんですけど
でも、何だか高梨さんの方が、何て言うのか・・・
あのぉ、高梨さんって彼女とかいるんですか?」
「んー、今はいないと思うけどね」
「ホントですか! じゃ、ぜひお願いします!
高梨さんに有希の事をどう思っているのか訊いてもらえませんか?
ダメならダメでも良いんです。
でも、ハッキリしないと有希もケジメが付かないと思うし」
「オーケー。解った。訊いてみるよ」
「ありがとうございます!」
そう言うと美奈子はペコリと頭を下げた。
『さてさて、引き受けはしたものの、どうやって晃に話そうか?
こりゃ、責任重大だぞ!』
俺の話し方ひとつで、もしかしたら上手くいくかもしれないし
もしかしたら全てがオジャンになるかもしれない。
上手くいけば美奈子に感謝をされるだろうけど
万が一、上手くいかなければ美奈子に頼りない男だと思われてしまうだろう。
『さて、どうやって・・・』
俺はしばし腕を組んであれやこれやと作戦を考えていた。
ところが実はこれは晃と有希が考えた計略だったのだ。
もちろん、これは後で解った事ではあるんだけど
その時には二人はもう既に付き合っていて
なんと晃と有希は俺と美奈子を近づけようとしていたのだ。
それを知らない俺はその夜、晃に電話をした。
『おぉ、どうした?』
考えあぐねた末に出した結論。
それは単刀直入だった。
なんとも我ながら情けない結論だと思った。
だが、下手な小細工はむしろ上手くいく事さえダメにするような気がしていた。
「いや、実は今日。菅原美奈子が来てさ」
『菅原? あぁ、お前が前に可愛いって言ってた子な? それで?』
「うん、それでね。有希さんってお前の班にいるだろ?
その子がお前の事を好きだって言うんだ。
で、今彼女がいないのなら付き合ってくれないか訊いてくれって言われてさ」
『有希? あぁ、有希ね・・・』
「どう?」
『どうって・・・まぁ、可愛い子だと思うよ』
「じゃ、付き合ってみたら?」
『そうだな、考えておくよ』
何だか、いつもの晃らしくなく妙に素っ気ない返事だった。
「何だよ? 気に入らないのか?」
『いや、そういう訳じゃ・・・
そうだ! そしたらさ。今度の日曜日に四人で会わないか?
いきなり二人でって言われても、何か照れくさいしさ。
良いだろ? 付き合えよ。お前にも責任はあるんだからさ』
「責任? 責任って何だよ?」
『お前、菅原美奈子が可愛いって言ってたろ?』
「まぁ・・・」
『なら、ここで親しくなっておくのってお前にとってもチャンスじゃない?』
次の日曜日。祐二さんの喫茶店で四人で会った。
他愛もない話やお互いの小さかった頃の話とかで盛り上がって
気が付けば四時間以上が経って時間は夕方の六時を過ぎていた。
「おっ、もうこんな時間か? 有希、この後どうする?
時間があるなら何処かで食事でもしてく?」
晃が有希に訊いた。
「はい、喜んで!」
有希は笑顔で答えた。
「お前らも行くだろ?」
晃が俺に訊いた。
「いや、これ以上お邪魔虫はしないよ。お二人で仲良くどうぞ」
「そっか。そしたら和也。お前、ちゃんと美奈子さんを送って行けよ」
「えっ? 俺?」
「何を言ってんだよ。当たり前だろ?」
「でも、美奈子さんだって都合とか・・・ねぇ?」
「いやでも、山崎さんに迷惑だし・・・」
俺と晃を見比べながら戸惑いの表情を見せる美奈子。
「そんな事はないよ。なぁ?」
晃が俺の背中を押した。
「もちろん」
「じゃ、美奈子さんを頼んだぞ」
そう言って晃は俺の肩をポンと叩くと有希と連れだって店を出て行った。
<美奈子さんを頼んだぞ>の意味がどういう意味だったのかはともかく
今、思うとしらじらしいくらいの晃と有希の小芝居に乗せられたかっこうで
店を出た後、俺は美奈子を送る事になった。
「あの二人、かなり良い感じでしたよね。きっと上手くいきますね」
歩きながら美奈子は本当に嬉しそうに言った。
「そうだね。上手くいくんじゃない?
何だか、あの二人はもう何年も付き合ってるみたいに自然に話が合っていたしさ」
「ですね。良かったぁ」
まるで自分の事のように美奈子は心からの笑顔を見せた。
その笑顔は俺の心臓を射貫くには十分過ぎるくらいの威力があった。
キッカケはともかく。
その件があったお陰で俺達も自然に付き合うようになっていった。
幸せな時間だった。
愛し合うという事は決して時間の長さではなくて
その期間にどれだけお互いの想いを尽くせるのか?
その深さなのだと実感できた日々だった。
それから夏が来て秋になり年が明けて
やがて冬が盛りを過ぎた頃、ようやく俺の就職が決まった。
「ホント!? 良かったね。うん、良かった!」
祐二さんの店のいつものカウンターではなく
その日は窓際のボックスの席に美奈子を座らせて就職の報告をした。
先ずは誰よりも先に美奈子に聞いて欲しかったのだ。
「ありがとう。何だかね。ようやくスタートラインに立てた気分だよ」
「そうね。大変なのは働き始めてからだものね。
何でも相談して。こう見えて私の方が社会人としては先輩だから」
「はいはい。お願いします! 頼りにしてます、先輩!」
「オッケー、任せといて! って、言いたいとこだけど。
でも、和也の方がずっと大人だもんね。
私なんか、頼りになるかしら?」
「あはは、頼りになるよ。さすがに信金勤めだけあってシッカリしてるしさ。
美奈子になら結婚をしても安心して給料を全部預けられるよ」
「えっ?」
驚いた顔で美奈子が俺を見た。
「オホン!」
ひとつ咳払いをすると席に座り直して俺は美奈子の目を見て言葉を続けた。
「あのさ。実はもうひとつ報告があるんだ」
「・・・」
「実は勤務先なんだけどね。S市に配属される事になったんだ」
「S市? そっか、けっこう遠いね・・・」
俺の視線を外して窓の外を見ながら美奈子はポツンと言った。
S市はここからだとJRでも五時間はかかるし車だと六時間近くはかかる距離にある。
「それでさ。あの・・・そんなに頻繁には戻って来れないと思う。
入社したら一ヶ月はビッシリ研修もあるし・・・
だから、その・・・一緒に来て欲しいんだ。
もちろん、美奈子も仕事の事だってあるだろうからすぐにとは言わないけど。
でも、なるべく早く来て欲しい。 美奈子、結婚しよう!」
「・・・」
目の前には戸惑った顔の美奈子がいた。
取らぬ狸の皮算用とはまさにさっきまで自惚れていた俺だ。
結婚の時期はともかく、すぐに良い返事がもらえるものだとばかり思っていたし
その<答え>しか想定してはいなかったのだ。
取り繕うように俺は続けた。
「いや、だから・・・すぐじゃなくて良いんだ。
美奈子の仕事が・・・」
そう言いかけた時に美奈子が呟いた。
「ありがとう。とても嬉しい・・・
でも、すぐに返事は出来ない・・・ごめんね」
「いや、良いよ。そんな急に言われたってね」
自嘲気味に俺は言った。
「そんなんじゃないの。ただ・・・すぐには決められない・・・」
「うん、判った。良く考えてくれないか?
俺は美奈子に一緒に行って欲しい。いや、美奈子と一緒に行きたいんだ」
「うん・・・ごめんね」
美奈子の結論が貰えないまま俺はS市に赴任した。
もちろん、それまでも変わらずに美奈子とは会っていたし
俺が赴任してからも二日に一度は電話をし他愛もない会話に笑い合っていた。
月に一度は極力帰って美奈子との時間を作っていた。
会っている時の美奈子は<何事>も無かったかのように
それまでと何ら変わらずに俺を愛してくれた。
俺も美奈子を愛した。
俺はいつも美奈子の結論・・・もちろん、良い意味での結論を待っていた。
でも、訊けなかった。訊くのが怖かったのだ。
俺が急げば急ぐほど出る結論は悪いものになるんじゃないか?
そんな思いがいつも俺の頭の中にあった。
そしてそれは現実になった。
美奈子の家庭は母子家庭でまだ高校生の妹と中学生の弟がいた。
母親が女手ひとつで美奈子達を育ててくれていたのだが
長年の無理がたたり、その頃母親は入退院を繰り返すようになっていた。
フルタイムで働けない母親の代わりに
高校を卒業すると就職をした美奈子は妹弟の学費を面倒見ていたのだ。
今にして思えば俺にも美奈子にも違った選択肢はいくつも有ったのだろう。
だが、あの時の二人は目の前の事しか考えられずにいたように思う。
<白か黒か?> <イエスかノーか?>
答えはどちらしかないと思っていたのだ。
別れて五年ほど経った時、晃から美奈子が結婚をしたと聞いた。
そして、それから三十年が経とうとしていた。
『なぁ、来週の土曜日にこっちに遊びに来ないか?
どうせヒマなんだろ?』
この前みんなで会ってから一ヶ月ほど経った頃に晃から電話があった。
「ヒマじゃないよ。こう見えてもけっこう忙しいんだ」
『どうせ洗濯とか部屋の掃除だろ?』
図星を突かれて俺は思わず苦笑するしかなかった。
『それじゃ決まりな』
朝一番の列車を乗り継いで午後には故郷の風景を車窓に臨んでいた。
駅に着くと晃が迎えに来てくれていた。
「おう、お疲れ!」
「あぁ、ただいま」
晃の家に向かう車の窓からアーケード商店街の中央広場に大きな七夕飾りがあるのが見えた。
「そっか、今日は七夕だっけ?」
「知ってるか? ここの七夕飾りは望みが叶う事で有名なんだぜ。
願い事を書いた短冊を飾って、それを好きな人に見てもらえるとその恋が叶うんだってさ。
お前も書いてみたら?」
「いったい誰に見せろって言うんだよ?」
「さぁな。誰か見てもらいたい人っていないのか?」
「いないよ。残念ながらね」
「美奈子は?」
「もう昔の事だよ。美奈子だってもうとっくに忘れているさ。
今更蒸し返したってどうしようもないよ」
「そうかな?」
「あぁ。でも、そんなの昔あったっけ?」
「いや、十年前からだ」
「何か云われになるような事でもあったのかい?」
「あぁ」
「ほぉ、それは興味あるね。で?」
「アーケード商店街がリニューアルしてな。
たまたまその時期が七夕だったもんで盛大に七夕祭りをやる事になってさ」
「うん」
「で、目玉に何か作ろうってなって大きな七夕飾りを飾るようになったのさ」
「それで?」
「それで? それだけだよ」
「何だよ、それ? じゃ、願い事がどうってのは?」
「そんな事、言ったっけ?」
「おいおい(笑)」
「まぁ、云われとか迷信なんてそんなもんだよ。
多分、若い奴らが面白がって言い出したんじゃない?」
「やれやれ」
「なんだい? ガッカリしたのか?」
「かもね(笑)」
「まぁ、生きてりゃ良い事だってあるさ」
「何だそれ?」
晃の家で有希の手作りの夕飯をご馳走になった後で三人で商店街に繰り出した。
七夕飾りを大きく囲むように出店が並んでいてかなりの人出だった。
昔では考えられないほどの賑わいだ。
「けっこう人が出てるね」
辺りを見渡して俺は言った。
「あぁ、毎年人出も増えているらしいよ」
そこに有希が何処からか戻って来た。
「もらって来たよ」
手にレジ袋と何か紙のようなモノを持っていた。
「よし、じゃあ書くか。今年こそは当たりますように!」
そう言うと晃はその紙を両手に挟んで神頼みのかっこうをした。
「それは?」
「短冊だよ」
「って、言うか抽選券ね」
有希がその紙を見せてくれた。
「抽選券?」
「ここの出店で五百円買う毎に一枚抽選券をくれるの。
「それはともかく、お前もこれに何か書けよ」
「いや、だから・・・」
「違うんだ。去年からイベントが始まってさ。
この短冊が抽選券になっていて
願い事をひとつと名前を書いて箱にいれるんだ。
司会者が短冊を引いて当たると豪華景品が当たるんだぜ。
今年の特賞はハワイ旅行なんだ。
実は俺らは新婚旅行に行ってなくてな」
「お前、それが目的で俺を呼んだのか?」
「いや・・・あはは、すまん!」
晃は腰を九十度くらいに折り曲げて頭を下げた
「そんな理由で俺を呼んだのは腹が立つけど
有希ちゃんには俺も世話になったからな。
しゃーない、協力するよ」
「すまん!」
カラオケ大会だとか地元の学生バンドの演奏だとか
賑やかに七夕のイベントも進んで八時を過ぎた頃から抽選会が始まった。
「なぁ、何て書いたんだ?」
晃がそう言ってニヤニヤ笑いながら訊いてきた。
「何だって良いだろ?」
どうせ当たる訳はないと思って書いたものの
こいつにだけは知られる訳にはいかないと苦笑した。
ステージ上での抽選会は地元FMの人気DJ氏が司会を務めていて
その傍らにはおそらくは二十歳前後だろうか
<ミス七夕>のタスキをかけた若い女性がアシスタントについていた。
順番に抽選が進んでいったが俺はもちろん晃も有希も一向に当たる気配すらなかった。
そしていよいよ残りは特賞のみになった。
「やっぱ、今年もダメだったか。
すまんな、お前まで引っ張りだしたのに」
申し訳なさそうに晃が呟いた。
「なぁに、まだ勝負はこれからさ」
「そうよ、最後に笑うのは私よ!」
有希は抽選券の半券を両手で胸に当てていたが
その片方の指を少しずらすと小さくピースサインを出した。
「さて、それでは!
はい、いよいよ特賞の発表を残すのみとなりました。
それでは最後の一枚を引いていただきましょう!
皆さん、心の準備は良いですか?
いきますよ! さぁ、今年の特賞は誰の手に渡るでしょう!
お願いしまーーーーーす!」
DJ氏が促すとミス七夕が
抽選用紙の入った箱をゆっくりグルグルかき回して
やがてゆっくりと抽選箱の口から一枚の抽選券を取り出して大きく上に掲げた。
「さぁ、皆さん! 注目ですよー! どうぞ、お名前を読み上げてください!」
そう言うとDJ氏はミス七夕の口元にマイクを向けた。
ミス七夕はひとつ大きく深呼吸をすると
名前を改めて確認してからゆっくりと読み上げかけた。
晃と有希が固唾をのんでその瞬間を見守っていた。
「特賞は・・・」
そこでミス七夕がまたひとつ大きく深呼吸をした。
ここでワザとタメを作るのも場を盛り上げる常套手段だ。
「おーい! 早く読み上げてくれよー!」
観客からも歓声が飛んだ。
最早、泣きそうな感じで晃が祈る。
有希も両手を合わせて強く目を閉じていた。
覚悟を決めたかのようにミス七夕はついに名前を読み上げた。
「特賞は・・・山崎和也さんです! おめでとうございます!」
DJ氏が当選した抽選券を受け取って会場に呼びかけた。
「山崎和也さん!
いらっしゃいますか?
この場にいなかったら無効ですよーーー!」
「きゃー! 和也クン、当たったわよ! さっ、早く早く!」
そう言うと有希は俺を急かせてステージの方に背中を押した。
会場のお客さん達のヤジとも歓声ともつかない声にはやし立てられて
かなり照れくさかったがDJ氏に促されて俺はステージに上がった。
軽くお辞儀をしながら壇上を進むとDJ氏の拍手に招かれるままに中央に立った。
スポットライトが当てられているせいか緊張のせいなのか
俺はこの場違いな雰囲気に気押されて汗だくになっていた。
なんせ、こんな事は生まれて初めての経験だ。
俺は逃げ出したくなる気持ちを必死に抑えつつ
心持ちか震える手を抑えるように両手を後ろ手に組んで何とか落ち着こうとしていた。
DJ氏は満面の笑みでマイクを俺に向けた。
「おめでとうございます! えー、山崎さんですね?
今日はどちらからおいででしたか?」
「S市からです」
「あら、わざわざですか? この為に?」
「あっ、いや・・そう言う訳では・・・」
「んー、それは困ったなぁー
この為にじゃないとするとずっと待っていた地元の人が怒っちゃいますね」
その声に会場から歓声が飛んだ。
「そうだ、そうだ! 抽選やり直しーーー!」
「あっ、それじゃ・・・」
弱気になった俺にDJ氏が笑いながら言った。
「あはは、冗談ですよ。
遠い所からおいでいただいた甲斐がありましたね。
おめでとうございます! さっ、目録です」
特賞の目録を手渡すとDJ氏は俺にマイクを向けて訊いた。
「ところで何て書いていただいたんですか?
どれどれ・・・ほぉ、なるほど。もし良かったら読み上げても良いですか?」
にこやかな笑顔でDJ氏は俺の返事を待っていた。
「あっ、いや・・・それは・・・」
俺はしどろもどろになった。
DJ氏が改めて俺に返事を促した。
「オホン、特賞が当たった方の願い事を読み上げて
この会場のみんなで一緒に願うのが慣わしなんですよ。
それともやっぱり、権利を放棄しますか?」
壇上で困っている俺に晃が無責任に声を飛ばした。
「和也、ハワイだぞ、ハワイ! 読め-!」
「応援の方ですね。あー言ってますが、どうします?」
この場の空気を白けさせる事は出来ない。
かと言って、こんな大勢の面前でアレを読むなんて絶対に無理だと思った。
余程と思ったのか? 見かねてDJ氏は助け船を出してくれた。
「もし、差し障りがあるようでしたら答えなくてもけっこうですよ。
私だってそこまで悪党じゃありませんからね。
ただ、ものすごーくこの内容には興味はありますが」
DJ氏はそう言うともう一度抽選券に書かれていた文字を目で追った。
「いや、その・・・ちょっと・・・その、勘弁してください。
まさか、当たるなんて思っていなかったもので・・・つい・・・」
俺はますますしどろもどろになって言った。
そんな俺にDJ氏は笑顔で続けた。
「判りました。けっこうですよ。
誰にだって、そっと大切にしておきたい想い出とかってありますものね。
それでは抽選券もお返しいたしますので、後でぜひあそこの七夕飾りに下げてください。
その願い、きっと叶いますよ」
「は、はい」
「それではS市からおいでいただいた幸運な山崎さんにもう一度、大きな拍手をどうぞ!
願い事が叶いますように!」
DJ氏はそう言うと俺の肩を抱いて会場を見渡して来場者の拍手を促した。
「この後は係の者が説明をしますのでステージの後ろのテントへどうぞ」
ミス七夕に促されてステージの後ろの階段を下りると
俺はミス七夕の後について事務局のテントに入っていった。
「お母さん、特賞の方をお連れしたわよ」
ミス七夕のその声に
事務服を着た四十代くらいの女性が愛想良く一礼をして迎えてくれた。
顔を上げて俺と目が合った瞬間、その女性の笑顔がこわばった。
「えっ!? 和也・・・? まさか・・・」
商工会議所で事務員をしているという美奈子だった。
「えっ? お母さんの知り合い?」
突然の再会に戸惑っていた二人を交互に見ながらミス七夕が驚きの声を上げた。
「えっ? あ、あぁ・・・そうね。ご無沙汰していました」
美奈子は俺に又、お辞儀をした。
「あぁ、しばらくだね。元気だった?」
とっさに繕ったつもりの俺の笑顔もきっと引きつっていたかもしれない。
「えぇ。なんとか」
「そっか。良かった・・・」
ぎこちない雰囲気の二人にミス七夕は気を遣ったのか努めて明るく言った。
「私、お邪魔ね。外に出てるわ。あっ、山崎さんでしたっけ?
私、娘の真奈です。後の説明とかは母に任せますので」
真奈ちゃんはそう言うと軽くお辞儀をしてテントの外に出ていった。
真奈ちゃんは俺の抽選券に書いた言葉も読んでいたはずだ。
それが母親の事だという事にもきっと気付いたに違いない。
『まさか、こんな事になるなんて』
「あの・・・」
美奈子はハワイ旅行のパンフレットを差し出すと伏し目がちに言った。
「あっ、はい?」
「とりあえず、説明を・・・」
「あっ、はい」
美奈子は丁寧に事務的な話をしてくれていたと思うけど
俺の耳には何も入っては来なかった。
その時、ふと晃と有希の顔が浮かんだ。
「あの・・・」
「はい?」
「あの、これって誰かに譲る事って出来るのかな?
あの、俺の友人で結婚をして何年も経つのにまだ新婚旅行に行ってない奴がいて。
で、その・・・出来ればその友人にプレゼントをしたいんだけど・・・」
美奈子は俺の顔を改めて見ると初めて笑顔になった。
「変わってないのね」
「えっ?」
「いつも自分の事より相手の事ばかり気を遣って」
「い、いや、そんなつもりじゃないんだけど」
それには答えずに美奈子は呟いた。
「私は・・・変わっちゃったな・・・」
「・・・」
「本当は当選は他の人には譲ったらダメなんだけど聞かなかった事にするわ。
友人って有希のとこでしょ?」
「ふっ。君もやっぱり変わってないよ。
勘の良いところと自分で責任を抱え込むところ。
そして、やっぱり今も優しいところ」
「そんな事・・・私は和也を裏切ったのよ」
美奈子の目からは涙が溢れた。
俺は美奈子の言葉を打ち消した。
「いや、そんな風には思った事はないよ。
ただ、あの時は君は君で精一杯に家族を支えようとしていた。 そうだろ?」
「・・・」
「きっと、お互いに迷子になっていたんだよ。
目の前の事だけに一生懸命になるしかなくて
自分の心を迷路の中に閉じ込めてしまってたんじゃないかなぁー」
「・・・」
「俺もそうだよ。仕事の事しか頭になかった。
君の気持ちだとか、状況とか・・・
そう。愛を押しつけようとしていただけだったんだと思う。
今だから・・・その、そう思えるっていうか。
あの頃は自分の事しか頭になくて『なんで?』とか、そんな風にしか思えなかった」
「お互い様よね」
「そう、お互い様だよ」
その時の俺の頭の中には<あの頃の事>が走馬燈のように繰り返し回っていた。
テントの入り口のところで隠れるように晃と有希が中の様子を覗いていた。
真奈ちゃんも一緒だった。
「押すな、おい、こらっ!」
「キャー!」
「えっ?」
驚いてテントの入り口の方を見るとそこに晃と有希が倒れ込んでいた。
その後ろには真奈ちゃんの心配そうな顔も見えた。
「いてて・・・」
腰をさすりながら晃は有希の手を引きながら立ち上がった。
「あはは、スマン。つい・・・」
「ごめんなさい」
有希も神妙な顔でこっちを言った。
「何やってんだよ?」
晃に向かってそう言ったものの
晃に対しても美奈子に対しても何だかとても気まずい体だった。
「あっ! お前、美奈子がここにいるって知ってたのか?」
「いや、そこまでは知らなかったよ。
真奈ちゃんがミス七夕だってのは知ってたけどさ」
慌てて晃がそれを打ち消した。
「ホントだよ! それに抽選だってまさかホントに当たるなんてさ」
「ホントよねー しかも、和也クンの抽選券を選んだのが真奈ちゃんだなんて。
これはもう運命じゃない? ねぇ?」
有希が晃に同意を求めた。
「おー、そうだよ! 絶対にそう! これはこうなる運命だったんだよ!」
晃は俺に言い含めるように言った。
「何が運命だよ? ねぇ?」
俺は思わず苦笑をしながら美奈子に向かって言った。
美奈子はただ微笑んでいた。
そこに真奈ちゃんがテントの中に入って来て美奈子に言った。
「お母さん、山崎さんって良い人だと思うわ。
今でもお母さんの事を心配してくれていたのよ」
「えっ? 何の話?」
美奈子が怪訝な顔で真奈ちゃんに訊いた。
「あれ、抽選券に書いていたのってお母さんの事ですよね?」
真奈ちゃんは俺の方を向くと訊いた。
「えっ? いや、あれは・・・」
「おっ、何だい? それ気になるな。ねぇ?」
そう言って晃は有希を見た。
それから俺の方を向くと言った。
「和也、何って書いたんだよ? どれ、見せろよ」
「嫌だよ!」
「見せろって!」
「ダメだ!」
「良いじゃん、減るもんじゃあるまいし」
「減るよ」
「な、訳ないじゃん。見せろって。いや、見せてくださいませ」
「しつこい!」
「何だ? 今頃判ったのか?」
「もう良いよ」
「いや、良くない!」
「何でだよ?」
「俺が困る」
「何でお前なんだよ?」
「いい加減に観念しろって」
「嫌だよ。恥ずかしい」
「何? 恥ずかしい事なのか?」
そんな俺と晃のやり取りを笑いながら見ていた真奈ちゃんが言った。
「全然、恥ずかしくないですよ。素敵です」
「もう止めてよ。顔から火が出そうだよ」
「じゃ、言うんだな。それが世界平和の為だ」
「何だよ、それ? 他人事だと思って」
「他人事さ。他人と言っても自分の事じゃないって意味でな。
大親友の事だからさ、すっごい気になってる」
そこに有希が口を挟んできた。
「ほらほら、美奈子もすごい気になっているみたいよ。ねぇ?」
そう言うと有希は美奈子にウインクをした。
「でも、和也が困ってるし」
美奈子はそう言うと同情するように俺を見た。
「もう・・・判ったよ」
最早俺は諦めの境地になっていた。
「おっ! やっと観念したね?」
「したんじゃない。させられたんだ」
「同じさ。で、何て書いたんだよ?」
俺は渋々ポケットから抽選券を出すと晃には渡さずに美奈子に手渡した。
美奈子はそれを読むとしゃがみ込んで両手で顔を覆って泣いた。
「えっ? 美奈子? ちょっと見せて」
有希が美奈子から抽選券を受け取ったのを見て晃もそれを覗き込んだ。
「和也クン・・・」
有希も両手で顔を覆った。
すると晃がこう言い放った。
「何だよ、これ? ねぇ、ボールペン借りるよ」
晃はテーブルの上にあったボールペンを取ると抽選券に何か書き始めた。
「おい、勝手な事をするなよ!」
俺は思わず晃に向かって叫んだ。
「良いから」
「良くないよ。いくらお前だって・・・」
そう言いかけた時に晃が美奈子の脇にしゃがみ込むとその抽選券を美奈子に手渡した。
「こうだよな?」
美奈子は晃から手渡された抽選券をただじっと見つめていた。
「おい、何だよ?」
俺は晃に問いただした。
すると涙を拭きながら美奈子は立ち上がると俺にその抽選券を渡してくれた。
その抽選券には晃のごつい字でこう書き足してあった。
<和也と>
「晃、お前・・・」
「別に急ぐ必要はないさ。
もう十分に遠回りをしたんだから、今更少しくらい時間がかかったって平気だろ?」
そう言うと晃は俺の肩をポンと叩いた。
その時の抽選券はもうすっかり色褪せてしまったけど今でも<俺達>の宝物になっていた。
ただ、晃達と飲むたびに話のネタにされるのにはいい加減辟易している。
あー、何て書いていたのかって?
もう忘れたよ。
「嘘ばっかり」
傍らで美奈子が微笑んだ。
<和也と美奈子が幸せになれますように>