
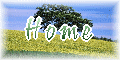
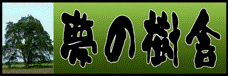
メリークリスマス
一人の男が街を歩いていた。
懐かしくてなのか?
それとも他に何か理由があるからなのか?
男は時折、立ち止まっては辺りを見回し
或いは、後ろを振り返りと
そんな事を何度か繰り返していた。
そしてひとつ白い息を吐くと又、歩き出した。
何時間歩いていただろう。
それでも、その間に男に振り向いた者は誰もいなかった。
いや、男がそこを歩いていた事にさえ
気がついた者はいなかっただろう。
折しもクリスマスイヴの夜だ。
街路樹には煌びやかな電飾が施され
ショーウインドウにはクリスマスカラーの飾り付けが
これでもかと見る者を引きつけようとしている。
それらを横目で見ながら帰宅を急ぐ人達
それらには目もくれず待ち合わせに急ぐ人達や
笑顔で談笑をしながら目的地へ急ぐ人達などが
様々な流れを作りながらみんな一様に足早に行き交っていた。
誰も他の人の事など目には入ってはいない。
そこにどんな男がいようが気にする人はいない。
今夜はそんな夜だ。
足早な群衆の流れはまるで
次から次とやって来る都会の電車が
幾重もの列を成しているように途切れる事は無い。
明らかに早さが違う男の足取りは
普段なら罵声の連射を浴びるのだろうが
幸か不幸か今夜は誰も罵声を浴びせる者などはいない。
むしろみんなそんな時間さえ惜しいのだろう。
「おっとっと!」
ぶつかりそうになるのを何度も避けながら男は呟いた。
「やれやれ、いったい何だっていうんだ」
男は歩くのを止めて道路脇のガードレールに腰を掛けると
右へ左へと絶え間なく行き交う人の流れを眺めていた。
「そういや、今夜はクリスマスイヴだっけ?
まぁ、俺にはもう関係ないけど」
自嘲気味にそう呟くと男はコートのポケットをまさぐった。
そこに入っているはずのタバコを探していたのだ。
「やっぱり入ってないか。
こんな事なら早くに禁煙をしておくんだったかな」
男は夜空に向かって白い息をフッと吐き出した。
何気なく通りの向かい側を見ると
ケーキ屋のショーケースの前でしゃがみ込んでいる女の子が目に入った。
真っ赤なニット帽に真っ赤なケープをまとって
同じく真っ赤なブーツを履いていた。
しゃがんでいて良く判らなかったが
幼稚園か小学校の低学年くらいだろうか?
男はしばらくその様子を見ていたが一向に女の子は動こうとはしなかった。
「ふふっ」
男は笑みを浮かべると思った。
きっと、女の子はあそこのケーキを買って欲しかったのだろうが
親はわざと意地悪にサッサと行ったフリをしているのだろう。
「で、すねてあそこにしゃがみ込んでいるって訳だ。
でも、ご安心を!」
男は舞台俳優のように大仰に両手を広げると<台詞>を続けた。
「ふてった女の子が両親と一緒に家に帰ってみると
何とそこには!
女の子が買って欲しかったケーキよりも何倍も豪華なケーキが!
たちまち女の子に満面の笑みが広がってハッピーエンドでございー!」
しかし、30分経っても女の子はそこを動こうとはしなかった。
それどころか親さえ一向に戻って来る気配はなかった。
男は車が途切れるのを待って車道を向こう側へと小走りに駆けた。
そして、女の子の前に立つと優しく声を掛けた。
「可愛いサンタさん、いったいどうしたんだい?
トナカイさんとはぐれたのかい?」
女の子は男を一瞥すると又、俯いてしまった。
困った男は女の子の隣に同じように並んでしゃがみ込んだ。
それでなくてもクリスマスイヴの夜だ。
ケーキ屋のショーケースの前に
大の大人と小さな女の子が並んでしゃがみ込んでいるなんて
店からしたら営業妨害以外の何物でもなかったろう。
それでも、二人を邪魔者扱いする者は一人としていなかった。
都会はいつでもそんなものだ。
他人の事なんて気にする人はいない。
繰り返すが、ましてや今夜はクリスマスイヴだ。
みんな自分達の事で忙しい夜なのだ。
街行く人達やケーキ屋に買いに来た人達だって
他人の事にかまっているヒマなんてないのだ。
男は女の子の方を見るでもなく独り言のように呟いた。
「オジサンもね、人とはぐれちゃったんだ。
全く、あいつったら何処に行ったんだか・・・」
「・・・」
女の子はやはり何も答えなかった。
「お父さんやお母さんは? きっと心配してるぞ」
「・・・」
「まぁ、良いさ。オジサンには関係ないもんな」
「別にはぐれてないもん」
女の子が始めて口を開いた。
「そっか。判った!
お嬢ちゃんはこのお店の子なんだろう?
仕事が終わるのを待ってるって訳だ?
でも、寒いのに大丈夫かい?
どうせなら店の中で待ってた方が・・・」
言いかけた言葉を女の子が遮った。
「違うよ。ここの子じゃない」
「じゃ、誰かを待っているのかい?」
「・・・」
「おやおや又、黙っちゃったね。さて、困ったぞ」
「良いから放っておいて!」
そう言った女の子の目には涙が浮かんでいた。
だが、それっきり又、男が何を話しかけても女の子は答えなかった。
男は口を閉じるとそのまま女の子と並んでしゃがみ込んでいた。
街はクリスマスイルミネーションとネオンで
昼間のように明るかったが冬は冬だ。
黙ってしゃがんでいた男は両手を擦り合わせると女の子に話しかけた。
「ねぇ? 寒くないのかい?
早く帰らないとお父さんやお母さんが心配するぞ。
いや、もう心配して捜索願を出しているかも。
とすると・・・俺の立場は何だ?
おいおい、よせよ誘拐犯じゃないってば!」
独り言のようにブツブツ話しかける男に
やっと女の子は俯いたままで口を開いた。
「帰りたくない・・・」
「えっ?」
「逃げて来たの・・・・」
「えっ? えっ? そいつは穏やかじゃないな。
って・・・ちょっと待てよ!
俺は完全に誘拐犯扱いじゃないかよ!?」
「バッカじゃないの?」
女の子は冷めた目で男を一瞥して言った。
「捕まる訳ないじゃん」
男はしゃがみ直すと女の子の方を向いて諭すように言った。
「そうかもしれないけどさ。
でも、逃げて来たってのは穏やかじゃないぞ。
いったいどうしたっていうんだい?」
「オジサンには関係ないでしょ」
「そりゃ俺には関係ないさ。
でも、オジサンは・・・ほら、おせっかいオジサンだから」
子供相手に何を言ってるんだかと思いながら
男は何とかこの場を取り繕わなきゃと思った。
こんなきれいな身なりの子が
まさかとは思いながら男は神妙な顔で訊いた。
「虐待されてたのかい?」
「別に・・・」
「じゃ、勉強しろとかうるさかった?」
「別に・・・」
「そうか判った!
お兄ちゃんと比べられて面白くなかったとか?」
「別に・・・兄弟いないし」
「お母さんとケンカをした?
それで家出のマネをかい?
なら、もう帰って仲直りをしなよ。
今夜はクリスマスイヴだぜ。
ご両親はプレゼントを用意して待っているよ」
「・・・」
「そこは又、だんまりかい?
やれやれ、参ったぞ」
「もう! いい加減にして!
放っておいてよ!
あなたははぐれた人でも探しに行けば?」
「そうなんだけどさ。
でも、そんなに急いで探さなくても良いんだ。
その内、ひょこっと現れる・・・そんな奴だから」
「その人と仲が良いの?」
涙を浮かべた瞳で女の子が訊いた。
「別に・・・おっと、これは君の台詞をパクった訳じゃないぜ」
「どうでもいい・・・」
「そうだったな。そっかそっか・・・」
「ママ・・・」
「ん?」
「毎日泣いてばかりいるの。
それを見ているのが辛いの・・・だから帰らない」
「お父さんは? まさか死んじゃったとか?」
「ううん。でも、パパは何も喋らない。
毎日、ママが泣いているから・・・
パパも家に帰ってからもずっと黙ったままだった」
「そっか、それは子供にしたら耐えられないよな?」
「原因は私だから・・・」
「そっか・・・」
「・・・」
「でも、本当は帰りたいんだろう?
そりゃそうだよな」
男は独り言のように呟いた。
「もう帰らないって決めたの。
じゃなきゃ、ママはずっと泣いてる」
「・・・」
今度は男が黙る番だった。
「オジサンこそ、どうして帰らないの?」
「帰っても誰もいないんだ」
「どうして? リコンしたの?」
「あはは、そうじゃないんだけどね。
何年になるかなぁー
男の子がいたんだけどね。
学校で虐められていたらしいんだ。
でも、その頃オジサンは仕事が忙しくってさ。
子供が悩んでいる事に気付いてやれなかった・・・
いや、後で気が付いてはいたんだけどさ。
疲れていてね。
で、今度の休みにゆっくりと話を聞いてやろうと思ってたんだ。
いや・・・言い分けだな・・・」
「・・・」
「そしたら次の日、自殺しちゃったんだ」
驚いた顔で女の子は男を見た。
「可哀想・・・」
それが、<どっち>に対しての言葉だったのか
男には知る由もなかった。
「で、子供の一周忌・・・
あっ、亡くなって一年経った時にお参りをしたんだけど
その後で、妻は子供と同じ場所で死んだんだ。
さすがにショックだった。
それからかな・・・
気が付いた事には無関心でいるのは止めようと思ったのは。
見て見ないフリをするのは止めようと決めたんだ。
で、おせっかいオジサンがここにいるって訳さ」
「大人も辛いね」
「辛いのに大人も子供もないさ」
「・・・」
「ねぇ?
おせっかいオジサンと知り合ったのも何かの縁だ。
オジサンが家について行ってやるよ。
だから、帰ろう?」
女の子は黙って首を横に振った。
「そっか・・・余計に辛くなっちゃうかな」
女の子は黙って頷いた。
「ここでしたか。東海林司さん、探しましたよ」
男が振り向くとそこには全身黒ずくめの男がにこやかに立っていた。
かなり物持ちの良い性格なんだろう。
その黒いスーツはかなりくたびれているように見えた。
「八ちゃん、フルネームで呼ぶなよ」
「決まりですから。
あなたこそ、『八ちゃん』なんて気安く呼ばないでください。
友達じゃないんですから。
もっともターゲットと親しくなる事も禁じられてますけどね」
「探すも何もあんたが美人に見とれていたせいだろ?
てっきり、一緒に歩いていると思ってたのにさ。
気が付いたらあんたはいなくなってた」
「そ、そんな。見とれていた訳じゃありませんよ。
ただ昔の知り合いに似ていたもんで・・・」
「あはは。八ちゃんも隅におけないね。
いったい何人の女を泣かせたんだい?」
「失礼な! 私がそんな事をする訳ないじゃありませんか」
「どうだか?」
東海林司は黒ずくめの男を見るとニヤリと笑った。
「誰? はぐれた人?」
女の子は黒ずくめの男と東海林司と呼ばれた男を見比べると訊いた。
「あぁ、こいつ八ちゃんっていうんだ」
「だから気安く・・・」
「まぁまぁ」
東海林司は黒ずくめの男の言葉を遮って続けた。
「なぁ、八ちゃん。
判ってるよ。ちゃんと付いて行くよ。
だが、それは今じゃない。
ほら、この子。
この子をちゃんと帰してやらないとさ」
「ん? その子・・・」
そういうと黒ずくめの男は脇に抱えていたバインダーを開いた。
そしてバインダーと女の子を見比べると女の子に声をかけた。
「お嬢ちゃん、田村・・・みゆきちゃんかい?」
女の子は驚いて黒ずくめの男を見た。
「オジサン、どうして私の名前を知っているの?」
「あー、やっぱりね。ちょっと待って。
今、連絡をするから」
「おい、どういう事だ?」
東海林司の言葉を手で遮ると男は誰かに電話をかけた。
「あっ、君が探していた子を見つけたよ。
そう、田村みゆきちゃんだ。
うん、<無事>だよ。
私のターゲットと一緒にいたんだ。
そう、駅前の・・・うん、その先にケーキ屋があるだろ?
・・・うん。そうしてくれ」
それから黒ずくめの男は
田村みゆきと呼ばれた女の子に向くと言った。
「田村みゆきちゃん。もうすぐ迎えが来る。
ここで待っていてくれるかい?
さぁ、東海林司さんは私と一緒に行きましょう」
田村みゆきは答えなかった。
「・・・」
「そんな! こんな子を一人でここには置いて行けないだろ?
第一、どんな奴が迎えに来るのか判らないのに放ってはおけない。
そいつが来るまで俺は絶対ここを動かないぞ!」
「でも、そろそろ時間が」
「そんなもんはお前らだったらどうにでもなるだろ?」
「いや、そうは言われましても規則を破る訳には」
「じゃ、腕尽くで俺を連れて行くかい?
こう見えても俺は学生時代はアマレスの全日本5位だったんだぜ」
「それは判ってます。調査済みですからね。
困りましたな・・・
出来ればこんな所で<チカラ>は使いたくないんです」
「だろ? 俺だって何も事を荒立てようと言ってるんじゃない。
ただ、迎えが来るまではみゆきちゃんに付いていてやりたいんだ。
俺はおせっかいオジサンだからな」
「良いよ、オジサン。ありがとう。
ちょっとの間だったけど、けっこう楽しかった」
田村みゆきは初めて東海林司に笑みを向けて軽く会釈をした。
「いや、ダメだ!
俺は見てみないフリをするのは止めたんだ!」
「困りましたね・・・おっと、そう言ってるうちに来たようですよ」
振り返ると黒ずくめの女がそこに立っていた。
<八ちゃん>が昭和の時代の
冴えないスーツスタイルのサラリーマン然としているのに比べると
目の前に現れた女は切れ長の瞳が涼やかで
ストレートに伸ばした黒髪がいっそうそのスタイルを神秘的に見せていた。
「死神752号、遅いですよ。
私はもう少しでこの東海林司さんと
レスリングをしなきゃならないとこだったんですよ」
「死神83号、すいません。
田村みゆきちゃんの資料を見ながら歩いている内に
つい、見失ってしまって・・・
あのぉ・・・この事はぜひ内緒で」
意外にもその神秘的なスタイルとは裏腹に死神752号は
ちょっと困ったような申し訳なさそうな<人間的>な面持ち
つまりは極めて<普通>の女の子のような表情を見せた。
「死神752号。あなたは私の研修生だった人ですからね。
あなたの評価は私の評価・・・仕方ないですねぇ。
でも、今回だけですよ。
私だって上司に睨まれたくはないんですから」
「はい。ありがとうございます」
死神752号は笑顔になると死神83号に深々と頭を下げた。
それを見ていた田村みゆきは東海林司に耳打ちをした。
「ねぇ? 83号だから『八ちゃん』?」
「あぁ、ピッタリだろ?」
二人は顔を見合わせて笑った。
そこへ死神83号が言った。
「何をこそこそ話しているんです?
逃げようたって無駄ですよ」
「判ってるよ、八ちゃん」
「だから、それは止めてください」
「八ちゃんって?」
死神752号が面白そうに話に割って入ってきた。
「何でもありませんよ!」
それをたしなめるように死神83号は言った。
そして、東海林司に向かって続けた。
「さぁ、東海林司さん。行きましょうか?」
「ちょっと待ってくれ」
「まだ何か?」
「そもそも、何でこんな幼い子が死んだんだ?
病気だったのかい?
それとも、事故とか事件とか」
「えーっとですね・・・」
死神752号がバインダーを開いて説明しようとした時
死神83号がストップをかけた。
「ダメですよ! ターゲットの身上は他の人に漏らしちゃ。
今の時代、個人情報の取り扱いはうるさいんですから」
「す、すみません」
死神752号は慌ててバインダーを閉じた。
それを見た東海林司は死神83号に向かって言った。
「八ちゃん。まぁ、堅い事は言うなよ。
どうせ、向こうに付いたら全部忘れちゃうんだろ?
なら、良いじゃないか少しくらい。
じゃなきゃ俺はいつまでも成仏出来そうもないな」
「オホン! あなたって人は死神を脅す気ですか?」
「そんなめっそうもない! ただ、知りたいだけさ」
「どうしましょうか?」
死神752号が困ったように死神83号に伺いを立てた。
死神8号は田村みゆきをチラッと見た。
「私なら別にかまわないよ。ホントの事だもん」
田村みゆきは答えた。
「そうですねー 例外中の例外ですよ。
そして、何処で誰に何を訊かれても絶対他言無用でお願いしますよ」
「もちろんさ!」
「じゃ、亡くなった原因だけ教えてあげてください。
でも、余計な事は一切言わないようにしてくださいよ」
「はい。田村みゆきちゃんはですね・・・」
再びバインダーを開くと死神752号は
ページを指でなぞりながら読み上げた。
「エーッと・・・はい、病気ですね。
生まれつき心臓が弱かったんです。
今年の春に小学校に入学したものの
すぐに入院・・・で、二度手術をしましたが
残念ながら・・・二日前にお亡くなりになりました」
そう言うと死神752号は持っていたバインダーを閉じた。
「そっか・・・こんなにちっちゃいのに。
可哀想にな・・・」
「別に・・・」
田村みゆきは街の遠くを眺めながらそっけなく答えた。
「なぁ?」
東海林司は死神83号を見ると言った。
「八ちゃん、もうひとつだけおせっかいがしたいんだけど」
「ダメですよ! これ以上規則は破れません!」
用件を察知してか死神83号はすかさず言った。
「いや、そんな難しい事じゃないんだ。
みゆきちゃんはあんな風に言っているけど
両親の事が気になってない訳がないと思わないか?」
「さて、私には判りかねますが」
「八ちゃんは仕事だからな。それで良いだろう。
だが、俺は人間だ・・・まぁ<元>が付くかもしれないけどさ。
だから、どうしても気になるんだよ。
例え、少しでも何とかなるならしてやりたいだろう?
死神にだって親子の情ってもんくらい判るだろ?」
「そう言われましても私には親はいませんし」
「そんな事はどうでも良いんだよ。
俺が言いたいのは、みゆきちゃんに心残りをさせたくないんだ」
「そうですか?」
死神83号は田村みゆきに訊いた。
「別に・・・」
「ほらっ、本人もこう言ってる事ですし問題はないのでは?」
「八ちゃん、お前さんってホント、人の心の機微って奴が判ってないね」
「<きび>? なんですか? 私は人間じゃありませんからね。
って、言うか・・・その八ちゃんは止めてください。
何度も言ってるじゃありませんか」
「判った、判った! もう八ちゃんには聞かないよ」
東海林司はやれやれと言った体で死神83号を見ると
今度は死神752号に視線を移した。
東海林司と目が合った死神752号は慌てて目を逸らせた。
「君・・・エーッと752号さん?」
「えっ? あっ、はい?」
名前を呼ばれて再び東海林司と目が合った瞬間
死神752号はしまったと思った。
だが、どうやら遅かった。
「みゆきちゃんの両親の事なんだけど」
「はっ、はい?」
「大丈夫なのかな? 立ち直れるかい?
口では言わないけどさ。
みゆきちゃんが気にしているのはそこだと思うんだ。
でも、会いにはいけないし
行ったところで両親と話が出来る訳でもない。
だよな?
逆に、もしかしてだけど、みゆきちゃんの気配を感じたら
きっとお母さんも余計に思い出して辛くなっちゃうだろうな。
それは何よりみゆきちゃんにとっても辛い事なんだよ」
東海林司は真剣な面持ちで死神752号に訴えかけた。
「で、どうなんだい?
あんたらなら、その人の運命みたいな奴も判るんだろ?」
「まぁ・・・」
死神752号は歯切れ悪く答えながら死神83号の方をチラッと見た。
死神83号も東海林司がこのままでは引き下がらない事を感じていた。
死神83号は目で<OK>の合図を送った。
ひとつ深呼吸をすると死神752号は東海林司に向かって笑顔を作って言った。
「田村みゆきちゃんのご両親なら大丈夫です。
多少、時間は必要ですけどね。
それで又、お子さんが産まれる事になっています」
「そしたらママもパパも私の事を忘れちゃうの?」
田村みゆきは初めて感情をむき出しにして叫んだ。
<ママとパパがみゆきの事を忘れる>
それは望んでいた事であり、望んでいなかった事でもあった。
田村みゆきの嗚咽が東海林司の胸を締め付けた。
『何とかしてやらなきゃ! 俺が何とかしてやる!』
東海林司が口を挟んだ。
「なぁ? 子供が産まれるって
それじゃ、みゆきちゃんは又、両親の元に生まれ変われるのか?
なぁ、そういう事なんだろう?」
死神752号は申し訳なさそうに答えた。
「可能性は確かにあります。
田村みゆきちゃんは又、生まれ変われる事になっていますから。
もし、田村みゆきちゃんがそう望むのであればですけど
元の両親の子供としてもう一度生まれる事は出来るでしょう。
ただ・・・」
「ただ? ただ、何だい?」
「ただ、もしそうなると
その子は又、同じ運命をたどる可能性も高くなるんです。
つまり、この悲しみや辛さが又、繰り返される事に。
なので・・・お勧めは出来ません・・・」
「そんな・・・」
東海林司は絶句した。
「そうだ! なら、他の親の元に生まれ変わったら
今度は健康な子供として産まれて
もっと長い人生を全う出来るって事なのか?」
死神752号は答えなかった。
いや、東海林司の真剣な表情に気圧されて答えられなかった。
死神83号が口を開いた。
「あくまで可能性の問題ですが、その可能性は高いです」
「そうか、そうなんだな?
みゆきちゃん、どうする? どうしたい?
みゆきちゃんの良い方にオジサンが頼んでやるから!」
田村みゆきは嗚咽を繰り返すばかりで答えられなかった。
「東海林司さん」
死神83号は優しく微笑むと言った。
「無理ですよ。そんな小さな子にそんな辛い選択は」
「うるさい! 八ちゃんは黙っててくれ!
なぁ、みゆきちゃん? どうしたいんだい?」
「私・・・」
「うん?」
「又、ママを泣かせるのは嫌だ・・・
ねぇ、オジサン。どうしたら良い? どうしたら良いの?」
泣きながらすがるように
東海林司のコートの裾をつまんだ小さな指が何度も揺れて震えた。
東海林司は思わず田村みゆきを抱きしめた。
「オジサン・・・どうしたら良いの?」
東海林司には答える言葉は見つけられなかった。
ただ、強く抱きしめるしか出来なかった。
死神752号はもらい泣きを隠すように二人に背を向けた。
「東海林司さん。運命は決まっているんです。
この子がいつ死んで、次はいつ何処に生まれ変わるのか。
私には判りませんが、運命は決まってるんです。
どうしようもないのなら、それに従ってみませんか?」
死神83号は静かに言った。
だが、それでも東海林司は諦めきれなかった。
「なぁ?」
田村みゆきを抱きしめながら振り向くと死神83号に言った。
「俺は又、生まれ変われるのか?
なら、俺は生まれ変われなくても良い。
地獄に落ちても良い。虫けらに生まれ変わっても良い。
いや、一生浮かばれないで彷徨ったって良い。
だから、みゆきちゃんを元の両親の元に生まれ変わらせてくれないか?
もちろん、今度は元気な身体で」
「それは出来ません。決まっている事を変える事は出来ないのです」
「そんな事は判ってるよ! 何かい? 俺の命じゃ不服だってのかい?」
「落ち着いてください。私だって同じ想いなんです。
出来るなら叶えてあげたい。死神だって悪魔じゃありませんからね。
人間の<キビ>とやらは判りませんが私にだって感情はあるんです」
「・・・」
死神83号は懐から懐中時計を取り出して時間を確認すると
努めて事務的に口を開いた。
「東海林司さん、時間です」
「待ってくれ! なぁ、待ってくれよ。もう少しで良い・・・待って・・・」
東海林司は田村みゆきを抱きしめたまま泣き崩れた。
死神83号は東海林司の肩を優しく叩くと耳元で囁いた。
「東海林司さん、あなたの気持ちは無駄にはしませんから」
それから死神752号を呼ぶと言った。
「さぁ、田村みゆきちゃんを連れていくんだ」
東海林司はうなだれたまま死神83号と連れだって歩き出した。
田村みゆきは死神752号に肩を抱かれたままその後ろ姿を見送っていた。
と、それを振り解き走り出すと田村みゆきが叫んだ。
「ねぇ? オジサンはどうして死んじゃったの?」
東海林司は振り返ると努めて笑顔を作って答えた。
「あー、オジサンかい?
歩道を歩いてたらさ、急に子犬が道路に飛び出してね。
助けようとして、このざまだよ。
でも、安心してくれ。
子犬は無事だったからさ」
「オジサンってバッカじゃないの?
ホントにおせっかいだね」
田村みゆきは涙を浮かべながらもせいいっぱいの笑顔で言った。
「自分でもそう思うよ。
でも、見てみないフリはもうしないって自分と約束したからね」
東海林司はそう言うとウインクをして
それから死神83号に促されて又、歩き出した。
その背中に田村みゆきは大声で叫んだ。
「オジサン、ありがとう! きっと又、会おうね!
約束だよ! きっと、きっと会おうね!」
二人の姿は宙に浮いたかと思うと間もなく
街中に煌めくイヴの夜のイルミネーションに紛れて消えた。
「さぁ、田村みゆきちゃん。私達も行きましょう」
死神752号は田村みゆきを促して歩き出した。
「ねぇ?」
田村みゆきが言った。
「なぁに?」
「死神ってさ。ずっと怖いって思ってた」
「そうなんだ? それはちょっとショックかも」
「でも、八ちゃんもお姉さんも良い人だね」
「死神83号って、ホントはすっごく怖いんだよ」
「えー? ホント? 映画みたいに人を殺すの?」
「殺したりはしないけど・・・でも、人間からしたら同じかもね」
「ふぅーん。
ねぇ? 83号が八ちゃんならお姉さんはナナさんだね」
「ナナ?」
「うん。752号だからナナさん。どう良いでしょ?」
「うん。判らないけど、何か良いね」
「でしょ? 番号よりも親しみが沸くわ」
「そっか、東海林司さんが八ちゃんって言ってたのもそれだったのかな?」
「そうだよ!」
「そっか、良いね」
「で、ナナさん。私はこれから何処に行くの?」
「あー、そうだった! ちょっと待ってて。見るから」
そういうと死神752号はバインダーを開いてページをめくり始めた。
「えーっと・・・あった。これね?
ふうーん・・・あー、そうなんだ!」
そう言って微笑んだ。
「何? 何?」
「ううん、何でもなーい」
「あっ、ずるーい! ナナさん、一人でニヤニヤしてる!」
「あはっ。そんな事はないですよー」
「ねぇ、教えて!」
「ダーメ! 決まりなの。
それにね、本人に教えちゃったら書いてある事が変わっちゃうの。
だから、ダーメ。でも、心配はしなくて良いわ。
私が保証する! ちょっと頼りないけどね。
じゃ、行こうか?」
「ナナさん、優しくしてくれてありがとう」
「まぁ! うれしいわ」
死神752号は微笑むと田村みゆきの肩を抱いた、
そして、さっき見たのと同じようにフワッと宙に浮くと
二人の周りは眩い光に包まれて、やがて消えていった。
しんしんと雪が降るクリスマスの夜
街中のイルミネーションも降る雪に霞んでいた。
病院の駐車場に車を停めると
男は小走りに病院の玄関に向かって走り出した。
「おっと!」
二~三度転びそうになりながらも何とかこらえて
男は無事に玄関に駆け込んだ。
エレベーターの前でゆっくりと上がっていく
オレンジ色の点滅をもどかしげに見ていた男は
ふと見た先に階段を見つけると階段に向かって駆けだした。
そのまま一気に三階まで駆け上がると
丁度そこは妻の入院をしている病室のすぐ前だった。
男は病室のドアを開けるとすぐさま妻の元に駆け寄った。
「まぁ、司さん! 早かったのね」
「司君、お帰り」
「あー、お義父さん! あっ、お義母さんも」
ベッドの傍らには満面の笑みを浮かべた妻の両親が立っていた。
病室に駆け入って来た娘婿を義父がねぎらった。
「ご苦労さんだったね。この雪じゃ大変だったろ?」
「あっ、いえ」
「そうそう。司さん、ごめんなさいね。
私達の方がパパより先に赤ちゃんに対面させてもらったのよ」
申し訳なさそうに義母が言った。
「いえ、全然」
司は笑顔で答えた。
「もう仕事は良いの?」
出産という大仕事をやってのけた充足感からか
いつも以上に清々しい笑顔で妻は尋ねた。
「クリスマスの夜に残業をさせるほど
うちの会社はブラックじゃないよ。
それより赤ちゃんは?」
妻のベッドの横には小さなベッドが並べて置いてあったがそこは空だった。
「今、看護師さんがオムツを替えてくれているの。
もうすぐ戻って来るわ」
「そっか」
産まれたばかりの赤ちゃんとの感激の初対面を期待していた男は
あからさまにガッカリした風で
それでも寸でのところで妻に大事な事を言い忘れていた事に気が付いた。
「縁(ゆかり)。お疲れ様。そして、ありがとう!」
そう言って男は妻の手を握った。
「すっかり赤ちゃんに夢中で私の事なんか忘れているのかと思ったわ」
縁はそう言ってわざと大袈裟に口を尖らせた。
「いや、そんな事なんかあるもんか!」
「ふふ。どうだか」
そう言いながらも縁は嬉しそうだった。
「ねぇ? 名前はどうしようか?
いくつか候補は考えてあったけど
いざ、赤ちゃんの顔を見たらどれが良いのか迷ってしまうわ。
だって、これから一生付き合っていく名前だもの。
こんな子に育って欲しいとか、幸せになって欲しいとか
つい、アレもコレもって欲張っちゃうわ」
「あはは。そんなもんだよ」
義父が笑顔で言った。
「私の時もそうだった?」
「そりゃもう大変だったわ」
義母が嬉しそうに笑った。
そして、ふと間を空けると思い出してでもいるように呟いた。
「あの子が亡くなって程なくしてあなたを身ごもったのが判ったの。
嬉しかったわ。あの子が戻って来てくれたって。
もちろん、あなたはあの子じゃないわ。
あなたはあなたよ。
でもね、あの時は心の支えを無くしていたから」
「うん」
神妙な顔で縁は話に頷いた。
「みゆきか・・・可哀想な事をしたよ」
義父がしんみりと言った。
司も幼くして亡くなった縁の姉の事は聞いていた。
司はそっと縁の手を握った。
「あなたが産まれるまでも大変だったのよ。
お父さんったら、アレもするな、コレもするなって。
ねぇ? どこかのお姫様じゃあるまいし
妊娠したぐらいで家事も放っておけないじゃない?
そうそう! 名前なんて、もう何十個考えたかしら。
お父さんなんてね、いちいち半紙に書き出して
画数がどうのとか、この字はダメだとか。
そりゃもう大騒ぎだったわ」
「お父さんらしいね」
「オホン。だって、お前・・・仕方ないじゃないか。
どうしても縁には幸せになって欲しかったんだよ。
みゆきの分も、いやそれ以上にね。真剣にもなるさ」
「そうね」
「あぁ、そうさ」
「でね。人間って幸せになる為には
たくさんの人に縁をもらって生きなきゃいけないの。
お父さんとお母さんとの縁、みゆきとの縁もそう。
そして、友達やら・・・今は司さんとの縁もそうよね。
その縁を繋ぐ事で幸せになれるのよ。
そんな縁をたくさんもらえますようにって願ったの」
「だから<縁(ゆかり)>なんだね。
初めて聞いた」
縁は司の手を取ると腕に抱きついて幸せを感じていた。
「お待たせしました。あらっ、パパも到着ね?
はい、お父さんですよー」
恰幅の良い、いかにも人の良さそうな看護師が
そう言うと、赤ちゃんを司の元に連れて来た。
看護師に抱っこされたままスヤスヤ眠っている娘を
初めて見た時、司は頷いた。
「うん、良い寝顔だね。この子は幸せになるよ。
だって、みんなから素敵な縁をたくさんもらった縁が産んだ子だもの」
「そうだね」
縁も頷いた。
「よし、決めた!」
「えっ、何?」
「名前さ。この子の顔を見て決めた」
「何? 今まで考えてた名前?」
「いや、今思いついたんだけどね。
でも、この子は絶対に気に入ってくれるよ」
「ねぇ、何?」
縁、義父、義母、
そして赤ちゃんをベッドに寝かせ付けていた看護師の視線が司に集まった。
司はみんなの視線に気が付いて少し赤面をした。
「やだなぁ-、そんなにじろじろ見ないでくださいよ」
「良いからもう、早く教えてよ!」
戸惑う司を縁がせき立てた。
「あの・・・クリスマスの雪の夜に産まれた子だからさ。
聖夜の<聖>に降る<雪>と書いて<みゆき>と言うのはどうかな?」
思わぬ名前に義父と義母は顔を見合わせた。
「ダ・・メ・・・かな?」
司は恐る恐るみんなを見渡した。
「でも、司君・・・」
義父の言いかけた言葉を縁が遮った。
「うん。キレイな名前! 良い、絶対良いよ!」
そう言うと縁は半身を起こすと傍らのベッドを覗き込み
髪を優しく撫でながら赤ちゃんに語りかけた。
「聖雪ちゃん、良かったね。素敵な名前を付けてもらって」
「そういや、みゆきの産まれた時に似ているかな?」
「いいえ、お父さん。私が産まれた時の顔にソックリですよ」
「おいおい、それじゃ司君が嫌がるぞ」
「まぁ! そうなの、司さん?」
義父の言葉に憮然として義母が訊いた。
「あっ、いえ。そ、そんな」
「冗談よ」
そう言って義母は声を上げて笑った。
みんなもそれに釣られて声を上げて笑った。
「おや、賑やかそうだね」
そう言って病室に入って来たのは主治医の八代医師だった。
何年も着古しているようなヨレヨレの白衣姿は
パッと見は冴えない印象だが、この地域では名医として知られていた。
「縁さん、調子はどうだい?」
「はい、お陰様で幸せです」
「そうかい、そりゃ何よりだ」
その言葉に微笑むと八代医師は赤ちゃんの寝顔を覗き込み話しかけた。
「うん、良い寝顔だ。
これだけ賑やかなのにスヤスヤ眠っているなんて
この子は元気な子になるな。
早く良い名前を付けてもらうんだぞ」
「あら、先生。名前ならもう付けてもらったんですよ。
ねぇ-、素敵な名前よね?」
聖雪に話しかけながら看護師が楽しそうに答えた。
「ほう! で、何ちゃんかな?」
「はい。聖夜の<聖>に降る<雪>と書いて<みゆき>です」
「<みゆき>ちゃんか。まさに今夜は聖雪ちゃんの為の夜だね。
そうそう!」
思い出したように言うと八代医師は小脇に抱えていた小さな箱を縁に手渡した。
「何ですか?」
「開けてごらん。サンタさんからのプレゼントだよ」
そう言って八代医師はニヤリと笑った。
縁が箱を開けると中には高さが15cm程のクリスマスツリーが入っていた。
「まぁ!」
「少しは病室も賑やかになるかと思って持って来たんだが
その必要はなかったかな。もう十分に賑やかだしね」
「いえ、そんな。ありがとうございます。
聖雪には何よりのプレゼントです」
「いや、一番のプレゼントは名前だよ」
「はい!」
縁は最高の笑顔で答えた。
「そうそう、加藤君?」
八代医師は看護師に話しかけた。
「そういえば、さっき婦長が探していたぞ」
「あっ、いけない! つい長居しちゃったわ。
縁さん、何かあったらすぐにコールしてね。
今夜は私が夜勤だから」
「はい、ありがとうございます」
「それじゃね。又、後で様子を見に来るわ」
ドタドタと加藤看護師が病室を出たと思った途端
又、病室のドアがゆっくりと開いた。
「メリークリスマス!」
そう言って入って覗き込むように来たのは
縁が出産の時に立ち会った日勤の看護師の七瀬だった。
「あらっ、七瀬さん! 先ほどはありがとうございました」
縁はそう言うと笑顔で頭を下げた。
「あっ、とんでないですよ。
どうですか? まだ間もないんだから無理はダメですよ」
「はい。大丈夫です。
こうしてみんなでこの子を囲んでいると不思議なくらい元気をもらえます」
「ホント、赤ちゃんってすごいパワーを持っているんですよねー」
そう言いながら七瀬は聖雪の頭を二度、三度と優しく撫でた。
それから縁に向かって訊いた。
「そう言えば名前はもう決まりました?
まだなら詰所に何故か名付けの本がたくさんあるんですけど
何冊か持ってきましょうか?」
「決まったんですよ」
「あらっ、ホントですか? 何て名前なんですか?」
縁は名前を教えた。
司が説明をしたのと同じ言い方で。
「あら、素敵! 誰が考えたんですか? 縁さん?」
「いえ、パパが」
縁はそう言うと嬉しそうに司を見た。
「まぁ、パパさんてロマンチストなんですね」
「普段はそんな所は見せないんですけどね」
「おいおい、それは余計だろ?」
「そうだよ。縁を選んでくれた時点で良い婿さんだと思ったよ」
義父が司をかばった。
「もう! 冗談に決まってるでしょ!」
「あはは、もう良いよ」
司は苦笑した。
「そうだ! 忘れるところだったわ。ちょっと待ってて」
そう言うと七瀬は病室を出て行ったが、すぐに戻って来た。
後ろ手には何か箱のようなモノを隠していた。
「じゃーん! はい、聖雪ちゃんにプレゼント!」
そう言うと七瀬は縁に箱を手渡した。
駅前の有名なケーキ屋の箱だ。
「どうしたの?」
「クリスマスですからねー、ケーキです!
部屋に帰って独りで食べるのも寂しかったんで一緒にどうかなって」
「嬉しいわ!」
「そうだ、肝心のクリスマスケーキを忘れてた」
司はそう言うと頭を掻いた。
「出産騒ぎでそれどころじゃなかったろうさ」
「騒ぎって?」
縁は父親をきっと睨んだ。
義父としては婿をフォローをしたつもりだったが
またしても少し的が外れたようだった。
「いや、それはその・・・」
「聖雪のバースデーケーキでもあるね」
今度は司が話題をそらそうと義父をフォローした。
「仲の良いお義父さんとお婿さんですね。
私もそんなお婿さんが欲しいなぁ-」
「七瀬さんなら大丈夫よ」
苦笑しながら縁は言った。
「えー? ホントですか?
じゃ、ダメだったら縁さんが責任を取ってくださいね」
「それじゃ、司さんの同僚でも紹介しようか?
ねぇ、司さん?」
「えっ? あっ、あぁ・・・」
「おいおい、いったい何の話になってるんだい?
ここは結婚相談所じゃなくて病室だったはずだが?」
八代医師がもっともな事を言ってみんなを笑わせた。
「じゃ、とりあえず私達はここで失礼するよ」
「明日又、来るからね。そうそう、何か必要な物はある?」
「ううん、とりあえずは大丈夫。
お父さん、お母さん、ありがとうね」
「何を言ってるの。ありがとうはこっちの台詞よ。
ねぇ、お父さん?」
「あぁ、その通りだ。良い子を産んでくれてありがとう」
みんなが帰って三人きりになった病室は静かだった。
初めて迎える家族三人の夜。
そして初めてのクリスマス。
司と縁は聖雪の寝顔を黙って見つめながら充実した幸せを感じていた。
「あー、まだ雪が降ってるんだね」
立ち上がって窓に向かい病室のカーテンを少し開けると司は言った。
縁は傍らの聖雪を黙って見ていた。
それから司に向かって頭を下げながら言った。
「司さん、ありがとう。
みゆき姉さんもきっと喜んでくれているわ」
司は又、ベッドの傍らに歩み寄ると聖雪の寝顔を見ながら呟いた。
「これも君がくれた素敵な縁さ。
お義父さんもお義母さんも八代先生も七瀬さんも加藤さんもみんな素敵な人だね」
「うん」
「みんなで幸せにならなきゃね」
「そうね」
縁も頷いた。
司はベッドの傍らに腰を下ろすと縁の肩を抱いて言った。
「縁と聖雪との初めての素敵な夜にメリークリスマス」
その言葉にベッドでスヤスヤ眠っていた聖雪が微かに微笑んだように見えた。