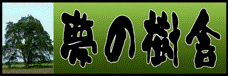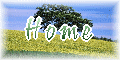
嗚 咽
「いやぁー、まさか
こんな所で君に逢えるとは思ってもいなかったよ。
帰ってたんだ? さぁ、先ずは乾杯しよう」
男は笑顔で右手に持ったグラスを
カウンターに並んで座った女の前に差し出した。
女は黙ったままで男のグラスに自分のグラスを合わせた。
「それにしても何年になるかな?
五年・・・いや、六年? いや、もっとかな?」
「五年十一か月よ」
女は自分のグラスを見ながら答えた。
「随分と詳しく覚えているんだな?
もしかしてまだ俺のこと・・・」
男は女の方に身を乗り出して話しかけたが
男の言葉を遮るように女は話し始めた。
「父が亡くなったの。あなたと別れて十日後。
来月が七回忌なの。だから・・・」
「お父さんが? そっか・・・」
男はバツが悪そうに座り直すと神妙な顔付で言った。
「あなたと別れた後・・・」
「うん」
「そりゃ泣いたわ。この人が世界で一番愛している人って。
・・・そう信じていた人に裏切られたんだもの」
「・・・」
「涙ってどうして枯れないんだろう?
それくらい泣いたわ。
そして何もかもがどうでも良くなって・・・」
「・・・」
男はただ黙って頷きながらグラスを両手で弄んでいた。
「故郷に帰ろうかって思ったの。
ここにいても何処にも居場所は無くなったみたいな気がして
ただ辛いだけだったし・・・
でも、帰るキッカケが無かったし
どんな顔をして帰ったら良いのかも解らなかったわ」
「どうして? 自分の家だろ?」
「私は父が大っ嫌いだった。
いつも横暴で自分だけが正義みたいな顔をして
私の言うことにはいつも『ダメだ、ダメだ!』ってそればっかり。
随分と反発もしたわ。
それで高校を卒業したらすぐに
家出同然で家を飛び出して奨学金で大学に通いながら
バイトを何個も掛け持ちをして生活していた。
で、そのままこっちで就職したの。
母は何かと気にかけてくれていて
時々、援助もしてくれたわ。
もちろん、父には内緒だったと思うけど」
「・・・」
「それっきり父とは話をしたことも無かったし
家にも一度も帰らなかった。でも・・・」
「うん」
「あなたと別れて一週間くらい経った頃かな。
母から突然電話が来たの。お父さんが倒れて危篤だって」
「・・・」
「私、どうしたと思う?」
「どうって?」
「おかしいわよね。
父が危篤だって知らされて自分でも予想外に動揺したの。
あんなに嫌いでずっと避けてさえいたのに。
でも、あなたと別れて泣いていたことさえ忘れるくらい
何もかもが真っ白になったの。
私が病院に着いた時にはもう父の意識は無かったわ。
もっとも、意識がちゃんとしていたら
私の顔を見た瞬間に怒鳴り出していたかもね」
女は自嘲気味に笑った。
それを見た男は悲しいくらいにキレイな笑顔だと思った。
「そんなことはないさ。
お父さんだってとっくに君のことを許していたと思うな」
そんな言葉が女の慰めにはならないことくらい解ってはいたけど
男は何か言わずにはいられなかった。
しかし、それには答えずに女は続けた。
「それから二晩ずっと病院で付きっきりだった。
色々と話をしたわ。一方的にだけどね。
恨み言もたくさん言ったし、それから・・・」
女はちょっと考えてから続けた。
「いや、文句や愚痴ばっかりだったかな。
アハッ、おかしいけど・・・
悪口たくさん言ってたら怒って目を覚ますかな? なんてね。
でも、何も答えてくれなかった・・・」
悲しげにそう言うと女はグラスに残っていたカクテルを一気に飲み干した。
「マスター、お代わりください」
「はいよ」
聴いていたのか聴いていなかったのか?
マスターはわざとのようにおどけて答えた。
新しいカクテルが置かれるのを待って女は話を続けた。
「それから三日目の朝に亡くなったの。
お医者さんもそんなに持つとは思わなかったみたい。
二晩続けて『今夜が山です』って言ってたのに
お医者さんも立場を無くすわよね。
本当に頑固なんだから・・・」
そう言いながら思い出していたのか
女の目には涙が潤んでいた。
「少しでも君といたかったんじゃないかな?」
胸を詰まらせながらやっとの思いで男は呟いた。
それは本心からだった。
「それは解らないけど・・・
でも、結果的に私に帰るキッカケを作ってくれたのは確かね。
バカみたい・・・他にも方法はあったはずなのに・・・
命を賭けて私に帰るキッカケを作ってくれなくたってさ。
そんなの・・・喜べるはずないよ」
女は必死で涙を堪えていた。
だが、その端から流れ落ちる滴を止める術も持ち合わせてはいなかった。
「だよな・・・」
男はポツリと呟いた。
女は出来る限りの笑顔で男を見ると言った。
「でも、その後の葬儀だなんかでバタバタしているうちに
気がついたらあなたのこともすっかり忘れてた」
「そっか・・・何か複雑だな」
男は相変わらずグラスを両手で弄ばせたまま
女の方は見ずに前を向いて言った。
女は男を見ると訊き返した。
「どうして?」
「んー、上手くは言えないけど。
それで俺のことを忘れられたのなら良かった気もするし
何て言うか・・・残念って訳じゃないけどさ。
やっぱ、お父さんには敵わなかったんだ・・・みたいなね」
「うふ。比べられることじゃないけどね」
「まぁね。そうなんだけどさ。
で? それからどうしたんだ?」
「どうって? そのままよ。
二週間ほど実家にいて、後はこっちに戻って
又、同じ暮らしをしていたわ。
毎日仕事に行って、帰ってきて又、仕事に行ってみたいな」
「そうなんだ? てっきり実家に帰ったものだと思ってた。
あの後、一週間くらいしてからだっけな。
君の部屋に行ったんだ。
ずっと待ってたけど夜中になっても君は帰って来なかった。
そしたら隣の部屋の人が帰ってきて
『どうしたんですか?』って言うから
実はこうでって話をしてさ。
そしたら、その人は『実家に帰ったみたいですよ』って。
そっか・・・<帰る>の意味が違ってたんだね。
そっか・・・」
女は何も答えなかった。
「まぁ、自業自得って奴だよな」
「・・・」
「うん・・・」
「でも、どうして私の部屋に?」
「うん、何かさ・・・後味が悪かったって言うか・・・
まぁ、自分勝手な話なんだけどね。
ちゃんと君と話がしたかったんだ」
「それでどうするつもりだったの?」
「許してもらえるとは思わなかったけど・・・
いや、心のどこかで<もしかしたら>みたいな
そんな都合の良い想いはあったかもな」
「すれ違うってさ」
「ん?」
「すれ違うって、結局は縁が無かったってことなんだよね」
「そうかな? もしかしたらさ。
ただ時期が違ってたってだけかもしれないんじゃない?
出会った時期が早過ぎたとか遅過ぎただけってこともあるだろ?」
「・・・」
「仮に、縁が無くて別れたとしてもさ。
今夜、こうして又、逢えたってことは縁があったってことに・・・」
「無理よ」
男の言葉を遮るように女は言った。
「無理・・・」
男は意を強くして女に言った。
「同じ暮らしをしてたってことはさ。
つまり未だ結婚はしていないってことだよね?
それじゃさ。あの・・・考えてくれないかな?」
「・・・」
「ううん。やり直しが出来ないなら・・・
そう! ここで出会った今の俺と付き合ってくれないか?」
「無理よ・・・もう、遅いの」
「遅い?」
「えぇ。私、今付き合っている人がいるの。
多分、来年には結婚をするわ。だから・・・」
「本当に?」
女は黙って頷いた。
だが、女は男に嘘を言ったのだ。
本当は付き合っている人なんていなかった。
そして何よりも女は未だ男のことを愛していた。
それでも女は嘘をついた。
「そっか・・・」
男は少し項垂れたままで続けた。
「ごめんな。俺はやっぱり身勝手なままだね。
何も進歩はしていないな」
男はサバサバした表情を浮かべると女に笑いかけた。
「進歩していないどころか、単なる自己中バカだ。
俺・・・又、同じ失敗をするところだったかもな。
本当、ダメだな・・・」
「ごめんね」
「いや、謝るのは俺の方だよ。
でも、最後の言葉は『ごめん』じゃなくってさ。
『ありがとう』って言わせてもらっても良いかな?」
女は涙を浮かべながら頷いた。
「ありがとう。幸せにな」
男は女に握手を求めた。
女は差し出された男の手をそっと握り返した。
その温もりはあの頃と何も違ってはいなかった。
あの頃、大好きだったあの温もりと。
女は男の後について無言で店の外に出た。
何かを口に出せば自分の感情の全てが崩れてしまいそうな気がしていた。
店の外に出ると男は振り返ると努めて笑顔で言った。
「さて、それじゃ駅まで送って行くよ。
それくらい良いだろ?」
女は黙って首を振った。
「そうだな」
「*****」
「えっ?」
女が小声で発した言葉に男は訊き返した。
女は言葉を飲み込むように笑顔を作ると言った。
「ううん。じゃ」
「あ、あぁ、じゃあ・・ここで」
そう言うと男は何かを断ち切るかのように
一度天を仰ぐと、そのまま女に背を向けて歩き出した。
女が最後に発した言葉は『ありがとう』だったのか?
それとも『さようなら』だったのか?
或いは、もしかしたら『あいしてる』だったのか?
雑踏の中に消えて行く男の背中を目で追いかけながら
女はずっとその場所を動かなかった。
いや、動けなかったのだ。
女はただ声を殺して呻くように嗚咽を漏らしていた。
もうとっくに失くしていたと思っていた涙が
身体中から溢れ出てくるのを必死に押し留めようとしてはいたが
それでも涙は後から後から溢れて来た。