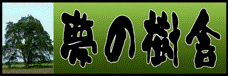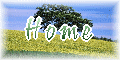
想い出喪失症
人には誰しも想い出がある
忘れられない想い出
忘れたくない想い出
時を経て
記憶が曖昧の領域に差し掛かってしまったとしても
想い出だけは失う事は無い
人が心に紡ぐ想い出は
時を経ても尚、色褪せる事なく
いや、むしろ
より美しさを加えていくものだ
何故なら
この地上における幾多の生き物の中で
それが唯一、人間だけに神が与えし特権なのだから
それでも尚
想い出すらも失ってしまったとしたら
それでも人は人だと言えるのだろうか?
それでも人は生きていると言えるのだろうか?
私には想い出が無い
いや
記憶と呼べるものは確かにある
しかし
それだけなのだ
断片的な記憶
曖昧な記憶
時にはそれらが誰の記憶なのかも曖昧に感じてしまう
本当に自分の記憶なのか?
いや・・・解らない
自分の記憶だと言う感情が無いのだから
その記憶には何の思い入れも無いのだ
想い出と呼べるものが無いのなら
そんな記憶はどうだって良い事なのだ
それらが自分のものでは無かったとしても
そんな事はどうだって良い事なのだ
誰か教えてくれ
私は生きているのか?
それでも私は生きていても良いのか?
「先生。どうなんでしょう?
私は生きているのでしょうか?」
男がうな垂れたままで訊ねると
精神科医は少し考えた後でこう言った。
「もしも、私の目の前にいる君が幽霊だとしたら
私は医者を辞めて坊さんでにでもなるしかないね」
「じゃ・・・」
「まぁ、待ちなさい。
だが、話はそう簡単ではないようだね」
「分かりません」
「そう、自分を責める事もないよ。
良くある事だよ」
「良く・・・あるんですか?」
「おそらくは、トラウマだろうね。
幼い頃、ご両親の愛情に恵まれなかったとか
愛する人とか信頼していた友人に裏切られたとか
尊敬をする職場の上司に騙されたとか。
そう言う心の深い傷がトラウマとなっていて
君の人生観そのものを奪ってしまったのかも知れない」
「そうでしょうか?
でも、私は両親にはとても愛されて育てられました。
生まれた時、100日のお祝い、七五三、入学・・・
行事の度に私の専用のアルバムは増えていったのです。
それは今でも大事に取ってあります」
「では、恋人とか親友に裏切られたとかはどうだね?」
「それも覚えがありません。
恥ずかしい話ですが
それほど深く愛した女性はいませんでしたし
親友と呼べるだけの友人もいません。
例え、裏切られたところで傷になるような相手は・・・」
「ふむ。なるほど。
では、学校の恩師とか職場の上司はどうかね?」
「それもやはり・・・心当たりがありません」
精神科医はしばらく無言で考えていた。
そして、何かを思いついたように頷いた。
「先生。何か解りましたか?」
「ひとつ確認なんだが。
過去の記憶はちゃんと残っているんだよね?」
「えぇ。断片的ですが、記憶は明確に残っています。
でも、それに対して何の感情も湧かないんです」
「なるほど」
「先生。私には感情と言うモノが無いんでしょうか?」
男は俯いたまま膝の上で両手を握り締めていた。
「まぁ、そう性急に決めつける事はない。
時に・・・」
「はい?」
「昨夜の晩御飯は何だったね?」
「はっ? 晩御飯・・・ですか?」
「うむ」
「昨夜は・・・そう、カレーライスでした」
やはりうな垂れたままで男は答えた。
「どんな?」
「どんなって・・・普通のです」
「お肉は豚だった? 牛?
それとも、魚介類とか?」
「それが何か関係あるんでしょうか?」
「これはとても大事な事なんだ。
それでどうだったのかね?」
「豚肉でした。ゴロっとした」
「ふむ」
又、顎に指を当てて精神科医は何事か考え込んでいた。
「で、それは美味しかったかね?」
「えぇ。いつも食べている味でしたから」
「美味しかったと?」
「まぁ。普通に」
「ふむ」
精神科医はイスから立ち上がり窓の方に向うと
遠くを見るでもなく何事か考え込んでいた。
「で・・・」
振り返ると精神科医は訊ねた。
「先週の日曜日は何をしていたかね?」
「先週ですか?
日曜日は昼前に起きて、午後から本屋に行きました。
昔読んだ記憶の本を読み直せば
もしかしたら、何か感情を思い出すかと思って」
「本・・・ね? それはどんな本だったのかな?」
「解りません。
もしかしたら本など読んだ事がなかったのかも知れません。
名作と呼ばれる本を何冊も手にとってみたのですが
どれも読んだ記憶が無かったのです」
「本を読んだ記憶が無い?
君はご両親に愛されて育ったと言ったね?
それなら小さい頃に絵本だとか
お母さんは読み聞かせてはくれなかったのかね?」
「お母さん・・・ですか?
何故、お母さんが絵本を読み聞かせしてくれると?」
「違うのかね?
そんな記憶は無いと?」
「解りません・・・」
「ふむ。解らない・・・なるほど」
「先生。私は・・・」
「まぁまぁ」
精神科医はそう言うと、男をなだめるように優しく言った。
「さぁ、落ち着いて。心をリラックスさせて。
そう。静かに目を瞑って。
もう一度、ゆっくり思い出してみよう。
君は幼い子供だ。
夜になった。子供はもう寝る時間だ。
君はベッドに入っている。
お母さんは君に布団をそっとかけて
そして、君の横に添い寝をしながら
今夜も絵本を読んでくれている。
どうだね? そんな情景が思い浮かんだかね?」
「はい。お母さんが私の横で絵本を・・・」
「どうしたね?」
「顔が・・・」
「顔がどうしたのかね?」
「お母さんの顔が・・・無いんです」
ショックを隠す事もせずに
男はうな垂れたまま顔を両手で覆った。
「顔が無い? どうしてだね?
ゆっくり見てごらん。お母さんは微笑んでいるだろ?」
「あぁ! 顔が!」
「わ、解った! 落ち着きなさい。大丈夫だ!」
「あぁ! お母さん・・・」
男は床に倒れ込むと、そのまま泣き崩れてた。
「先生。私はやはり欠陥人間なんでしょうか?」
「いや、そもそも人間なんて言う生き物は
みんなすべからく欠陥を抱えているものなのだ。
完璧な人間なんていやしない。
君が特別な訳でもないさ」
「でも・・・」
「時に、お母さんはまだ健在かね?」
「えっ? いや・・・」
「そうか。いつ亡くなったのかね?」
「いや、そう言う訳では・・・」
「じゃ、今は何処に?」
「・・・」
「まぁ、話したくなければそれでも構わんが。
人にはそれぞれ事情もあるだろう」
「私には母の記憶が無いのです。
だから・・・今、何処でどうしているのか?
生きているのか? もう死んでいるのかさえ
私には解らないのです」
「記憶が無い?
では、お父さんは?」
「それも・・・
ただ、私の・・・これもまぁ、多分ですが
私の幼い頃のアルバムだけはさっきも言ったように
私の手元にあります。
実際、それが私の写真なのかは解りませんが・・・」
「そうか、きっと・・・
君にモノ心がつく前に亡くなってしまったんだろうね。
じゃ、君は今まで何処でどうして生きてきたのかね?
誰に育てられたのだね?」
「育てられた?」
「そうだ。誰かに育てられなければ
子供だった君が今まで生きてこられる訳がないだろう?」
「私は・・・」
「私は?」
「今のままです」
「今の?」
「はい」
「どう言う事だね?」
「解りません」
精神科医は深く失望の溜め息をついた。
こんな患者は初めてだった。
全く、要領を得ない。
どう話を引き出そうとしても直ぐに何処かで止まってしまう。
『記憶喪失?』
ふと、そんな言葉が頭に浮かんだ。
もちろん、それは一番最初に浮かんだ言葉だった。
でも、精神科医が”知っている”記憶喪失とは
何処かが違うようにも思えた。
『何らかの記憶障害?』
それは二番目に浮かんだ言葉だ。
無理にこじつけるならそれで良いのだろうが
だが、それも何か違うように思えた。
第一、仮にだ。
両親が早くに亡くなっていたにしても
写真くらいは見て育っているはずだ。
それなのに
絵本を読み聞かせをする母親を思い起こそうとしたら
彼は顔が無いと言った。
普通なら、若い頃の母親の写真を見ていたとしたら
若い頃の母親の顔を思い浮かべるはずなのだ。
だが、彼は顔が無いと言った。
それは何を意味するのか?
精神科医は考えあぐねていた。
「先生」
「ん? なんだね?」
「私は記憶喪失なんでしょうか?」
「そうかも知れない。
だが、そうではないかも知れない」
「と、言いますと?」
「ふむ。今までのどの症例にも当てはまらないのだ」
「やはり、私は生きてはいないのですね?」
「そうかも知れない・・・」
「じゃ、私はここにいるべき人間ではないのですね?」
男はうな垂れたまま
今にも消え入りそうなくらいの声で呟くと
嗚咽とも溜め息ともつかないような声を漏らした。
精神科医もそれに呼応するかのように又、深く溜め息をついた。
「もし、そうだとするなら。
精神が病んでいるのは、むしろ私の方なのかも知れんな」
「そんな!」
「もちろん。そんな事は私が一番認めたくはないがね」
「・・・」
「君には記憶はある」
「はい」
「だが、その記憶に対する感情が湧かない」
「はい」
「感情が湧かないのは記憶だけじゃないようだね。
対人関係もしかり、食べ物についてもしかりだ」
「はい」
「私も精神障害で感情の無い人間は
今まで何人も診てきたが・・・
彼らは怒る事はもちろん、泣く事さえしないのだ。
だが、君はさっき泣き崩れた。
そこが普通の精神疾患の患者とは根本的に違うのだよ」
「難しい事は解りませんが・・・つまり?」
「君には感情がちゃんとあると言う事だ。
感情はあるのだが、何て言うか・・・そう。
記憶とその感情がリンクしていないのだよ」
「記憶とリンクが?」
「うむ。しいて言うなら『想い出喪失症』
もちろん、そんな病名は無いがね」
精神科医は
思わず口をついた”病名”に苦笑するしか無かった。
「想い出喪失症・・・想い出・・・喪失・・症・・・」
男は相変わらず俯いたままで自分に言い聞かせるかのように
その言葉を繰り返し、繰り返し呟いていた。
「まぁ、そう自分を責めてはいけないよ。
君が悪い訳じゃない。病気なんだ。
病気なら治療をすれば良い。
難しいかも知れんが、私も力になろう。
さぁ、君。顔を上げてごらん。
俯いてばかりじゃ、気持ちが滅入るだけだ」
男はやはり俯いたまま何も答えなかった。
「さぁ、これからの事を前向きに話そうじゃないか」
「何処を向けば良いんです?」
「ん?」
精神科医は怪訝な顔で男を見た。
問診を始めてからもう30分は経っただろうが
そう言えば、この患者の顔って見ただろうか?
男が診察室に入って来た時から
話をしている間もずっとうな垂れたままだった事に
精神科医は初めて気がついた。
「君・・・?」
「先生。私はいったい何処を・・・?」
そう言いながら男は静かに顔を上げた。
「ギャー!」
精神科医は思わず悲鳴を上げた。
男には”顔”が無かったのだ。
顔はその人の人生を表していると言う。
その表情、その皺の一本一本が
そして、そのひとつひとつに刻まれている想い出が
今まで生きてきた歳月の証でもある。
もし、人にその想い出が無いとしたら?
記憶だけがいくら残っていたとしても
ICチップと何も変わらない
ただの物体でしかなくなってしまう。
ただの物体であるなら
元より顔の部位だとか表情などは必要ない。
たが、果たして
そんな記憶の何処に価値があるのだろう?
人は記憶を検索などしない。
思い出すのだ・・・