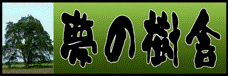オ ム レ ツ
大学4年の1月。
冬休みに東京から北海道の実家に戻っていた俺は、
就職活動の為に旭川にいる俊夫のアパートに数日間居候をしていた。
俊夫とは高校は別々だったのだが下宿の3年間を一緒に過ごした。
俊夫は同い年だが1年浪人をしていたので今はまだ大学の3年生をしている。
お互い、1人っ子同士でフォークソング好きと言う共通点のせいか、高校1年の時に
意気投合をして以来、兄弟のように付き合っていた。
大学受験を境にお互いの生活は変わってしまったが、その付き合いは今も変わっていない。
バイトに明け暮れる俊夫に代わって、一宿一飯の恩義と言う訳ではないが、食事の支度は
俺の役割だった。
その日、仕事探しから帰った俺はいつものように晩ご飯の支度をしていた。
数少ないレパートリーではあったが、ご飯を炊いて、味噌汁を作り、その日のメインディッシュは
オムレツと決めていた。
オムレツと言っても、レストランみたいな洒落たプレーンオムレツでは無い。
母親直伝のどちらかと言えば田舎料理の類だろうか。
例えれば、スペインのお袋の味であるスパニッシュオムレツ(と、本人は思っている)とでも言おうか。
ベーコンやタマネギ、ピーマンにニンジンやシイタケなんかをスライスして、塩コショウで炒め、
それを卵3個で包むのだ。
中はもちろん、半熟。 ふわふわとしたその卵を箸で割ると具と絡んでトロトロになるのが良い。
かけたケチャップにからめると、その仄かな酸味が又、いっそう美味しさを増す。
もっとも、何にでも醤油をかけたがる俊夫の事だ。
『どうせ、これにも醤油をかけちゃうんだろうなぁ〜』
そう思いながら、具を炒めていた時、玄関のチャイムが鳴った。
『おっ、俊夫だな? 今日は早いな』
「まだ、晩飯出来てないぞ」
そう言いながら玄関の戸を開けると、そこにはニコニコした笑顔で加奈子が立っていた。
加奈子とは夏休みに俊夫のアパートに来ていた時も何度か会っていた。
加奈子は俊夫の大学の同級生で、あまり授業を受けていない俊夫の為にと2〜3日に一度くらい
授業のノートを届けてくれていた。
『加奈子ちゃんは俊夫の奴が好きなんだろうな』
そう思いながらも、面と向かっては訊いた事が無い。
何より、俊夫には高校時代から付き合っている恋人がいるのだ。
加奈子もそれは知っているはずであった。
どっちにしても、まぁ〜そんな事は余計なおせっかいだと思いながら、加奈子を部屋に招き入れた。
「俊夫はまだバイトですか?」
「うん、でももうすぐ帰って来ると思うよ。 ちょっとそこに座って待ってて。」
加奈子をテーブルのところに座らせて
「コーヒーで良いかな? インスタントだけど。」
「あっ、良いですよ〜 すぐに帰りますから。」
俺はお湯を沸かすと、お客さん用のカップにコーヒーを入れて加奈子の前に置いた。
「いつも悪いね。俊夫なんかの為にさ。 おっと、何だかまるで俺が俊夫の親父さんみたいだな。」
そう言うと加奈子は
「お父さんと言うよりは、奥さんみたい。」
と、笑った。
台所でオムレツの仕上げをしていた時だった。
加奈子は傍に来ると覗き込んで訊いた。
「今晩は何ですか? オムレツですか?」
「そう、今夜はね〜 たかさん特製オムレツ!」
「わぁ〜 美味しそうですね〜」
まるで品定めをするかのように、ジロジロ眺めると
「へぇ〜 たかさんって料理が上手なんですね〜 良い奥さんになれますよ!」
と悪戯っぽく笑った。
「私、上手く形が作れないんですよね〜 いつも、途中で崩れちゃって。」
加奈子のちょっと困ったような、照れたような仕草が可愛いと思った。
「大丈夫だよ。 加奈子ちゃんだって、もっと上手くなるよ。 食べさせたい、食べてもらいたいって
そう思える相手が出来たらね〜 おっと、勝手に彼氏がいないって決め付けちゃったね?
ごめん、ごめん。」
と、苦笑いでごまかす俺。
『そんなぁ〜 彼氏なんていないですよ〜』
と、俺は加奈子が否定をしてくれるのを期待していたのかも知れない。
知ってか、知らずか、加奈子はその言葉には触れずに
「タマゴ料理って基本じゃないですか。 私ね、オムレツが上手に作れるようになったら
お嫁さんに行きたいなぁって思ってるんですよ。 おかしいですか?」
そう言うと、加奈子は又少し照れたように笑った。
その笑顔を見ていると、何だか妙に嬉しくなった。
「そんなに褒めてもらったからには、ぜひ加奈子ちゃんにも食べて行ってもらわなくっちゃね。」
「あっ、そんな良いですよ〜 2人分しか作ってないんでしょ? 私、ノートを置いたらすぐに
帰りますから。 その代わり、また今度絶対ご馳走して下さいね。」
「大丈夫だよ。 2人分にしては多いんだ。 俺も少しダイエットしないとまずい口でしょ?
人助けだと思って食べていってよ。 あっ、心配しないで。胃腸薬は買ってあるからさ。」
俺は何だか自分でも良く分からないくらい喋り続けた。
他愛もない時間だったが、加奈子と話していると妙にホッとして、心が和むのを感じていた。
「おっ、何だ。加奈子来てたのか?」
玄関の戸を開けるなり、俊夫はそう言って部屋に入って来た。そして加奈子の向かい側に座った。
「何だはないでしょ。 誰のお陰で授業に出ないでもノートが見れると思ってるのよ。
少しは感謝しなさいよね! そう言うとこは、少しはたかさんを見習って欲しいもんだわ。」
加奈子は少しむくれてそう言ったが、顔は全然怒ってはいない。
「たか? へぇ〜」
「何よ?」
「いや、別に。」
俊夫は意味有り気にニヤニヤしながら俺の方を見た。
「何の話だ? もうちょっとで晩飯出来るよ。」
と、俺。
「晩飯の前にコーヒー飲みたいなぁ〜 マスター、ホット1丁ね。こちらのお嬢さんにも。」
「あっ、私はもう頂いてますから。」
「へいへい、じゃ、マスター。俺の分大盛りね。」
「大盛り? コーヒーの大盛りってどんなだよ?」
そう言って、俺はコーヒーの並盛りを俊夫に手渡した。
俊夫はそのコーヒーをひと口飲むと
「うげっ、苦げぇ〜 何だよ、これ? すっげぇ、苦いぞ。」
俺は澄ました顔で
「当店ではコーヒーの大盛りは用意してございませんので。
その代わり、サービスとして豆を大盛りで入れさせて頂きましたが。」
「たかさんの勝ち!」
加奈子はそう言って、手をパチパチはたいて愉快そうに笑った。
腰に手を当てて自慢気なポーズを取る俺に俊夫は
「いつから2対1になったんだ?」
と、苦笑するだけだった。
「それじゃ、私これで帰るね。 新婚さんのラブラブなお夕飯の邪魔をしちゃ悪いから。」
加奈子はそう言って悪戯っぽく笑った。
「おいおい、誰と誰が新婚さんだって?」
俺と俊夫は奇しくも同時に声を揃えて文句を言った。
「ほらぁ〜 息もピッタリ! お似合いよ〜」
「よしてくれ!」
また、俺と俊夫は声を揃えて言った。
思わず、お互いに顔を見合わせると3人で大爆笑になった。
食事も終わると、今度は加奈子が入れてくれたコーヒーを飲みながら、
他愛も無いお喋りで時は過ぎていった。
夜中に下宿を窓から抜け出して、下宿の仲間と遊びに出た事。
消灯時間を過ぎて、食堂で息を呑んで11PMを観てたら、突然下宿のおばさんが起きだしてきて
みんなで慌てて逃げ出した事。
下宿の裏の公園でジンギスカンをしていたら、草に火が燃え広がって火事になりかけた事。
あの時はお前が悪い。いや、お前だなどとやりあう二人を加奈子は楽しそうに笑いながら見ていた。
「あっ、大変! もうこんな時間だわ。 バスの最終に間に合わなくなっちゃう。」
そう加奈子が言って立ち上がると、俊夫が
「ホントだな。 たか、加奈子をバス停まで送ってやってくれるか? 俺は明日までにノートを
写しちゃわなきゃならないからさ。」
「あっ、大丈夫ですよ。 1人で帰れますから。」
「良いから送ってもらえって。 たかなら大丈夫。
羊の皮を被った羊だから、加奈子を襲ったりしないよ。 あー? たかが襲われる心配をした方が
良いのか?」
「んもう、そんな事しませんよ〜だ! たかさんだって、そんな事をしません!」
加奈子は口をとがらせながらそう言った。
「へぇ、たか、随分信用されてんだね?」
俊夫はそう笑いながら言った。
「俊夫じゃないんですからね。」
加奈子がそう言うと俊夫は
「男は見かけじゃ分からないぞ〜 たかみたいに、優しく見える奴の方がホントは怖いんだぞ。」
「そんな事ないです。」
2人の話を聞いていた俺は
「ねぇ? 俺って信用されてんだか、バカにされてんだか・・・どっちだ?」
と、苦笑いの俺に加奈子は
「たかさんは少なくとも、俊夫よりは信用出来るのは120%分かってますから安心して下さい。」
「ん? それってフォローになってる?」
と、俺はまた苦笑い。
「おい、早くしないとホントに遅れるぞ。」
俊夫の声に促されて、俺は加奈子をバス停まで送って行く事になった。
俊夫のアパートからバス停まではゆっくり歩いても10分ほどの距離だった。
角毎に薄明かりの街灯があるだけの薄暗い路地を2人は並んで歩いた。
お互いに少し照れながら、何となく言葉も少なげになっていた。
口を出る言葉はどうって事のないくだらない話ばかり。
そしてそれは永遠を願うにも余りに短すぎる距離だった。
バス停に着いて5分もしない内にバスはやって来た。
『こんな時に限って定刻通りかぁ・・・』
俺は日本の交通機関の生真面目さを独り言のようにぼやいていた。
「えっ?」
「あ、いや・・・」
「じゃ・・・」
バスに乗りかけると加奈子はふと足を止めて
「たかさん、ご馳走様でした。 オムレツとっても美味しかったです。
また、ご馳走して下さいね・・・でも、襲われなかったのは少し残念だったかなぁ〜
あっ、冗談ですよ! 気にしないで下さいね。おやすみなさい。」
そう言うと足早にバスに乗り込んで行った。
加奈子は中ほどに座ると窓越しにこちらに手を振っている。
やがて、静かに走り出したバスを俺はずっと見送っていた。
『また、春休みにでも会えるさ。その時には・・・』
結局、それが加奈子に会った最後になった。
加奈子は実家の都合で、春休みを待たずに故郷に戻って家業の手伝いをする事になったのだと
俊夫から聞いたのは、就職の準備の為に再び旭川を訪れた春休みすぐの事だった。
オムレツが作れるようになったらお嫁に行きたいと言っていた加奈子。
あれから3年が経った。
今頃は誰かの為に、オムレツを作っているのだろうか・・・