
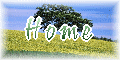
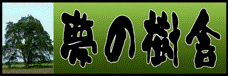
プラネタリウム
「やっぱり止めておくよ」
『何でだよ?』
俺の言葉に電話の向こうの卓夫が訊き返した。
「だってさ。勇人を預けるところも無いし」
『だから、勇人も連れて来いって言ってんじゃん』
「そういう訳にもいかないよ」
『弘樹、何を気にしてんだよ?
みんな知ってることなんだし、気にすることないって』
「みんなって・・・お前なぁー
話を広めたのはどうせお前だろ?」
俺は苦笑いしながら言った。
『いやいや。ホント、みんな心配してるんだって。
だからさ、お前が勇人を連れて来てさ。
ほら、元気なところをみんなに見せてやれって』
「でもさ。お前みたいな酔っ払いがウジャウジャいるところに
五歳の勇人は連れてけないよ。教育に良くない」
『人の三倍は飲んべのお前が良く言うよ』
「俺か? 俺は今、酒は控えてるんだ」
『マジか?』
「あぁ、マジだ。俺は変わったんだ」
『そっか、えらいな。それも子供の成せるワザかな?』
「なんとでも言え。まぁ、そういう訳だから今回はパスさせてくれよ」
『良し、解った・・・と、言いたいところなんだけどな』
「何だよ?」
『都子がどうしてもお前を呼べってきかないんだよ』
「都子が? なんで?」
『あ-、お前が勘違いしないように最初に言っておくけどな。
都子は春に結婚したんだ。
ほら、一級上の佐々木って知ってる? 不動産屋の息子』
「あぁ、金回りの良かった奴だろ?」
『その、佐々木なんだけどさ。
いつの間にか都子とくっついていたらしくってさ。
招待状を貰って俺らもビックリさ』
「なんだい、それなら呼んでくれたら良かったのに」
『丁度、ほら。お前の離婚云々の時期だったろ?
さすがに遠慮したんじゃないか?』
「まぁ・・・」
『でさ。その都子が今度の同窓会は
高校を卒業して十二年目、みんなもう三十歳になる記念すべき同窓会だから
どうしてしても、お前を呼び出せってさぁ』
「三十歳の記念って、どういう理屈だよ。全くもう」
『何でもね。十二年ったら干支が一回りじゃん?
今年は卒業した年と同じ干支なんだってさ。
だから、絶対にみんなで集まるんだって、そういう理屈みたいよ』
「そっか、もうそんなになるのか・・・」
『あいつなりに心配してるんだよ。高校の三年間、一緒の仲間だったしさ』
「そりゃまぁ、ありがたいけどね」
『だろ? それで決まりだな。来いよ、待ってるからさ』
「おいおい。でも、それとこれとは別だろ?」
俺は又も苦笑いをするしかなかった。
『今更、何を言ってるんだ? 俺の顔を潰す気か?』
「お前の顔なんて、踏んだって潰れないよ」
『失礼な奴だな』
卓夫はちょっと憤慨をした然で言った。
『あっ、そうだ! 忘れるとこだった!』
「今度は何?」
『そんな素っ気ない言い方すんなよ。喜んで良いぞ、朗報だ!』
「朗報? それは怖いね」
俺は更にワザと素っ気なく言った。
昔から卓夫がそういう話し方をする時に朗報なんて有った試しが無かったのだ。
『今度の同窓会はスターライトホテルだって言ったろ?』
「あぁ、優美のオヤジさんのとこだろ?」
『その優美がだな、お前と勇人の為に部屋を取ってくれてるんだ。
それが、優美が奮発をしてだな。ホテルで唯一のスイートだってさ。
こんな田舎で一泊、なんと十万円だぞ! 凄いだろ?
しかもだ。そこを同級生のよしみでロハでご招待だってさ。
あっ、でもな。
因みにキャンセルの場合は自己負担で宿泊料の百パーセントだってよ。
お前、払える?
もっとも、もう客の予約を断ってるからキャンセルは出来ないらしいけどな』
「お前ら・・・そこまでやる?」
『だから、みんな心配して会いたがってるんだって。
それじゃ、年明けを楽しみにしてるからな』
そう言って、卓夫の電話は切れた。
「高校を卒業して、もう十二年か・・・なんか色々あったな」
俺は勇人の寝顔を見ながらしばし思いに耽っていた。
卓夫と都子は中学からの同級生だった。
高校一年生の時は都子と優美、卓夫と俺が同じクラスで
それともう一人、卓夫の小学校からの同級生だった一哉が
高校でも卓夫と同じクラスになったこともあり
良くこの五人でつるんで一緒に遊んでいた。
最初に声を掛けてきたのも確か都子だったと思う。
五人はそれぞれ性格も趣味も違ったけど
いや、だからこそだったのかも知れないけど
何をするにも何かを話すにも俺達は初めからウマが合っていた。
花火や夏祭りにも行った。サイクリングや海水浴にも行った。
たまには学校をサボってショッピングセンターを用もないのにただブラついてみたり
ゲームセンターなんかにも行って
見つかりそうになった補導員から逃げ回ったこともあった。
決して、何かにいつも反抗をするとか、不良という訳でもなかった俺達だけど
反抗の為に反抗をするみたいな、ただ折れるとか負けるとか
それだけは絶対に嫌で、変に粋がって尖ったりもしていたことは否めない。
までもその頃は誰もが一度は通る道だった。
と、今なら思えたりする。
学校帰りにいつも溜まっていた喫茶店で集まっては
今のことより将来の夢なんかを良くみんなで語っていた。
何でも叶うと思っていたあの頃。
未来は無限に有ると思っていたあの頃。
二年生の文化祭では卓夫の「目立つからバンドやろうぜ」の一言で
五人でステージに立ったりもした。
もちろん、仲間受け以外の何物でもなくステージは大盛り上がり。
「又、来年もやろうぜ!」
文化祭からの帰り道。
道端の自販機で買ったジュースで乾杯をしながら五人で約束をしたのだが
高校二年生の終わりに一哉はオヤジさんの転勤でアメリカに行ってしまい
それは叶わぬ約束になってしまった。
それからも四人はいつもつるんでいた。
しかし、三年生の後半くらいになると進学組、就職組の間に
わだかまりではなかったはずだけど、少しづつお互いの空気感みたいなのが
違って流れるようになっていき、いつか四人が集まることも少しづつ減っていった。
高校を卒業すると、地元に残って就職をした奴もいれば
都会で就職をしたり大学に進学をする為に地元を離れた奴もいた。
卓夫は稼業の大工を継ぐ為にオヤジさんの工務店で働き始めた。
それが今では五人の若い衆をまとめていっぱしの棟梁を張っているらしい。
都子は地元の信用金庫で勤める事になった。
今の旦那とも、そこで客と銀行員として再会したとのこと。
優美はオヤジさんのホテルを手伝えるようにと隣町の専門学校に進学をし
卒業して今はそのホテルを手伝っている。
同窓会と言えば地元を離れた奴らも出席しやすいように
大概はお盆とか正月休みに行われるものだが
ご多分にもれず俺達の同窓会も決まって正月休みの頃にやっていた。
地元の奴が交代で幹事を務めてくれていたのには俺も感謝をしている。
そして、今年の幹事が卓夫だった。
俺も最初の数年は毎年、正月は実家に戻っていたので毎回参加をしていた。
高校二年の初め頃に父親を亡くして、母一人、子一人で生活をしてたので
進学してからも就職をしてからも
お盆休みと正月休みだけは何をさておいても帰省していたのだ。
本当なら高校を卒業したら地元で就職をとも考えていたのだが
意外にもそれに反対をしたのが母だった。
「男は家を出て自立をするものです。
その為には一度は都会に出て広く世間を見なければダメだよ。
学費のことは心配しなくても良いから大学には行きなさい」
母はいつもそう言っていた。
それが本心だったのか、どうだったのかは今はもう知る由もない。
俺は母の言葉通りに大学に進学をし卒業するとそのままこっちで就職をした。
そして、社会人になって二年目の秋を迎えた時、母は長年の無理が祟ったのだろう。
或る日、母から連絡があった。
「入院をしたけど、ただの過労ですって。
大したことはないから心配しないで。
仕事も大変だろうから正月まで帰って来なくて良いからね」
バカな親不孝息子の俺はその言葉を真に受けてついぞ見舞いには行かずじまいだった。
その数日後、仕事中に入院先の病院から母が危篤だと連絡が来た。
俺は急いで会社から休暇をもらって飛行機に乗った。
「なんで、もっと早く・・・」
それは、『なんで、もっと早く帰らなかったんだろう!』という自責の念と
『なんで、もっと早く母は教えてくれなかったんだろう?』
と、いう母への抗議の気持ちの両方だったと思う。
子供の前では決して『疲れた』とか『辛い』とか言ったことのない母だった。
それを知っていたくせに何で俺は・・・
そんなことが何度俺の脳裏を駆け巡ったことだろう?
そんな時に限って焦る気持ちとは裏腹に
全ての乗り物がやたら遅く、その時間はやたら長く感じるものだと改めて知らされた。
病室に駆けつけるとベッドの周りには医者と三人の看護師が付き添ってくれていた。
俺が母の手を握って話しかけると母は笑顔を見せて一言。
「弘樹、一人前になったかい?」
それだけを言った後で静かに息を引き取った。
母、つまりは<帰る実家>を亡くした俺は
それからはお盆の墓参りくらいしか地元には帰っていなかった。
結婚をしてからは尚更で何かと相手の実家を行くことも増え
特に勇人が産まれてからは家族で旅行に行ったりとか
まとまった休みに家族の行事予定を組むことも多くなり
ここ何年かはつい同窓会とも疎遠になっていた。
その後は色々あって結局、今年の春に俺達は離婚をした。
経済的なこともあって勇人は俺が引き取る事になったのだが
それが五歳の勇人にとって良かったのかどうか、俺にはまだ解らないでいた。
そんな俺の噂が地元でどう伝わっていたのか?
それはどうあれ、卓夫からの誘いの電話は嬉しくもあり
また一方では、みんなにどんな顔をして会ったら良いものか考えあぐねていて
同窓会の招待状も締め切りを気にしながらもなんとなく出しそびれていたのも事実だった。
たぶん、卓夫はそんなことを察知してくれていて俺に電話を掛けてきたのだと思う。
あいつは昔からそういう奴だった。
「わー、雪だ! ねぇ、お父さん、雪だよ!」
そう言うと勇人は何処に向かってか駆けだした。
北国の正月頃なら当然と言えば当然ではあったのだが
空港に降りた途端に見えた辺りは一面真っ白だった。
俺には珍しくもない普通の冬景色だったが都会産まれの勇人には別世界にも見えたのだろう。
無理もない。今まで勇人を連れて帰省していたのはいつもお盆だったのだから。
「おい、気を付けろよ。滑って転ぶぞ」
小走りで追いかける俺。
「大丈夫だよー」
勇人は立ち止まってこっちを向くと、そう言ってべーをした。
「こいつ!」
追いかけようとする俺に慌ててきびすを返すと勇人は又、走り出したのだが
ちょっと走り駆けたところで誰かにぶつかって、その場に尻餅をついた。
「あっ、ごめんなさい」
立ち上がりながら、そう謝る勇人にその男は笑って答えた。
「勇人クンだな? 噂通りの腕白、大いにけっこう!」
「卓夫!」
卓夫は俺を見ると真顔で言った。
「良かった。来てくれなかったらどうしようかと思ってた」
「何だよ? そんなに都子に弱みを握られてるのか?」
「あはは。それは内緒だ」
卓夫はそう言うと愉快そうに大声で笑った。
「疲れたろ? 取りあえずはホテルにチェックインして荷物を置いてくるか?」
自慢のSUVを運転しながら卓夫は訊いた。
「あぁ、でもまだ一時半だぞ。チェックインには早過ぎないか?」
「おいおい、何処に泊まると思ってんだ? 何とでもなるさ。
なんせ、スイートのお客様だからな」
「止めてくれよ。スイートだなんて身分不相応も甚だしいよ。
普通のツインの部屋で良いよ。部屋代も俺が払うし」
「おいおい、今更何を言ってんだ?
そんなことを許したら俺が優美に怒られちまうじゃないか!」
「何だよ、お前。優美にも弱みを握られてるのか?」
「あぁ、地元にばかりいると何処で何をしても周りは知り合いだらけだからな。
俺の弱みを握っている人間を殺したらこの町の住人はみんないなくなっちまうよ」
「オジサン、そんな強い人なの?」
後ろの席から大人の話に口を挟んで勇人は驚いた目をしていた。
「えっ? 強い? あはは、強いか。
そうだ、オジサンは強いぞー お父さんの弱みも握ってるしな」
運転をしながら卓夫は俺の方を向くとニヤリと笑った。
「俺の弱みってなんだよ? そんな覚えはねぇよ」
俺は不満げに答えた。
「ねぇ-、お父さんの弱みって何?」
勇人が話に飛びついた。
「勇人!」
俺は思わず大声を出した。
「お前ね-、子供の前でいい加減なことを言うなよな」
俺は卓夫に抗議をした。
「あはは、すまんすまん」
卓夫はそう言いながら勇人に向かってわざと小声で言った。
「後でな」
「おい、聞えてるよ」
俺は憮然として言った。
ホテルに着いて、荷物を下ろしている間も勇人は卓夫のSUVの周りを
珍しそうに何遍も回っては見たり触ったりしていた。
「オジサン。これ何て車なの? 格好いいね」
「おー、そうか? そうだろ? 格好いいだろ?
これはローバーって言うんだ。外車だぞ」
卓夫は荷物を持ちながら得意げに答えた。
「ろうば? ろうばってお婆ちゃん?」
「へっ? おいおい、勇人クン、そりゃないよ。
ローバー。勘弁してくれよ。オジチャン、泣いちゃうぞ」
そう言うと卓夫は荷物を車に戻してから勇人の脇を思いっきりくすぐった。
「キャハハ! こちょばいよー」
勇人は笑いながら嬉しそうに逃げ回っていた。
こんな勇人の笑い声を聞いたのは何年ぶりだろうか?
「お前、子供の扱い上手いな」
そう言う俺に卓夫は自慢げに答えた。
「俺は自慢じゃないけど、子供と年寄りと動物には嫌われたことはないんだ」
「その割にはお前はまだ独身だけどな」
俺がそう言うと卓夫は苦笑いで答えた。
「そうなんだ。子供と年寄りと動物は俺の良さを良く判ってくれるんだけど
何故か年頃の女だけは俺の良さを判らないらしい」
真面目に答えてるんだか、ふざけてるんだか。
でも、そこが卓夫の良いところだと思った。
もちろん、そんなことは本人には絶対言わないけど。
そんなことを思って俺はニヤニヤしていたらしい。
「何、一人でニヤけてるんだよ? 気持ち悪ぃぞ」
チェックインを済ませ部屋に案内されると勇人は大はしゃぎだった。
「ねぇ、お父さん。見て、すごいよ。部屋がいっぱいある!」
確かに、想像していたのとは違った。
部屋に入ると、そこは居間に当たるのだろうか?
広々とした部屋の右と左にそれぞれ寝室らしき部屋が有った。
決して、派手とか華美では無かったが落ち着いた感じの
それでいて品があるというか、部屋の真ん中にドンと置いてある
ゆったりとしたソファやテーブルなどなど。
調度品はどれも安物ではないことが家具には疎い俺にもすぐに判った。
「ねぇ、お父さん。凄いよ! うちのマンションより広いかも」
俺は苦笑するしかなかった。
確かにその通りだと俺も思っていたのだ。
「今夜はここに泊まれるの?」
俺の両手を握ってブンブン振りながら勇人は言った。
「あぁ、そうなるみたいだね」
「ヤッター!」
勇人はまたも大はしゃぎをした。
「ところで優美は? 着いたって挨拶くらいはしとかなきゃな」
「後で良いさ。時間はゆっくりある。あいつは今頃は宴会場で準備の最中だしな。
今、行ったってゆっくり話なんか出来ないよ。後の楽しみにしときな」
「そっか・・・」
「まぁ、そんなに残念がるな。俺だって別に意地悪で言ってる訳じゃないんだ」
「あぁ、判ってる。ありがとうな」
「止せよ。さてと、それじゃ飯でも食いに行くか? まだだろ?」
「そうだな。それじゃ・・・そうだ。あのラーメン屋ってまだやってるのかな?
高校の時、部活帰りに良く寄った店。何て言ったっけ?」
「遊華楼だろ? まだやってる。けど、違う店にしよう」
「何処だい?」
「行ってみてのお楽しみってやつだ」
そう言うと卓夫はニヤリと笑った。
『こいつ、こんな笑い方をするやつだっけ?』
俺は高校時代の卓夫のことを思い出そうとしていた。
「何だって?」
「いや別に」
俺は思わず苦笑いをした。
「さぁ、着いたぞ」
そこは、およそ卓夫には似つかわしくない外観からしてお洒落な店だった。
「へぇ-、お前がこんなお洒落な店を知ってるなんてね」
「だろ?」
店のドアを開けるとカランカランと音がなった。
それに合わせて店の中から『いらっしゃい』と声が聞えた。
店に入りかけたところで卓夫は立ち止まると俺に向かって訊いた。
「さて、今の声は誰だったでしょう?」
「えっ?」
いきなりそんな質問をされたって答えられるはずもなかった。
「判らないよ。俺の知ってる人?」
「さぁてな。じゃ、行くか」
もったいを付けて卓夫は言った。
店の中で待っていたのは、どう見ても俺の知らない女性だった。
「いらっしゃいませ。どうぞ、こちらへ」
愛想の良い笑顔で迎えてくれたその女性は俺達を日辺りの良い窓際の席に案内をした。
「お決まりになりましたら声を掛けて下さい」
三人分のお冷やをテーブルに置くと、女性はひとつ会釈をしてカウンターの中に戻って行った。
「さて、何にする? 勇人は何が良い?」
メニューを勇人に見せながら卓夫は言った。
俺は、その間中もその女性のことを思い出そうとしていた。
だが、いくら考えてもいっこうに思い出せないでいた。
「弘樹は何にする?」
卓夫の声に我に返った。そして、改めて訊いた。
「なぁ、あの女性って・・・ホントに俺が知ってる人か?」
「そんなこと、言ったっけ?」
卓夫はシラーっと答えた。
「えっ? だって、お前・・・『誰だったでしょう?』って」
「でも、お前が知ってる人だなんて一言も言ってないはずだけど?」
「何だよ、それ。じゃ、判る訳ないじゃん」
「取りあえず注文しようぜ。ここ、けっこう美味いんだ」
そう言うと卓夫はカウンターに向かって手を挙げた。
「はい、お待ち下さい」
注文伝票を持って女性が席の前に来た。
「お決まりですか?」
「あぁ。これとこれ、それとこれね。それから、この子にはメロンソーダも」
「はい、かしこまりました」
伝票に注文を書き込むと女性は注文を繰り返して確認をした。
良く通るその声は聞いているだけでも心地良い感じがした。
女性はカウンターに戻って奥の厨房に注文を伝えると、手際良くメロンソーダの準備を始めた。
「で? 誰なんだよ?」
そう訊く俺に卓夫はとぼけて答えた。
「何が?」
「何がじゃないよ。彼女だよ。誰?」
「そう、ご名答! いやぁ-、一発か。さすが弘樹だわ」
そこに、その女性がメロンソーダを持って来た。
「お待たせ致しました」
勇人の前にメロンソーダを置くと何故か俺に向かって会釈をした。
いや、そう見えたのだが。
卓夫が女性に声をかけた。
「いやぁ-、驚いたわ。こいつね。
俺がお前は誰だと思うって訊いたら、一発で彼女って答えたんだけど合ってる?」
「あれ? そうだっけ? 知らなーい」
女性はそう言って笑った。
声の良さに加えて笑った時のえくぼが印象的な美人だと思った。
いや、待てよ!
卓夫は今、何か言ったぞ!?
「えっ? 彼女? お前の? 卓夫の? 誰の?」
俺はけっこう混乱して慌てた。
卓夫はそんな俺を見て嬉しそうにニヤついていた。
「紹介するよ。俺の彼女。香奈子だ」
「えー!? お前、いつの間に? そんなこと一言も言ってなかったじゃん!」
「百聞は一見にナントやらって言うだろ?
人生はサプライズが有った方が楽しいってもんさ。
それに、どうせ来るんだったら言うより実際に見て貰った方が早いと思ってな」
「いや、それにしても急過ぎるだろ。
それなら、もっとちゃんと挨拶したのに」
俺がブツブツ言っているのを聞きながら卓夫は満面の笑みを見せていた。
「良いんですよ、そんなこと。弘樹さんの噂は時々聞いてましたし」
「おい、お前。どんな噂だよ?」
俺は卓夫に詰め寄った。
「いや。変な話はしてないよ」
「変なって何だよ?」
「まぁまぁ、親友同士の久しぶりの対面じゃないですか」
揉めそうな雰囲気をなだめるように香奈子ちゃんが話に入ってきて
そして卓夫の方を向くと衝撃の一言を言った。
「じゃ、私からも卓夫ちゃんにサプライズ。エーッとね、出来ちゃった」
香奈子ちゃんが悪戯っぽく笑っていた。
どうやら今度は卓夫が仕掛けられる番だったようだ。
「出来たって・・・まだ、料理は来てないじゃん?
えっ? お前・・・香奈子・・・ってか。えー? 何?」
卓夫はそう言うと、きっと思い当たる節でもあったんだろう。絶句した。
確かに人生にはサプライズが有った方が楽しいに決まっている。
ましてや、こんな嬉しいニュースなら尚更だ。
「マジ?」
「マジ」
「そっか。じゃ、結婚するぞ!」
立ち上がると卓夫は香奈子ちゃんを抱き寄せた。
「それ、軽すぎるよ。プロポーズはもっとロマンチックが良かったのに」
香奈子ちゃんは少し口を尖らせた。
しかし、その目には薄らと涙が浮かんでいるようにも見えた。
「おめでとう!」
ようやく状況が飲み込めた俺は二人に向かって言った。
「でも、いつまで抱き合ってるんだい?こんな子供の目の前で」
俺がそう言うと二人は慌てて離れた。
そして、今度はお互いを見ながらしきりに照れ合っていた。
卓夫の昔を思えば、尚更何とも微笑ましい光景だと思った。
「で、予定日は?」
俺は香奈子ちゃんに訊いた。
「多分、七夕の頃です」
香奈子ちゃんは嬉しそうに答えた。
「本当か? じゃ・・・どうしよ? 家に挨拶に行かなきゃ!
で・・・いつが良い? でも、出来ちゃったなんて言ったら・・・
俺、お父さんに殺されるかな?」
「そうねー、お父さん、警察官だからね。撃たれるかも」
香奈子ちゃんは平然と答えた。
「おい、それはヤバいよ! そっか、まずはお父さんの前で土下座するか?
お母さんには・・・何て言ったら良い? あー、どうしよ?」
こんなにパニクってる卓夫は初めて見た。
「結婚式には呼んでくれよな」
俺は卓夫に言った。
「もちろんさ。それまで俺が無事に生きてられたらな」
卓夫の言葉に一同は大笑いをした。
「いやぁ-、驚いたよ。でも、良いサプライズだったな」
ホテルに帰る途中の車内で俺はしみじみと卓夫に言った。
「驚いたのは俺だよ。お前を驚かせるだけのはずだったのにさ。
それにしても・・・はぁ・・・」
卓夫が珍しくため息をついた。
「なんだよ? もう今からマリッジブルーか?」
「そんなんじゃないよ。挨拶だよ、挨拶。お前は何て挨拶したんだ?」
「そんな昔のことは忘れたよ」
もちろん、忘れたなんてのは嘘だったが
今更の話をして卓夫のめでたい話に水を差すのも嫌だった。
「はぁ-、お父さんの前で何て言ったら良いんだろ?
厳格なお父さんだって言ってたしなぁー。結婚前に子供が出来たって知ったら・・・」
「まぁ、そん時は潔く撃たれて来いよ」
「お前なぁ-、すっかり他人事だと思ってるだろ?」
「いくら親友でも、こればっかりは他人事だからな」
「そんな殺生な。そうだ! お前も一緒に行く?」
「何でだよ。お前の一世一代の晴れ姿じゃないか。頑張れ!」
「やっぱ、他人事だ」
「あはは、いつもの卓夫は何処に行ったんだよ?
そうだ! ならさ。今日の同窓会でみんなの前で予行演習でもやるか?」
「止せよ! こっ恥ずかしい」
「でも、お父さん役もお母さん役もたくさんいるぜ。
なんなら俺が媒酌人役でもやろうか?」
「へっ、残念だったな。媒酌人ってな夫婦って相場が決まってるぜ。
一人じゃ無理、無理」
「そっか、そしたら媒酌人はやっぱ都子夫妻かな?」
「いやいや、それだけは止めてくれ! それならお前と優美で良いよ」
いきなりの卓夫の発言に俺は一瞬ドキッとした。
「そうだ! それ、案外良いかもな。あいつも一人だし。弘樹、どうだ?」
今度は俺が動揺する番だった。
「どうって言われたって答えようがないよ」
「でも、悪い気はしないだろ?」
「知らねぇーよ」
「お父さん、結婚するの?」
後ろの席から身を乗り出してきて勇人が訊いてきた。
「えー? いや、そんな話じゃないよ」
「なぁーんだ」
ガッカリした口調の勇人に向かって卓夫が言った。
「だよな。勇人だってお母さんが欲しいよな?」
「そんなんじゃないけど・・・でも、お父さんが寂しそうだし」
「おい、弘樹。子供に言われてるぞ」
俺は苦笑いをするしかなかった。
同窓会の会場に着くと受付には都子と数人の地元の女子がいた。
その横の手提げ金庫の所には優美がいて会計係をしていた。
都子が卓夫と俺を見つけると「キャー」と歓声を上げて、こっちに向かって手を振った。
受付の周りにいた一同が一斉にこっちに注目をした。
「弘樹クーン、元気にしてた? あらっ、この子が勇人クンね?
昔の弘樹クンの面影があるわー、やっぱ親子って似るのね」
周りの事などお構いなしに都子は機関銃のように喋り続けた。
「ねぇ、変わらないね。ホント、久しぶりだよね。元気でやってた?」
そこまで言うと都子は、つい口が滑ったとでも思ったのだろう。
「ごめんね。また余計なことを言うとこだったわ」
「良いよ。まぁ、色々あったけど、今は勇人と元気でやってるよ」
「そっか、良かった。優美、弘樹クンよ」
横の会計の所にいた優美が手を止めてこっちを見た。
「やぁ、しばらく」
「うん、元気でやってる?」
俺が優美に声を掛けると
昔と変わらない可愛い笑顔で優美が言った。
「あぁ、こいつがいるから落ち込んでる暇もなかったしね」
俺は勇人の頭を撫でながら答えた。
「そっか、良かった」
それから勇人に向かって優美が微笑みながら「こんにちは」と挨拶をした。
勇人も少し照れながら「こんにちは」と返した。
「あー、そう言えば。すごい立派な部屋を用意してくれてたのに挨拶にも行かなくてゴメン」
「ううん。私もずっとここで準備に忙しかったもの。部屋、気に入ってくれた?」
「気に入るも何も、勇人なんか『うちより広い』って大はしゃぎでさ」
「そっか、良かった。ゆっくりしてってね」
「あぁ、ありがとう」
そんなやり取りをニヤニヤしながら見ていた卓夫が声を掛けてきた。
「さぁ、積もる話は後だ。中でもお前を待ってる奴らがたくさん手ぐすねを引いてるぜ」
「そうだな。とっておきのサプライズも有るしな」
今度は俺がニヤっとする番だ。卓夫をチラッと見て言った。
「サプライズって何?」
さすがと言うべきか、嗅覚のするどい都子が話に割ってきた。
「何でもないよ。ほら、行くぞ!」
卓夫は慌てて俺の手を引っ張った。
そして、会場に入りかけた時、卓夫は俺の耳元で囁いた。
「俺に子供が出来たって話はまだ内緒な。もちろん、結婚のこともだ」
「なんで? 良いじゃん、めでたい話なんだし」
「絶対ダメだ! 良いか? こんな地元の奴らがワンサカいる中で
結婚前に子供が出来たなんて言ったら明日には町中に広まってしまう。
そしたら、俺の立場はどうなる?
香奈子のお父さんに挨拶をするまでは絶対みんなには内緒だ! 良いか?」
「あぁ、判った」
いつになく真剣な卓夫の表情に俺は頷くしかなかったが
卓夫の言い分ももっともだと思った。
田舎町の<世間>は狭い。それは都会人が思ってる以上だ。
俺の離婚話も親が生きている時だったら、きっと卓夫に相談もしなかっただろう。
世間が狭いが故に田舎町では生きにくいこともあれば同じくらいそうでないこともある。
それらも全部引っくるめて地元で生きていくことを選んだ奴ら。
地元を離れた俺からしたら羨ましいことでもあった。
ただ、今から俺がそう出来るかと訊かれたら。
『さて、どうなんだろう?』
俺は自問自答をしていた。
同窓会も終わりに近づいた時
演台に上がった卓夫はマイクを持つと会場に向かって話始めた。
「さてさて、高校を卒業して早十二年。
俺らももう三十歳なんだって。ホントか? 俺が一番信じられないんだけど」
「卓夫も大人になったよなー」
会場から笑いと冷やかしのヤジが飛んだ。
卓夫は会場に向かって両手を挙げて答えると話を続けた。
「そうだ、三十歳になるなんて高校の時は信じられなかったよな。
まして、社会人になってさ。今はもう色々なことを経験してさ。
そういや、結婚をした奴もいれば、離婚・・おっと、これは禁句だったか?」
卓夫はわざとに俺の方を向いて言った。
「別に良いよ。どう足掻いたってお前の口は封じられないからな」
「その通り! ヨッ、歩くスピーカー卓夫!」
会場からのヤジに助けられて話題がそれた。ありがたいのは昔の友達ってとこか。
「いやいや、スピーカーだったら都子には叶わないぞ」
「私が何だって? あんたのネタをブンシュンに売りつけるわよ」
売られたケンカに都子が返す。ただし、遥に都子の方が強烈だ。
「いやいや、そんな滅相も無い。都子さん、勘弁して下さいよー」
ワザと大袈裟に卓夫が両手を合わせて謝るそぶりを見せた。
それを見て会場は更に盛り上がった。
『果たして、卓夫の結婚話を聞いたら都子はどんな反応をするんだろう?
いや、もしかして、案外もう既に知ってるなんて?』
俺は心の中で呟くと一人ニヤニヤしていた。
卓夫はひとつ咳払いをして、ポケットから出したハンカチで額の汗を拭くと
又、気を取り直したかのように話を続けた。
「まぁ、それはともかく、そろそろ同窓会も宴もたけなわってとこだけど
みんな、ゲップが出るくらい周りの色んな奴らとお喋りが出来たかい?」
相変わらず卓夫らしい独特の言い回しだったが会場の男連中にはウケたようだ。
会場からも「おー!」と返ってきた。すごい盛り上がりだった。
「うん、そりゃ何よりだ。俺も幹事をやった甲斐が有ったって事だな。
良し、みんなが高校生に戻ったところで、これから記念写真を撮るぞー!」
「オー!」
それから、みんなで会場の前方のテーブルやイスをどかして写真を撮るスペースを作った。
「お前はこっちな。ほら、ここ空きすぎだよ。誰かここ入れよ」
卓夫が列を仕切っていた。
「弘樹、お前はここだ」
卓夫は俺を真ん中の列に手招くと当たりを見渡して言った。
「そう、勇人はその隣な。勇人の隣に怖いオジサンはマズいから・・・
おー、優美、勇人の隣に立ってやれ。後は・・・大丈夫か?」
俺と勇人と優美が並ぶ事になった。もちろん、これは卓夫の計らいだったろう。
でも、何だか照れて俺は勇人を近くに引き寄せた。
「良いですか-?」
写真屋が声を掛けた。
「あー、そこのお子さんと右の女性の間は空きすぎですね。
もっと寄ってもらって良いですか?」
「あっ、はい」
優美が勇人のピッタリ横に来ると俺の方を向いて「ですって」と笑顔で言った。
「はい、良いですね? じゃ、いきますよ。
二枚撮りますので一枚撮り終わってもそのまま笑顔でいて下さいねー。
はい、いきます! さてさて、ネズミの好きなものは?」
カメラマンの言葉に一瞬、呆気に取られてみんなお互いの顔を見合わせていた。
「あれ? おかしいなぁ-、ここ笑うとこだったんですよー」
カメラを伏せると棒立ちになってカメラマンがぼやいた。
「あー」と、それに気付いた何人かが笑うと一同に笑いが伝染をしていった。
「はい、それそれ! もう一回、はいチーズ!」
写真を撮り終えると、みんなに向かって卓夫は言った。
「良し、みんな。二次会はここのスイートだ。
因みに、今夜は弘樹がそこに泊まるらしいけど、みんなで邪魔をしに行くぞ-!」
「おいおい」
俺は慌てて卓夫を遮った。
「あはは、嘘だ、嘘! 二次会は引き続きここでやりまーす。
なんせ、この人数で入れる店は他にないからな。
ってことで、ここの準備が出来るまで三十分、各自好きにしといてくれ」
「焦ったろ?」
会場の外のロビーに出ると笑いながら卓夫は言った。
「焦るも何も、俺はここに泊めてもらう身だ。文句は言えんよ」
「あはは。勇人がいるんだ。いくら俺でもそんな野暮はしないさ。
勇人だって、こんなにうるさかったら寝れないだろ?」
「もし、勇人がいなかったら?」
「そりゃ、お前の部屋が三次会の会場になってるさ。朝までな」
「おいおい」
そこに都子がやって来た。
「楽しそうね」
「あぁ、久しぶりの同窓会だしな」
卓夫が答えた。
「でも、みんな変わって無くて安心したわ」
思い出して俺は言った。
「そういや、都子。結婚をしたんだってな? おめでとう」
「ありがとう」
「ごめんな。出席できなくて」
俺は都子に謝った。
「あら、招待しなかったのは私よ」
「でも、それは俺に気を遣ってだろ?」
「良いじゃない、そんなことはもう。
それより、どうだった? みんなに根掘り葉掘り訊かれた?」
「少しだけな。殆どの連中はとっくに知ってたみたいだしさ」
そう言うと俺は卓夫を見た。
「嫌よねー、男のスピーカーって」
都子は卓夫を見て笑いながら言った。
「へぇ、へぇ。今度からは口にチャックをしときます。
怖い人に聞かれないようにね」
「あら、誰のことかしら?」
都子はとぼけて答えた。
「相変わらず仲が良いわね。どうしてあなた達、結婚をしなかったのかしら?」
そこに優美がやって来て声を掛けた。
「誰が、こんな奴と」
卓夫が憮然と答えた。
「あら、それは私のセリフよ」
都子も口を尖らせて返した。
「まぁ、まぁ。続きは中でどうぞ。今夜は貸し切りだから時間はたっぷりよ」
優美が二人をなだめて会場の中へと促した。
でも、確かにそうだ。昔からこの二人の息はピッタリだ。
までも、だから都子には今の幸せがあるんだろうし、それは卓夫もだ。
それがきっと縁というものなんだろう。
「弘樹クンはどうする? 勇人クンはもう部屋に入った方が良くない?」
優美が訊くと勇人は俺の方を見上げて訊いた。
「部屋で待ってなきゃダメ?」
「そうだなー、まだ八時か。
一人で部屋にいてもつまんないだろ? 勇人、もう少し付き合うか?」
「うん、良いの?」
「良いさ。俺達はもう仲間だからな」
卓夫が勇人の肩をポンと叩いてそう言うと勇人も嬉しそうに頷いた。
「良し、決まりだ」
二次会がお開きになっても、なかなか離れがたいのか
みんなロビーでそれぞれに固まって談笑を続けていた。
「さて、どうする?」
腕時計を見ながら卓夫が訊いた。
「もう十一時になるのか。さすがに勇人はここまでだな」
疲れたのか、勇人はロビーのソファにもたれてウトウトしていた。
「そうだな。勇人も今日は頑張ったな」
それを見ながら卓夫は言った。
「お前のお陰だよ。こんなにはしゃいでる勇人を見たのは久しぶりだよ」
「そうか、そりゃ良かった」
「うん、ありがとうな」
「何だよ、かしこまってさ。良いって」
「あぁ」
「弘樹、じゃあ、またな」そう声を掛けてきてみんなが帰り始めた。
そこに都子と優美もやって来た。
「じゃ、私もそろそろ帰るね。旦那が迎えに来てるの」
都子は嬉しそうに言って、スカートの端をちょっと摘まんでお姫様ポーズをしてみせた。。
「お前、体よく旦那に監視されてんじゃねぇの?」
それを見て卓夫がふざけて言った。
「あら、ジェラシーも愛よ、愛。まぁ-、貴方には一生判らないかな?」
都子は澄まして答えた。
「言ってろ! はいはい、バイバイ。またな」
卓夫が手を振ると都子は俺に向かって「またね」と言うと玄関に早足で向かって行った。
その後ろ姿を見送ると卓夫は言った。
「じゃ、俺も帰るわ。弘樹、すまんな。明日は仕事なんで送りに行けないんだ」
「いや、十分だよ。今日はお前のお陰で楽しかったよ。
ご機嫌なサプライズもあったしな」
俺が笑って言うと優美が訊いた。
「ご機嫌なサプライズって? ねぇ、何があったの?」
「な、何でもないよ」
卓夫は慌ててごまかしながら俺を見て睨んだ。
当然、俺は知らんぷりを決め込んだ。
「そうだ、優美。明日時間あるだろ?
なら、こいつらを空港まで送ってやってくれないか?」
「そんな。良いよ。優美だって仕事があるだろうし」
「なぁに、優美は社長令嬢だぞ。そんなもんナントでもなるさ。なぁ?」
「誰が、社長令嬢よ? それを言うなら卓夫だって社長のご子息様じゃない?
『今日は休みだー!』って一言言えば何とでもなるんじゃない?」
「いやいや、何処かのお嬢様ん家と違ってうちは零細企業なの。
俺が働かなきゃ従業員は路頭に迷うんだよ」
「まぁまぁ、そのくらいにしとけよ。俺は大丈夫だよ」
慌てて俺は二人をなだめた。
もっとも、お互いにこんな口が利けるのも同窓の馴染みってとこだろう。
「誰が送らないって言ったの? 私が責任を持って送ります」
「よし、これで俺も安心だ。優美の運転はちょっと心配だけどな」
また、卓夫が憎まれ口を叩いた。
「はいはい、一生卓夫は助手席には乗せないから安心して」
「おっ、弘樹なら助手席に載せるってか?」
その言葉に優美は顔を赤らめて否定をした。
「もう、そんなんじゃないわよ」
「まぁ。良いや。とにかく、優美。頼んだぞ」
「はいはい、じゃあね」
「じゃあ、邪魔者は消えるよ。グッナーイ」
そう手を振ると卓夫は帰って行った。
「今日はありがとう。そして、会場の手配とか色々とご苦労様でした」
俺が頭を下げた。
「いやね、止めてよ。これも商売よ。
ひさしぶりのバンケットで売り上げ貢献よ。お礼は私がしたいくらい」
優美はそう言って笑った。
「勇人クン、すっかり寝ちゃったね」
「あぁ、けっこうはしゃいでいたからな。疲れたんだろ。
じゃ、俺は部屋に入らせてもらうね」
「勇人クンは? 一人で大丈夫?」
「おんぶしていけばなんとかなるよ」
そう言って俺は優美に支えて貰いながら勇人をおんぶした。
「じゃ、部屋まで送るわ。それじゃドアも開けられないでしょ?」
「助かるよ」
部屋に上がるエレベーターの中で二人は無言だった。
『こんな時は何の話をしたら良いんだっけ?』
そう思っている間にエレベーターは最上階まで上がり部屋の前まで来た。
「ちょっと待って」
そう言って優美はカードキーで部屋のドアを開けて電気を点けると俺を中に招き入れた。
部屋に入ると優美は奥の寝室のドアを開けてくれた。
「大丈夫?」
「あぁ」
また、優美に支えてもらいながら勇人をベッドに寝かせた。
「パジャマは何処?」
「あぁ、そこの鞄」
「開けて良い?」
「あぁ、一番上にあるウルトラマンの青いやつ」
「これね?」
勇人のパジャマを持ってくると優美は着替えも手伝ってくれた。
勇人の布団を直して居間に戻ると優美はコーヒーを入れてくれていた。
「あっ、そんなの自分でやるよ」
「良いの。たまにも私もここのコーヒーを飲みたいの。
この部屋のコーヒーだけ特別なのよ。百グラム千五百円もするのよ」
「へぇ-、そうなんだ。それは豪華だね。
俺なんか、いつもインスタントだから」
「あら、私もよ。従業員用はインスタントなの」
優美はそう言うとソファの前のテーブルにコーヒーを置いてくれた。
そして、自分も向かい側のソファに座るとコーヒーを両手で挟んで口を付けた。
「勇人クン、良い子ね」
「いやいや、普段はけっこうなもんなんだけどね。
やっぱ、知らない大人がたくさんいたらあいつでも猫を被るみたいだよ」
「あはは、そうなの? 見えないけど」
「そうさ。まったく誰に似たんだか? あいつ、けっこう頑固でさ。
俺の言うことなんか聞かないし、ヤンチャだし」
「でも、子供ってみんなそうだよ。聞き分けの良い子供なんて逆に怖いわ」
「確かにね。子供は子供らしく・・・か」
「そうよ。それに弘樹クンの子供なんだから、やっぱ弘樹クンに似たんじゃない?」
「えー? 俺って、そんな頑固で聞き分けがないか?」
「どうでしょ? 昔の弘樹クンしか知らないから」
「そうだね。俺も昔の優美しか知らない」
「ねぇ? 私って昔はどんなだった?」
「んー」
俺は正直、答えあぐねていた。
<本当>のことは言いにくかったし、違うことは答えられなかった。
「あー、答えられないんだ? ショックだわー 私って、そんな感じだったのね」
「いや、違うよ」
「じゃ、どんなだった?」
「コーヒーを飲んで考える」
「何それ? でも、弘樹クンらしいね」
「何が?」
「そういうとこ。決して、他人が傷つきそうなことは言わなかったもんね」
「そんなことないよ」
誰かが言っていたけど。
もし、この世にタイムマシンがあるとするなら、それは昔の友達なんだとか。
どんなに離れていた時間が長くても、会った瞬間に昔の関係に戻れる。
確かにそうかも知れないと思っていた。
高校を卒業してからもう十二年も経っているのに
今日の俺達もみんな再会した瞬間からあの頃の高校生に戻っていた。
「ねぇ? そう言えば」
「うん?」
「さっき、言ってた、ご機嫌なサプライズって何のこと?」
「えー? その話かい? いや・・・それは」
俺の頭の中には怒っている卓夫の顔が浮かんだ。
「それは・・・きっと、そのうち判るよ」
「えー? ひどーい! 気になるわ。ねぇ? 何の話?」
テーブルを挟んで座っていた優美が身を乗り出して来た。
「な・い・しょ。一応、男の約束なんだ」
俺は口の前に人先指を立てて答えた。
「私は女だから関係ないわ」
優美はむくれた顔をして見せた。
「いやいや、そういうことじゃないでしょ」
「じゃ、絶対に口を割らせて見せるわ」
そう言うと優美は俺の隣に座ってきて俺に良しかかる風にしてソファの袖に押した。
「おいおい、ヤバいよ」
「何が? 言う気になった?」
「そうじゃない」
「何?」
俺は優美を抱き寄せると初めて優美にキスをした。
長いキスの後で俺の肩に寄りかかって優美が又、訊いた。
「ねぇ? 私って、どんなだった?」
「そうね、昔は可愛かったよ」
「嘘ばっかり!」
「嘘じゃないよ」
「でも、そんな素振りもなかったわ」
「だって、一哉がいた時の五人、その後で四人になってからもみんな仲が良かったろ?
だから、そんな関係が壊れるのが怖かったんだ」
「うん、判る。考えたら私もそうだったかも」
「あの頃はまだ幼かったんだよ、きっと。でも、あの時はあれで良かったんだ」
「そうね」
「うん」
「ねぇ? じゃあ、今は?」
優美は肩越しに俺を見上げて訊いた。
答えの代わりに俺はもう一度優美にキスをした。
同窓会から一ヶ月が経った頃、卓夫から電話があった。
『よぉ、元気にしてたか?』
「お陰さんでね。で、お前は?
まだ生きてるってことは香奈子ちゃんのお父さんには会ってないのか?」
『バカ言え。とっくに挨拶には行って来たよ。慣れない一張羅のスーツを着てな』
「あはは。で、どうした? 許してもらえたのか?」
『あぁ、お父さんの前で土下座をして、お嬢さんを下さいってな』
「ほぉ、それは見たかったな」
『よせよ。友達には見せられない姿だ』
「確かに」
そう言って電話越しに二人で笑った。
「で、子供のことも話したのか?」
『まぁね。土下座したままな』
「あ-、やっぱり見たかったなぁ-
で、一発くらいは殴られてきたのかい?」
『覚悟はしてたんだけどね』
「うん」
『見事に返されたよ』
「何を?」
『土下座』
「えっ?」
思わず言葉に俺は素っ頓狂な声を上げた。
「何だって?」
『お父さんもテーブルの横に座り直してさ。で、俺の前に来てさ。
あー、いよいよか? 一発なら我慢するぞって覚悟をしてたらさ。
一言、よろしく頼むって言って、まさかの土下座返しさ』
「あはは。まさかまさかの拍子抜けってやつかい? 良いお父さんだな」
『あぁ、香奈子も産まれてくる子供も大切にしなきゃ』
「お前なら大丈夫だよ」
『先輩、結婚生活で判らないことがあったらよろしくな。
あっ、お前に訊いちゃダメだったか?』
「そうそう、俺は結婚生活失敗の見本だからな・・・って、おい!」
『自分で言うな』
「俺に言わせるな」
又、二人で笑った。
『でさ』
「うん?」
『気になってたんだけど』
「何が?」
『お前と優美だよ。あの後、何かあったろ?』
卓夫の急な優美の話に俺は内心ドギマギした。
「別に」
俺は努めて平静に答えた。
『いや、怪しい! 絶対に怪しい!』
決めつけるように卓夫は言った。
「なんでだよ?」
『あの後、二~三日して優美に会ったんだ。
ほら、俺が幹事だったからさ。お礼もかねてホテルに都子とね。
そしたら、何か憑きものが落ちたっていうかさ。
何だかさぁー、優美が妙に明るかったんだよな。
で、都子が言うには、アレは絶対何かあったって。
あいつ、そういうのは鋭いからな。
あの後で何かあったとしたら、お前しかいないだろ?
さぁ、ネタは上がってんだ。潔く白状しろよ』
「ないよ、別に」
『嘘をつけ! で、どうした? キスくらいしたのか?』
図星を突かれて俺は動揺した。
で、すぐさま話題を変えた。
「それよか、なんだ? 用事があったんだろ?」
『あー、忘れてた! 結婚式の招待状を送るからな。絶対、来てくれよ』
「あー、日取りが決まったのかい? いつ?」
『今度のゴールデンウイークの初日だ。連休だし、ゆっくり帰ってこれるだろ?』
「でも、今からで良くゴールデンウイークなんて予約が取れたな?」
『持つべきものはホテルの同級生だよ』
「優美のホテル?」
『あぁ。ついでにお前と勇人の部屋も又、頼んでおいたよ。
ただし、今度はスイートは俺達だけどな。お前は普通のツインにしといた』
「じゃ、今度はスイートで夜通し宴会だな?」
『いや、神聖な初夜だからな。お前らに邪魔はさせないぞ!』
「今更、神聖もないだろ?」
『いや、それとこれは別だ』
「何と何が別だって?」
『判った! じゃ、お互いに邪魔はしないってのでどうだ?』
「俺と勇人は別に邪魔されてもかまわないよ」
『そっちじゃない。お前と優美だ』
又、話がこっちに戻ってきた。
「だから、何でもないって」
『いいや、都子の勘は絶対正しい!』
「なんか、すごい理屈になってるぞ」
俺は思わず笑いながら言った。
『まぁ、良い。今度会った時は白状するまで取り調べをするからな』
「今度ったら、お前の結婚式だぞ。そんなことしてるヒマなんてあるのかい?」
『大丈夫だ。取調官は都子だからな。で、容疑者はお前と優美。
さてさて、いつまでシラを切れるかな?』
「じゃ、行くの止めようかな」
『そんなことをしたら優美が泣くぞ』
「なんでだよ?」
『優美だけを容疑者にして、お前は知らん顔か? それでも男か?』
「お前なぁ、さっきから理屈がメチャクチャだぞ。
判ったよ。行くよ、行きます。はい、行かせていただきます」
『そう、それで良いんだ』
俺は思わず苦笑するしかなかった。
『じゃ、そういうことで。一応、招待状は出すけど出席にしとくから』
「そんな招待状あるのか?」
『もちろんさ。勇人と二人分の特等席を用意しておくよ。
俺からの特別サービスでお前の隣の席は優美にしとくから』
「ありがたいね」
『だろ? じゃあな』
「あぁ、香奈子ちゃんによろしくな」
『うぃっす!』
電話を切った後で思った。
今頃、卓夫は都子にどんな<報告>をしてるんだろう?
卓夫の披露宴は同級生やら職場の若い衆やらが多くて同窓会以上の盛り上がりだった。
香奈子ちゃんのお腹もまだそんなに目立っていたくて
純白のウェディングドレス姿がとてもキレイだった。
そんな香奈子ちゃんが両親への感謝の手紙を読んでいた時
当の新婦の両親より泣きじゃくっていたのは他ならぬ卓夫だった。
で、同級生の女子ももらい泣き・・・かと思いきや
やはり、人間は誰かに先に泣かれると泣けなくなるものらしい。
男子も女子もみんな冷やかし組に回って歓声を上げるやら
泣きじゃくっている卓夫をここぞとばかりにスマホで写真を撮りまくっていた。
それらの写真はきっと来年の同窓会で良い酒の肴になるんだろう。
その時の卓夫の顔が楽しみだと思った。
「良い披露宴だったね」
ホテルの部屋に戻った後で、優美は入れたコーヒーを持って来ながら言った。
そして、ベッドに腰掛けていた俺の隣に越を降ろした。
勇人はツインベッドのもう一方のベッドで寝ていた。
今回も又、二次会が終わるまで付き合わせてしまったから
さすがに疲れたんだろう。
聞えるような寝息をたてながらグッスリと寝ていた。
その寝顔を見ながら俺は答えた。
「まさかのあいつの泣き顔も見れたしね」
「でも、大丈夫かな? けっこう酔ってたよね?」
「卓夫かい? 新婚初夜に身重の新婦に介抱されたなんてなったら
きっと卓夫は一生、香奈子ちゃんに頭が上がらなくなるね。
いや、結婚前から既にかな?」
「ふふ。でも、夫婦はそのくらいの方が良いんだって」
「おや、経験者みたいな発言だね?」
「結婚式はもう何百回も経験済みよ。他人様のばかりだけど」
そう言うと優美は小さくため息をついた。
「今までに結婚は考えなかったの?」
俺が訊くと、優美は俺の方をチラッと見て答えた。
「そうねぇー、どうだろ?」
「そういや、都子の尋問はけっこうしつこかったよな」
「まるで私を犯人扱いだったわ」
「俺もだよ。共犯者扱い」
「共犯者ってさぁ-、この場合主犯は誰?」
意地悪っぽく優美が俺の方を見た。
「はい、白状します。俺がやりました」
「素直でよろしい!」
そう言うと嬉しそうに優美は俺の肩にもたれかかってきた。
キスをしようとする俺の唇の前に優美は人先指を立てて言った。
「今日はダメよ。勇人クンがいるし」
「そうだな」
俺は少しバツが悪くなって頭を掻いた。
「それじゃ、私も戻るわ。ゆっくり休んでね」
そう言うと優美は立ち上がりしなに俺の唇に軽くキスをした。
「おやすみなさい」
「あぁ、おやすみ」
ドアを開ける前に振り返ると優美はニコッと笑いかけた。
そして、ドアを開けた時だった。
「キャッ!」
突然、優美の悲鳴が聞えた。
「えっ? どうした?」
俺は何かあったのかと急いでドアのところに向かうと
なんと、そこには今までドアに耳を当てて中を伺っていましたと言わんばかりの
中腰で斜めに重なった体勢の卓夫と都子がいた。
「お前ら、何をしてんだよ?」
俺の言葉に構わず卓夫は都子に向かって言った。
「隊長。現行犯です!」
「やはりね。私の目に狂いは無かったわ」
得意げに都子は言った。
「はい、さすが隊長でございます!」
卓夫は都子に敬礼をした。
俺と優美は、その二人の様子を呆気に取られて見ていた。
「さぁ、弘樹、優美。今から尋問を始める。もう観念しろよ」
俺と優美は顔を見合わせて苦笑いをするしかなかった。
「お前らさぁ、いったい何をやってるんだ?」
「もちろん、容疑者を見張ってたんだ。決定的な証拠を掴んだぞ」
「おいおい、本気か?」
「もちろん!」
「ってかさぁ-、卓夫。お前、今日は何の日か知ってるよな?」
「あぁ。俺の結婚式だ」
「その結婚式が終わった初夜にだ。
肝心の新婦を放っておいて、お前は何をやってるの?
香奈子ちゃんも呆れてるだろ?」
「ふふ。ご心配には感謝する。でも、大丈夫だ。
香奈子は友達の三次会を回っていてまだホテルには戻って来てないんだよ。
部屋に戻ったら、ちゃんと連絡が来ることになってるから、ご心配なく」
卓夫は平然と答えた。
「さて、それじゃ尋問を開始する」
そう言うと卓夫と都子はズケズケと部屋に入って来た。
ベッドに並んで座る俺と優美。
小さなテーブルを挟んでソファには都子が座り
卓夫は推理ドラマで最後に謎解きをする探偵よろしく
立ったまま部屋の中の全員を見渡していた。
最初に訊いたのは都子だった。
「弘樹クン、優美。良いわね? 正直に答えてもらうわよ。
さて、あたた達の関係は?」
いきなりの直球な質問、いや尋問だった。
優美を見ると困った顔を浮かべていた。
ここは俺が答えねばなるまいと思った。
「まぁ、見ても通り。そう言うことだ」
俺は観念をして答えた。
「それじゃ答えになってないぞ」
卓夫は俺の方に近寄ると俺の顔を覗き込むように言った。
「それは、いつから?」
裁判官のように冷静に都子は訊いた。
「あの夜・・・同窓会の」
俺は渋々答えた。
「やっぱりね! 私の想像通りだわ」
我が意を得たりと都子は満面の笑みを浮かべて言った。
「これで、隠匿罪が確定だな。で? どっちから押し倒したんだ?」
「隠匿罪って何だよ? それに、別に押し倒してはいないよ」
俺が答えると卓夫は都子に向かって言った。
「隊長。こいつは我々に隠していた上に偽証もしようとしています」
都子は平然と言い放った。
「良し、尋問を続けなさい」
「おい! 正直に白状をするんだ。
どちらかが押し倒さなければ、そんな関係になる訳がないだろ?」
「じゃ、お前も香奈子ちゃんを押し倒したんだな?」
俺は反撃に出た。
「い、いや。俺達は自然とだな・・・どちらともなくってか・・・」
卓夫がそう言いかけた時、ドアをノックする音が聞えた。
これ幸いと俺は立ち上がるとドアを開けた。
「夜分にすいません。もしかして卓夫ちゃん来てません?
部屋に戻ったらいなかったもので・・・あっ、やっっぱりここだ!」
そう言って部屋に入ってきたのは香奈子ちゃんだった。
「どうしたの?」
ふいに隣のベッドから声がした。
寝惚け眼の勇人だった。
「あぁ、ごめん。煩かったろ? もう、みんな帰るからね。
さぁ、寝ていなさい」
「うん」
そう呟いて勇人は又、壁の方を向いて寝直した。
「良し。同窓会はこれでお終いだ。さぁ、解散!」
「じゃ、続きは俺達の部屋でどうだ?」
俺は呆れて言った。
「バカ言うんじゃないよ。俺達は香奈子ちゃんに嫌われたくないんだからな」
香奈子ちゃんは訳も分からず苦笑していた。
「都子も、旦那さんが心配してるぞ。さぁ、解散、解散!」
俺はみんなを追い立てるようにドアの方に押し出した。
「続きは又、今度だ。必ず白状させるからな!」
捨て台詞を吐いて卓夫は出て言った。
「はいはい、じゃあな。お幸せに」
「じゃ、私も行くね」
優美は振り返ると俺に言った。
「優美にはまだ話があるわ」
都子は優美の腕を強引に取ると俺に向かって「ふふ」と不敵な笑みを見せた。
「無事に解放されたら良いけど」
俺は優美の困った顔を想像していた。
なんせ相手はあの都子だ。
明日にでも優美に顛末を聞いておかなきゃと思った。
俺はベッドに入ると、何となくこれからのことを考えていた。
勇人のこと、そして優美のこと。
俺の新しい人生の歯車は、これからどんな風に回って行くんだろうか?
そしてその時、勇人はどう思うんだろうか?
若い頃ならすぐにでも出来た決断も
今は勇人のことをまずは考えて決めなければならない。
ただ、それは決して足かせではなくて言うなれば親としての責任だ。
「勇人と一緒に考えていこう」
今の俺には勇人という家族がいる。そしてそれは俺の生きがいだ。
六月の終わりに近い或る日、卓夫から電話が来た。
「産まれたぞー! 弘樹、俺も親父になったんだ!」
「ホントか? おめでとう! で、どっち? 男の子? 女の子?」
「女の子だ。俺に似て超可愛いんだぜ」
卓夫の喜びが電話口からビシビシ伝わってきた。
それを感じて俺も自分のことのように嬉しかった。
「確かに、香奈子ちゃんに似たら美人になるね」
「いやいや、絶対に俺似だ。美人になるぞー」
「あはは。香奈子ちゃんは何て言ってるんだい?」
「あいつか? あいつは絶対に私似だって譲らないんだけどさ。
でも、女の子は父親に似た方が幸せになるて言うじゃん?
だから、絶対に俺似だよ。俺が言うんだから間違いないさ」
「いやでも、客観的に言わせてもらうなら香奈子ちゃんに似てる方が良いって」
「そこまで言うなら見に来いよ。そしたら俺が正しいって判るから」
「そうだな。ぜひ、そうさせてもらうよ」
「あぁ」
「で、いつ頃退院出来るんだ?」
「七月の四日か五日頃には退院出来そうだってさ」
「そっか。じゃ、その後に行くよ。お前の新居も見せて欲しいしさ」
卓夫はずっと実家暮らしだったが、結婚を機に市内のマンションに引っ越していた。
「あぁ。決まったら教えてくれ。みんな集めておくからさ。
あっ、でも優美は知らないぞ。お前から連絡しとけよ。
まぁ-、今更俺が言うまでもないだろうけど?
じゃ、待ってるからな」
「あはは。刑事部屋の尋問が無いならね」
「それはもう良い。優美がすっかり都子に白状をしたからな」
「白状をしたんじゃなくて、されられただろ?」
「そんなことはどうでも良いさ。結果は同じだ」
「おいおい、無茶苦茶言うなよ」
「わはは」
俺の抗議も虚しく電話はそのまま切れた。
そうだ。忘れていた。
卓夫の結婚式の夜、都子に連行をされた優美は明け方まだ尋問をされ続けて
有ること、無いこと、都子の良いように白状させられたって言ってたっけ。
全くもう、あいつらときたら。十二年経った今でも高校生の時のままだ。
でも、それは本当にありがたいことでもあった。
良い奴らだと改めて思っていた。
その夜、仕事が上がる時間を見計らって優美に電話をした。
『もしもし?』
「あぁ、俺。今日、卓夫から電話があったんだけど女の子が産まれたんだってね」
『うん、私のところにも電話が来たわ。凄い嬉しそうだった』
「でも、無事に産まれて良かったよな。あいつも親父かぁー」
『娘さんに何て呼ばせるのって訊いたのね。
そしたら、卓夫クンってば、パパって呼ばせるんだって。
娘さんにパパァー♪なんて呼ばれたら卓夫クン、悶絶しちゃいそうよね』
「あいつはパパって柄じゃないよな。でも、良いパパにはなりそうだけど」
『そうね。ホント、良かった』
「だね。あっ、そうだ! それでさ。
早速あいつに見に来いって誘われたんだけど、いつ都合が良い?」
『弘樹クンに合わせるよ』
「そっか。じゃ、今度の土曜日とかは? あっ、土日はホテルは忙しいんだっけ?」
『夜の二~三時間はね。宴会が入ってるから。でも、午後と宴会の後は大丈夫よ』
「じゃ、土曜日で良い?」
『うん、オッケー』
「で、悪いんだけどさ。又、部屋を取れるかな?」
『土曜日ね? 大丈夫、ツインの部屋を取っておくわ。
勇人クンも一緒よね?』
「うん、ありがとう。頼むよ。
それでさ。頼みついでにもうひとつ良いかな?」
『何?』
「その、誕生祝いのプレゼントなんだけどさ。
女の子だって言うけど、何が良いのかな? なんか、判らなくってさ」
『任せておいて。私、そういうの得意なの。仕事柄ね。
じゃ、私と一緒でってことで買って良い?』
「うん。助かるよ。ありがとう」
『ねぇ、今気が付いたんだけど今週の土曜日ったら七夕よ』
「あっ、そっか。ねぇ? アーケード街の七夕祭ってまだやってるの?」
『やってるわよ』
「じゃ、夕方でも勇人を七夕祭に連れて行こうかな。
こっちでもやってるけど、そっちほど盛大じゃないんだよね。
勇人も喜ぶと思うし」
『そうだねー。良し、じゃ私も付き合う!』
「えっ? 仕事は?」
『大丈夫! 私一人がいなくてもホテルは回るわ。それとも迷惑?』
「もちろん、大歓迎だよ。
でも、優美がいなくてもホテルが回るって、それはそれで問題ないのかい?」
『お父さんが元気だからね。親に甘えるのも娘の仕事なのよ』
優美はそう言って笑った。
「卓夫も間違いなく、その口だろうな」
『きっとね。あっ、そうだ!
ねぇ、大岳山の展望台覚えてる?
今ね、キレイに整備されて星空の見える夜景スポットって人気なのよ』
「へぇー、そうなんだ?
昔は街灯も少なくて夜になると薄暗くて怪しげな感じだったのにね」
『あら、そうだったの? なんか、エッチっぽーい』
「そうだね、確かにカップルの乗った車ばっかで
闇に紛れてってか、まァー、健全って感じじゃなかったかもね」
『ふぅーん、詳しいんだ? で、誰と行ったのかな?』
「いやいや、そんなんじゃないよ。男同士の噂話さ」
『そういうことにしといてあげるわ。
でも、今やカップルの人気スポットナンバーワンなんだって。
実は私もまだ新しくなってからは行ったことがないんだけど、一度行きたかったの。
ねぇ? せっかくだから三人で行ってみない?』
「良いネ。それは勇人も喜ぶと思うよ。
勇人も宇宙が大好きなんだ。
あいつの将来の夢はスターウォーズのスターファイターのパイロットだからね」
『さすが、男の子だね』
「あはは。そうだね。じゃ、土曜日に」
『うん、待ってる』
「うん。じゃ、おやすみ」
『おやすみなさい。勇人クンにもよろしくね』
土曜日、空港に着くと優美が迎えに来てくれていた。
卓夫の家へと向かう車内で俺は訊いた。
「ねぇ? それでプレゼントは何にしたの?」
「色々考えたんだけど、普段遣い出来るような洋服にしたの。
子供ってすぐに汚すから洋服は何着有っても良いでしょ?
でも、これから着る服はきっと周りの人がたくさんくれるだろうからと思って
敢えて、来年の今頃着れるサマードレスにしたのよ。
良かったかしら? 一応、有名ブランドなんだけどね」
「うん、良いんじゃない? そっか、そう言うところは、さすが優美だね。
俺なら、そこまで考えつかなかったと思うよ」
「お父さんね。ボクの服を買う時も店員さんに
この子に似合う服を下さいって言うんだよ」
後ろの席に座っていた勇人が身を乗り出してきて言った。
「余計なことは言わなくて良いの」
俺は勇人の方に振り返るとゲンコツのポーズをした。
「でも、勇人クン。それ大正解なのよ。
お店の人は何が一番人気か何が流行ってるか一番知ってるんだから」
「そうなの?」
「そう、その通りだ」
俺は俺を立ててくれた優美に感謝しつつ大きく頷いてみせた。
卓夫の家に着くと卓夫と香奈子ちゃんが満面の笑顔で迎えてくれた。
結婚、そして子供が産まれて、まさに二重の絵に描いたような幸せオーラ全開だ。
赤ちゃんはというと、寝室に置かれたベビーベッドでスヤスヤ寝ていた。
産まれてからまだ二週間にもなっていない赤ちゃんは
本当に小さくて、勇人もこんなだったっけかなぁーなんて思い出したりしていた。
その勇人はことの他、赤ちゃんを見るのが嬉しいようで
「可愛い、可愛いねー」を連発していた。
「ホント、可愛いね。勇人クンも産まれた時はこんなだったかな?」
赤ちゃんも見ながら優美が勇人に言った。
「えー? 覚えてないよ」
「あはは、そうね」
「どうだ? 可愛いだろ?」
卓夫が俺達の向かい側に来て赤ちゃんを覗き込みながら自慢げに言った。
「あぁ、お前に似なくて良かったよ」
「バカ言え。俺にソックリだろ?
可愛くなるぞー。まぁ、今でも十分可愛いけどな」
「もう誰か来る度にこの調子なのよ。早くも親バカ大将でしょ?」
居間から寝室を覗き込みながら香奈子ちゃんが言った。
「大将って何だよ? 可愛いから可愛いって言ってるだけじゃん」
卓夫が少し不満げに答えた。
「はいはい。良かったら、こっちで冷たい物でもどうぞ」
それに構わず香奈子ちゃんは俺達を見ると
『ずっと、この調子なのよ』というように笑いながら言った。
居間に戻ってソファに座ると俺は卓夫に訊いた。
「で、名前は何ちゃん?」
「『みき』だ。美しい妃と書いて『美妃』。どうだ? ピッタリだろ?」
「そうだね。これで香奈子ちゃんに似てくれたら完璧だね」
俺はすかさず答えた。
「おいおい、それじゃダメなんだ。娘は父親に似ないとな」
「幸せにならない?」
「そうそう。だから、絶対に俺似にするぞ!」
「するぞってね」
俺は苦笑した。
「でも、卓夫ちゃんがこんなに美妃を可愛がってくれるとは思わなかったわ。
ミルクもおしめ替えも率先してやってくれるのよ。
そうそう、食後の食器洗いもね、最近はやってくれるの。ねぇ?」
香奈子ちゃんが卓夫を見ながら言った。
「へぇ-、あの卓夫がね。いや、そういうとこが卓夫らしいのかな?」
「何だよ、それ?」
「別に」
「おい! 随分、意味ありげに言ってくれるじゃん。何だよ?」
「だから。見た目とは裏腹のお前の優しさは昔から変わらないって話だよ」
「見た目は余計だ」
卓夫は憮然として答えた。
「までも、親ってさ。子供の為ならバカにでも何でもなれるんだよな」
俺は隣の勇人を見ながら呟いた。
「あぁ。それが親ってもんだろ?」
卓夫は答えた。
そんな二人のやり取りを優美と香奈子ちゃんは微笑みながら見ていた。
「そういや、都子は?」
俺は訊いた。
「あぁ。あいつは今日は旦那さんの用事とかで、どうしても抜けられないんだってさ。
お前らによろしくって言ってたよ」
「そっか。どうりで静かだと思った」
「でも、都子ったらさ。美妃が産まれた次の日だっけ?
電話したらさ。飛んで来てくれたよ。
で、二~三日前か。改めてお祝いだって言ってね。
新生児用から六ヶ月くらいまでの服をごっそり
これでもかってくらい持って来てくれたよ。
いったい、うちに何人産まれたんだってくらい。
お前は初孫を喜ぶジジババか? って、言って笑ったんだけどな」
卓夫は笑いながら、そしてとても嬉しそうに言った。
「でも、皆さんって本当に仲が良いんですね。
なんかズケズケ言い合ってるのを見るとこっちがハラハラするんだけど。
でも、本当に良い人ばっかり。ありがとうございます。
これからも卓夫ちゃんをよろしくお願いします。」
香奈子ちゃんが神妙な顔で頭を下げた。
「いやいや。こっちこそ」
「そうですよ。気にしないで」
俺と優美はかえって恐縮をしてしまった。
「そうだ! これ、お祝いなんだけど。都子に比べたらささやか過ぎるみたいだけど」
優美に突っつかれて、俺はまだお祝いを渡してなかったことに気が付いた。
「あら、すいません。ありがとうございます」
「おー、ありがとうな。どれ、さっそく開けてみたら?」
卓夫に勧められると香奈子ちゃんは言った。
「開けてみても良いですか?」
「えぇ、どうぞ。気に入るかしら?」
優美が答えた。
包みを開けると香奈子ちゃんが歓声を上げた。
「まぁ、可愛い! 見て」
ピンクに花柄のサマードレスを両手に掲げて香奈子ちゃんが卓夫に言った。
「来年の今頃なら、きっともう美妃ちゃんも歩けてるわよね。
お散歩にでも着てもらえたらなぁーって思って。
それに、新生児用って、きっと誰かが贈ってくれるだろうから。
赤ちゃんって成長が早いから新生児用ばかりにならない方が良いかなと思ったの」
「その辺は都子がたくさん贈ってくれたみたいだしね」
優美に続けて俺は言った。
「もうひとつも開けてみて」
大きな紙袋の中に入っていたもうひとつの箱を指して優美が言った。
「何かしら? まぁ-!」
香奈子ちゃんが二回りほど大きなその箱を開けると
出てきたのはお揃いの柄の大きさの違う三着のパジャマだった。
「これ、私と卓夫ちゃんのも? わぁ-! ねぇ、私達と美妃とお揃いよ!」
「えー? 俺もこれを着るの? 可愛い過ぎるんじゃね?」
照れながら卓夫は頭を掻いた。
「いやいや、きっと似合うよ」
照れている卓夫を見て俺は笑いながら言った。
「お前、他人事だと思って適当なこと言ってないか?」
「いやいや、心からだよ」
「いや、それは絶対嘘だ!」
「嘘じゃないって」
「いや・・・」
卓夫が返しかけたところで香奈子ちゃんが割って入ってきた。
「本当にありがとう! 私、親子でお揃いって夢だったの」
三人分のパジャマを抱きかかえながら香奈子ちゃんが言った。
香奈子ちゃんに夢だったと言われたら、それ以上は返せない卓夫だった。
「まァ、良いけどさ」
諦め顔の卓夫は仕方ない体で言った。
「それは良いけどさ。ひとつ条件がある」
卓夫は香奈子ちゃんに向かって言った。
「なぁに?」
卓夫はオホンとひとつ咳払いをして、そして言った。
「妃も産まれた事だしさ、美妃の前ではもう卓夫ちゃんは止めてくれ。
俺にも父親としての威厳ってもんが必要だろ?」
「じゃ、なんて呼ぶの?」
香奈子ちゃんは訊いた。
「ほら、まぁ・・・なんてか・・・あるだろ?」
珍しく卓夫がモジモジしながら言いにくそうにしていた。
仕方が無い、俺が助け船を出してやろう。
「香奈子ちゃん、卓夫はね、パパって呼んで欲しいんだってさ」
「そうなの?」
「弘樹、てめぇ-、勝手なことをいうんじゃないぞ!」
顔を真っ赤にして卓夫は立ち上がった。
「あれ? 違ったの? 香奈子ちゃん、ゴメン。違ったみたいだ」
俺はシラーっとワザと意地悪く言った。
「いや、その・・・」
卓夫はそのまま黙って床にあぐらを掻いて座った。
香奈子ちゃんはその様子を見て吹き出しそうになるのを堪えて卓夫に言った。
「パパ。これからもよろしくね」
「でもさ。パパって威厳のある呼び名だっけ?」
俺は又も卓夫に意地悪く言った。
「ダディよりはマシだろ?」
卓夫はぶっきらぼうに答えた。よほど恥ずかしかったんだろう。
「まぁ、確かにね」
「もう、そのくらいで許してあげたら?」
優美が笑いながら俺に言った。
それを聞いた卓夫は俺に向かって言った。
「優美、これからはこいつのことは勇人クンの前ではヒロちゃんって読んでやれ。
あっ、もしかして、もう呼んでる?」
「な、訳ないだろ?」
そこに勇人が言った。
「ねぇ? ヒロちゃんて誰のこと?」
その言葉に一同は大笑いをした。
「でも、プレゼント、正解だったね」
ホテルに戻る車内で俺は優美に言った。
「うん、喜んでくれて良かった」
「めでたく卓夫の呼び名も決まったしね」
「でも、ホントに卓夫クン、嬉しかったんだね」
「あんなに子煩悩だとは思わなかったけどね。
でも、考えたらあいつは昔から人一倍優しかったよなぁー」
「そうだね」
優美はしみじみと答えた。
ホテルに戻って車を止めると優美は訊いた。
時間は夕方の四時を少し回ったところだった。
「どうする? このまま七夕に行く?」
「その方が良いかもね」
空を見上げながら俺は答えた。
どんよりと低く垂れ込めた雲は今にも雨を降らせそうな感じだった。
七夕祭をやっているアーケード街までは歩いても五分足らずだ。
俺と優美は勇人を真ん中に挟んで両方の手をそれぞれ握りながら歩いていた。
アーケード街に着くと入り口から既に天井からたくさんの七夕飾りがぶら下がっていた。
店の入り口やショーウインドウにも色とりどりの電飾が飾られていてそれは見事だった。
アーケードに沿って、普段は道路の中央付近にはたくさんの出店もならんでいた。
もう既にその辺りは人出がいっぱいだった。
「さすがに混んでるね」
「そうね。毎年近隣の町村からもたくさん人が来るしね」
「ワァ-、すごーい!」
天井からぶら下がるたくさんの飾り物や丁目毎に置かれた大きな七夕飾り。
そして、見たこともないくらいのたくさんの人を見ながら勇人は歓声を上げた。
「勇人、手を離すなよ。迷子になるからな」
俺が勇人の手を強く握ろうとすると手を引っ込めながら勇人が言った。
「ボク、優美お姉さんが良い」
そう言って、勇人は優美の腕にしがみついた。
「おいおい、そりゃないだろ?」
そう言う俺に答えず、嬉しそうに優美は勇人に言った。
「さぁ、勇人クン。何を食べようか? 今日はたくさんご馳走しちゃう!」
「ホント? わーい!」
それから三人でアーケード街を何度も言ったり来たりしながら見て回った。
勇人はというと七夕飾りもそっちのけで優美にべったりくっついて
チョコバナナやリンゴ飴やら、フライドポテト、ソフトクリームまで買って貰い
終始ご満悦で優美と大はしゃぎで歩き回っていた。
そんな二人を見て俺も嬉しかった。
きっと、勇人にとっても忘れられない七夕になったろう。
が、しかし、それは俺にとっても・・・だった。
夜も七時を回っていた。
「さて、そろそろ帰ろうか?」
「えー? もう? まだ、いたーい」
勇人が珍しくごねるように言った。
それだけ楽しい時間だったんだろう。
「でも、もう七時だぞ。晩ご飯を食べたら又、出掛けるんだぞ」
俺はしゃがむと勇人の肩に両手を乗せながら言い聞かせるように言った。
「ホント? 何処? 優美お姉さんも一緒?」
「あぁ」
「でも、ボク。もうお腹いっぱい」
「おいおい、お父さんは何も食べてないんだけど。お腹空いたよ」
「そう言うと思って焼きそばを買っておいたわ。
いか焼きも買ったのよ。部屋に戻って食べましょ」
「なんかお祭りっぽいね」
「あら、お祭りよ」
優美は笑いながら言った。
もう少しでホテルに着こうかという時、ポツポツと雨が降り出してきた。
「やっぱり来たか。さぁ、急いで帰ろう」
俺と優美で勇人の手を取りながら三人は小走りでホテルまで帰った。
買って来た総菜に加えて、優美が卵焼きとサラダとスープを作ってきてくれて
その夜の俺達三人だけのディナーが始まった。
「何もなくてゴメンね」
申し訳なさそうに優美が言った。
「いやいや、十分だよ。なぁ?」
俺は勇人に同意を求めた。
「うん。ボク、卵焼き大好き!」
「あれっ? お前、もうお腹がいっぱいじゃなかったの?」
意地悪く言う俺に勇人は平然と答えた。
「卵焼きは別腹」
「そう、良かった。じゃ、食べよっか」
優美が嬉しそうに言った。
食事の後、ホテルの部屋の窓から俺は外の様子を恨めしげに見ていた。
「けっこう降って来たね」
「そうね。これじゃ星空を見に行けないわね」
隣に来て優美が残念そうに呟いた。
「星、見れないの? 天の川、見たかったなぁー」
そう言うと勇人も窓のところにやって来た。
「雨だからなぁ-。仕方ないよ。又、今度連れて行ってやるよ」
「今度っていつ?」
「今度は今度。又、機会があればね」
「つまんなーい」
「お盆とか帰って来るんでしょ?」
優美は俺を見て言った。
「うん。その予定だけどね」
「じゃ、その時の楽しみにしましょ。ねぇ、勇人クン。約束しよ?」
「うん、判った!」
「じゃ、指切りね・・・あっ、そうだ!」
突然、何かを思いついたように優美は声を上げた。
「何?」
「うん。ねぇ、ちょっと待ってて」
そう言うと優美は部屋を出て言った。
「あっ、ちょっと!」
優美の背中越しに声をかけたが、どうやら優美の耳には入らなかったようだ。
それから十分ほど経ってから優美は部屋に戻って来た。
「ねぇ、どうしたの?」
「うふふ。内緒。ねぇ、二人とも、少しだけ部屋を出てロビーにでも行っててくれる?」
優美はそう言うと俺達の背中を押して部屋を追い出した。
二十分ほどした頃、ロビーでブラブラしていた俺達を優美が呼びに来た。
「お待たせ。さぁ、どうぞ」
訳も分からないまま部屋に通されたが、部屋の中は真っ暗だった。
「おいおい、何も見えないよ」
勇人も俺の腕にしがみついていた。
スペースファイターのパイロットになるのが夢の勇人の大の苦手は暗い場所だった。
優美が俺と勇人の手を握ると、そのまま後ろ向きに少し先まで連れて行った。
何処だろう? 部屋の真ん中当たりだろうか?
部屋の中央にはテーブルとソファがあったはずだが、それらしき物には当たらなかった。
「さぁ、そのままそこで仰向けになって寝てね」
言われるままに俺と勇人はカーペットの上に横になった。
「まだよ。さぁ、ちゃんと目を瞑ってね。勇人クン、大丈夫?」
「うん・・・大丈夫・・・」
心細げに勇人は答えた。
「良い? 目を瞑ってる? 弘樹クンもね」
「うん」
「じゃ、私が良いと言うまで絶対に目を開けちゃダメよ」
「判った」
勇人が答えた。
そこで優美のカウントダウンが始まった。
「三、二ぃ、一。はい、目を開けて!」
なんてことだろう!
目を開けると空一面に煌めくような星が拡がっていた。
「ワァ-!」
思わず勇人が歓声を上げた。
「これって・・・? プラネタリウム?」
「ご名答! そうよ。室内用のだけどね。
でも、けっこうイケてない? 私達専用の宇宙よ」
優美は楽しそうに言った。
「あぁ、凄いね。キレイだ」
俺も独り言のように呟いた。
優美も勇人の隣で仰向けに寝そべると星を指さして言った。
「勇人クン、判る? あの真ん中に長く伸びているのが天の川よ」
「うん。織り姫と彦星は何処?」
「天の川が斜めに伸びているでしょ?
その左上の方にちょっと大きく光ってる星、判る?」
「うん。あれ?」
「そう、あれが織り姫よ。そして、天の川を挟んで右下で光ってるのが彦星よ」
「へぇ-、すごいキレイ」
「ちょっと見ててごらん。星が少しづつ動いていくのよ。
色々な夏の星座があるんだけど、判るかなぁ-?」
「うーん、判んない」
「そうだよね。まだ、ちょっと難しかったね」
「でも、キレイだね。じっと見てると吸い込まれそうになる」
俺は呟いた。
「そうね」
それからしばらく俺達は無言のまま静かに動いていく星々を眺めていた。
どれくらい経ったろうか?
暗くて気付かなかったが、いつの間にか勇人は寝入っていたようだった。
静かな空気の中で勇人の寝息が聞えてきた。
「あら、勇人クン、寝ちゃったのかな?」
「今日は忙しかったからね。それにあれだけはしゃいだら、さすがの勇人も疲れるさ」
「そうね。でも、少しは楽しい想い出になったかな?」
「なったさ。それにしても勇人の奴、今日は優美にべったりだったね」
「今まで何度か会ったけど初めてよね。私も嬉しかったわ」
「ホント? ありがとう」
「ううん。こっちこそよ。楽しかったわ」
その時、俺は高校時代の或ることを思い出していた。
「ねぇ? そう言えばさ。高校の時、二年の頃だっけ?
優美とプラネタリウムを見に行ったこと・・・あったよね?」
「うん、覚えてるよ。私が誘ったんだもん」
「あれって、確か・・・俺の親父が死んだ後だっけ?」
「うん。そうだった・・・かな」
「そっか・・・あの頃から優美には気にしてもらってたのかな?
ダメだな。俺、全然そういうのに疎くってさ。ゴメン・・・」
「ううん。ホント言うとね。卓夫クンなの」
「えっ?」
俺は思わず半身を起こすと勇人の向こう側で寝そべっていた優美を見た。
「卓夫が?」
「うん。卓夫クンがね。
弘樹、お父さんが死んで悲しいはずなのに泣けないって言ってたって。
きっと、お母さんの為にも涙は見せられないと思ってるんじゃないか?
お母さんを悲しませたらお父さんが悲しむって、だから。
でも、悲しい時に泣けないのはダメなんだよ。
いつまでも悲しみに区切りが付けられなくて不幸になるだけだ。
だから、お前。あいつを何処か泣けるところに連れて行ってやれって。
で、色々考えて選んだのが科学館のプラネタリウムだったの」
「あいつがそんなことを? 俺には何も言ってなかった・・・」
俺はもう一度寝そべると星空を見ながら呟いた。
「男同士ってさ。そういうの恥ずかしいんじゃない?
弘樹クンだって、あの時卓夫クンにそんなことを言われたら
何て言うかさ・・・んー、きっと強がって見せたよね?
卓夫クンを心配させまいとしてさ」
俺は何も返せないでいた。
「良いね、男同士って」
優美は独り言のように呟いた。
俺もまた、独り言のように呟いた。
「そうだったんだ・・・
だからかな? 俺、あの時どんな星空を見たのか覚えてないんだよね。
いや、それどころかついさっきまで見に行ったことさえ忘れていたんだ。
そっか・・・俺、そこで泣けたんだな」
「私は気が付かなかったけどね」
「・・・ありがとう」
「えっ? 何?」
「ううん、何でもないよ」
俺は卓夫や優美の優しさに今更のように感謝をしていた。
「そうか・・・何だか、だんだん思い出してきた」
「何?」
そう言うと優美は寝ている勇人を踏まないように気を付けながら
そっと俺が寝そべっている方に回ってきて横まで来ると膝をついて俺を見ていた。
そんな優美を見上げながら俺は言った。
「あの時さ。優美が俺の手をずっと握っててくれてたんだよね?」
「違うわ。弘樹クンが私の手を握ってくれたのよ」
「えー? そうだっけ? 俺の記憶では確か・・・」
「良いでしょ? 昔の話よ」
言いかけた俺の唇にストップとばかりに人先指を当てると優美は微笑みながら言った。
「そうだね」
そう言うと俺はその人先指をほどいて優美の手を握ると
そのまま優美を自分の方にと引き寄せた。
「優美、ありがとう」
「ううん・・・」
こみ上げてくる色々な想いに身を任せながら
俺達は寄り添ったまま飽きることもなくずっと空に煌めく星達を見ていた。
俺達専用の宇宙の下、優しい時間だけが流れていた。
それはやがて未来へと繋がっていく大切な時間なんだと俺は静かに確信をしていた。