
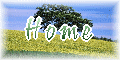
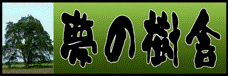
プレゼント
「お前は全然変わらないなぁー すぐ解かったよ」
何年かぶりで会った友達に良くそう言われる。
多分、喜んで良いことなんだろうけど
時々複雑な気持ちになったりもする。
「そんなに俺って大人っぽくなってないのかなぁー?」
なんてね。
でも、平均的に男は解り易い方なんだと思う。
例え、髪が可哀想なくらい薄くなっていようが
服のサイズがスリーサイズアップしようが
基本的に見た目それ自体はそんなに極端には変わらない。
ところが女子は劇的に変わるなんてことが多々ある。
当たり前の話だけど中学の頃はすっぴんで
オシャレなんかには縁が無かったような女子でさえ
十数年も経って社会人になると
化粧をして髪を染めたりパーマをかけたりするようになる。
ましてや髪型はショートカットとか
せいぜいポニーテールや三つ編みくらいで
尚且つ、制服姿やジャージ姿しか見ていなかったりすると
スーツ姿やおしゃれなワンピースを着ているだけで
そりゃイメージからして根本的に変わってしまう。
そうなると男にはもう誰が誰だかすら解らなくなるのだ。
いや、それは俺だけなのかな?
このお盆に中学を卒業してから初めての同窓会があった。
みんなもう三十歳。
外見の変わった変わらないもあるだろうけど
それ以上にきっとみんな生活自体の方が変わっているだろう。
サラリーマンをしている奴とか自分で商売を始めた奴とか
社会人としてもそれなりにいっぱしになっているんだと思う。
結婚をして子供ができた奴もいれば
風の噂ではもう離婚している奴もいるんだとか。
多かれ少なかれみんな変わっているはずだ。
そんなみんなと十五年ぶりに会うのが楽しみだった。
「おー、高代じゃないか?
なんだ、お前は変わらないなぁー」
「えっ?」
「俺だよ、俺。久保田だよ」
「あー、あの久保田か?」
そこにいたのは紛れもなく中学時代は野球部のエースで
しかも成績も学年でトップクラスで女子にもファンが多かった久保田だった。
中学時代は仲の良いグループの仲間だったはずなのに
すぐにはそうと気が付かないくらい当時の面影は既にほぼ無い。
「なんだお前。随分と恰幅が良くなったな?」
「あはは、遠慮せずに太ったと言ってくれ。
事実だ。がはは!」
久保田はそう言うと豪快に笑った。
久保田と言えば中学の頃は
どちらかというと理知的なイメージだったはずなんだけど
今はバリバリの営業マンだという話だから変われば変わるものだ。
「そういや結婚したんだってな?
幸せ太りってやつかい?
毎日、御馳走ばっかり食べ過ぎなんじゃない?」
「まぁな。確かに御馳走は食べてるな。
だが、かみさんの手料理じゃないぜ。
うちのやつは料理はからっきし下手だからさ」
「良いのか、そんなことを言って。
何処かで奥さんが聴いているかも知れないぞ」
「かまわんさ、事実だ(笑)
で、家でほとんど食事をしてなくてな。
ほとんど毎晩接待だなんだと飲み歩いているって訳さ」
「そりゃ太るな。
でも、そんな生活ばかりしてたら早死にするぞ」
「あはは、かもな。
まぁ、確かにかみさんの手料理ばかりを食べていたら
俺も小食になって少しはお前みたいにスマートでいられたかな。
でもな・・・」
そう言うと久保田は俺に耳打ちをするように小声で呟いた。
「うちのやつは料理は下手だけどアッチの方は凄いんだぜ。
だから、毎晩飲み歩いても俺は浮気はしていないんだ」
「なんだそれ? 自慢かい?(笑)」
「がはは」
「あら、楽しそうね」
そう言って声をかけてきたのは
見たことがあるような無いような着飾った二人の女性だった。
久保田と俺が顔を見合わせてキョトンとしているのを見て
その片方が笑いながら言った。
「あら、私達が美人になり過ぎていて解ってないって顔ね?」
「あっ、いや・・・」
「じゃ、私は誰?」
「えーっと・・・」
「やっぱり解ってないんだ? ショックだわー」
「いや、ちょっと待て! ここまで出かかってるんだ」
苦しそうに久保田が言い訳をしながら俺に援護を求めた。
「俺? いや、その・・・」
俺達がしどろもどろになっているのを見て
クスクス笑いながらもう一人が訊いた。
「じゃ、私は解る?」
「えっ? えーっと・・・***」
「えっ? 何? もう一度言ってよ」
「***」
「もう! はっきり言ってよ。
あー、本当は解ってないんだ?」
ちょっと拗ねたような仕草をしながら悪戯っぽく笑ったその笑顔は
どんなに変わっていても忘れるはずがなかった。
柴田みゆき。初恋の人だ。
「柴田・・・だろ? 柴田みゆき」
「きゃー、嬉しい! 本当に覚えていてくれたんだ?」
「ねぇ、じゃ私は?」
最初に訊いた女子が不満そうに訊いてきた。
「えーっとねぇ・・・」
「加藤裕子クンだろ?」
その声に振り向くとそこには当時担任だった岩崎先生が笑顔で立っていた。
「キャー! 先生!」
加藤裕子が嬉しそうに叫んで岩崎先生の手を握ると
飛び跳ねながらブンブンとその手を何度も上下に振った。
「おいおい」
笑いながら岩崎先生は言った。
「そのくらいで勘弁してくれ。
歳を取ると関節が外れやすくなるんだから」
「いやでも、先生は全然変わってないですよ」
久保田も先生に握手を求めながら言った。
「そりゃ、君達を担任していた頃は
私ももう四十歳を過ぎていたからな。
君達ほどは変わっちゃいないさ。
それにしても、君達ももういっぱしの社会人って感じだな。
そういう君達を見るのも先生冥利に尽きるよ」
岩崎先生は俺達を見回すと嬉しそうに言った。
同窓会が終わって二次会に出る話になった。
「高代はどうする?」
久保田が俺に訊いた。
他の男連中も一緒だ。
「もちろん付き合うさ」
「良し、そうこなくっちゃ。
柴田、お前も来るだろ?」
「ごめん、娘が独りで待っているから」
「そっか、残念だな。なぁ、高代?」
久保田は俺の肩を抱きながらそう言った。
当時、仲の良かったグループの一人だった久保田は
柴田みゆきが俺の初恋の相手だと解っている。
「あぁ、そっか。じゃ、また今度の時にでもね」
内心ではガッカリしながらも俺は努めて平静に答えた。
「うん、ごめんね」
「あら、私はとことん付き合うわよ」
加藤裕子が両手を広げて大袈裟な格好で言った。
「えー? お前かよ?」
「あら、失礼ね」
加藤裕子がふくれっ面で文句を言った。
「これでも会社では人気ナンバーワンなんだからね」
「何処のキャバクラだい?」
「まぁ! みゆきぃー 男子が虐めるぅー」
「男子は昔から変わらないのよ。
好きな子にはわざと意地悪をするの」
慰めるように
でも半分笑いながら柴田みゆきは加藤裕子に言った。
「だよねぇー 美しいって罪なんだわ」
しょってる加藤裕子。
「そうそう、だから二次会では存分に魅力を見せつけて来たら?」
「おっけー」
自信家は立ち直りも早いらしい。
「あっ、そうだ! ねぇ、せっかくだし連絡先の交換しておこうぜ。
また集まりたいしさ。なぁ?」
久保田が俺の肩をポンと叩きながら加藤裕子と柴田みゆきに同意を求めた。
「うん、いいわよ。じゃ、私はこれね」
そう言って加藤裕子はスマホを久保田に差し出した。
「良い? 行くわよ」
それからめいめいに連絡先を交換し合った。
もちろん、<自然の流れ>で俺と柴田みゆきもだ。
交換と言っても今は携帯やスマホの赤外線通信だからアッと言う間だ。
「じゃ、みゆき、またね。今度電話するわ」
「うん、待ってるね」
「おー、柴田。またな!」
みんなに見送られながら柴田みゆきは帰って行った。
二次会での加藤裕子情報によると・・・
(情報と言っても
幸いにも酔った加藤裕子が勝手に話してくれたのだが)
柴田みゆきは
高校卒業後に東京の会社に勤めて結婚をしたが
三年前に離婚をしてこっちに戻って来て
今は駅前のデパートの女性服売り場で働いている。
<独り>で五歳になる娘を育てていると言うことだった。
同窓会の後も柴田みゆきのことは気になってはいたけど
かと言って同じ市内に住んでいるとはいっても
ドラマのようにそう都合の良い偶然はなくて
ましてやデパートの婦人服売り場なんて
俺には一番縁の遠い場所だった訳で
何も起こらないままに季節は秋から冬へと過ぎて行った。
北の街もいつしか根雪になって
あちらこちらでイルミネーションが
華やかに街を飾る季節になった。
そしてクリスマスイブの夜。
子供達にとっても恋人達にとっても特別な夜だ。
だからと言って俺には何も関係がないただの夜だ。
「おーい!」
会社を出ようとすると同僚の遠藤が声をかけてきた。
「あぁ、遠藤。どうした?」
「いや、すまんけどさ。
何も言わずにこれもらってくれないかな?」
そう言うと遠藤は俺の手に紙のようなモノを握らせた。
「何?」
「ケーキの引換券だ。
駅前の『モン・サン・ミッシェル』だぜ。知ってるか?」
「あぁ、地元の超有名店だろ? みんな知ってるさ」
「そこのクリスマスケーキの引き換え券だ。
ありがたく思え。お前にやる。
しかもタダだ。金はもう払ってある」
「何だよ? 子供に持って帰るんじゃないのか?」
「子供に食わすのにこんな高いケーキは買わないよ」
「じゃ、どうしたんだよ?」
「フラれた・・・」
「えっ?」
「せっかくホテルを予約してさ。
高級フレンチのディナーも予約して
こんな高いケーキも買ったっていうのにさ」
「フラれたって、お前・・・浮気してたのか?」
「してたっていうか・・・する予定だったんだ。
行きつけのスナックのチーママなんだけどさ。
何年も通って口説いてきたのにさぁー
いざその時となったら何てことはない。
イブは本命の男と過ごすんだってよ。
なら早く言ってくれよな、本当にさ」
遠藤はブツブツと呟いた。
「そりゃ、自業自得ってやつだろ?
でも、それならそれで家に持って帰れば良いじゃん。
きっと、奥さんだって子供さんだって喜ぶぜ」
「いや、家ではうちの奴が盛大なケーキを作ってる。
見た目は悪いけど・・・まぁ、美味いんだけどな。
でもさ、それを解っていて
こんなケーキを買って帰ったらどうなると思う?
『あんた、ケンカを売ってるの?』ってさ。
うん、間違いない。
だから、頼む! 遠慮なくもらってくれ!」
「でも、俺だって一人なんだから食べきれないよ」
「なんだ、今夜も一人なのか?」
「悪かったな。余計なお世話だよ」
「あはは、すまんすまん!
でも、頼むよ。人助けだと思ってさ」
普段はケーキ店には全く無縁な俺にとって
『モン・サン・ミッシェル』は
店の中に入るのもはばかるほど混み合っていた。
ましてや今夜は夜が夜だ。
明らかに恋人同士と見える多くの若いカップルに交じって
居心地が悪そうに並んでいる中年サラリーマンの姿もあった。
多分、帰りを心待ちにしている家族のために
恥ずかしいのを我慢して頑張って並んでいるんだろうな。
そんなことを考えながら
俺は何度も店の前を行ったり来たりしながら
店の中が空くタイミングを見計らっていた。
何度となく<このまま帰ろうか>
そんな気持ちが心を過った。
それほど今夜は場違い感を増幅させられている気がした。
『どうしようかな・・・でも、遠藤に悪いか。
明日、ケーキの感想を訊かれても答えられないのはマズイしなぁ』
特別な夜だからか店の中はいっこうに空く気配がなかった。
何度目かに店の前に立った後で
俺は意を決して店の中に入っていった。
ケーキを引き取った後で
何とはなく帰路を歩いていたらデパートの前を通りかかった。
柴田みゆきが勤めているデパートだ。
時間は八時を随分過ぎていた。
もうデパートは閉店している時間だ。
多分、ついさっきまでは
これでもかというくらい華やかだったであろうショーウインドウも
今は灯りを消していて妙な静けさだけがそこにはあった。
スーツだってワイシャツだって
近所の量販店で済ませていた俺には
高級品を扱うデパートなんて縁遠い場所だった。
超有名ケーキ店にデパート。
特別な夜だからか?
今夜は普段の俺には縁遠い場所にばかり縁が出来てしまうようだ。
そんな考えに思わず苦笑いをしてしまった。
灯りの消えたショーウインドウを見ながら歩いていると
デパート横の従業員通路から飛び出してきた黒い影とぶつかりそうになった。
「きゃっ、ごめんなさい!」
「あっ、いやこちらこそ。大丈夫ですか?」
「あっ!?」
二人は同時にお互いに気が付いた。
それは誰あろうか柴田みゆきだった。
「柴田?」
「高代君?」
「大丈夫?」
「えぇ。あー、ビックリした」
「俺もだよ。まさかこんなところで柴田に会えるとはね」
「だって、ここは私が勤めているデパートだもの」
「あっ、そうか!」
まるで<そのこと>には気がついていなかった風を装って俺は答えた。
「何か随分と急いでいるようだったけど?」
「あっ、いけない! プレゼントを買いに行かなきゃならないの」
「プレゼント?」
「えぇ、娘に・・・」
「だって、柴田はデパートに勤めているんだろ?
おもちゃとかぬいぐるみとかだって売ってるんじゃないの?」
「でも、もう五歳よ。デパートの包装紙って訳にはいかないもの」
「なんだ、包装紙くらい替えたら良かったじゃん。
今は百均でも売ってるし」
「あっ、そうか! 気が付かなかった」
「あはは。意外と・・・あっ、いや(笑)」
「なぁに? どうせ私はヌケてますけど?」
「いやいや、そうじゃなくってさ」
<意外と可愛いところがあるな>
そう言いかけて続きの言葉には出来ないでいた。
「あー、急がなきゃ! お店が閉まっちゃう」
思い出したように柴田みゆきが言った。
「そうだね。それは急いだ方が良いよ」
「うん、バタバタしちゃってごめんね」
俺は手を振りながら走って行く柴田みゆきを見送っていた。
その背中はだんだんと小さくなりすぐに人ごみの街に消えて行った。
「まぁ、こんなもんだよな」
特別な夜の偶然の出会いは神様を信じない人間にも
何か特別な予感と期待を与えるようだ。
だがそれは或る意味、特別な夜の夢。
ちょうど降り出した雪のように儚い夢なのだが。
「あっ、雪だ・・・」
俺は真っ暗な夜空を見上げながら
ただ静かに落ちてくる白い雪を見ていた。
「ドラマだったらきっと
こんな夜はこの雪に紛れて天使が降りてくるんだろうな」
急に思い浮かんだ乙女チックな空想が妙に可笑しくて
俺はふと口についた独り言に笑ってしまった。
「さぁ、帰るか・・・あっ!
どうせならこのケーキ、柴田にやれば良かったかな?」
後悔後に立たずと言うけどそれは本当だ。
まぁ、今更のように思っても
今までだってそれで随分後悔をしてきた。
結局は学習能力が低いってことなんだろうな。
そんなことを思いながら俺は帰り道を歩き出した。
歩いて十分も経っただろうか。
突然、スーツのポケットから着信音が聴こえてきた。
俺は慌ててポケットからスマホを取り出した。
「あっ!」
それは柴田みゆきだった。
「もしもし?」
「あっ、高代君? 柴田です」
「あ、あぁ。プレゼントは買えた?」
「ダメ・・・
駅前のおもちゃ屋さんに行ったんだけど売り切れだった。
・・・どうしよう。
ねぇ? 他に何処かおもちゃ屋さんって知らない?」
「おもちゃ屋さんねぇー あっ、そうだ! あるよ!
ねぇ、今何処?」
「駅前、おもちゃ屋さんの前」
「そっか。じゃあ、そこを右に行って・・・」
確か、駅前から三条通りに出て二丁か三丁行った所に
小さなおもちゃ屋さんがあったはずだ。
でも、随分前のことだし今もあるかどうか確信はなかった。
「そうだ! じゃ、デパートの前で待ってて。すぐに行くから」
「ごめんね、ありがとう・・・」
ケーキが崩れないように胸の前に抱えるとデパートに急いだ。
デパートの前では柴田みゆきが待っていた。
「待たせてごめん、急ごう!」
「うん」
楽しそうに語らいながら街を歩くカップル。
忙しそうに帰りを急ぐサラリーマン。
イヴの夜はいつも以上に華やかで賑やかだった。
でも、こんな風に走っているのはきっと俺達だけだったろう。
信号を無視して道路を横断するにはイヴの夜は適さない。
それほど走っている車は途切れることはなかった。
信号が変わる度、まるでダッシュでもするかのように走っては
また、信号で止まる。
もどかしい思いで信号が変わるのを待つ。
そしてまた、無言で走り出す。
少し積もった雪に転びそうになりながら
それでも転ばずに走れたのは特別な夜の奇跡と言っても良いのかもしれない。
走りながら俺はいつか観た映画を思い出した。
「ふふ」
思わず笑った俺に気が付いた柴田みゆきは
走りながらも怪訝な顔で俺を見た。
「どうしたの?」
「いや、昔観た映画を思い出してね」
「映画? どんな?」
息を切れせながら俺は答えた。
「『ジングル・オール・ザ・ウェイ』だったかな。
クリスマスの夜にやっぱり子供の為におもちゃ屋さんに行くんだけど
目当てのモノが何処も売り切れでさ。
で、何件もハシゴをするんだけど・・・さて、どうなるでしょう?
みたいな、そんな感じ(笑)
あっ、笑い事じゃなかったね。こんな時にゴメン」
俺はどうも何かにつけてタイミングが悪いみたいだ。
柴田みゆきがこんなに困っているのに余計なことを言って
かえって心配を助長してしまっただろう。
「ごめん・・・」
柴田みゆきは急に立ち止まると
俺を見て息を切れせながら訊いた。
「それでどうなったの?
映画だからもちろんハッピーエンドよね?」
並んで走っていた俺も慌てて立ち止まると柴田みゆきを見た。
そして答えた。
「もちろん」
「じゃ、大丈夫だわ! きっと見つかる!」
「そうだね。さぁ、急ごう!」
「うん!」
俺達はまた走り出した。
息を切らせながらその店の前に着いた時
店主らしき人物がちょうど店のシャッターを下すところだった。
「あっ、すいません! ちょっと待ってください!」
叫ぶ俺にその人物はシャッターを下ろす手を止めて振り向いた。
店を出るといつの間にか雪は止んでいた。
「良かった」
柴田みゆきはやっと買えたプレゼントを大事そうに抱えながら呟いた。
「最後の一個だったもんね。ラッキーだったね」
「ありがとう、高代君のおかげだわ」
「いや、柴田の気持ちが通じたんだよ」
「でも・・・」
「でも?」
柴田みゆきは買ったプレゼントを両手で抱えたまま呟いた。
「うん・・・正直に言うとね。
美咲・・あっ、娘ね。
美咲の欲しかったのってコレなのか自信ないんだ。
遠慮してなのか? それともそういう歳なのか?
『プレゼントは何が欲しいの?』って言っても
『サンタさんに頼んであるから秘密』って言って
私には教えてくれなかったの」
「うん」
「テレビのコマーシャルやマンガの本の広告とか
美咲が真剣に観ていたから多分、そうかなって思ってるんだけど」
「うん」
「でも、違ったらどうしよう?
さっきまでは<コレ>って決めて探していたのに
いざ見つかって買えたとなると何だか不安になったりしてね。
あはっ、変だよね?
娘の欲しいモノも知らないなんてダメな母親だわ」
柴田みゆきはそう呟くとフッと溜め息をついた。
俺は歩いている足を止めると柴田みゆきを見て言った。
「大丈夫じゃない? 確か五歳だったよね?
ん・・難しいっていうか微妙な年頃ではあるかも知れないけど
母親が買ってくれたプレゼントだもの。
それが嬉しくないはずがないよ」
「ふふ、相変わらず優しいね。
ねぇ、覚えてる? 中学三年の時の文化祭」
「えっ? なんだっけ?」
「あの時も高代君は私達のために走り回ってくれた」
「そうだっけ?」
頭を掻きながら俺は答えた。
もちろん覚えてはいたんだけど今となっては気恥ずかしい想い出だった。
「教室の飾り付けをしていた時
飾りに使うピンクのテープが足りなくなって
他の男子達は『有る色で続けよう』って言ったけど
女子は『それじゃ変だ』って言い合いになったじゃない?」
「そんなことあったっけ?」
「そしたら高代君が『俺が探してくる』って。
あの時もあっちこっち探して買いに行ってくれたのよね?
でも、高代君が戻って来る前に
中の女子が他のクラスに訊いてくれて見つけたんだけど
その後で、せっかく買って戻って来た高代君は
一言も文句も言わずに続きを手伝ってくれた」
「・・・」
「あの時は腹が立たなかった?」
「さぁ・・・どうだったかなぁ・・・忘れたよ」
「高代君らしい言い方・・・相変わらず優しいんだね。
それに比べて私は変わっちゃったなぁー」
「そんなことはないよ」
「ううん。変わったわ。
離婚もそうだけど、色々なものを見ちゃったし
良いこともあったけど、そうじゃないことも。
美咲がいなかったら今頃、私はきっと私じゃなくなってたかも」
柴田みゆきは寂しげにそう言うと
又、ゆっくりと歩き出した。
「そっか・・・」
他に気の利いた言葉も見つけられずに
そう言うと俺も又、並んで歩き出した。
無言で歩く二人。
しばしの沈黙が長い時間に思えた。
「でも」
俺はケーキを片手に持ったまま
おもむろに両手を挙げ少し伸びをしながら数歩歩き
そして立ち止まって柴田みゆきを見ると
やっと見つけた言葉を並べた。
「それを<変わった>っていうなら俺もだよ。
俺だって色んなものを見たと言うか・・・見せられたって言うかさ。
考え方だっていつまでも学生のままじゃやっていられないしね。
良くも悪くも変わってるんだと思う。
でもさ。それも含めて<成長>って言うんじゃないのかな?」
「うふふ。やっぱり高代君は変わってない。
ううん、もっと優しくなってるのかなぁー?
きっと良い恋愛もたくさんしたのね」
「それはどうだか。未だに独身やってるしさぁー
その辺は一番自信が無いとこかな(笑)」
頭を掻きながら俺は答えた。
確かに、過去には恋愛もいくつかしたし
結婚をしたいと思った女性がいたこともあった。
でも、何でだろう?
その時はそれほど真剣にはなれなかった。
一度タイミングを逃すと人間って逃し癖がつくのか?
それともそれが俺の持って生まれた性質なのか?
結婚をしたい時に相手はいなくて
そうでもない時は相手が出来ても積極的になれずに今日まできていた。
やはり俺は根っからタイミングの悪い男なんだろうか?
俺は俯くと少し自嘲気味に笑った。
「どうしたの?」
「えっ? あっいや・・・」
俺は我に返って又、頭を掻いた。
「変なの(笑)」
柴田みゆきはさっきまでの不安気な様子も忘れたように屈託なく笑った。
『やっぱり、柴田は笑顔の方が似合ってるな』
改めて柴田みゆきの顔をまじまじと見つめるとそう心の中で思った。
「何?」
柴田みゆきはきょとんとした顔で訊き返した。
「ん? いや、別にね」
「何よー? 絶対、何か思ってたでしょ?」
柴田みゆきが問い詰めるように訊いた。
「あはは、別に何でもないよ」
「そう? でも、怪しい・・・」
「怪しくないよ。気のせい、気のせい(笑)」
そこで柴田みゆきは神妙な顔に戻ると改めて俺に礼を言った。
「ごめんね。せっかくのイヴなのに変なことに付きあわせちゃって」
「いや、どうせ帰ってもヒマだったしさ。
あっ、そうだ! これ」
俺は持っていたケーキを差し出した。
「何?」
「ケーキ。しかも、駅前の『モン・サン・ミッシェル』」
「すごーい! 有名店よね? 知ってるわ。
でも、いつもデパートで売れ残りばかり買っているから縁が無い店だわ」
「どう?」
「えっ? どうって?」
柴田みゆきは少し困惑をした表情をした。
「これ、もらってやってくれないかな?
せっかくクリスマスケーキとして生まれてきたのに
<こいつ>可哀想な奴なんだ」
「えっ? 可哀想って? ケーキが? どうして?(笑)」
「実はさ・・・」
俺はこのケーキをもらうことになって顛末を話した。
「でさ、注文主には捨てられて、やっと次の主に貰われたと思ったら
そいつは独り者でどう考えても美味しいうちに食べきれそうもない奴で。
このままだとこいつは明日の夜には
汚いアパートの一室でカサカサになっている・・・かも知れない?(笑)」
「あはは、何それ?(笑)」
「だからさ。<こいつ>の幸せのために柴田にもらって欲しいんだ」
「えっ? でも・・・
お礼をしなきゃならないのは私の方なのに悪いわ」
「いや、だからさ。
俺の為にじゃなくってさ。<こいつ>の為にね。
<こいつ>だってケーキをして生まれたからには
可愛い子供や素敵な女性に食べて欲しがってると思うよ。
少なくとも俺なんかよりはね(笑)」
「でも・・・」
「さぁ、遠慮せずに!
これも人助け・・・いや、ケーキ助けだと思ってさ(笑)」
柴田みゆきは少し考えてから想定外の言葉を言った。
「じゃ、一緒にケーキ助けしましょ」
「えっ?」
今度は俺が困惑をする番だった。
もちろん、嬉しくないという意味ではなかった。
その言葉の意味を測りかねてという意味でだ。
そんな俺の表情を感じ取ってか柴田みゆきは
多分わざと?
大袈裟に顔の前で手を合わせて俺に謝る仕草をした。
「ごめんね。又、高代君に迷惑をかけるところだった。
私ってすぐ調子に乗っちゃうタイプなんだわ。
ホント、ごめんね。気にしないで」
「いや、全くの全然だよ!」
俺は慌てて否定をした。
しかも混乱をしていたのか?
はたまた単に動転していたのか?(何に?)
<頭が頭痛>みたいな変な日本語になっていたのにも気が付かなかった。
もしかしたら声も上ずっていたかも知れない。
柴田みゆきは<クスッ>っと笑った。
「えっ? 何か変だった?」
「ううん。多分、大丈夫よ。
高代君って嘘がつけないタイプね」
柴田みゆきはそういうと又<クスッ>と笑った。
そしてしみじみと言った。
「なんか懐かしいね」
「あぁ、そうだね。
同窓会の時はあまりゆっくり喋れなかったけど
今は卒業してから十五年ぶりだなんて気がしないなぁー」
「うん、私もそう思ってた」
「十五年か。長いね」
「うん・・・」
「あの頃、俺は自分が三十歳になるなんて想像できなかった。
でもきっと、四十歳になっても五十歳になっても
同じことを思うんだろうな。
気持ちは全然変わってないのに不思議だよな」
「そうね。私も五十歳になっている自分なんて想像も出来ないな。
どうなっているんだろう?」
「柴田ならきっと幸せになっているさ」
「その根拠を述べよ」
柴田みゆきは俺の方に人差し指を突きつけると笑いながら言った。
「えー? そう言われても・・・」
「こらこら。根拠も無しに言ったの?」
「まぁ、しいて言えば・・・柴田・・・だから?」
「何それ? 答えになってない」
「希望的観測ってやつ?」
「なんかテキトー!」
柴田みゆきはふくれっ面になって文句を言った後で大笑いをした。
つられて俺も笑った。
「あー、おかしい!
こんなに笑ったの久し振りだわ」
「それはよござんした」
俺はおどけて答えた。
「じゃ、場も和んだということで
はい、これケーキさんの為に持って帰って」
「でも・・・」
「いいから、いいから」
俺は柴田みゆきの手にケーキを持たせた。
「美咲ちゃんが喜んでくれると良いけど」
柴田みゆきはプレゼントの袋を手首にかけたまま
両手でケーキを抱えると視線を俺に向けた。
「美咲がどのくらい喜ぶか確かめに来る?
ううん、来て欲しいの・・・」
「えっ?
でも、突然俺なんかが行ったら美咲ちゃんもとまどうんじゃない?」
「かもしれない・・・でも、何とかなるよ」
「そうかなぁー」
「希望的観測」
「あー! それ、俺のマネだ!(笑)」
結局、俺は図々しくも柴田みゆきをアパートに同行をすることになった。
柴田みゆきのアパートは十五分ほど歩いた先の閑静な住宅街にあった。
一棟に四件が入るそんなに大きくはないアパートだったが
築年数は十年という割にはキレイな今風のちょっと洒落たアパートだった。
「ここよ。小さいアパートでしょ?」
「いや、俺のアパートよりは遥かにキレイだよ」
「じゃ、夜なのでちょっとだけ静かに上がりましょ。二階なの」
俺は無言で敬礼をして見せた。
柴田みゆきは又、<クスッ>と笑った。
建物の真ん中にある階段を上がると
柴田みゆきは右の玄関を黙って指差した。
そしてショルダーバッグから鍵を取り出して玄関のドアをそっと開けた。
<カチャッ>
静かに開けたつもりだったが
その気配に気づいたのか小さな女の子が居間のドアを開けて駆け寄って来た。
「ママー!」
と、叫んだかと思うと
その瞬間、柴田みゆきの後ろにいた俺に気がついて
美咲ちゃんは固まったように立ち尽くしていた。
「あっ、美咲。この人はね・・・」
柴田みゆきが慌てて説明をしようとした時
美咲ちゃんは満面の笑顔になるとこう叫んだ。
「わぁー! クリスマスプレゼントね?
私、サンタさんにお願いをしていたの。
『新しいお父さんが欲しい』って!
ママー、ねぇ、そうでしょ?」
果たして俺なんかが美咲ちゃんにとって
特別な夜に願った通りのプレゼントになったのか?
それはまだ今は解らない。
でも、少なくとも俺にとっては
この瞬間が
特別な夜の特別なプレゼントになったのは間違いない。
今までは何かにつけタイミングが悪かった俺だけど
こんなこともある。
なんせ今夜は特別な夜だからね。