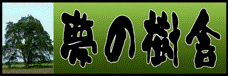由紀子は居間のソファに横になって、観るとは無しにつけっ放しのテレビを観ていた。
もう、時計は深夜の1時を指そうとしていた。
「変ねぇ・・・ いつもなら遅くなる時は電話くらいくれるのに・・・」
夫の健二は食品関係の営業マンで、地方を走る事も多い。だから、帰りが遅くなる事もしばしばでは
あったが、そんな時は決まって電話をくれていたものだった。
「何か急な仕事で遅くなっているのかしら・・・」
どんなに遅くなっても健二は帰宅をしてから晩ご飯を食べる。
由紀子は起き上がると、健二が帰ってきたらすぐに食べられるように味噌汁を温めなおしておこうか
どうしようかと考えていた。
その時、電話が鳴った。
由紀子は慌てて受話器を取った。
「もしもし、あなた?」
「浅田さんのお宅ですか? こちらは警察署ですが・・・」
それからの事は良く覚えてはいなかった。
急いで息子の和彦を起こすと、由紀子は着の身着のままで、
気が付くと市立病院の地下の一室に立っていた。
顔に掛けられた白い布を取ると、そこには今朝まで元気だった健二がいた。
まだ、眠っているだけのような安らかな顔だった。
「どうして・・・」
健二の遺体に抱きついて泣きじゃくる和彦を他人事のような不思議な感覚で見ていた。
由紀子は未だ、何が現実で、何が夢なのかさえ受け止められないでいた。
警察官らしき男が事故の状況を説明している。
「急に飛び出してきた自転車を避けようとして・・・」
「それだけ? たった、それだけの事で?」
由紀子にはそれに続く言葉が見つからなかった。
警察官の言葉も自分とは関係の無い、何処か遠くで聴こえている声のように思えた。
「これは現実なの?」
いつもは他人事のように新聞やテレビのニュースで観ていた出来事が、
まさか自分の夫の身に起こるなんて思いもよらない事だった。
9月20日。
健二の葬儀が終わって3日目の朝だった。
いつもなら、毎朝が戦場のような慌しさだった。
いつもギリギリに飛び起きて来る健二に食事もそこそこに弁当を持たせて送り出し、
それから2階の和彦の部屋へ行き、
布団を剥してもなかなか起きようとはしない和彦を起こす。
由紀子がひと息をつけるのは、2人を送り出して朝食の後片付けを終わらせた8時半過ぎだった。
それが、今朝は7時だと言うのに物音ひとつしない。
和彦も未だ起きて来ない。
由紀子は和室に祭った祭壇の前に座って健二の遺影を見ていた。
「あなた・・・」
いつも、それっきり言葉にならなかった。
『帰って来てよ』
『成仏してね』
『どうして・・・?』
何を言っても、何か違うような気がしていた。
いや、未だに現実を受け止められないのだ。 と、言うよりも、認めてしまうのが怖かったのだ。
遺影の中で微笑む健二は、居間に飾ってある家族3人の写真の笑顔そのままだった。
今にも、2階の寝室から健二が慌てて駆け下りて来るような気さえしていた。
でも、もうそんな音は聞こえて来ない。
由紀子が点した線香の香りだけがそこに漂っていた。
由紀子と健二はお見合い結婚で、お互いが30歳を過ぎてからの結婚だったので、
普通の新婚家庭のような甘い新婚生活なんかは無かった。
結婚なんてこんなものだと思いながら、それでも、健二は優しかったし、
何より誠実だったので、1人息子にも恵まれて、それなりに幸せな毎日だった。
息子の和彦は今年高校に入った。 これからの和彦の塾や受験、そして大学生活を考えると
決して余裕が有る訳では無かったが、健二が真面目に働いてくれてたお陰で少しは蓄えも出来た。
10年前には家も建てた。 特別、何の贅沢が出来る訳でも無かったが、それでも家族3人が健康で
いられる事に幸せを感じていた。
ささやかな幸せ・・・それはずっと続くと信じて疑いもしなかった。
ホンの数日前までは・・・
9時を過ぎた頃、玄関のチャイムが鳴った。
「はい」
出てみると、健二の会社の後輩の藤江が立っていた。
「おはようございます。 お疲れのところなのに、こんなに朝早くから申し訳ありません。」
「まぁ、藤江さん。 先日はありがとうございました。 どうぞ、お入りになって。」
藤江は健二の祭壇に手を合わせると、由紀子の方に向き直って一礼をした。
「先輩には私が入社をした時からずっと可愛がってもらっていたんです。 ホントに優しくって・・・
私が初めて契約を取れた時なんて、まるで自分の事のように喜んでくれたんです。」
「ええ、覚えているわ。 確か、お祝いだとか言って、一緒に飲みに行ったのよね?
酔っ払って帰って来るなり、『藤江がやったぞ〜!』って、それはもう自分が昇進をした時以上に
喜んでいたわ。」
『そうね、そんな人だった・・・』
由紀子は改めて健二の遺影を眺めていた。
しばしの沈黙が2人の間に流れた。
「あっ、そうそう!」
そう言うと、藤江は黒いバッグを差し出した。
「奥さん、これは机に有った先輩の私物とパソコンです。
パソコンは仕事でも使っていたようなのですが、パスワードが掛かっていました。
もし、仕事関係の書類とかメールとかがあれば後ででも教えて頂きたいのですが。」
そう言うと、藤江は丁寧に慰みを言って会社に戻って行った。
健二が会社のパソコンの他に、自分でノートパソコンを持っていたのは聞いていたが、
実際に見るのは初めてだった。
「確か、出張用とか言ってたわね。」
由紀子がバッグからノートパソコンを取り出して、電源を入れてみると、確かにパスワードが
掛かっていた。
「パスワードか・・・ 何だろう? 誕生日? 違う・・・電話番号? 違う・・・車のナンバー?
ん〜 違うわね・・・」
結局、分からないまま、由紀子はパソコンの電源を切った。
次の日の夕方、弟の卓也が顔を見せた。
卓也は同じ市内に妻の君子と2人の娘と住んでいた。
仕事帰りに、由紀子と和彦の様子を見にやって来たのだった。
卓也はスーツの上着を脱ぐと居間のソファに腰を下ろした。
「姉さん、どう? 少しは落ち着いたかい? 和彦もいるんだから、元気を出さなきゃダメだよ。」
「そうは言ってもなかなかね・・・」
「そりゃ分かるけどさ・・・ あれっ? あのパソコンはどうしたの?」
ダイニングテーブルの上に置かれた健二のパソコンを目ざとく見つけると卓也は訊いた。
「主人が会社で使っていた個人のパソコンなんだって。 今日、藤江さんが届けてくれたの。」
「ふぅ〜ん・・・ ねぇ? 開けてみた? もしかしたら、義兄さんの重大な秘密が隠されていたりしてね。
いや、もちろん冗談だけどさ。」
卓也はそう言うと屈託無く笑った。
由紀子も昨日からずっと気になっていた。 秘密はともかく、健二のパソコンを開く事で
仕事をしていた時の健二に触れられるようなそんな気がしていたのだ。
「何をバカな事言ってるのよ。 そんな秘密なんか有る訳無いじゃない。 有るなら、とっくにバレて
いるわよ。 そう言う事の出来る人じゃないんだから。」
「いや、分かってるって。 冗談だよ。 ところで和彦は?」
「今、塾に行ってるわ。 学校は休んでも塾は休んでいられないんだって。」
「までも、家にいるよりは気が紛れて和彦には良いかもね。」
「そうね。 どうせ私は普段から家で1人だしね。 慣れてるわ・・・」
そう言うと、由紀子は卓也の向かいに座ってため息をついた。
「まぁまぁ、そうじゃないかと思って可愛い弟君が顔を出したって訳だからさ。」
卓也はわざとおどけた言い方をした。 少しでも由紀子を慰めたいと思っていたのだ。
「はいはい、感謝してあげます。」
「えー!? あげますかい?」
「冗談よ。」
由紀子は笑って答えた。
それから、少し卓也の方に向き直って言った。
「ホント・・・今回の事では何から何まであなたにはお世話になりっぱなしね。 感謝してるわ。」
「何言ってんだよ。 お互い様さ。 あんまり真面目に感謝されると何だかこそばいな。」
由紀子はふと思いついたように卓也に訊いた。
「卓也、あなたならパソコンのパスワードは何にする?」
「えっ? パスワード? そりゃ言えないなぁ〜 だって姉さん、うちの奴にタレこむつもりだろ?
パソコンの中には秘密がいっぱい詰まってるんだから教えてやんないよ〜」
卓也はおどけて言った。
「何よ、秘密って?」
「そりゃまぁねぇ〜 ほら、人生いろいろってね。」
卓也は笑いながら言った。
「もう、そんな事しないわよ。 例え、あなたの悪行三昧がパソコン中に溢れていたって
加奈ちゃん達を母子家庭にはしたくないもの。 君ちゃんには黙っていてあげるわよ。」
由紀子も笑いながら答えた。
それから、少し真面目な顔に戻ると
「主人のパソコンなんだけどね。 仕事でも使っていたらしいんだけど、パスワードが掛かっていて
開けられないのよ。 藤江さんが何か仕事関係の書類でもあれば教えて欲しいって言ってたから
気になってるの。」
「あー、あれかい? ちょっと見て良い?」
「ええ、良いわよ。」
卓也はパソコンの電源を入れながら訊いた。
「そうだなぁ〜 パスワードね・・・ 大概は生年月日とか電話番号とか車のナンバーとかだよな。
仕事でしょっちゅう開くんだから、そんな面倒なパスワードにはしてないと思うんだけどね。」
「私もそう思って色々試してみたんだけど。」
「う〜ん・・・ まぁ、色々やってみようよ。 義兄さんの誕生日っていつだっけ?」
「10月15日よ。 でも、それはやってみたわ。」
「1015、0115、115・・・違うなぁ・・・ 電話番号は・・・違うか・・・車は何番?」
「5842よ。」
「5842・・・ ん〜 後はなんだろ? 因みに姉さんの誕生日は?」
「5月21日よ。 あなた何年弟をやってるのよ?」
「あはは、ごめんごめん。 ガールフレンドの誕生日なら忘れないんだけどなぁ〜」
卓也は楽しそうに笑って言った。
「おっと、脱線、脱線・・・5月21日ね? 0521・・・521・・・ ん〜 姉さん、愛されてないね?」
卓也はまたおどけて言った。
「余計な事は言わなくて良いの!」
「はいはい、すんませ〜ん。 ん〜 違うなぁ・・・ 姉さん、和彦の誕生日は?」
「和彦? 8月10日だけど・・・」
「8月10日か・・・810・・・ 0810・・・」
卓也はニヤッとして由紀子を見た。
「開いたの?」
「和彦でビンゴだよ! ほらっ」
主を亡くしたノートパソコンは今、起動音を高らかに鳴らして再び立ち上がった。
「さてと・・・ したら帰るよ。 姉さんもやる事が出来たみたいだし、邪魔はしないよ。」
卓也はそう悪戯っぽく笑った。
「卓也、ありがとうね。」
「いやいや、なんのなんの、お安い御用で。」
「ごめんね。助かったわ。」
由紀子は卓也に心からそうお礼を言った。
由紀子は卓也がパソコンの中身にまであれこれ訊かない事に感謝をした。
由紀子がゆっくりと健二の思い出に触れられるように気を遣ってくれたのは明らかだった。
「あー、腹減ったぁ〜 じゃあね、何かあったら連絡して。 あなたの可愛い弟君は
すぐに馳せ参じますよって。」
卓也はそう笑いながら玄関に向かった。
と、振り返ると又、例の悪戯っぽい笑顔でこう言った。
「あのさぁ〜 パソコンの中から何が出てきても驚いちゃダメだぜ。
義兄さんの大事な形見なんだからさ。 捨てるんなら俺にくれ〜」
「もう! 卓也ったら・・・ 良いから、早く帰りなさい! 君ちゃんに秘密の事言うわよ!」
「おー! 怖っ!」
卓也はそう言って玄関の戸を閉めた。
由紀子は笑ってそれを見送っていた。
ダイニングテーブルの上で健二のパソコンは次の動作を待っていた。
しかし、由紀子は開いたデスクトップを眺めたままだった。
別に健二の秘密が怖かったからではない。
それに、そんなものは有るはずもないと思っていた。
仮に有ったとしても、もう今となっては全て過去の事なのだ。
むしろ、健二の触れていたキーボード、マウス・・・健二の仕事、そんな事に例え少しでも
触れられると思うと、それだけで愛しかった。
そして、それらを想い、見ているだけで胸が詰まった。
健二のパソコンは次の動作を催促でもするようにファンが唸りをあげた。
「ん〜 仕事のファイルばかりね。 でも、どれが大事なのか分からないわ・・・」
とりあえず、仕事関係と思われるファイルをひとつのフォルダーにまとめてみた。
藤江からは何か仕事関係のファイルが有ればメールで送って欲しいと言われていた。
「そうだ、藤枝さんの名刺・・・アドレスが書いてあったわね。」
由紀子は藤江の名刺を取り出すとアドレスを確認した。
「これね・・・」
由紀子は仕事関係のフォルダーを圧縮するとデスクトップに保存をした。
そして、それからメールソフトを立ち上げた。
{ 接続中です・・・確認中です・・・受信中です・・・2件受信中です・・・3件・・4件・・・・・ }
「何日分だろう・・・随分来てるわね。」
全部で11通のメールが来ていた。
「仕事関係のメールならこれも転送しておかなきゃ・・・あらっ?」
由紀子はもう一度受信ボックスを見た。
普通の受信ボックスに5通。
そして、[ kenji ]と分けられていた受信ボックスには6通の着信が有った。
9月20日 ”優子” 件名: もし・・・
《ねぇ? 私はどうしたら良いの? もし・・・私の事が嫌いになったのなら、そうだと言って。
もし、健二が止めたいと思っているなら、しつこくはしません。 だから、お願い!
ひと言だけでも良いから・・・》
由紀子は自分の目を疑った。
「何、これ・・・? 来たのは・・今日ね・・・優子って誰?」
由紀子はもう一度、そのメールを読み直した。
「あの人は浮気をしていた?」
信じられない気持ちで、由紀子は急いで前日のメールから順に開いていった。
9月19日 ”優子” 件名: 健二・・・
《心配しています・・・ もしかして、怪我とか病気とか? 何も手につかないの・・・
いえ、忙しいだけよね? そう思いたい。 せめて、ひと言で良いわ。 お願い・・・
健二は何も言わないで音信不通になるような人じゃない。 だから、余計に心配なの・・・》
9月18日 ”優子” 件名: 心配です・・・
《どうかしたのかしら・・・? こんなに健二からメールが来なかった事はなかったよね?
何か有った? 忙しいなら、落ち着いてからで良いからメール下さいね。》
9月17日 ”優子” 件名: 大丈夫???
《忙しいのかなぁ〜? なら良いけど・・・少し心配しています。
そうそう! 今日ね、お友達とランチに行って来たの。 素敵なお店! あなたの好きな
エスプレッソもとっても美味しいのよ。 今度のデートはそこで決まりよ♪ それじゃ・・・》
9月16日 ”優子” 件名: 忙しい?
《忙しいかしら? 最近、出張や残業が多いって言ってたものね。 身体が心配・・・
メールはゆっくりでも良いから、書けるようになったら又、メールをしてね。
それじゃ、あまり無理はしないでね。》
『亡くなった日だわ・・・』
由紀子は最後に9月15日のメールを開いた。
9月15日 ”優子” 件名: 今度・・・
《健二、こんばんは〜 今頃はまだ仕事してるかな? 今日は何処を走ってきたの?
今日ね〜 お友達と温泉に行って来たの。 昼間からすっかり贅沢気分だったわ〜
まだまだ紅葉には早いけど、今頃の温泉も良いものですよ。 今度は健二と行きたいなぁ〜
なんてね。 でも、泊まりなんて絶対無理だもんね? は〜い、そこまで無理は言わないわ。
安心してね(笑) でも・・・いつか、日帰りでも良いから一緒に行けたら良いなぁ〜♪
さてと、それじゃそろそろ食事の支度をしなくっちゃ。 それじゃ頑張ってね〜!》
由紀子は言葉を失くしていた。
親しげな優子からのメール。
ショックだったのはもちろんだったが、それ以上に裏切られていたと言う事実が由紀子を
絶望の淵へと追いやった。
それは言葉にはし難い事実だった。
「どうして?」
怒りを通り越して、ただ哀しかった。
何気ない顔をして騙していた夫。
何も知らずに騙されていた自分。
悔しくて、哀しくて・・・溢れる涙を由紀子は拭う事も忘れてパソコンの画面を見ていた。
「どうして? 何が不満だったの? 不満が有るならどうして私に言ってくれなかったの?」
しかし、今はもう問い詰める相手はそこにはいないのだ。
一瞬、由紀子は激情が心の中を突き走るのを感じていた。
「もう良い! 全部消してやる!」
これ以上は何も見たくない。何も知りたくない。 そんな一心だった。
由紀子は、今まで優子から来たメールを全部選択をした。
後は、削除を押すだけ・・・
しかし、由紀子はマウスにのせた人差し指を押す事は出来なかった。
何をためらっているのか、由紀子には分かっていた。
「真実を知りたい・・・」
健二は由紀子の何が不満で優子と付き合うようになったのか?
それが知りたかった。
何処で知り合って、どんな付き合いをしていたのか等は今更どうでも良かった。
ただ、健二が何を考えていたのか?
何を優子に求めていたのか?
そして、自分が与えられなかったものは何だったのか?
その真実が知りたいと思ったのだ。
由紀子はメールの選択を解除して、そしてマウスからそっと指を離した。
由紀子はしばし画面を凝視したまま動かなかった。いや、動けなかったのだ。
頭の中が混乱しているのを感じていた。
「知ってどうするの? 優子さんに文句でも言う気?」
しかし、自問自答の答えは出てこなかった。
その時、玄関のチャイムが鳴る音がして、和彦が居間に入って来た。
「母さん、ただいま。 ん? 何をしてるの?」
「ううん、何でもないわ。」
由紀子は慌ててパソコンの蓋を閉じた。
「お腹空いたでしょ? すぐにご飯にするわね。」
そう言うと、由紀子は急いで台所に向かった。
「ねぇ? これ、どうしたの?」
「何が?」
由紀子には分かっていたが、わざとはぐらかすように答えた。
「パソコンだよ。 誰の?」
和彦が訊き返した。
由紀子はどう答えようかとしばし考えた。
でも、どうせいずれは分かる事だ。
「それね、お父さんが会社で使っていたんだって。 会社の方が届けてくれたの。
でも、仕事のファイルがたくさん有るみたいだから、まだ触らないでね。」
「父さんの? ホント? ねぇ? ちょっと見て良い?」
「ダメよ。 仕事のファイルが入ってるって言ったでしょ? 全部整理がついたら見せて上げるわよ。」
「ちぇっ、つまんないなぁ〜」
和彦は由紀子の傍に来ると
「ねぇ? じゃあさ、仕事の整理がついたら僕にくれる? 母さんは家のが有るだろ?
父さんの形見だもん、絶対大事に使うからさ。 ねぇ? 良いでしょ?」
「そうね・・・ そうするわ。 だから、もう少し待ってて頂戴ね。」
「了解! あー、そう言えば腹ペコなんだ。 ねぇ? ご飯まだ?」
和彦はそう言うと、上機嫌で居間に戻ってソファに寝転がった。
食事を終えて和彦が2階に上がると、
由紀子はダイニングテーブルの上に置かれたパソコンの前に座った。
「どうしよう・・・」
由紀子は優子からのメールを思い出していた。
意を決したように、由紀子はノートパソコンの蓋を開けた。
パソコンは静かにスタンバイから復帰をすると、やがてファンが唸りをあげた。
和彦が帰って来てお喋りをしたお陰で、少しは冷静になれた気がした。
それから、由紀子は優子から来たメールと、健二が送ったメールを交互に読み始めた。
2人は長い付き合いだった。 2年近くになる。
その頃は、丁度和彦が中学の2年生も後半で、塾の事や受験の事で由紀子の頭の中は
一杯だった。 そして、健二の事はいつも二の次扱いだった。
しかも、当の和彦は元来がノンキな性格で、いつになっても真剣に勉強をしようとしなかったので、
由紀子は毎日のようにヒステリックに文句を言っては、夜遅くに帰ってくる健二に愚痴をこぼしていた。
健二も課長に昇進をしたばかりの頃で、仕事も責任も増えて身体的にも、精神的にも何かと
大変な時期だった。
ギスギスした空気。 そんな家庭の雰囲気。
いつもヒステリックに文句を言い、愚痴を並べる由紀子に健二の心も疲れきっていた。
本来なら、安らぎになるべき家庭がいつもそんな調子だったので、健二は仕事の愚痴も言えず、
疲れも癒せずに、1人で全てを抱え込んでストレスの吐き場所も無いまま疲れきってしまっていたのだ。
そんな時に、気晴らしにと悪戯心で覗いたとあるサイト。そこで偶然に優子と出会った。
最初は軽い気持ちで、健二にも浮気なんてつもりは頭にも無かった。
ただ、心の安らぐ場所が欲しかったのだ。
1日のホンの束の間にせよ、自分を取り戻せる時間。 つまり、本音で話せて、そして仕事の事も
家庭の事も何もかも忘れて心を癒す時間が欲しかった。
そして、優子と出会う事で、いつしかそれらは充たされていった。
だから、家庭に戻っても、いつも変わらないでいられたし、我慢の限界を踏み越えないで済んだ。
とは言えそれは、言ってみれば単に男のワガママだったかも知れない。
それは健二にも分かっていた。
しかし、健二にとってはそんな時間がいつからかかけがいの無いものになっていったのは確かだった。
優子は家庭を顧みない夫に諦めに似た気持ちを抱いていた。
子供の進学の事を相談しても、夫はいつも全てを優子に任せっきりで何も答えようとはしなかった。
お互いの実家の事、親戚との付き合いや近所の事、例え何かゴタゴタが有っても全て優子任せで、
いくら相談をしても俺には関係無いみたいな風で冷たく突き放されていた。
優子の気苦労も夫にとっては他人事でしか無かったのだ。
それでも、最初のうちは何とか夫と話すように努力はしていた。
優子にとって頼れる相手は夫だけだったし、何より夫の事を愛していたから、
いつかは分かってくれる。 そう信じていたのだった。
しかし結局は、いつも仕事が忙しいの一点張りで優子の話などまともに取り合おうとはしなかった。
それが、いつしか夫への不信になり、いつか諦めに変わっていった。
そんな中で1日中家で家事をして、ただ過ぎていく時間。
優子の虚しさは増すばかりだった。
優子と夫は大恋愛の末、親の反対を押し切って駆け落ち同然で結婚をした。
もう20年前の話だ。
最初の頃は、家には何も無かったが、夫がそこにいてくれさえすればそれで幸福だった。
夫は優しかったし、何より何においても優子の事を一番に気にかけてくれていた。
優子もそんな夫に精一杯の気持ちで応えていた。
初めての子供が生まれた時には、この世の幸福を1人占めしているかのように思えた。
その幸福は永遠に続くと信じていた。
『それなのに・・・』
優子はいつか離婚も考えるようになっていたが、子供達の事を思うと出来ないでいた。
子供達には相変わらず優しいお父さんなのだ。
普段は家にいない分、優子に内緒で子供達には時々何かを買ってやったり、
小遣いを渡していたのも優子は見て見ないふりをしていた。
そのせいか、特に下の子はたまに家に夫がいればベッタリで、まとわりついて離れないくらいに
夫になついていた。
そんな子供達に悲しい想いだけはさせたくないと思っていた。
『自分さえ我慢をしていれば・・・』
それで、優子は働きに出る決心をした。 夫は相変わらず無関心で賛成も反対もしなかった。
週に3日のパートだったが、外に出る事で優子の気持ちも段々と晴れていった。
そんな時、偶然夫の浮気を知った。
ある日、夫から携帯にメールが入った。 それは夫が愛人に宛てたメールだった。
それが間違って優子宛てに送信されたのだ。
その事に夫は気付いているのかいないのか、夫は優子には弁解も何もしなかった。
あくまで普段通りの素振りだった。
優子もあえて問い質す事もしないで素知らぬ素振りで振舞った。
『仮面夫婦ね・・・』
優子は自嘲気味に呟いた。
そんな事があってから、優子はネットでたまたま知ったサイトに書き込みをするようになった。
サイトで知り合った男性と他愛の無いメールのやり取りをする事で気を紛らせたいと思った。
メールだけで良かったのだ。
優子には浮気をする気は無かった。
夫への当てつけで自分が変わっていく事が怖かった。
しかし、サイトで知り合った男はみんな2〜3回もメールのやり取りをすると、
もうまるで恋人気分で優子を誘ったり、
中には下品な言葉で優子を困らせるようなそんな男達ばかりだった。
そんな男達とはすぐにメールを打ち切っていた。
中にはしつこい男もいたが、大概無視をしているとそのうち、諦めてメールも来なくなった。
『もう、メールなんて止めようかな・・・何だか虚しいだけね。』
それでも、いざメールを止めると時折寂しさも戻ってきて、又ついサイトを覗いてしまうのだった。
そんな時に知り合ったのが健二だった。
健二は今までの男達とは何処か違っていた。
いつまで経っても、優子を誘おうとはしなかったし、
何より、健二の何気ない気遣いや優しさが嬉しかった。
話もいつも楽しくて、優子はメールを読んでいてつい噴出している自分に気付く事もしばしばだった。
そんな健二に優子はいつか、段々と好意以上の気持ちが芽生えていくのを感じていた。
最初に誘ったのは優子の方だった。
優子はそんな事が出来る自分に驚いてもいたが、それよりも自分の気持ちに素直でいたいと
思っていた。
実際に会っても、健二はメールのままだった。
むしろ、メールの時よりは少しシャイな感じで、そんな飾らない正直さが優子は益々好きになっていった。
時折、時間を合わせては、2人でお茶を飲んでお喋りをしたり、
食事に行ったり、カラオケに行ったりもした。
2人は2人で過ごす僅かな時間を大切にしていた。
お互いを思いやり、言葉を交わし、気持ちを通じ合わせていた。
そんな2人が身体の関係を持つようになったのはむしろ自然な事だったのかも知れない。
全てを読み終えると、由紀子はただ黙ってパソコンの画面を見ていた。
不思議と2人への怒りも憎しみも沸いて来なかった。
何か、小説でも読んでいるような、そんな感じさえした。
もちろん、だからといって健二を全て許した訳では無い。
優子の事を認めた訳でも無い。
ただ、健二の心の内が少しだけ覗けた気がして嬉しかった。
嬉しかったと言うのは適切では無いかも知れないが、本当にそんな感じだったのだ。
健二が優子とメールを始めて5通目くらいにお互いに写真を交換したのだろう。
そこには、優子の微笑む写真も添付されていた。
由紀子は優子の写真をまじまじと見つめていた。
そう特別に美人とまでは言えなかったが・・・美人と言うよりは可愛いといった感じか・・・
45歳と書いてあったが、それよりは幾分若く見えた。
そして、変な言い方だが、健二が選んだ相手がただの浮気性な軽薄女では無かった事に
何故かホッとしていた。
「どうしよう・・・」
由紀子の中に、ふと妙な感情が沸いて来るのを禁じえなかった。
「優子さんと話がしてみたい・・・」
由紀子は優子に親近感を感じてしまっていた。
親近感と言うよりは、同じ健二と言う共通項を通しての同志のような、それは不思議な感覚だった。
自分でも何故そんな気持ちになったのか分からなかった。
普通で考えたら、絶対有り得ない気持ちであろう。
夫の浮気相手に親近感を感じると言う事だけでも有り得ない話だ。
それなのに、罵声を浴びせたり、罵る為ではなく、
ただ純粋に会って話がしたいと思うなんて有るだろうか?
由紀子は優子にメールを送る決心をした。
但し、送り手の名前は「健二」のままで・・・
|