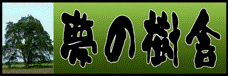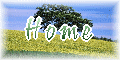
サンタクロース見習いの恋
「これ、そっちの積み込みはどうじゃ?」
「あっ、はい! もうすぐです」
「あぁ、そう言えばトナカイにもたっぷりとエサをやっておかねばのぅ」
「そうですね。今夜は長い旅になりますからね」
少年はそう言うと額の汗を拭った。
少年の名前は<ルカ>と言った。
ルカはルカ自身が気が付いた時からサンタクロースの見習いをやっていた。
ルカがどう言う経緯でサンタクロースの見習いになったのか?
又、どう言う生い立ちなのか?
それはルカ本人も知らない事だった。
一度、サンタクロースに訊いた事があった。
だが、それに明解な答えは返っては来なかった。
「いつかは自分自身で知る時が来るじゃろう」
八頭のトナカイをソリに繋ぎ終えるとルカはサンタクロースに声をかけた。
「準備OKです」
「よし、それじゃ行こうかの」
「はい!」
「振り落とされないようにな」
そう言ってサンタクロースがムチを入れると八頭のトナカイはぐんぐん加速を始め
アッと言う間に二人を乗せたソリは空高く舞い上がった。
ルカは夢中で助手席の縁にしがみついていた。
今夜はルカにとっても初めてのサンタクロースとの旅だった。
遥か眼下には無数の街の灯りが拡がっていた。
そして夜空にはそれ以上に星達が煌めいていた。
「ウワアー! すごい! 空も地上も星だらけだ!」
ルカはウットリとそれらを眺めていた。
「ノンビリしているヒマは無いぞ。
それっ、そろそろ最初の”目的地”じゃ」
「あっ、は、はい!」
最初の村に着いた。
広々とした牧場の敷地の中に大きな二階建ての家が建っていた。
裕福な家庭なのだろう。
一階の居間には
キレイに飾られた天井にも届きそうなくらい大きなクリスマスツリー。
赤々と燃えるレンガ造りの大きな暖炉。
そして、中央にはクリスマスカラーのカバーを掛けた大きなソファ。
そこにワイングラスを持った夫婦が並んで座って談笑をしていた。
二階の子供部屋はもう電気が消えていた。
大きなフカフカのベッドに並んで寝ている兄と妹。
幸せそうな寝顔だ。
「さて、それじゃ行くかのぅ」
「はい」
サンタクロースは大きな袋をヨイショとかつぐと
ルカを従えて子供部屋に降りて行った。
サンタクロースは兄の枕元に車のオモチャをそっと置き
妹の枕元にはクマのぬいぐるみを置いた。
ルカにも子供達が朝起きて歓声を上げるのが見えるようだった。
「さて、それじゃ次じゃ。さっ、あまり時間は無いぞ」
それから三軒の家にはやはり同じように
子供の枕元にはそれぞれ男の子にはオモチャ、女の子には人形やぬいぐるみを置いた。
五軒目の家は谷合の村落に有った。
トタン屋根に壁は長板を貼っただけのみすぼらしい家。
今にも消えそうな小さな薪ストーブ。
木枠の窓の隙間に入りかけた雪が薄らと氷になっていた。
そんな部屋の片隅で男の子は薄い掛布団一枚で寒さに震えながら眠っていた。
サンタクロースは掛布団の襟を男の子の首の辺りを包むように掛け直した。
「この子に今、必要なモノはコレじゃな」
そう言うと脇に置いていた袋から小さな光を取り出すと
男の子の胸の辺りにそっと置いた。
その光は一瞬、フワッと光ったかと思うと男の子の胸の中にスーッと入っていった。
それは<夢>だった。
ソリに戻るとルカはサンタクロースに訊いた。
「あの・・・今の子にはオモチャはあげないんですか?」
「あぁ、そうさな。
あの子にオモチャをあげたところでどうなる?
明日も明後日も来週も来月も楽しく遊ぶと思うかい?」
「そりゃ・・・でも、どんな子供だってオモチャは嬉しいですよ」
「じゃが、今あの子が生きる為に必要なモノはオモチャじゃなかろう。
これからも続くであろう厳しい生活の中、生きていく為に必要なモノは<夢>じゃ。
ワシ達は何もオモチャだけを与えている訳では無いのじゃ。
むしろ、世界中にはオモチャを与えられる子供の方が少ないのじゃよ」
それから幾つかの国と何万と言う子供に<プレゼント>をした後で
次の街に着いた。
大都会の高層マンションの十五階の部屋。
人並み以上には裕福な家庭に思えた。
明るい色の壁紙と沢山の星が描かれた天井の子供部屋。
ベッドにはキャラクターの絵柄の暖かそうな羽毛布団。
だが、男の子の布団の襟元は涙で濡れていた。
男の子は友達に虐められていたのだ。
ただ、周りの子達より家が裕福だと言う理由だけで。
その時、男の子は声にならない声で寝言を呟いた。
「もう、いやだ・・・」
その様子を観ていたサンタクロースはルカに訊いた。
「さて、ルカ。お前ならこの子に何を贈るかの?」
「僕ですか?」
ルカは男の子の寝顔を見ながら少し考えてからこう言った。
「この子には<勇気>を贈りましょう」
クリスマスイヴの奇跡。
皆さんは、どうしてたった一晩の内に
サンタクロースが世界中の子供達にプレゼントを届けられるのか知っていますか?
これこそが神様がサンタクロースに与えた奇跡のひとつ。
いや、使命だと言った方が良いのかも知れません。
もちろん、世界中にサンタクロースの支部があって
何十万人ものサンタクロースが一斉にプレゼントを配っている訳ではありません。
サンタクロースはクリスマスイヴの夜だけ時間を超える事が出来るのです。
どうしてかって?
実はサンタクロースの身体は
この世に生まれてくる事の出来なかったたくさんの子供達の魂で出来ているのです。
だから、
<子供達に”幸せ”を与える事>
それがサンタクロースの願いであり使命なのです。
そして、サンタクロースのプレゼントは何もオモチャだけではありません。
子供達が本当に望んでいるモノや幸せを感じられるモノ。
例えば、それは夢だったり希望だったり想い出だったりと
そんな形が無いモノだと言う事もあるのです。
ヨーロッパからアフリカ、そしてアジア大陸を駆け抜けて
やがて真ん丸の月が夜空の真上に来た頃。
サンタクロースとルカはアジアの東の端の島国へと着きました。
「やれやれ、やっとそろそろ半分まで来たかのぅ。
ルカ、どうだね? 疲れたじゃろう?」
「いえ、やっと僕の使命が少しだけ解ってきたところです。
ただ、それが何処で何をどうしたら良いのか?
それがまだ解らないのです。
だから疲れたなんて言ってられません」
「何、焦る事はない。
実はのぅ、ワシらは
ワシらが選んで<プレゼント>を配っている訳では無いのじゃ。
子供達の<声>を聴けば自ずとそれは解ってくるじゃろうて」
サンタクロースとルカを乗せたソリはまるで決められた順番が有るかのように
正確に子供の居る家を辿っていった。
「次はあそこですね?」
ソリが下降を始めるなりルカは一軒の家を指差して言った。
「そうじゃ。だんだん解ってきたようじゃの?」
「はい!」
その家は良くある建売のごく普通の一軒家だった。
濃紺の三角屋根に明るい水色のサイディングの壁とルーバー窓が印象的だった。
そして、小さいが良く手入れの行き届いた庭。
その庭先には犬小屋があって茶色の小型犬が眠っていたが
二人に気が付いたように、ふと立ち上がると上空を見た。
犬と目が合ったサンタクロースは
指を口の前に立てると<シー>と黙ってのサインをした。
サンタクロースを知っているのかは解らなかったが
犬は又、何事も無かったかのように身体を伏した。
「良し良し、良い子じゃ」
サンタクロースがソリを降りて犬の頭を撫でると犬は気持ち良さそうに目を閉じた。
犬もサンタクロースの夢を見るのだろうか?
「そうじゃ、ルカ。
ここはお前が一人で行っておいで」
「えっ? 僕が・・・ですか?」
「そうじゃ。そして、お前が上げたいと思う”プレゼント”をしてくるのじゃ」
「で、でも・・・」
「何、大丈夫じゃて。お前もサンタクロースなんじゃからのぅ」
「サンタクロース? 僕が?」
「あぁ、そうじゃ。子供達から見たらの」
「は、はい。解りました!」
「ここの子供は、あの二階の部屋じゃ」
そう言うとサンタクロースは二階の花柄のカーテンが掛かった部屋を指差した。
多分、女の子なのだろう。
「それじゃ、行って来ます」
二階の子供部屋に入ったルカは人の気配に思わず立ちすくんだ。
「誰?」
歳は十三〜四歳くらいだろうか。
少女はベッドから起き上がると真っ直ぐルカの方に歩いて来た。
稀にサンタクロースを”見よう”と起きている子供がいるが
サンタクロースが部屋に入った瞬間に魔法に掛かったように子供は眠ってしまうものなのだ。
だから、どんなに頑張って起きていても
結局、子供達にはサンタクロースは見る事が出来ない・・・はずだった。
ルカは驚いて身動きが出来ずにいた。
こんな事態を誰が予測出来ただろうか?
「そこにいるのは誰? 男の人? ううん、パパじゃないわ」
「あっ、あの・・・怪しい者じゃないから」
ルカは咄嗟にそう言うのが精一杯だった。
少女は怪訝そうに訊いた。
「あなた、誰なの?」
「ぼ、僕は・・・」
「ねぇ、もしかしてサンタさん? ねぇ、そうでしょ?
でも、声が若いわ・・・」
「あっ、あぁ・・・そう。そうなんだ! でもまだ見習いなんだけどね」
「見習いのサンタさん? うふふ、おかしな人ね」
「あの・・・怖くないの?」
「どうして? あなた、サンタさんなんでしょ?」
「そう・・・だけど」
その時、ルカは初めて気が付いた。
少女にはルカが”見えて”いないのだ。
「君・・・僕が見えていないのかい?」
「えぇ。でも、そこにいるのは解るわ」
『どうしたら良いんだろう?
まさか、こんな事になるなんて!』
ルカは考えあぐねていた。
こんな事態はおそらくはサンタクロースでさえ想像していなかっただろう。
どうして良いのか解らずルカはすぐにでも逃げ出したい気持ちだった。
だが、サンタクロースとしての責任もある。
ルカは思い切って少女に尋ねた。
「ねぇ、ところで君。プレゼントは何が良い?」
「いらない」
「どうして? 欲しいものは無いの? 着せ替え人形とかぬいぐるみとか」
「もうたくさんあるわ。パパもおばあちゃんもたくさん買ってくれるの。
だからもう、これ以上プレゼントをもらっても”みんな”とは遊べないわ。
それに私、きっと春まで生きてられないの」
それは突然の言葉だった。
「えっ? ど、どうして? まさか・・・病気なの? 何の病気なの?
病院は? 入院をしてなくて大丈夫なのかい?」
突然の言葉に考えもまとまらないままにルカは少女に尋ねた。
「もう手遅れなんだって。
この前、パパとママがお医者様と話しているのを聴いちゃったの」
少女は寂しそうに俯いてベッドに腰を下ろした。。
「そんな!」
ルカは言葉を失った。
『何て言う事なんだろう?
初めてプレゼンを渡すはずの子が病で余命幾ばくも無いなんて』
ルカは呆然と立ち尽くしていた。
『こんな時、サンタクロースならどうするんだろう?』
ルカはチラッと後ろを振り返ると
家の外にいるであろうサンタクロースにすがるように心の中で助けを求めた。
だが、もちろんサンタクロースには届くはずも無かった。
「ねぇ、どうしたの?」
少女の声でルカは我に返った。
「あっ、あぁ・・・何でも無いよ」
「そうだ!
プレゼントはいらない代わりに何かお話をして。
サンタさんの町ってどんな所?
普段は何をしているの?
今夜はどんな町でどんなプレゼントをして来たの?
どうして、あなたはおじいさんじゃないの?
サンタさんって本当はみんなそうなの?
もしかして何人もいるのかしら?」
矢継ぎ早に質問を繰り出した少女の瞳はキラキラ輝いていた。
何も見えていないなんて信じられないくらいに。
「あっ、ごめんなさい!
こんなにいっぺんに質問をしたって答えられないよね?
私って意外とせっかちなのね。
今、気が付いたわ」
少女はそう言うと舌をペロッと出して笑った。
「私、<明日花> 明日に花って書いて<あすか>って読むの。
ねぇ、あなたのお名前は?」
少女の笑顔にドギマギしながらルカは答えた。
「僕は<ルカ>」
「ルカ? まぁ、素敵なお名前ね。どんな意味があるのかしら?」
「さぁ・・・ただ、そう呼ばれていたから」
「お父様が付けたのかしら? ねぇ、サンタクロースってお父様?」
「いや、そう言うのじゃないと思う。
僕には家族がいないんだ。
サンタクロースにも家族はいない。
そう言うモノなんだ」
「そう・・・何か可哀想・・・」
「でも、寂しいと思った事は無いんだ。
いつも<誰か>といるような気がするんだ。
もちろん、サンタクロースはいつも一緒だったけど、何て言うかな。
そう言うのとも違う<誰か>がいつも僕と一緒にいるんだ」
「ふぅ〜ん。何か良く解らないね。不思議な話だわ」
「明日・・花ちゃん、隣に座って良いかい?」
ルカは明日花に訊くと返事を待たずに明日花に並んでベッドに腰を下ろした。
「で・・・住んでいる所だっけ?」
明日花の笑顔を見ているうちにルカは少し落ち着きを取り戻した。
『少し話をしていたら、この子に本当に必要な”プレゼント”が見つかるかも知れない』
「住んでいる所はね、ずっと北の国なんだ」
そう言いながら、ルカは気が付いた。
何も知らないのだ。
住んでいる家は解る。
家の前に拡がる牧場に何十頭ものトナカイが自由に草を食べている。
でも、町はと言うと解らなかった。
近所にどんな人が住んでいるのか?
いや、そもそも他に住んでいる人なんているのだろうか?
「ねぇ?」
「あっ、ごめん」
「どうかしたの? 訊いちゃいけなかった?」
「い、いや・・・そう言うんじゃないんだ。
ただ・・・解らないんだ」
「解らない? どうして?」
「さぁ・・・どうしてだろう?
気が付いたら僕はサンタクロースの家で手伝いをしていたんだ。
でも、それがいつからなのか?
サンタクロースにとって僕は何なのか?
それが解らないんだ」
「ねぇ? じゃ、あなたのパパやママってどんな人?」
「うん・・・それも解らないんだ。
今はニコラウスと言うサンタクロースの手伝いをしているんだけど。
でも、君の言うパパではない・・・それは確かだと思う。
さっきまで考えた事も無かったけど、でも本当に解らないんだ・・・」
「でも、サンタさんらしい話ね」
明日花はニッコリと微笑むと言った。
「サンタらしい? そうなのかな・・・」
「そうよ! これで、普段は役所勤めでイブの夜だけサンタさんに変身するとか
実はサンタさんってオモチャ工場で働くロボットだとか
そんなんじゃ夢が無くなるわ」
「あはは。明日花ちゃん、君は想像力が素晴らしいね!」
ルカは明日花と話をしていると愉快な気分になった。
「でも、少なくともあなたはロボットじゃなさそうね?」
「多分・・・ね。でも、人間とも違うと思う。それだけは解るんだ」
「どんな風に?」
「ん〜 何て言ったら良いのか・・・先ず、お腹が空かないんだ」
「えー? じゃ、何を食べているの?」
「何も」
「何も?」
「うん、何も。トナカイに草は食べさせるけどね。
でも、僕やサンタクロースは何も食べないんだ」
「平気なの?」
「でも、何も食べないけど・・・でも、さっき気が付いたんだ。
子供達に<プレゼント>を配って回っていると不思議と満たされていくんだ。
ねぇ? 僕はロボットなのかな?」
「良くは知らないけど、こんな優しいロボットはいないと思うわ。
でも、サンタさんって神様の親戚なのかも。だからお腹が空かないのよ」
「まさか! 神様は神様だよ。僕はそんな偉い人じゃないもの」
「ねぇ? ルカは病気とかはしないの?
風邪を引いたりとか、頭が痛くなったりとか、熱が出て働くのが辛くなるとか?」
「いや、それは無いよ。そんな記憶も無いんだ」
「羨ましい・・・」
そう言うと明日花はルカの手を握った。
「温かい・・・あなた、本当に良い人なのね」
明日花が手を握るとルカも心が温かくなったような気がした。
ふと、ルカがベッドの横の机に目をやると一冊のスケッチブックが目に入った。
「明日花ちゃんは絵を描くのが好きなの? あのスケッチブック・・・」
「外で遊べないから」
明日花は少し寂しそうに答えた。
「そっか・・・ねぇ? ちょっと見せてもらっても良い?」
「ダメよ。恥ずかしいもの」
「ねぇ、ちょっとだけ」
「内緒にしてくれる?」
「内緒に? もちろんだよ」
「じゃ、ちょっとだけよ」
照れたように頬を赤らめると明日花は机のスケッチブックを手に取るとルカにそっと手渡した。
スケッチブックには窓から見える景色だろうか?
雪に覆われた白い大地と葉を落とした幾つもの樹木が。
そして、遥か向こうには同じく雪を被った白い山並み。
その上の空はとてもキレイな水色に塗られていた。
ページをめくると今度は色々な動物達が描かれていた。
「あっ、これはウサギだね? これは猫。それから・・・これは馬だ」
「うふふ。良かった。タヌキだとか怪獣なんて言われなくって」
「まさか! とても上手だよ!」
「私ね。絵本作家になるのが夢だったの」
「だったって、そんな。まだこれからじゃ・・・」
そう言いかけてルカは言葉に詰まった。
確か明日花は目が見えていなかったはずだ。
でも、こんなに上手に絵が描かれている。
それはつまり以前はちゃんと目が見えていたと言う事だ。
それに、明日花の話が本当なら明日花にはそれほど時間が無いのだ。
今はどんな言葉をかけたとしても、それは気休めにもならないだろう。
ルカは胸が詰まった。
こんなに苦しい想いは生まれて初めてだった。
「あー、せめて目が見えたらなぁ〜
そうしたら、外に出られなくたって絵は描けるのに」
明日花はそう言うと大きな溜め息をひとつ、ついた。
「そうだ、ちょっと待って!」
ルカは<プレゼント>の入った大きな袋の中を探し始めた。
『新しい目は無いんだろうか? どんな病気も治る薬は?』
「どうしたの?」
「いや・・・ちょっとね。そうだ! ちょっと待っていてくれる? すぐに戻るから」
ルカが外に出ると家の上にサンタクロースを乗せたソリが浮かんでいた。
「あの・・・」
ソリの助手席に乗り込んでルカがサンタクロースに話しかけると、
その言葉を遮ってサンタクロースは答えた。
「全部、ここで見ておったよ」
「はい。あの子に上げたい<プレゼント>があるのですが袋の中にそれが見当たらないんです。
何とか、何とか、ならないんでしょうか?」
「うむ。袋の中には世界中の子供達へのプレゼントが入っておる。
じゃが、どうしようも無い事もあるのじゃ」
「そんな!
だって、サンタクロースは子供達に
夢だって希望だって勇気だって上げてきたじゃないですか。
病気を治す薬くらい無いんですか!」
ルカは夢中でサンタクロースにくってかかった。
「これ、ルカ! 落ち着きなさい!」
「あっ、す、すいません・・・」
我に返ったルカは膝の上で拳を握りしめて項垂れた。
その震える拳には大粒の涙が滴り落ちていた。
「お前の気持ちは良く解る。
じゃがのう、人間には運命と言うものがあるのじゃ。
サンタクロースはプレゼントは渡す事は出来ても運命まで変える事は出来ないのじゃ。
例えば、さっきは男の子に勇気を贈ったじゃろ?
だが、その勇気をどう活かすのか?
それとも、何の役にも立たずに失くしてしまうのか?
それはその子次第なのじゃ。
それ以上の事はワシ達には出来ないのじゃ」
「じゃ・・・僕はあの子に何を上げたら良いんでしょう?
希望ですか? 春までには死んでしまうあの子に?
勇気ですか? 死を恐れない勇気ですか?
夢を上げたところで、それは却って残酷過ぎます・・・
僕には・・・僕には、もう解りません・・・」
すがるようにサンタクロースに向かってルカは訴えた。
「僕はどうすれば良いのですか?」
「昔・・・もう、ずっと昔の事じゃ」
遠くを見つめながらサンタクロースは独り言のように呟いた。
「ワシもずっと以前に先人から聴いた話なのじゃが。
その昔、自分の命と引き換えに子供の命を救ったサンタクロースがいたらしいのじゃ。
じゃが、それは掟を破る事になる。
サンタクロースは神では無いのだから本来、人間の運命を変えてはならぬのじゃ」
「そのサンタクロースは・・・どうなったんですか?」
「さぁな。解らぬのじゃ。
消滅してしまったのか?
何処かで魂だけが彷徨っておるのか?
誰にも解らぬのじゃ」
「でも、助ける事は出来たのですね?」
「子供はな。そう聴いておる」
「では、その方法が解ればあの子を助ける事が出来るのですね!」
「じゃが、それは昔の話じゃ。
果たして本当の事なのか?
ただの伝説なのか?
ワシにも解らぬのじゃ。
ただ・・・」
「ただ?」
「強い気持ちで結びつく事が出来れば、もしかしたら・・・
実はの、ワシらの身体は生まれて来れなかった子供達の魂が集まって出来ておるのじゃ」
「生まれて来れなかった?
子供達の魂・・・そうか!」
ルカがいつも一緒にいると思っていた<誰か>が解った気がした。
「そうなんだ。
だから僕は寂しくは無かったんだ!」
「その魂があの子の魂と真の意味で結びつく手立てがあれば
もしかしたら助けられるかも知れん。
じゃが、それはルカ、お前の死をも意味するのじゃぞ」
「解りました!」
そう言うとルカはソリを飛び降りた。
「これ、何処へ行くのじゃ?」
「あの子の所にです。
僕の命に代えてでも、あの子は絶対に僕が助けます!」
ルカの瞳には清々しいくらいの希望が宿っていた。
「これ、ルカ! 待ちなさい!」
サンタクロースが止める声も今のルカには聞こえてはいなかった。
「ごめん、ごめん。スッカリ待たせたね」
「えっ? だって、今行ったばかりじゃないですか?」
「あっ、そうか。時間の感覚が違うんだった」
「えっ?」
「あっ、いや、何でも無いよ」
『絶対に助けるとは言ったものの、いったいどうしたら良いんだろうか?
強い気持ちの結びつき・・・それはどう言う事なんだろう?』
「明日花ちゃんはさっき、絵本作家になるのが夢だって言っていたよね?
どうして、絵本作家になりたいと思ったの?」
その問いに明日花の顔が一瞬曇った。
だが、俯いた顔を静かに上げるとニコッと笑顔を見せて話を始めた。
「私ね。弟がいたの。三つ違いだったわ。<空>って言うの。
空は体が弱かったから外で遊べなくて・・・だから、いつも絵本を読んでいたの。
絵本の中で色々な国に行ったり、いろんな冒険をしていたわ。
そして、私に向かってキラキラ目を輝かせて言うの。
『お姉ちゃん! これ凄いんだよ! ねぇ、知ってる?』
絵本の中の話を私に得意気に話すの。
空が夜、寝る時は良く私が絵本を読んであげた・・・」
「そっか」
ルカは返す言葉も見つけられないまま、ただ黙って聴いていた。
「でも、死んじゃったの。二年前になるわ。
私と同じ病気だったって・・・
おかしいわよね。『空のような大きな男になるように』って付けられた名前だったのに
大人にもならないうちにお空に還って行っちゃった・・・」
「・・・」
「だからね。私は空のような子供達の為に絵本を書きたかったの。
外で遊べなくたって、絵本の中でたくさん遊んでくれたらなぁ〜って。
絵本の中ではみんな平等なの。体の丈夫な子も、そうじゃない子も。
お金持ちの子も、そうじゃない家の子も、みんなみんな夢を見られるような
そんな絵本を書けたら素敵かなぁ〜なんてね」
「うん、とても素敵だと思うよ」
「ありがとう。でも、もう本当の夢になっちゃった・・・」
寂しそうに微笑む明日花の言葉にルカの胸は”何か”に強く締め付けられるようだった。
今までに経験をした事がないような切なくて苦しくてどうしようもない気持ちが
胸いっぱいに溢れてきていたのをルカは鎮める事が出来なかった。
それが”どう言う感情”なのか?
それは同情なのか? それとも初めて知った恋心だったのか?
そんな事も経験の無いルカには知る由も無かった。
ただ、切なくて、苦しくて、何処か虚しくて、何かが熱くて
何も出来ない自分が悔しくて、理不尽な運命をただ呪うもやり切れなくていた。
『でも・・・どうしたら良いんだろう?』
そんなルカの様子に気が付いたのか、明日花はルカの手を取りながら言った。
「ごめんなさい。嫌な話を聴かせちゃったわね。ごめんなさい・・・」
「い、いや・・・そんな事はないよ」
ルカは明日花の手を握り返すと答えた。
「そんな事はない。でも、僕が何とかする。きっと何とかするから!」
「ありがとう・・・その気持ちだけで十分よ。
でも、もうどうしようもないの」
「いや、そんな事は無いよ!」
「今夜は素敵なクリスマスイヴだったわ。
優しい<サンタさん>にも逢えたし、私ってラッキーよね?
ルカ、ありがとう・・・」
明日花は笑顔でそう言った。
だが、ルカはそれに答える言葉が見つけられないでいた。
「・・・」
「どうしたの? そんな哀しそうな顔はしないで。
私、今・・とても幸せなのよ」
ルカは驚いて明日花に訊いた。
「えっ? 明日花ちゃん・・・見えるの?」
「ううん、感じるの。ルカの哀しそうな顔」
「明日花ちゃん・・・」
明日花の目から大粒の涙がひと筋流れ落ちた。
「おかしいね。幸せでも涙って出るんだね」
ルカは思わず明日花を抱き締めた。
「ルカ?」
「明日花ちゃん!」
明日花を強く強く抱きしめた。
その時だった。
ルカの身体が明るく光り出すと、その不思議な光は明日花を優しく包み込んでいった。
やがて、その光は明日花の部屋の窓から外へと溢れ出した。
辺り一面が昼間のように一瞬明るくなったかと思うと
その光は静かに消えていき、何事も無かったかのように
又、辺りは夜の風景に戻っていた。
事の次第を感じ取ったサンタクロースはソリの上で立ち上がると叫んだ。
「おー、ルカ! ルカ!! 何と言う事じゃ・・・」
その時、サンタクロースの頬に冷たいものが当たった。
いつの間にか雪が降り出していたのだ。
その雪に迎えられるかのように家の煙突から微かな蛍火のような光がひとつ。
ユラユラ揺れながら空へと昇って、やがて降る雪の中に消えて行った。
十五年後。
「あっ、もしもし。明日花先生? 倉久です。
これからちょっと良いです?
前に話してた新しい編集者を連れて来てるので後程、お邪魔します。
あっ、はい。そうですね〜 三十分後くらいに。はい、お願いします」
倉久と後輩の編集者は最寄りの駅で電車を降りると駅前のケーキ屋に入った。
「あの、コレとコレ。
あっ、それからコレも。
先生はここのケーキが好物なんだ。
覚えておけよ」
ショートケーキのたくさん並んだショーケースを指差して選びながら倉久は後輩に言った。
「あっ、はい!」
「良し、じゃあ行くか」
ケーキ屋はもちろんだったが、クリスマスはまだ一か月後だと言うのに
街はすっかりクリスマスムードで華やかに飾り付けられていた。
「なんで、こんな煌びやかな中を男二人で歩かなきゃならないんだ?」
倉久がすれ違うカップルを横目で見ながら文句を言った。
「で、お前。彼女はいるのか?
編集者にクリスマスは無いからな。
覚悟しておけよ」
「良いですよ〜
どうせ、独り身なんだから仕事をしている方がマシです。
そう言う先輩はどうなんですか?」
「さっ、ここだ。着いたぞ。
ここのマンションの七階なんだ」
倉久は質問をはぐらかすように言った。
「やっぱりねぇ〜」
後輩はニヤニヤしながら呟いた。
「なんだ? 何か言ったか?」
「いえ、別に」
「お前、後でしばくぞ!」
倉久は苦笑いでそう言った。
「明日花先生、原稿の進み具合はどうですか?」
明日花の仕事部屋に入るとマフラーを外しながら倉久が尋ねた。
「ん〜 もう少しかな。
ちょっと今、スランプ」
明日花はそう言うと頭を掻いた。
「先生、頼みますよぉ〜
締め切りは来週なんですから。
そうそう!
先月号の話、とっても評判良かったですよ。
なんて言うんだろう?
読んでると温かくなるんですよね」
「どんな風に?」
意地悪く明日花が訊き返した。
「どんな風・・・そうそう!
ホンワカって言うんですか?
童心に戻れると言うか、その・・・
そう、母に読み聞かせをしてもらっているような・・・」
「はいはい、訊かない方が良かったかなぁ〜」
「いや、本当ですって!
うちの連中もみんな言ってます。
先生も知ってるでしょ? うちの編集部の山田。
あいつなんか先生の絵本が出る度に本屋で買って息子に読ませてるんですよ」
「で、あなたは?」
「えっ? ぼ、俺はその・・・まだ独身なんで・・・
でも、子供が出来たら絶対に読ませますよ!」
「うふふ。じゃ、それまでは頑張って書かなきゃ。
何十年後になるか解らないけど?」
「先生、ひどいなぁ〜
俺だって、その気になれば相手の一人や二人くらい・・・」
「いるの?」
「えぇ、ま、まぁ・・・」
「先輩」
いつまで経っても倉久が紹介をしないものだから後輩はシビレを切らして催促をした。
「おっ、すまんすまん。
先生、こいつが今度からお世話になります。三田です。
先月に総務部から文芸部に異動になって来たんですが
こいつ、編集者としてはまだまだ新米なんで
先生、ここはひとつビシビシしごいてやって下さい」
「あら、私は鬼じゃないわよ」
明日花はクスクス笑いながら言った。
「三田陽佳<みたはるか>です。よろしくお願いします」
「明日花です。こちらこそ、よろしくお願いしますね」
三田は挨拶をすると名刺を差し出した。
その名刺を受取ると明日花は三田の顔と名刺を何度も見比べていた。
「陽佳・・・これで<はるか>って読むんだ?」
「えぇ、変わってるでしょ?
名前を聴いた時は『やった〜女だ!』って喜んだんですけどね。
でも、来たらこいつでした」
倉久は三田を見ながら肘でこづいてみせた。
「先輩が勝手に間違えたんでしょ? ひどいなぁ〜」
「でも<はるか>なんて聴いたら誰だってそう思いますよね?」
倉久は明日花に同意を求めた。
だが、それには答えずに明日花はまじまじと三田を見つめると尋ねた。
「ねぇ? 何処かで会った事があるかしら?」
「いえ。でも、僕はずっと先生のファンでした」
「何処にでもある顔ですよ」
倉久がちゃちゃを入れた。
「顔は放っておいてくださいよ。
仕方ないじゃないですか、生まれた時からこの顔なんだから。
でも、先生のファンだと言うのは本当です!
先生の絵本『空がいっぱい』大好きでした。
えーっと・・
”空には雲がいっぱい
空には風がいっぱい
空にはお日様の光がいっぱい
空には鳥が飛んでいる
空には葉っぱも飛んでいく
でも
みんな仲良しだ
どれだけいっぱい詰めたいものがあっても
空はもっともっと大きい
だから
もっともっと夢を飛ばそう
たくさんたくさん空に夢を詰め込もう”
この話、ずっと好きでした。
でも、先生って<空>の話が多いですよね?
何か思い入れがあるんだろうなぁ〜って思ってました。
それは何か解らないけど・・・
上手く言えないんですけどね、先生の書く話って夢を感じるんです。
それも、とても温かな夢って気がします」
三田の話を聴いていた明日花は胸が熱くなるのを感じていた。
「ありがとう。
そこまで言ってくれた人は初めて。
嬉しい・・・ありがとう」
「いえ、そんな」
微笑む明日花と照れる三田。
「なんだぁ、この疎外感は?
えっ? 俺だけ、話に入れない?」
倉久は二人の顔を見比べながらぼやいた。
「あら、そんな事ないですよ。
遠慮なく話に入ってきたら?
遠慮なんて倉久さんらしくないわよ。ねぇ?」
明日花はそう笑いながら三田を見た。
「あっ、そうだ!
ところで、三田。
お前の夢は何だっけ?」
倉久が反撃とばかりにニヤニヤ笑いながら三田に訊いた。
「えっ? 先輩。
もう、その話は止めて下さいよぉ〜」
「あら、何?」
愉快そうに明日花が訊いた。
「いやね。こいつ、異動前の編集長面接の時に『君の夢は?』って訊かれて。
で、何て答えたと思います?
『サンタクロースです』って真面目な顔をして答えたんですよ。
普通は『ふざけた奴だ!』ってなるでしょ?
そこがうちのおかしなところで逆に編集長の『おもしろい奴だ』で異動決定ですよ。
笑っちゃいますよね? うちの編集部、大丈夫かなぁ〜?」
「もう、勘弁して下さいよ。
念願の文芸部と言う事で、ましていきなり編集長と一対一で面接ですからね。
あの時は舞い上がっちゃって頭が真っ白になってたから
何を訊かれたんだか、何を答えたんだか全然覚えていないんですから」
三田は泣きそうな顔で倉久に訴えた。
明日花はクスっと笑いながら助け船を出した。
「でも、出版社って夢を売る仕事ですものね。
まして文芸部なら、サンタさんってあながち的外れじゃないと思うわ。
少なくとも
『僕の夢はスーパーマンです』って言って編集者になった伝説の人よりはね?」
明日花は悪戯っぽく笑って言った。
「えっ? そ、そ、それは・・・」
意表を突かれて倉久の顔色が見るからに真っ赤になった。
「えっ? 何ですか? スーパーマンって?」
三田は思わず話に食いついた。
明日花は笑いながら説明を続けた。
「その誰かさんね。
倉敷の<倉>に久しいの<久>そして、健康の<健>に人間の<人>で
倉久健人<クラヒサタケト>って言うんだけど、読み替えたら<クラークケント>
つまり、スーパーマンに変身する元の人よね?」
「そ、そんな昔の話ですよ。嫌だなぁ〜」
「へぇ? 先輩ってスーパーマンだったんですか?
でも、アレって確か、新聞記者でしたよね?」
「編集者なんだから似たようなもんだろ?」
倉久は開き直ったように憮然として答えた。
「つまり、どっちもどっちですよね?
やりぃ、先輩の弱みを聴いちゃった。
これでサンタの話は無しですよ。 せ・ん・ぱ・い!」
「わ、解ったよ。だから、お前ももう忘れろよ」
「はいはい、解りました・・・あれっ?
先生? どうしたんですか?」
明日花には二人の話も途中からは聞こえていなかった。
考え込んでいたのだ。
何かが明日花の心の中で引っ掛かっていた。
『読み替えたら・・・?
<クラヒサタケト>・・・読み替えたら<クラークケント>
・・・読み替えたら?』
明日花はハッとして三田の名刺を見返した。
三田陽佳<みたはるか>
読み替えたら?
<みたはるか>・・・<みた>・・<みた>?
いや・・・<さん>・・・<さんたは・・>!?
思わず明日花は三田の顔を見た。
その瞬間、明日花は十五年前のクリスマスの夜の出来事をハッキリと思い出した。
「まさか! ううん、偶然よね・・・?」
「えっ? 先生、どうしたんですか? 何か?」
倉久は怪訝そうに尋ねた。
「あっ、ごめんなさい。なんでも無いわ」
「そうですか? それなら良いんだけど・・・」
「えぇ、大丈夫よ、ごめんなさいね。
ちょっとボーっとしちゃった」
そう言うと明日花は舌をペロッと出して自分の頭を自分でこづいた。
「あっ、先生。疲れてるところ長々とお邪魔してすいませんでした。
とりあえずは顔合わせも済んだし、今日はここで失礼します」
明日花はちょっと考えてから倉久に向かって言った。
「ねぇ、今書いている話、書き換えても良いかしら?
前の打ち合わせと違っちゃうけど」
「えっ? えぇ、まぁ・・・構いませんけど・・・
でも、時間は大丈夫なんですか?
締め切りに間に合わないと困りますよ」
「えぇ、多分」
「そんなぁ〜 多分じゃ困りますよぉ〜
こいつの初仕事になるんですから頼みます! この通り!」
倉久は両手を前で合わせると大きく頭を下げた。
普段は憎まれ口も多いが、こう見えてなかなか後輩の面倒見の良い男なのだ。
「そっか、今度からは三田さんが担当だったわね?
よし! それじゃ頑張って書くわ! 任せておいてネ」
「はい、よろしくお願いします!」
三田も大きく頭を下げた。
それから一週間後。
原稿が上がったと連絡を受けた三田は明日花の元を訪れた。
もちろん、駅前のケーキ屋で明日花の好物のケーキを買って。
「はいこれ。お待たせしました」
そう言うと明日花が三田に原稿の入った封筒を手渡した。
「あの、読ませていただいても?」
「えぇ、どうぞ。あっ、今お茶を入れるわね。
コーヒーと紅茶はどっちが良い?」
「あっ、いや。構わないで下さい」
「じゃ、コーヒーね。
私も丁度飲みたかったの。
そこに座って読んでてくれる?」
仕事場のソファを指差してそう言うと明日花は台所に入った。
明日花の心は内心ドキドキしていた。
三田があの時の<ルカ>ならアレを読めば必ず何か反応をしてくれるはず。
そう思っていた。
明日花がコーヒーカップを二つ持って仕事場に戻ると
三田は真剣な表情で原稿を読んでいた。
明日花が戻って来たのにも気が付いていないようだった。
明日花は脇から三田の前のテーブルにそっとコーヒーカップを置くと
自分はコーヒーを一口啜りながら三田の向かい側に座った。
黙々と食入るように原稿を読む三田。
その表情の変化を逃すまいとじっと三田を見つめる明日花。
やがて、三田は最後のページを読み終えると大事そうに原稿を閉じて
「フーッ」と大きなため息をついた。
そして明日花を見ると紅潮させた破顔をますます膨らませるかのように興奮して言った。
「先生! 良かったです、感動しました!
特に、あの
”サンタクロースは生まれて来れなかったたくさんの子供達の魂で出来ている。
だから子供達に幸せを与える事がサンタクロースの使命であり願いである”
こんな発想は今まで無かったですよね?
『あー、だからなんだ!』って、読んでいて震えちゃいました。
やっぱり先生はすごいです!
こんな話を誰より先に読めるなんて編集者になって良かったです」
興奮冷めやらぬといった風に三田は何度も頷いていた。
「それだけ?」
明日花の中でガッカリした気持ちがつい言葉になって漏れた。
「えっ? い、いや・・・他にももちろんあります。
例えば、サンタクロースが自分の命と引き換えに少女を・・・」
「いや、そう言う事じゃなくて」
「えっ?」
「ううん。解らなかったら良いわ」
「いや、そんな!」
三田は明らかに困惑をしていた。
それが明日花にも見てとれた。
『やっぱり、名前の並び替えなんて偶然だったんだわ。
そりゃそうよね。
あんなお伽噺みたいな話が現実にある訳はないもの。
あの夜の事はやっぱり夢だったのね・・・』
「先生?」
「・・・」
「先生?」
「えっ? あ、あぁ、ごめんなさい」
「いえ。どうされたんですか?
申し訳ありません。
ありきたりの感想しか言えなくて・・・
編集者としては失格ですよね」
「ううん。そうじゃないの。気にしないで」
そう言って笑顔を作りながらも明日花は明らかに失望を隠せなかった。
だがそれは三田の責任ではない。
ただ、自分で勝手に期待をして自分で勝手に失望しただけだったのだ。
明日花はそう思い込もうと決めた。
『奇跡なんて、そんな簡単に起こるものではない。だから奇跡なんだ』
そう自分に言い聞かせて。
「先生。ありがとうございました。
早速、これを編集部に持って帰って編集長に見せます。
あっ、先輩にも!
先輩、今は大御所先生が担当なもんで
『疲れる!』って愚痴ばっかりだったんですよ。
これを読んだらきっと元気になります」
「あらっ。倉久さん、偉くなったのね」
「副編(副編集長)です。性格は変わってませんけどね」
「ふふ。よろしく言っておいてね」
「はい。ありがとうございます」
三田は深々と頭を下げると大事そうに原稿の入った封筒を小脇に抱えて帰って行った。
その後ろ姿を見送りながら明日花はそっと呟いた。
「ルカ・・・違っても良い。夢でも良い。
私の感謝の気持ちは変わらないわ。ありがとう・・・」
「三田。お前、今夜は何か予定があるのか?」
昼の休憩から戻ると倉久に呼び止められた。
「今夜・・・ですか? えーっと、ちょっと待ってください」
三田はおもむろに手帳を開いた。
「そうですねぇ・・・えー、
今夜は駅前商工会の美人OLと某お嬢様大学生との合コンが二件入ってますね」
「何? ほ、本当か?」
「えぇ。何と言ってもクリスマスイヴですからね。
今夜は盛大になるだろうなぁ〜」
三田はわざと大仰に言いながら倉久を見るとニヤリと笑った。
「良し、解った。お前は今夜は残業だ!
合コンは任せておけ。
俺が忙しいスケジュールをやり繰りして何とかするから!」
倉久が真顔で返す。
「先輩、ダメですよ。
男の参加資格は二十代なんですから」
「何、大丈夫だ。見えるだろ?
俺だって気持ちは十分に二十代だし」
「嘘ですよ」
「何だよ、俺だってだなぁ〜 ・・・えっ?」
「う・そ・で・す!
予定なんか何も無いですよ。
先輩、一緒に残業でもします?
付き合いますよ」
三田は苦笑しながら倉久に言った。
「何だ、嘘かよ。
嫌だよ、イヴに男二人で残業なんてするくらいなら
ここから飛び降りた方がマシだぜ」
「あはは。じゃ、先輩がお亡くなりになったらケーキでもお供えしときますよ」
「うるさいよ!」
二人は顔を見合わせながら大笑いをした。
そこに三田の携帯電話が鳴った。
「あっ、明日花先生だ!」
「おっ、明日花先生からデートのお誘いかい?」
それには答えずに三田は慌てて受話ボタンを押した。
「あっ、先生。先日はありがとうございました。
編集部でも大評判でした・・・えっ?
あっ、はい。・・・はい。
えぇ、大丈夫だと思います。
はい・・・はい・・・はい、解りました。
無理をしないで下さい。こっちは何とかしますから。
・・・はい、・・・はい、お大事に」
「どうした?」
「あっ、いや・・・実は明日花先生が昨日から熱で寝込んでいるそうなんですよ。
それで明日の締め切りを延ばしてくれないかって」
「それで?」
「いや、二〜三日なら大丈夫ですから」
「バーカ! そうじゃないだろ?
先生の具合だよ!
とっとと先生の所に行って確認して来い!
それが編集者の勤めだろうが!」
「あっ、は、はい」
「あっ、途中で薬も買って持って行けよ」
「あの・・・ケーキは?」
「お前、バカか? 当然だろ?
必ず買って行けよ。イヴなんだからな」
倉久はそう言うと笑って三田の背中をポンと叩いた。
三田は明日花の仕事場のマンションに着くとインターフォンを鳴らした。
だが、返答は無かった。
「おかしいなぁ〜」
もう一度インターフォンを鳴らそうとした時、チェーンロックの掛かったドアが少し開いた。
「三田さん! どうしたの?」
パジャマにガウンを羽織った姿の明日花が驚いた顔でドアを開けると三田を玄関先に招き入れた。
明日花の額には熱冷まし用の大きな冷却シートがしっかり貼られていて前髪は逆立っていた。
それに気が付いたのか
明日花は慌てて額の冷却シートを剥がすと後ろ手にそれを隠して前髪を指で何度も直した。
「ごめんなさい、変な顔をしっかり見られちゃったね。
でも、どうしたの?」
「いや、そんな事無いです。
あの、寝込んでいると聞いたものですから、ちょっと。
先生、大丈夫ですか?」
「えぇ、まぁ。熱はまだあるけど少し寝ていれば大丈夫だと思うわ。
とりあえず、入って。ここは寒いわ」
「はい。じゃ、少しだけ失礼します」
三田は明日花の後をついて居間に入った。
「散らかっててごめんなさい。
その辺に座ってて。
今、コーヒーでも入れるわ」
「いえ、そんな! 大丈夫です。構わないで寝ていて下さい」
明日花はじっと三田を見た。
その視線に気が付いた三田は顔を赤らめると頭を掻いた。
「そうですよね。恋人でもない男が部屋にいたら安心して寝てられないですよね。
すいません、すぐに失礼します」
「ふふ」
「あっ、先生。これ・・・解熱剤です。
それから総合感冒薬、漢方の咳止め薬でしょ。
喉飴に・・・そうそう、栄養ドリンクも買って来ました!」
「あらあら。私って相当な重病人みたいね」
明日花はクスっと笑った。
「あれ? おかしかったですか?」
「ううん。嬉しいわ」
「あっ、そうだ! ケーキも買って来ました。
イヴですから・・・あっでも、今は・・・食べられませんよね?
置いておきますから後で食べて下さい」
「やっぱりコーヒーを入れるわね。
一緒に食べましょ」
「いや、そんな」
「なぁに? イヴの夜に重病人に独りでケーキを食べろって言う気?」
「い、いや・・・」
「きっと私、余計に寂しくなって死にたくなるわ。孤独死かぁ・・・」
明日花は胸の前で指を組むと、三田をチラッと見てから大袈裟に十字を切った。
「もう、先生!」
「あはは、冗談よ、冗談」
明日花はそう言うと悪戯っぽくウインクをしてみせた。
「もう、からかわないで下さいよぉ〜」
「そうだ、せっかくだからせめてムードだけでもクリスマスっぽくしましょ」
そう言うと明日花は台所に行き、戻った手には赤いローソクの立てられた燭台を持っていた。
「どう? らしいでしょ?」
明日花はテーブルを挟んで三田と向かい合わせに座った。
テーブルの上には二つのコーヒーカップと二つのショートケーキ。
そして、テーブルの真ん中には燭台。
明日花はろうそくに火を点けるとリモコンで部屋の明かりを消した。
ろうそくの火が部屋の真ん中を柔らかく浮かび上がらせていた。
時々、ろうそくの火が微かに揺れていたのは
それは二人の息遣いそのものだったろう。
三田はドキドキしながら、ろうそくの火を見つめていた。
いや、その火の向こう側にいる明日花を見つめていた。
「わー、ロマンチック〜
うふふ。何だかドキドキするね。
額の大きな冷却シートと爆発頭を見られた後じゃ興醒めでしょうけど?」
「い、いや。そんな事は無いです!」
三田はムキになって否定をした。
明日花は少し微笑むと顔の前で手を合わせた。
「さっ、食べよ。いただきま・・・」
言いかけた途中で明日花はテーブルにそのまま突っ伏した。
「先生!」
慌てて三田は明日花の元に駆け寄ると明日花の額に手を当てた。
すごい熱だった。
「先生! 大丈夫ですか?
しっかりして下さい! 先生!
あっ、そうだ救急車を呼ばなきゃ!」
三田が携帯を取り出すと明日花は震える手でそれを止めた。
「先生、ダメですよ!
今、救急車を呼びますから!」
「だい・・じょうぶ・・・」
苦しそうな表情をしながらも明日花はようやくの体で答えた。
「大丈夫じゃないですよぉ」
三田は明日花をそっと抱きかかえるとベッドに優しく寝かせた。
明日花はうなされてでもいるかのように苦しそうに大きな荒い息をしていた。
「やっぱり、救急車を・・・」
三田が言いかけると明日花は半分起き上がりながら三田の首に手を回した。
「ルカ・・・」
「えっ?」
「ルカ・・・やっと、逢えたね・・・」
「先生?」
荒い息をしながらも明日花は必死に三田にしがみついていた。
「先生!」
思わず三田も明日花をかばうように抱き締めた。
「ルカ・・・」
「ルカ・・・? 誰だ・・・? 何処かで聞いた・・・事が・・・」
その瞬間、三田は全てを思い出した。
あのクリスマスの夜。
ルカがサンタクロースとして最初で最後に贈ったプレゼント。
それは、ルカだった自分が自分の命と引き換えに明日花に与えた”生命”だった。
ルカの身体を構成していた無数の子供達の魂がひとつになって明日花の身体に宿り
明日花の魂と同化した時、身体にみなぎった”新しい魂”は
明日花の身体中を駆け巡り病気と言う病気を残らず消滅させていった。
そして、イヴが明けたクリスマスの朝に明日花が目覚めると身体は健康体に戻っていたのだ。
後日、明日花を診察した医者は驚きを隠さずに言った。
「奇跡です!」
その時、ルカの身体に最後に残ったひとつの魂。
それはルカ自身だった。
ルカも又、生まれて来れなかった子供の一人だったのだ。
だが、たったひとつの魂だけではルカの身体は支えられるはずもなく
ルカの身体も又、同時に消滅をしたのだが
その魂は天に導かれるように空へと還って行ったのだ。
神様は還って来たルカの魂を慈しみをもって慰めると、
しばらくの休息の後でその魂に再び新しい”生命”を与えた。
しかし、どの時代のどの場所に生まれるかはルカには知る由も無かったのだが
生まれ変わる前に神様はルカに言った。
「生まれ変わる先は強い縁に拠って導かれるであろう」と。
翌朝、明日花が目覚めると三田は明日花の右手を両手で握ったまま
明日花のベッドにもたれ掛るようになって眠っていた。
「えっ? どうして、三田さんが?
あっ、そうか・・・」
明日花は昨夜の事を思い出した。
「それじゃ、三田さんはずっと私の看病を?」
明日花は胸の奥が温かくなるのを感じた。
しかし、それは熱のせいではなかった。
熱はすっかり引いていたのだ。
「それにしても又、あの夢・・・
三田さんが現れてから良く見るようになったけど、本当に関係ないのかなぁ。
三田さん。ねぇ、どうなの?」
明日花は眠っている三田を見ながら呟いた。
それから三田を起こさないようにそっと手を解くとベッドから起き上がり
三田の背中に自分の毛布を優しくかけた。
明日花が台所でコーヒーを入れていると寝室でドタドタ走り回っている三田の声がした。
「先生! 何処ですか? 先生?」
「こっちよ」
そう言いながら明日花が居間に戻ると
慌てた形相の三田が寝起きのはねた髪で息を切らせて立ちすくんでいた。
「どうしたの? あらぁ、髪の毛が爆発してるわよ。
どうやら寝癖は私と良い勝負ね。これでアイコだわ」
明日花は楽しそうに笑った。
「先生〜 もう、何処かに行っちゃったかと思いましたよ」
へなへなと三田はその場に座り込んだ。
「行かないわ。だから、あなたももう何処にも行かないで」
「えっ?」
「うふふ。何でもない。さっ、コーヒーが入ったわ。冷めないうちにどうぞ」
明日花は思っていた。
三田がルカなのかどうかは、もうどうでも良い。
でも、これから大事な人になっていくであろう予感。
それは大切にしていきたいと。