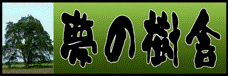聖夜と天使と赤いバラ
〜 Fantasy of ten red roses 〜
「花はいかがですか?」
そう言って声をかけてきたのは
小学校の2〜3年生くらいだろうか?
目がクリッとしていてショートカットのクセ毛が可愛い少女だった。
「花はいかがですか?
きっと、良い事がありますよ」
少女は大人びた言い方でまたそう言うとニコッと微笑んだ。
こっちを真っ直ぐ見るその瞳は
奇妙なほど慈愛に満ちているようにも見えた。
だが、今は夜の8時を既に回っている時間だ。
しかも、今夜はクリスマス。
クリスマスに花売り娘とかマッチ売りの少女と言うと
まるで外国の絵本の中の話のようだが
目の前にいるのは紛れもない花売りの少女だ。
ただ、そんな薄幸そうにも見えないし
身なりだって、そんなにみすぼらしい服装でもない。
暖かそうな赤いケープの中には白いセーター
手袋もはめていれば、ちゃんと内側に起毛のある長靴も履いている。
だが、どう考えても小学生がバイトをしている時間ではない。
いや、そもそも小学生でバイトと言うのも変な話だがきっと家業が花屋なんだろう。
それにしても、いくらクリスマスとは言え
こんな時間まで小学生を働かせると言うのはいったいどういう親なんだろう?
「ねぇ、お嬢ちゃん?
どうしてこんな時間にここで花を売っているんだい?
お父さんかお母さんに売らされてるの?」
少女はニコニコしたまま何も答えない。
「そっか、きっと親に口止めされてるんだね?
可哀想に・・・
ねぇ、後何本売ったら家に帰れるの?」
「これ」
そう言うと少女は透明なセロハンに包んだ10本の赤いバラを差し出した。
「お兄さんにあげる」
「えっ?」
「これを持ってると良い事がありますよ」
「いかがですか?」と言われて今度は「あげる」と言われると
何だか不安になってくる。
こんな少女相手に何か裏があるんじゃないかと思ってしまうのは
俺もかなり世の中に擦れてきたって事だろうか?
「あげるってね・・・
そうはいかないよ。
君は売らなきゃ帰れないんだろう?」
「良いの。 これ、お兄さんにあげる」
これはもしかしたら新手の商売なんだろうか?
客の同情を引いて
いくらかでもお金を貰えたら儲けものってかい?
「でも、タダって訳にはいかないよ。
貰う理由は無いもの」
「お兄さん、優しそうだから」
親に”カモ”を見つけたらそう言えって言われているのだろうか?
「いや、でもね・・・
分かったよ。 じゃ、こうしよう。
いいかい? お金はちゃんと払うからさ。
そしたら、すぐ家に帰るんだよ。 良いね?」
「いらない」
「いや、だからそう言う訳にはいかないよ。
本当はいくらなの?」
「・・・」
「困ったなぁ〜」
「うふ、本当に優しいのね」
小学校2〜3年生の子に優しいと言われても嬉しくはないけど
そう言って微笑んだ少女はまるでいっぱしの大人の女性のようだった。
「じゃ、これ。 素敵なクリスマスになりますように」
そう言って少女は俺に10本のバラの花束を押し付けるように手渡すと
手を振って人波の中に消えて行った。
「何だこれ?」
俺は呆気に取られたまましばし少女の走って行った方向を見ていた。
考えてみたら毎朝、毎晩ここを通っているけど
あんな子が花を売っているなんて見た事が無かった。
クリスマスだから?
そう言えばそうなのかも知れない。
「何だか不思議な子だったな。
もしかしたら、本当に良い事があるかもなぁ〜」
今年は本当についていなかった。
バレンタインデーには3年付き合っていた彼女と別れるはめになったし
ゴールデンウイークの直前には10年勤めた会社が倒産した。
その後、何とか今の会社に採用はされたものの
お盆には墓参りの帰りに事故を起こしたし・・・
「そう言えば、今年は何かイベントがある度に災難が襲ってきたよなぁ〜
って、事は・・・クリスマス!?
おいおい、止めてくれよな。
・・・何にも無きゃ良いけど」
そう独り事を呟いて思わず苦笑してしまった。
「まぁ、良いか。
それにしてもクリスマスの夜に30過ぎの独身男と赤いバラね〜
似合わない組み合わせだな。
さて、どうする?
あぁ、そうだ! 『セイント』に土産で持って行くか。
いつも世話になってるし、たまには良いかな。
マスターがビックリしそうだけど」
行きつけのバー『セイント』のマスターの驚く顔を想像して
ニヤニヤしながら歩き出した時だった。
「キャッ!」
「あっ、ごめん!」
誰かとぶつかったと思ったら足元に赤いコートの若い女性が倒れていた。
「だ、大丈夫ですか?」
「えぇ、ごめんなさい。 考え事をして歩いていたものだから・・・」
立ちあがって、コートの裾を払いながらその女性は言った。
軽くウェーブのかかった長い髪の似合うなかなかの美人だ。
「いやいや、こちらこそ。 大丈夫ですか?」
私が訊くのにも答えず、その女性は呟いた。
「あぁ〜ん、もう。 信じられない!」
足元を見ると倒れた時に彼女の下敷きになったのか
大きな包装紙に包まれたキレイな花束が見るも無残に散らかっていた。
「あぁ、どうしよう・・・」
「大変! あのぉ、すぐに弁償しますから」
「えっ? あぁ、嫌だ、私ったら。 ごめんなさい、違うんです」
「えっ、でも・・・ 俺もぼんやりしてたし。 弁償します」
「いや、良いんです。 どうせ行こうかどうするか迷っていたし。
これで踏ん切りがつきました」
そう言いながら、彼女は地面に散らばった花を拾い始めた。
「あっ、手伝います。
でもこれ・・・せっかくの花なのにダメになっちゃいましたね」
「そうね・・・でも、きっと・・・そう言う事なんだわ」
「あのぉ・・・良く事情は分かりませんが、これじゃ代わりになりませんか?」
「えっ?」
そう言って俺はさっきもらったバラを差し出した。
「これ、たった10本しか無いんですけど」
「まぁ、キレイなバラ!」
「えぇ、今もらったばかりなんですよ。 そこで、花売りの少女から」
「花売りの少女? 今の時代、そんな少女がいるんですか?
しかも、もらったって・・・
もしかして、私に気を遣って、そう言ってくれてるんじゃありません?」
「いやいや、違いますよ。 本当なんです。
目がこうクリッとしていて、ショートカットで少しクセ毛っぽい感じの
小学校2〜3年生くらいの可愛い女の子だったんです。
『花はいかがですか?』って声をかけられたんだけど
結局、いつの間にか『あげる』になっちゃって。
俺も何が何だか良く分からないんですよねぇ〜」
俺がそう言うと彼女はクスッと笑いながら言った。
「もしかして、クリスマスだし、天使だったんじゃないですか?」
「天使?」
「えぇ、だって、クリスマスに花売りの少女なんて出来過ぎた話ですよ」
「ですよね? 俺も最初はそう思ったんだけど。
花売りだ、マッチ売りだって、いくらクリスマスとは言え
絵本の中の話だろうって。 でも、そこにいたんですよ」
「変ねぇ〜 私も、花を買いに行く前に、さっきここを通ったのに
そんな子は見かけなかったわ」
「多分、何処かから場所を変えて来たのかも知れません。
それとも、売れ残りを処分したかっただけかも」
「でも、本当に天使だったかもって思ってた方が何か楽しくないですか?
もしかしたら天使の祝福だったのかも知れませんよ」
「あはは、天使の祝福ね。
本当にそうなら嬉しいんだけどね〜」
「きっと、そうですよ!」
「そっかぁ〜 じゃ、信じてみますか」
二人は顔を見合わせて笑った。
「あっ、そうだ、これ! これ、どうぞ。 持って行ってください。
何処かに行く途中だったんでしょ?」
「あっ、忘れてた!」
そう言うと、彼女はペロッと舌を出して笑った。
「でも、何だかもう行かなくても良いかな・・・」
「どうしたんです? 待ち合わせだったんじゃないですか?
デートとか?」
「あっ、違います! そんなんじゃないんですけど・・・」
「ごめん、何か立ち入った事だったかな?」
「ううん、そんなんじゃないです。 会社の女子会なんですよね。
それもお局様の号令で。 みんな陰では文句を言っているんだけど、
でも、断れないんですよね」
「それなら尚更行った方が良いですよ。
一人だけ行かなかったら仲間外れになっちゃいますよ。
今日で会社を辞めるつもりなら行かなくても良いけどね」
「あはっ、そうですね。 でも、仕事は好きだし、
こんな事では辞めたくないなぁ〜」
「でしょ? なら、行った方が良いですよ」
「そうね。 でも、本当にこのバラをもらって良いんですか?」
「えぇ、10本じゃ、この花束の代りにはならないかも知れないけど。
それに、どうせ薄暗いバーで
タバコとお酒の匂いにまみれるところだったんだから
少なくとも女性に囲まれている方がバラも嬉しいでしょ?」
「あはは、面白い言い方ね」
「文学的でしょ?」
「え〜 それはどうかな?」
彼女がそう言うと、また二人で大笑いをした。
考えたら、こんなに笑ったのも久しぶりな気がした。
それも初めて会ったばかりの女性と
こんなにも打ち解けて笑えるなんて言うのは
33年の人生でも初めてだったと思う。
「それじゃ、遠慮なく」
「うん、楽しいパーティをね・・・って、楽しくないんだっけ?(笑)」
「はい、どうせなら割り勘負けしないくらい楽しんできま〜っす」
「あはは、そうだね。 行ってらっしゃい」
「はい! 行ってきます!」
そう言うと、彼女はちょっと悪戯っぽい笑顔で敬礼をしてみせて
それから深々とお辞儀をした。
「本当に、ありがとうございます」
「うん」
俺も笑顔で彼女に手を振った。
すると行きかけた彼女が振り返るとこう言った。
「あのぉ、これからバーで待ち合わせですか?」
「えっ? いや、そんなじゃないよ。
こんな夜に独りで部屋に居てもつまらないからさ。
それなら、行きつけの店で時間を潰そうかと思ってね。
そこのマスターって元は神父なんだけど
ちょっと面白い人でね。
店の名前も『セイント』って言うんだ。
こんな夜にはふさわしいでしょ?(笑)」
「元神父さんのお店が『セイント』ですか?
何だか面白そうですね。
あの、私も後で行って良いですか?」
「えっ? そりゃ、かまわないけど」
「何時までいます?」
「そうだなぁ〜 12時を過ぎる頃までは確実かな。
クリスマスの夜にシンデレラじゃないけど(笑)」
「うふふ、分かりました。
じゃ、それまでには絶対行きます!
あっ、そうだ! 場所は何処ですか?」
「この先を2丁ばかり行くと左手にコンビニがあるんだけど
そこを過ぎた道を左に曲がった先のビルの地下なんだ。
そうそう、これ。 そこの店のマッチなんだけど」
「了解です! じゃ、後で。 きっと行きますね」
そう言うと彼女は小走りで駆けて行った。
「メリークリスマス!」
そう言いながら『セイント』に入って行くと
案の定、マスターが独りで退屈そうにパイプをくゆらせていた。
5年以上ここに通っているけどマスターの名前は知らない。
歳の頃なら50歳を少し過ぎたくらいだろうか。
髪は少し白髪交じりの長い髪を後ろで束ねている。
日本人にしては彫りが深く、通った鼻筋。
髪の毛とは対照的に
キレイに揃えた口髭と顎鬚がまさに聖者の趣を添えていた。
教科書で見たイエス・キリストはこんな感じだったかも知れない。
マスターが昔はかなりモテたであろう事は想像に難くない。
でも、マスターからそんな自慢話は聞いた事が無いし
何しろ自分の事はほとんど語らない。
訊いても、いつも笑って誤魔化していた。
確かに、人には語りたくない事もあるのだし
俺も無理には訊こうとはしてこなかった。
でも、マスターは人に話しをさせるのは商売柄以上に上手いと思っていた。
俺も大概には強がり屋で他人には弱い所を見せたくはないと思っている。
弱い所を見せたくないと言うより・・・
相手に余計な心配をさせてしまうのが嫌なのだ。
そう言う性分。
だから、逆に他人には壁を作っているって思われるタイプだろう。
それは自分でも分かってはいるんだけどね。
だけど、なんでだろう?
マスター相手にならどんな愚痴も悩み事も自然に言えてしまう。
その辺も元神父たる所以なのかも知れない。
「おや、まっちゃん。 いらっしゃい。
こんな夜にまでここに来るとはあんたも寂しい人なんだね?」
「いやいや、マスターほどじゃないんだけどね。
クリスマスだしさ。 言って見ればこれも慈善の心みたいなもんかな」
「慈善の心?」
「でしょ? 今にも潰れそうなこの店の為に少しでも援助になればってさ」
「潰れそう? 冗談じゃない。
こう見えてもさっきまではお客も満杯でね。
今やっと、お客も引いてやれやれとホッとしてたところなんですよ」
「へぇ、それにしては随分カウンターも片付いてるよね?」
「キレイ好きですからね」
と、マスターは澄まし顔で言った。
そして、ニヤッと笑うと俺の方に顔を近づけてこう言った。
「で、どうしたの? せっかくの夜にデートも無いのかい?」
「いや、待ち合わせなんだ。 まだ少し時間があるんだけどね」
「ほぉ、まっちゃんもついに彼女が出来たのかい?
今夜は大雪にならなきゃ良いけど」
そう言いながら
マスターはカウンターの端から外を見る仕草をした。
もちろん、ここは地下だし店には窓なんか無いんだけど。
「失礼だなぁ〜 俺にだって彼女の一人や二人はいますよ」
「ほぉ、それにしちゃ、ここには連れて来て無かったよね?」
「そりゃ、スケベなマスターに見せたらアウトだからね」
「何を人聞きの悪い。 こうみえても昔は神父だったんですよ。
見習いだったけど(笑)
だから、そんな人の彼女まで取りませんって。
で、その彼女さんとやらとは何時に待ち合わせなの?」
「用事が終わってから来るって言ってたから遅くなると思うけど」
「来る? 何処に?」
「ここに」
「ここ? あれ? あれれ?
さっき、スケベなマスターにどうたら言って無かったっけ?」
「今夜は特別ですよ。
クリスマスだし、なんと言ってもここは『セイント』だし」
「ほう、それじゃ私も神父の格好でもしてた方が良いかな?
なんならここで結婚式でもしちゃいますか?」
「あはは、それはまだ気が早いよ」
「それはそうと、名前は何て言うの?」
「名前?」
「えぇ、彼女さんの」
しまった! 名前を訊くのを忘れてた!
「えーっと・・・」
「あれ? どうしたの? まさか、名前を知らないなんて・・・」
「・・・」
「マジ?(笑)」
「いや、でも待ち合わせは本当なんだよ。
実はさっきね・・・」
俺はマスターに花売りの少女の事。
それから彼女との事を正直に話した。
「へぇ、面白いね。 花売りの天使がくれた恋ってやつかな?」
「あはは、そうなら良いんだけどね〜」
「それにしても、相変わらずまっちゃんは人が良いね。
なのにどうして彼女が出来ないんだろう?
今の女性は男を見る目がないよね?」
「ホントだよね〜(笑)
あっ、これ・・・
例の花束なんだけどさ。
そんなこんなでだいぶよれちゃってるけど
使える花だけでも使わない?」
「どれ・・・? うん、まだ使えるのもけっこうありそうだね。
じゃ、遠慮無くもらって飾らせてもらうよ」
そう言うと、マスターは花束を開いて花を選り分け始めた。
「うん、いけるよ。
どう、こんな感じで?」
マスターは手際よく花を数本選り分けると
深いグリーンのガラスの花瓶に花を挿した。
「ごめんね。 今度はちゃんとしたのを買ってくるよ」
「いやいや、気にしなくって良いよ。
でも、こんなサプライズも
なんか、クリスマスっぽくて良いね」
「でも、彼女は本当に来るのかなぁ〜?」
「信じる者は救われる・・・ってね」
「あはは、出たね? 得意のフレーズ」
「こう見えても、元は神父様ですからね」
と、どや顔のポーズ。
「自分で”様”って言う?」
「ダメかい?」
「いや、良いけどさ。
そういや、一度訊こうと思ってたんだけど
なんで神父になったの?」
「あぁ、昔の話だけどね。
実はなりたくてなった訳じゃないんだよね」
「うん」
「若い頃は怖いもの知らずでさ。
バイトして金を貯めては
世界中を貧乏旅行してたんだよ。
あっちこっち、色んな所に行ったなぁ〜」
「へぇ〜」
「色んな街で色んなものを見たり、現地の人に触れたりしてさ。
けっこう、色んな人と友達になって
内緒で向こうでバイトさせてもらったり
寝る場所を借りたりしながら旅行を続けてたんだ。
で、ある時、西アジアのある国に行ってた時に
泊めてもらえる場所が無くて野宿してたんだけどね。
目が覚めたら、あらビックリ!(笑)
リュックから何からみんな盗られててね」
「え〜? 笑ってる場合じゃないっしょ? それで?」
「うん。 まぁ、それでも若かったからさ。
まぁ、命が助かっただけ儲けものみたいに思って
何とかなるさって能天気に考えてね。
それで、とりあえずは
何処か近くの街に行ってバイトでも探そうと思ったんだけど
丁度そこは内戦があったりで結構荒れててね
働こうにもそんな場所もなくてさ。
ほら、こっちは何処の馬の骨とも分からない日本人でしょ。
向こうには他に日本人なんかいなかったしさ」
「うん。 それでどうしたの?」
「で、さすがの俺も困り果ててさ。
ぶらぶら歩き回って腹も減ってきたし
どうしようかって思った時に教会を見つけてね。
で、何か食べさせて貰えないかって行ったんだよ。
そしたら、無愛想なおっさんが出てきてさ」
「うん」
「言葉が通じないから。 俺もカタカナ英語くらいしか喋れなかったし。
で、必死に身振り手振りで『腹が減ってる』ってね(笑)」
「どんな風にしたのさ?」
「いや、ここでやれったってもう出来ないよ(笑)」
「あはは」
「でも、とにかく必死でやった訳」
「そりゃ、見てみたかったな(笑)」
「よせよ。 本当に必死だったんだから。
生きるか死ぬかみたいなさ」
「で?」
「そしたら、その無愛想なおっさんが『来い』みたいに
俺を教会の中に招き入れてくれてさ。
で、ちっとも美味くないパンとスープを食べさせてくれたんだ」
「あはは、そんなに美味くなかったの?」
「あぁ、もう二度と食べたくないね。
でも・・・美味かったなぁ〜」
「何それ?(笑)」
「とりあえず、金も無いし、寝る場所も無かったから。
何でも良いから働かせてくれって
これまた、身振り手振りでね」
「一宿一飯の恩義ってやつだね?」
「そうだね。 結局そのまま下働きみたいな事をやって
半年くらい経った時
その無愛想なおっさんがさ。
『お前、神父やってみないか?』みたいなね」
「え〜 そんな簡単で良いの?」
「まぁ、普通はダメだよ。ちゃんと勉強をしないとさ。
でも、その国自体が政情も何も不安定な国でさ。
新しい神父が来てもすぐに帰っちゃうような状況だったらしい。
だから、手伝ってくれるなら誰でも良かったんじゃないかな」
「へぇ〜 面白いね」
「でも、こっちは聖書なんか読んだ事もないしさ。
もちろん、言葉だってそんなに分からないときてる。
だけど、そのおっさんが全部用立ててくれて。
まぁ、神父見習いみたいな事をやりながら
そのおっさんと3年くらいその教会を拠点に一緒に各地を回ったんだよ。
おっさんが忙しい時は
これでも信者相手にいっぱしに説教なんかしたりしてさ」
「うん。 それで?」
「で、3年くらい経った頃。
そのおっさんが家族の都合で国に帰る事になってさ。
それで俺も日本に帰って来たんだ」
「その”おっさん”はその後どうしたか知ってるの?」
「あぁ、何でも国に帰って今じゃ大きな教会の牧師になってるらしいよ。
帰国して1年くらい経った頃、一度手紙が来たんだ。
写真付きでね。 ほら、あれさ」
そう言ってマスターは壁に貼ってあった
一枚の古ぼけた写真を指差した。
そこには穏やかな笑顔の恰幅の良い紳士と優しそうな女性。
それから、産まれたばかりだろうか。
その女性はおくるみに包んだ赤ちゃんを抱いていた。
「この人が? 全然無愛想そうじゃないじゃん?」
「あぁ、とっても良い人だったよ。
俺が今、こうしていられるのもこの人のお陰さ。
でも、最初に会った時は本当に無愛想だったんだ。
無愛想と言うよりは・・・
そうだな。その国が国だっただけに、そうならざるを得なかったのかもね。
何度も命を落としそうになったって言ってた。
貧しい国の人が相手だから、いくら親身になって相談に乗ったり
いくらほどこしを与えても、信心深い人ばかりじゃなかっただろうし
何度も裏切られたみたいだったからね」
「うん・・・神父さんだって人間だもんね。
だんだんそうなったっておかしくないかもね」
その”おっさん”の人生を思い浮かべようとしたけど
平和ボケした日本でノホホンと暮らしてる俺には思い浮かぶはずもなかった。
穏やかな笑顔に刻まれた顔の皺がきっと全てを知っているんだろう。
「あっ、でもさ。 最初は神父さんって言ってたよね?
それがなんで今は牧師さんなの?」
それって、何が違うんだっけ?」
「プロテスタントとかカトリックって聞いた事があるだろ?
一般的には旧教と新教とか言われてるんだけどね」
「うん」
「ちなみに、カトリックの教会では神父って言うんだけど
プロテスタントの教会は牧師なんだ」
「へぇ、そうなんだ?」
「元々、おっさんの親父さんって人が牧師だったんだけど
お決まりの反抗みたいな時期があったらしくってね。
それで、家を飛び出して神学校だかに通って神父の道を目指したんだって」
「えっ? それって同じ教会でしょ?」
「そうなんだけど、カトリックとプロテスタントって違うんだよ。
言って見れば、親への当てつけみたいなもんだったって言ってたけどね。
ともあれ、勉強した後で神父になって各地を回ったらしいんだけどさ。
そうこうしている内に、親父さんが倒れてね。
それで国に戻ったんだけど、それで色々あったんじゃないかな。
結局、親父さんが牧師をやっていた教会で跡を継いだみたいだね」
「でも、親に反抗した割には
やっぱり神様に使える仕事に就いてるって言うのが面白いね。
蛙の子は蛙って事かな?
あれ? でも、牧師さんって結婚は出来るの?」
「あぁ、カトリックは基本的には独身じゃないとダメなんだけど
プロテスタントは結婚出来るんだよ。
だから、多分親の教会を継いだ後で結婚したんじゃないかな」
「なるほどね〜」
「ちなみに言うとね。 聖者とか聖人って言うだろ?
あれはカトリックなんだよ。 プロテスタントにはいないんだ」
「へぇ〜 じゃ、サンタクロースの元になった・・・何だっけ?
そうそう! 聖ニコラウスだっけ? その人もカトリックだったの?」
「ん〜 それは難しい質問だね。
そもそもは伝説とか語り継がれた話が世界各地を巡っているうちに
形を変えていって、だんだんと今のサンタクロースになったみたいだから
厳密にカトリックだったかどうかは分からないな。
ロシア正教会なんかでも12月25日では無いけど
12月19日を聖ニコラウスの祭日としてたりするしさ。
もっとも、採用している暦が”ユリウス暦”で
今の暦で言えば1カ月くらいずれているとも言われてるんだけど」
「う〜ん、ダメだ! 酔っ払って腐った頭じゃ理解出来ない!」
「あはは。 まぁ、キリスト教にも色々あるって事だよ。
今はサンタクロースはクリスチャンだけのものじゃないからね(笑)」
「確かにね(笑) 俺なんかも、正月は神社に初詣に行くし
お盆には墓参りに行くし、クリスマスだって人並みには祝いたいしね」
「日本人は特に宗教に関してはあまり拘りのない人が多いよね」
「あぁ〜 でも、結婚式をするならやっぱり教会が良いかなぁ〜」
「その前にまずは相手を見つけなきゃね(笑)」
「止めてよ! せめてクリスマスくらいは夢を見させてよ」
「夢って言えば、例の彼女さんって何時頃に来るんだっけ?」
「こらこら! 夢って失礼じゃない?」
「あっ、ごめん、ごめん。 ついね(笑)」
「もう! 12時までにはって言ってたけど
会社の女子会パーティって言ってたから帰らせてもらえるかどうか」
「彼女さん、来ると良いね」
「まぁね〜 まだ彼女でも何でもないけどさ」
俺がそう言うとマスターはCDデッキのCDを入れ替えて言った。
「でも、クリスマスの夜に恋人が出来たら
それこそ、ハッピークリスマスだね」
狭い店の中にジョンレノンの「Happy Xmas (War Is Over)」が静かに流れた。
それからマスターと俺は酒を飲みながら他愛もないお喋りに時間を費やした。
マスターからしたら俺なんかは儲けにならない客なんだろうけど
それでも心地良い時間を過ごさせてくれるのはマスターの人柄と言うか
やはり、元神父だったからだろうか?
見習いでも何でも、俺にしたら神父は神父だ。
「ねぇ、マスター?」
「ん? なんだい?」
「いや、独り事。 こんな儲けにならない客相手じゃ可哀想かなってね」
「あはは、何を急に愁傷な事を言ってるんだい?
まっちゃんらしくないよ」
「クリスマスだからかなぁ〜 人の温かさが沁みるんだよねぇ〜」
「ダメだ、この人(笑) まっちゃん、やっぱり早く結婚しなさいよ」
「そういや、これも訊いた事は無かったけど、マスターって奥さんは?」
「逃げられた」
「えっ?」
「儲からない客ばかり相手にしてるもんだからさ。
愛想を尽かされてね(笑)」
「いや、笑い事じゃないしょ?」
「いや、冗談だよ。 まぁ、色々とあってね」
マスターはそう言いながら
深くタバコを吸いこむとフーっと溜め息のように煙を吐き出した。
ジョンレノンのCDも曲が変わって
今、薄暗い店の中で誰かを慰めるように「Jealous Guy」が流れていた。
時計の針が12時を少し過ぎた。
彼女はまだ来ない。
マスターは俺に気を遣ってか黙ってグラスを磨いていた。
俺もあえて何も言わずに静かに流れるジョンレノンを聴いていた。
12時半を過ぎた。
『やっぱり、そう上手くはいかないかな』
そう思いながらも時計を見ながら俺は諦めきれないでいた。
「マスター、もう一杯作ってくれる?」
「いや、それはちょっと待ってからの方が良いみたいだよ」
「えっ? 何が?」
「ほらっ」
マスターが店の入り口を指差すと階段を駆け下りてくる靴音がした。
「ごめんなさ〜い!」
息を切らせて”彼女”が店のドアを開けた。
頭やコートの肩には薄らと雪がのっていた。
「あ〜ん、もう! 急に雪が降ってきて濡れちゃった。
ごめんなさい。 すっかり遅刻ですよね」
「いや、大丈夫だよ。 俺はシンデレラじゃないから(笑)」
「うふふっ」
「いらっしゃい。 さぁ、どうぞこちらへ。
人の良いお兄さんがお待ちかねでしたよ」
そう言うと笑いながら彼女を俺の隣の席に手招きした。
「人が良いのはマスターでしょ?」
「いやいや、今夜はまっちゃんに譲りますよ」
「あらっ、何の話ですか?」
そう言いながら”彼女”は赤いコートを脱ぐとイスの背もたれにかけて
それから思い出したように俺を見ると言った。
「あの、そう言えば私。 名前も言ってなかったですよね?
ごめんなさい。 親切にしてもらったのに」
「あっ、いやいや、こちらこそ」
マスターはニヤニヤしながら俺達を見ていた。
それを見たら俺も汗が出そうなくらい熱くなった。
きっとマスターには
俺の顔が赤くなっているのがシッカリ見えていたに違いない。
「私、星野麻里って言います。
恥ずかしながら、ギリギリ20代に引っ掛かってます」
「恥ずかしながらって、全然恥ずかしくないじゃん。
俺なんかもう3年前に30を突破しちゃったんだから」
「突破っておかしくないですか?(笑)」
「いやぁ〜 恥ずかしながらもなかなかだよ。
ねぇ、マスター?」
「さぁ〜 どうでしょう。
こう見えても私は痴話話に参加する程ヒマじゃないもので(笑)」
「まぁ、マスターったら」
「あはは。 そうそう、何か作りますか?」
「そうねぇ〜 今も飲まされてきたから、何か軽いものをお願いできます?」
「かしこまりました」
そう言うとマスターは棚から1本の瓶を取り出してカクテルを作り始めた。
「あっ、俺は真継聖司。 歳は・・・って、言っちゃったっけ?(笑)
写真の真に継ぐって書いて、聖書の聖に司で”たかし”」
「”まつぎ”さん? なんか、まっすぐ〜って感じで素敵ですね。
私は普通の星野に植物の麻に古里の里で”まり”です。
ホント、ありふれた名前ですよね〜」
「いえいえ、そんな事はないですよ。
クリスマスの夜に相応しい名前じゃないですか?
マリア様の”まり”ですからね。
はい、どうぞ」
そう言って、マスターはオレンジ色のグラスを麻里の前にスッと置いた。
「まぁ、きれい! でも、ただのオレンジジュースじゃないですよね?」
「はい、クリスマスですからシャンパンを使ったカクテルにしてみました。
『ミモザ』って言うんですよ」
「『ミモザ』って、確か花の名前でしたよね?」
「そうですね。もっとも、本来『ミモザ』と言う花は
豆科のオジギソウの仲間の花の事だったんですが
フサアカシアの花がそれと似ていた為に
間違ってそれが『ミモザ』として広まったそうです。
で、そのフサアカシアの花の色に似た色なので
このカクテルには『ミモザ』と付けられたと聞いています。
ちなみに、花言葉は『豊かな感受性・感じやすい心』だったと思います」
「そう言えば、『ミモザ』って、ゴスペラーズの歌にもあったよね?
あれもその花の歌なのかな?」
「あっ、そうそう! 私、好きでした!
でも、あれって女性の名前じゃないですか?
確か・・・
『誰かと比べるような 恋なんてしなくていい』
そんな出だしだったかな・・・」
そう言うと麻里は『ミモザ』のグラスを両手で包み込むようにしながら
その歌を口ずさんだ。
「♪ガラスの靴で踊るミモザ 金色の甘いキスを
連れてゆくよ君がいれば・・・mm♪」
俺はそんな麻里を黙って見ていた。
そんな俺の視線に気がついたのか、麻里は急に照れて歌うのを止めた。
「もう、あまり見ないでくださいよ〜 恥ずかしいじゃないですか」
「いや、そんなつもりじゃ・・・」
「良いね〜 若いって」
そうマスターは楽しそうにちゃちゃを入れて来た。
「若くないですよ」
二人が同時にその言葉を打ち消した。
「おや、もう息もピッタリですね?」
俺は麻里と顔を見合わせると
何だか照れるやらおかしいやらで二人してゲラゲラ笑い合った。
「そう言えば、マスターって元神父さんだったんですか?」
「えぇ、見習いだったですけどね」
「道理で・・・」
「道理でって?」
俺は麻里に訊いた。
「何かね、マスターを見た途端にイエス様かと思っちゃったんです。
一瞬、ビックリしちゃいましたよ」
「実は・・・良いですか? 誰にも内緒ですよ」
マスターは声を潜めると手を口の前にやって
他の人には聞かれないようにとでも言うように小声で言った。
もちろん、店の中には三人しかいないのではあるが。
「実は・・・私。 生まれ変わりなんですよ」
「えっ!? ホントですか?」
麻里も声を潜めてそう言った。
「えぇ・・・おじいさんのね」
マスターがそう言うと麻里は一瞬キョトンとした顔で
それから、私を見て、それからまたマスターの顔を見ると
意味が分かったのか、ゲラゲラ笑いだした。
「あはは、マスターったら〜」
「だよね。 俺にはマスターの後ろに後光は見えないもん(笑)」
俺も初めて聞くマスターのジョークだった。
「へぇ、マスターでもそう言うジョークを言うんだね?」
「クリスマスの特別サービスです。
ショーのお代は高いですけどね(笑)」
「でも、元神父って言うのは本当なんだよね?」
「えぇ、それは本当ですよ」
「何がキッカケだったんですか?」
麻里が身を乗り出して訊いた。
それからマスターは俺に話してくれた話をもう一度麻里に話した。
俺も、もう一度話を噛みしめるようにマスターの話に聴き入った。
「へぇ〜 でも、それも何か縁だったんですね」
「そうですね。 私の人生観も変わった気がします。
この神父さんのお陰でね」
そう言うと、マスターは壁の写真をしみじみと眺めた。
「この人ですか・・・何だか、優しそうな人ですね。
とても無愛想な人には見えないわ」
「えぇ、本当に優しい人です。私の恩人ですから」
「でも、クリスマスの夜にこんな素敵な話を聴けるなんて
来て、本当に良かったです」
「俺のお陰だね?」
「えー、そうでしたっけ?」
「おいおい(笑)」
「あっ、そうそう! 忘れてた!
マスター、ちょっとおトイレ借りて良いですか?」
「えぇ、そっちの奥ですよ」
「はい、すみません。 私ったらガマンをしてたのを忘れてました。
あらっ、嫌だ! こんな事を言うから
私って色気が無いっていっつも言われるんですよね」
舌をぺろっと出すと麻里はトイレの方に急ぎ足で歩いて行った。
そんな気さくな麻里を可愛いと思った。
「あはは、トイレに行くのに色気を出したってね〜」
トイレに行く麻里を目で追っていた俺は振り返るとマスターに言った。
「そう言う事じゃないですよ」
「マスター、もう! 分かってますって」
「なら良いんですけどね」
「いやだなぁ〜 俺だってね、女性のデリカシーくらいはもう分かる歳ですよ」
「ホントですか? でも、彼女、可愛いですね?
そう思ったでしょ?」
マスターはそう言うとニヤリと笑った。
まるで俺の心を見透かしているかのように。
「ねぇ、あれ!」
トイレから出て来た麻里は急ぎ足でカウンターに戻って来ると
カウンターの前のボックス席の棚を指差して言った。
「何?」
「あれ! あの天使の人形ですよ! ちょっと、来て!」
そう言うと麻里は俺の手を取ってボックス席の所に連れて行った。
「ほらっ、10本の赤いバラ!」
「あっ!」
「ねぇ? これって偶然?」
「・・・」
俺は言葉が無かった。
ボックス席の棚に飾ってあったその天使の人形は
目がクリッとしていてショートカットのクセ毛が可愛い少女の天使だった。
そして両手で抱えるように10本の赤いバラを持っていた。
「本当?」
マスターがそう訊いた。
「うん。まさにこの子・・・」
俺は納得出来なかったが、どう見てもあの花売りの少女に見えてしまう。
「ん〜」
マスターは何かを考えていた。
「でも、そんな事って有り得ないよね?」
「でも、あったら素敵ですよね」
そう麻里は目を輝かせて言った。
「そうだけど・・・ ねぇ、マスター。 どう思う?」
「キリストは数々の奇跡を起こしてきたって言われてるからね。
この人形が長く教会に置かれていたものだとしたら
あながち、無い話ではないかな」
「この人形って例の神父さんのじゃないの?」
「神父さんのって訳でもないみたいだね。
いつからかは分からないけど、ずっとあの教会にあったんだと思う。
で、俺達が教会を引き払う事になった時
粗方のものは処分したり、別な教会に引き取ってもらったりしたんだけど
この人形だけは俺に託したいって言ってくれてね」
「この人形だけって、どう言う事なんだろう?」
「さぁ、ただ・・・あの町は必ずしも平和な町じゃなかったからね。
俺が日本に帰るなら、平和な町で過ごさせたいって思ったんじゃなかな」
「それならアメリカに持って帰っても良かったのにね」
「そうだね。
でも、神父から牧師に転身するって事が頭にあったのかもしれないな」
「そっか」
三人はまじまじとその人形を見ていた。
「でも・・・」
「ん?」
「でも、なんで俺なんだろう?」
「何が?」
「いやさ、何か奇跡を起こしてくれるなら
普通は俺じゃなくてマスターになんじゃない?
マスターはずっとこの人形を大切に飾ってる訳だしさ。
感謝をするなら俺じゃなくてマスターにでしょ?」
「そうよね〜 あっ、そう!
ねぇ? もしかして、マスターは”こっちの側”の人間だって思ってるのかも。
だって、神父さんだったんでしょ?」
「見習いだけどね」
「それでも神父さんは神父さんよ。
神父だから、見習いだからって言うよりも心持ちの問題だと思うわ」
「なるほどね」
俺は妙にその説得力のある言葉に頷いた。
「そうよ、絶対にそうよ!」
「おや、随分力を込めたね?」
マスターはそう言うと俺を見てニヤッと笑った。
「何? その意味深な笑いは?」
「いや、なんでも(笑)」
「どうしたの?」
「いや、なんでもないよ」
俺は照れて頭をしきりに掻いていた。
「あー、もしかしてアレじゃない?
ほらっ、あの時!
まっちゃんの武勇伝(笑)」
「えっ?」
「ほらっ、先々月のケンカ騒ぎ」
「えー? あれ?」
「えぇ、あれ(笑)」
「えっ、何ですか、それ?」
麻里は興味津々と言う風で身を乗り出して来た。
先々月のある夜
数人で来ていた客同士が酔っ払って店の中でケンカを始めた。
止めに入ろうとした俺を一人の酔っ払いが押しのけると
棚にあったこの天使の人形を掴んで
別の客に殴りかかろうとしていたところを
俺が寸でのところでこの人形を取り返したんだけど
その時にその酔っ払いの客を殴ってしまった事で
駆け付けた警察官に捕まり一晩留置場で過ごした事件があった。
「まっちゃんもやる時はやるもんだよね」
「いやぁ〜 生まれてこの方ケンカなんてした事はなかったんだけどさ。
でも、あの時はなんか”守らなきゃ!”って思ったんだよね」
「もしかしたら”守らなきゃ”じゃなくて
”守って!”って声が聴こえたんじゃないですか?」
「ん〜 どうだったんだろう? あまり覚えていないんだよね」
「天使の恩返しなんて素敵だわ♪」
麻里の目がまた一段と輝いた。
「天使の恩返しが10本のバラねぇ〜
なんか、らしいね」
俺も思わず笑顔になった。
「でも・・・」
麻里は真顔で言った。
「ん?」
「でも、そんな大切なバラを私にくれて良かったのかしら?
何だか、罰とか当たらないと良いんだけど」
「罰って俺に?」
「えぇ、だって聖司さんにお礼にくれたんでしょ?
それを私なんかがもらって
しかも、私はそれを自分達のパーティに持って行ったんですよ」
「いや、もしかしたら『わらしべ長者』かも知れないよ」
そう言うとマスターは一人でニヤニヤしている。
「わらしべ長者? マスター、どう言う事?」
「さぁね。 自分で考えたら?」
「そんな事を言ったって・・・」
「人の良いまっちゃんは自分の事になるとからっきしなんだね。
まっちゃんらしくて良いけどさ」
「マスター、どう言う事よ?」
「あっ!」
麻里は”それ”に気付いたらしく
見ると頬を赤らめていた。
「何? どうしたの?」
「・・・」
「おや、麻里さんは気がついたかな?(笑)」
「えっ? 何? どう言う事?」
「まっちゃん、『わらしべ長者』の話ってどんなだっけ?」
「うん。 確か、最初に持っていたわらを次々と別なモノに交換していくうちに
最後はお金持ちになったって話でしょ?」
「そうだね」
「それがどうして俺なの?」
「まっちゃんは天使からご褒美に10本の赤いバラをもらいました」
小学校の生徒に勉強を教える先生のような口調でマスターは続けた。
「さて、その10本のバラは今、何に変わってるでしょう?」
「何に・・・?」
「そう、何に変わってるでしょう?」
「あっ!」
俺は思わず麻里を見た。
麻里は顔を赤くしたまま俯いている。
「いくら天使だって何もキッカケが無ければ何も出来ないからね。
つまり天使はバラをくれたんじゃなくてキッカケをくれたんだよ。
まさに聖夜の奇跡って奴だね。
まぁ〜こんな奇跡でも無いと、まっちゃんに彼女が出来る事はないだろうからね」
「ひどいなぁ〜 俺だってね」
「俺だって? そう?」
「いや、確かにさ・・・否定は出来ない・・・」
「あはは」
「でも、会ったばかりなのにいきなりそんな話をされても
麻里さんだって迷惑ですよね?」
「いえ・・・でも、天使のくれた奇跡なら
そう言うのもロマンチックですよね」
「でも、聖夜の奇跡だからなぁ〜
、明日になったら『あなたは誰?』なんてね(笑)」
マスターがそう言って他人事のように笑う。
「マスター、ひどい! そんな事、ないですよぉ〜」
と、麻里が口を尖らせた。
「えっ? と、言う事は・・・良いの?」
「はい。 私で良かったら」
「もちろんだよ!」
そう、もちろんだ。
初めて麻里に会った時からきっと俺は麻里に恋をしていた。
「なんだ〜 このベタな展開は?
いくら天使の奇跡にしたってこれじゃあまりに安直だぞ(笑)」
そう言いながらマスターは二人の前にカクテルグラスを二つ。
そして同じものを自分の前にひとつ置いた。
「まぁ、キレイな赤! マスター、これはなんて言うカクテルなんですか?」
「本当はブランデーベースだと『キャロル』つまり「讃歌」って意味なんですが
今夜はクリスマスなのでシャンパンベースにアレンジしてみました。
そうですね〜 しいて言えば『セイント・オブ・キャロル』ってとこでしょうか。
今夜のお祝いに」
そして三人で乾杯をした。
きっと、今夜は忘れられない夜になるだろう。
「でも、本当にあの子はこの天使だったのかなぁ〜?」
そう言って、俺は目の前に置いた天使の人形をまじまじと見つめた。
「さてね〜 どうだろ?
でも、どっちにしたってこうして君達は出会った訳だし
何だか、いつの間にか付き合うみたいになってるんだから
それで良いんじゃない?」
「いえ、きっと天使ですよ!
だって、私。 聖司さんもマスターも今日初めて会ったなんて気がしないんです。
ずっと前からこうして会っていたような親しみやすさがあるんですよね」
「前世の縁って奴かな? そうだとしたら、やっぱり天使の縁なのかもね」
「うん、 何か、そんな話も今夜なら素直に信じられるね」
俺は神妙に頷いた。
「もしさ、君達が結婚をする事になったら
この人形を君達にプレゼントさせてもらうよ」
そう言ってマスターは俺にウインクをしてみせた。
その翌年のクリスマスイヴに
俺達は小さな教会で身内だけのささやかな結婚式を挙げた。
式を取り持つ神父はもちろんマスターだった。
本来なら正式な神父さんにお願いをしなくちゃならないのだろうけど
残念ながら俺達だって正式なクリスチャンじゃないし
何より、俺達の天使の持ち主だ。
マスターをおいて他に相応しい人はいるはずがない。
その辺を説明したら
教会の神父さんは驚くほど心良く了解をしてくれて
逆に式の補助を買って出てくれた。
これはまさに恐るべき天使の力だ。
「新郎、聖司。 汝は夫として、順境にある時も逆境にある時も、
病の時も健やかなる時も、生涯、麻里に愛と忠実を尽くすことを誓いますか?」
「はい。 誓います」
「新婦、麻里。 汝は・・・」
式が終わった後でマスターが控室に入って来た。
「どう? 疲れたろ?」
「疲れたって言うより大緊張でしたよ」
「でも、麻里さんきれいだったね」
「えぇ」
「そうそう!」
マスターはそう言うと緑色のリボンをつけた大きな箱を差し出した。
「えっ? 何ですか?」
「プレゼント。 例の奴だよ。 約束しただろ?」
「あっ、あの天使?」
「うん。 大事にしてくれよな」
「もちろん! でも、本当に良いんですか?」
「あぁ、君達のキューピッドだからね。
緑色のリボンってのも良いだろ? クリスマスっぽくてさ」
マスターは俺の肩をポンと叩くと
「じゃ、後で」
そう言って、控室を出て行った。
「麻里、あれからもう40年だね」
”あの夜”を想い出しながら
俺は暮れかけたクリスマスの街を当て所も無く歩いていた。
あの天使に見守られながらの幸せだった日々。
やがて、俺達にも娘が生まれ
そして、今はその娘も自分の幸せを見つけてこの街で暮らしている。
これからまた麻里との穏やかな幸せな日々は続いて行くはずだった。
そんな矢先の麻里の病気。
40年目のクリスマスを待つ事なく
長い闘病生活の後、先月の末に麻里は還らぬ人となった。
「ごめんね」
それが麻里の最期の言葉だった。
謝るのは俺の方なのに。
麻里を守ってやれなかった俺の方なのに。
「今度ばかりは天使の奇跡も叶わなかったな・・・」
「麻里、出来るならもう一度逢いたい。
逢って、もう一度だけこの手で抱きしめたい」
クリスマス一色の街。
あちらこちらで光の帯が、光の造作がキラキラ輝いている。
街を歩く人達はみな眩しいほどの笑顔だ。
手を繋いで歩く家族連れ。
肩を寄せて歩く恋人達。
俺は麻里と出会った夜の事。
その後、何年間も”ここ”を一緒に歩いた事。
この街で一緒に生きた事。
一緒に泣いた事。
一緒に笑った事。
そんな事を止めどもなく想い出していた。
「いかんな。 ここには想い出が有り過ぎる」
想い出に出会いたくて”ここ”まで歩いて来たけど
想い出す度に麻里のいない右側が切なくて心が千切れるくらい寂しかった。
「帰るとするか・・・ おや、雪か・・・?」
輝く星々の中を白い綿帽子がゆらゆら揺れながら落ちてくる。
「きれいだ・・・」
俺にはそれらがまるで無数の天使が舞い降りて来ているように見えた。
立ちすくんで空を見上げているとふいに後ろから声を掛けられた。
「花はいかがですか?」
そう言って声をかけてきたのは
小学校の2〜3年生くらいだろうか?
目がクリッとしていてショートカットのクセ毛が可愛い少女だった。
何処かで会った事があったような気がした。
だが、こんな小さな子に知りあいはいない。
他人の空似だろうと思った。
「花はいかがですか?
きっと、良い事がありますよ」
「良い事? さぁ、良い事なんてもう何もないさ」
「おじいさん、寂しそう・・・」
「おや、同情してくれるのかい?
お嬢ちゃん、ありがとうよ」
「これあげるわ」
そう言うと少女は10本の赤いバラを差し出した。
「いやいや、貰う訳にはいかないよ。
じゃ、こうしよう。
おじいさんが全部買ってあげるよ。
赤いバラは私の亡くなった奥さんが一番好きな花だったんだよ。
ありがとう」
そう言って財布からお金を取り出そうとすると
「相変わらず優しいのね。
でも、いらない。 素敵なイヴになりますように」
「えっ? 何処かで会った事が・・・?」
そう言いかけた俺に
少女は10本のバラの花束を押し付けるように手渡すと
手を振って人波の中に消えて行った。
「あっ、これ、お嬢ちゃん?」
俺は呆気に取られたまましばし少女の走って行った方向を見ていた。
「それにしても、不思議な子だな・・・
赤いバラ・・・これも何かの縁かな。
せっかくだ。 帰って麻里の仏前に飾らせてもらおうか・・・」
そして振り返って歩きかけた時だった。
「キャッ!」
「あっ、ごめん! だ、大丈夫ですか?」
「ふふ、相変わらずね、あなたって」
そこには昔と変わらぬ微笑みを湛えた麻里が立っていた。
俺は一瞬言葉を失った。
「ま、麻里! 本当に麻里なのか?」
「まぁ、キレイなバラ!」
それには答えずに”麻里”は10本の赤いバラを受け取ると言った。
「さぁ、あなた。 行きましょ」
「えっ? 何処へ?」
「『セイント』よ。マスターが待ってるわ」
「でも、『セイント』はもう・・・」
『セイント』のマスターも七年前に亡くなっていた。
店も今は名前も持ち主も変わってしまっていた。
それ以来”そこ”には行った事もなかった。
「そうか、そう言う事か・・・麻里、迎えに来てくれたんだね?
そうだな。一人で生きていても仕方ないしね。
よし、さぁ、行こうか」
「何を言ってるの? 変な人ねぇ〜 うふふ」
「えっ? だって、俺を迎えに来たんだろ?」
「迎えって?」
「だって・・・」
「さぁ、行きましょ」
そう言うと麻里は俺の右腕に自分の左腕を絡めて頭を持たせかけてきた。
久しぶりに”感じる”麻里の温もり。
『これは本当の出来事なんだろうか・・・?』
いや、例え夢でも良いと思った。
今ここに麻里がいてくれる。
それが夢だろうと何だろうと構わない。
「ねぇ、きれいな雪・・・」
「あぁ、本当だ・・・」
さっきまでと同じ雪が麻里と一緒だと言うだけでこんなにも違って見える。
人を愛すると言うのはきっとそう言う事なんだろう。
「ほらっ、あそこ」
麻里が指を指す方を見ると懐かしい『セイント』の看板が見えた。
「さぁ、マスターが待ってるわ」
麻里に促されて店のドアを開けた。
「おや、来たね? まっちゃん、久しぶり。元気そうだね」
あの頃と同じ聖者然の風貌で
にこやかな笑顔のマスターがそこにいた。
「メリークリスマス! さぁ、さぁ、勝手知ったる何とやらだろ?」
そう言って、マスターは”いつも”のカウンター席に手招きをした。
「マスター・・・」
「さぁ、座りましょ。 マスター、いつものお願いね」
「いや、今夜は久々にまっちゃんもいるんですから例の奴にしましょう」
「あっ、マスター特製の『キャロル』ね? 嬉しい♪」
マスターはそう言うとカクテルグラスを二つ俺と麻里の前に置いた。
あの夜、マスターが作ってくれた『セイント・オブ・キャロル』だ。
そして、同じグラスを自分も持つと
「じゃ、まっちゃんと麻里さんに乾杯」
「マスターにもね」
麻里も微笑みながら言った。
そして、あの夜と同じように三人で乾杯をした。
何もかもがあの夜のままだった。
なぜか、家に置いてあるはずの天使の人形まで
場所はボックスの棚からカウンターへと変わったけどそこに置いてあった。
ただ、ひとつだけ違った事と言えば
カウンターの上に置かれていたその天使の人形がバラを持っていなかった事だ。
「あれっ? マスター、この人形ってバラを持ってなかったっけ?
もしかして、違う人形?」
俺はマスターに訊いた。
「いや、天使の人形はこれひとつだよ」
「でも、バラは?」
「あぁ、あれね? ほらっ、そこにあるじゃない?」
「えっ?」
マスターは麻里の隣の席に置かれた10本の赤いバラを指差した。
「これ・・・?」
「あぁ、そうだよ。 天使の持っている赤いバラはね。
時々、奇跡を起こすんだ。
でも、それがいつかは天使も気紛れだから分からないんだけどね」
そう言われて天使の人形を見るとその天使は悪戯っぽくウインクをしてみせた。