
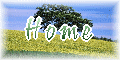
星を渡る想い
世の中には理不尽なことっていくつもあって
正直者が得をするなんてことの方がほとんど稀で
優しい人がいつも報われる訳でもなくて
正義がいつも勝つなんてのはドラマの中くらいだろう。
それは分かっている。
今までも何度も他人のそんな場面を見て来たし
自分自身だって何度もそんな目に遭ってきたんだから。
「アナタハ神ヲ信ジマスカ?」
街を歩いていると、時々そんな風に声をかけられる。
「じゃ、あなたは本気で神様を信じているの?」
俺はいつもそう訊き返す。
「モチロンデス。神ハイツモ私達ノスグ傍ニイテ
私達ヲ見守リ、導イテクレルノデス」
「見守っているって?
何処に導いてくれるって?
天国にか?
だから神様は何度も戦争を起こし
飢饉を起こして
時には大災害を起こして
何百人、何千人もの命を天国に導いているのか?
じゃ、愛する人を失い残された人は
神様に見守られていない人ってことになるのか?」
そう、それじゃ残された俺はいったいどうすれば良いんだ?
殺風景な病室の白い壁と白いカーテンに囲まれた小さな空間。
白いパイプに白いシーツのかかったベッド。
無機質な画面に幾つかの波形が流れ数字が上下を繰り返す機械と由美を繋ぐ命の線。
吊るされた点滴のパックとビニール管の中を頼りなさげに伝う透明の液体。
その中でひと際華やかだったのが
由美のお母さんが用意をしてくれたパステルカラーの花柄のタオルケットだった。
「可愛い色だね」
「でしょ?」
「うん、良いね」
「せっかく春になったんだから、せめてこれくらいはね。
今年もこんな花柄のワンピースなんて着て歩けそうもないし」
笑顔を見せた後で由美はちょっと寂しそうにそう言った。
「そんなことはないさ。
元気になれば又、いつだって着て歩けるよ。
そういや、由美のワンピース姿なんて見たことがなかったよね?
出し惜しみしてた?(笑)
いっつもTシャツかトレーナーにジーンズだったじゃん」
「そんなことはないんだけどさぁ〜
なんか、私って可愛げが無いじゃん?」
「あはは、そんなことないって」
「髪もこんなだしなぁ〜」
少しくせ毛の強いショートカットの髪の端を両手で引っ張りながら由美は言った。
「きれいなストレートヘアだったらロングも似合うんだよね」
由美は大きく溜め息をついた。
「そんなことないって。そのままで十分に可愛いさ」
「じゃ、私に花柄のワンピースなんて似合うと思う?」
「あぁ、もちろんだよ。馬子にも衣装って言うじゃん?」
「あー、ひどい! それって、そうやって使う言葉だっけ?」
「あれっ、何か違うっけ?」
「もう!」
難しい名前の病気が由美を蝕んだのは半年前。
俺達が付き合い始めて二度目の秋のことだった。
入院生活が始まったのは秋も深まった頃でそれから二度の大手術を受けた。
由美の症状は幾度も一進一退を繰り返していた。
薬がうまく効いていればいつもの朗らかな由美がそこに居た。
でも、副作用のきつい時は酷い鬱になったり
そうでなければやたら神経過敏とでも言うのか
凡そ、俺の知っている由美とは違う由美になっていた。
お母さんは由美の前では気丈に振る舞って
いつも笑顔を絶やさないではいたけど
時々、そっと病室を抜け出ては病室から離れた物陰で顔を覆って泣いていた。
嗚咽を漏らさないように、由美に気取られないようにしながら
そして、いつも愛する娘を不憫の思い
そんな娘を産んだことを、自分を責め続けていた。
何度もそんな場面を見ていながら
俺はお母さんにかける気の利いた言葉さえ持ってはいなかった。
みんな解っていた。
それは誰のせいでもないと。
お母さんのせいでもなく、もちろん由美のせいでもない。
十万分の一の確率で誰かに起きる病気。
誰がその「一」になるのか?
それは公平に決められているのか?
誰がそれを決めているのか?
それは悪魔なのか?
それでも、それは神様の仕事のひとつなんだと
いったい誰がそれを弁護するのだろう?
「織姫と彦星が羨ましいわ
離れ離れになっても一年に一度は逢えるんだもの」
その日、珍しく体調の良かった由美はベッドから身体を起こすと窓辺に立ち
中庭でワイワイ言いながら
七夕の飾り付けをしている子供達の様子を見おろしながらそう呟いた。
「急に何だい?
俺達なんか二日に一遍は会えてるじゃないか?」
「そうね・・・」
病院には小児病棟もあって
そこでは何十人もの幼い子供達が病気と闘っていた。
そんな子供達がそれぞれの願いを込めて一枚づつ短冊を吊るしていた。
どの子供の顔も病気など感じさせないくらい活き活きとしている。
それが逆に見る者を辛くさせていた。
「願い事、叶うと良いな」
俺は由美に並んで窓辺に立つと独り言のように呟いた。
由美はそれには応えずに黙って小さく頷いた。
「それじゃ、俺も後で短冊を書いて吊るして来ようかな。
ナースステーションに置いてあるかな?」
「いい大人が恥ずかしいよ」
「関係ないよ。大人にだって願い事はあるんだしさ。
そうだ! ねぇ? 一緒に書く?」
「嫌!」
「どうして? 良いじゃん」
「だって、私・・・」
「ん?」
「きっと悪い子になってしまう」
「どうして?」
「世界一、ワガママな女になるわ」
「なれよ」
「えっ?」
「良いじゃん。世界一の、いや・・・宇宙一のワガママになれよ。
俺が受け止めてやるよ」
「だから書けないのよ」
由美はそう言うとベッドに身体を寝かせ
タオルケットの端を掴んで引き寄せるとそのまま顔を覆い隠した。
そのタオルケットは小刻みに震えていた。
今年の七夕は今度の日曜日だ。
医者の余命宣告期限が過ぎてからもうすぐ三か月が経つ。
由美は辛い治療にも負けずに頑張っていた。
そう、頑張っていた。
もしも、神様が居て何処かで由美を見守ってくれているなら
きっと奇跡を起こしてくれるに違いない。
その時の俺はまだ神様のことを信じていたんだ。
目覚ましよりも早く俺を起こすかのように携帯が鳴ったのは金曜の明け方だった。
「もしもし・・・」
半分寝惚けながら電話を取った俺に聴こえてきたのは
切羽詰まった由美のお母さんの声だった。
「あっ、健二さん? 由美が・・由美が危篤なんです。
あなたの名前をうわ言のように呼んでいて・・・」
後は言葉になっていなかった。
「わ、分りました。すぐに行きます!」
俺は動揺を鎮めるべく勢いよく流した冷たい水で顔を洗うと
急いで着替えを済ませて車を走らせた。
時々、当たる赤信号がこんなにももどかしいと思ったことはなかった。
「早く、早く!」
イライラするのを抑えられずにハンドルを指で叩きながら俺は念じていた。
そして、隣の信号が黄色になるや
俺は前の信号が青に変わる瞬間も待てずにアクセルを踏んだ。
対向車線にパトカーがいたとしてもその時の俺には見えていなかっただろう。
そのくらい俺は焦っていたし、すべての時間がもどかしかった。
それでも、早朝のせいもあってか
いつもの三分の二くらいの時間で病院の駐車場に滑り込んだ。
俺はエレベーターホールより近い階段を選んで三階まで駆け上がった。
そのまま病室まで駆けると息を切らしたまま病室のドアを開けた。
そこにはもう医者も看護師もいなく
由美の命を繋いでいたあの無機質な機械の電源も消されていた。
白い布を顔にかけられた由美の身体にすがるようにお母さんは泣き崩れていて
お父さんは明けかけた蒼い空を見るともなく見るように窓の外を見ていた。
「由美・・・」
何もかもが信じたくはない光景だった。
俺に気づいたお母さんが涙を拭きながらそっと立ち上がると言った。
「さっきまで頑張ってたのよ。
最期に『健二さん、ごめんなさい』って・・・それっきり・・・
あんなに待ってたのにね・・・」
顔にかけられた白い布をめくるとお母さんは由美に話しかけた。
「由美、健二さんが来てくれたよ・・・」
由美はまるでただ眠っているだけのような本当に安らかな顔をしていた。
土曜日の通夜と翌日曜日午前の葬儀、そして午後からの繰り上げ法要を終えて
由美を実家に連れて帰ったのはもう夕方になっていた。
仮祭壇に祀られた由美の遺影は去年の夏に二人で沖縄に旅行をした時のものだ。
初めて見たコバルトブルーの海と白い砂浜。
喧騒を忘れてゆったりと流れる時間の中に溺れるように過ごした忘れられない三日間。
とびっきりの笑顔ではしゃいでいた由美は今はもう黒い縁取りの額の中にしかいない。
「由美・・・」
俺は由美のお父さんやお母さんの少し後ろに座り
遺影を眺めながら走馬灯のように巡る由美との想い出に浸っていた。
時折り、由美のお母さんが鼻を啜りハンカチで涙を拭う以外はみな物音ひとつ立てずに項垂れていた。
そうして時が止まったかのような沈黙の時間がしばらく続いていた。
誰もが悲しみを堪えながら受け止めなければならない現実と闘っていたのだ。
「健二さん・・・」
どれだけ時間が経っただろうか。
俺の方を向き直るとお母さんは俺に頭を下げて言った。
「健二さん、ありがとうございます。
健二さんがいつも傍にいてくれたから由美はきっと最期まで幸せだったわ」
「いえ、俺なんか何も・・・」
「ううん。本当にありがとうね」
お母さんは涙を拭うと又、深々と頭を下げた。
「そんな・・・お母さん、頭を上げて下さい」
俺はきちんと座り直すとお母さんに言った。
「こちらこそありがとうございました。
結婚どころか婚約すらまだしていないのに家族同然に扱っていただいて
本当なら水入らずで想い出に浸りたいであろうところを・・・
こんな席にまで俺に居させてくれて・・・」
「いや、本当に君がいてくれて助かったよ。感謝しているよ。
母さんと二人だったら、こんなに立派に由美を送り出してやれんかっただろう」
お父さんは笑顔を作って俺に言った。
「・・・」
「いろいろな段取りやら連絡やら本当に助かった。
うちはとうとう一人娘のままだったけど
息子がいるってこんなに心強いことだったんだなぁ〜 なぁ、母さん?」
「はい」
頷くとお母さんは笑顔を作って言った。
「でもね。健二さんはまだ若いんだから何も縛られることはないのよ。
うちにも遠慮しないで、早く幸せを見つけてね。
その方が由美もきっと喜ぶから。あの子ならそうよね?」
お母さんはお父さんの方を向くと言った。
「そうだな。
まぁ、昨日の今日で健二君もまだ気持ちの整理がついてないだろうけど何も気にしなくて良い。
亡くなった者も大事だけど、それより残った者の方がずっと大事なんだ。
私達もそう思うようにするよ。
もちろん、娘を忘れるという意味ではないけどね。
そう、忘れるもんか・・・忘れるはずがない・・・」
お父さんの言葉に頷きながら涙をひとしきり拭うとお母さんは微笑みながら言った。
「さぁさ。キリがないわね。健二さんも帰って少し休んでちょうだい。
ここ二〜三日全然寝てないでしょ?
あなたまで倒れちゃったら私が由美に怒られるから」
「はい、ありがとうございます」
それから俺は改めて遺影の前で手を合わせ線香を点けるともう一度お参りをしてから
後ろ髪を引かれる想いを断ち切りながら由美の家を後にした。
十分に悲しみに浸る間もなく
むしろ現実感が感じられないまま葬儀までの時間がただ慌ただしく過ぎて
今日が何曜日だったのかも忘れていた。
本当の意味の悲しみはおそらくこれからジワジワと湧いてくるのだろう。
だが、今はそこに頭が至る間もないほどクタクタに疲れ果てていた。
家に戻るとそのまま着替えもせずにベッドに倒れ込むように俺は眠りについていた。
その夜、俺は夢を見た。
それは見たこともない風景だった。
荒涼とした岩肌と砂に覆われた大地。
<俺達>はバギーのような二人乗りの車に乗って小高い丘陵地に出た。
二人共、宇宙服を着ていた。
後ろを振り返るとどれくらい離れているだろう?
眼下には巨大な透明のドームが見えた。
多分、俺達はそこから来たのだろう。
ドームの中には煌めくばかりの光を灯した巨大な高層ビル群がそびえていた。
絵葉書でしか見たことはないが
その景色はやや俯瞰で見たニューヨークの夜景の何個か分はあるのだと思う。
「やっぱり、ここが一番キレイね。ドームの中から見るのとは大違い」
君はそう言うとバギーを降りて近くの小岩に腰をおろした。
「あぁ、そうだね。シティのドームは紫外線対策とやらでフィルターがかけられているし。
そのフィルターも昼間は青空で夜は星空とはいえ投影された映像だから実物とは違うしね」
そう言いながら俺も並んで腰をおろした。
見上げた空には蒼く輝く地球とその少し上には天の川が長い帯のように見えていた。
ここに来ると星々の煌めきが本当に良く分る。
この場所は二人のお気に入りの場所だった。
とはいえ、規則が厳しくてここに来られるのは一ケ月に一度。しかも二時間だけだ。
それ以上はいくら宇宙服を着ていても強烈な紫外線が人間には非常な害になるらしかった。
「ねぇ、知ってる?」
君が訊いた。
「えっ? 何を?」
「小さい頃に本で読んだんだけど人類が大昔に地球に住んでいた頃ね。
今日、七月七日は七夕だったんだって」
「<たなばた>? 何だいそれは?」
「<七夕伝説>といって昔の地球の神話なのか童話なのかは分らないけどこんな話よ」
織姫は天帝の娘で機織の上手な働き者の娘であった。
彦星もまた働き者であり、天帝は二人の結婚を認めた。
ところが、めでたく夫婦となった二人は夫婦生活が楽しくて
やがて織姫は機を織らなくなり、彦星は牛を追わなくなった。
このため天帝は怒り、二人を天の川を隔てて引き離したが
悲しみに暮れる織姫を不憫に思った天帝は年に一度、七月七日の夜だけ会うことを許した。
天の川に何処からかやってきたカササギという鳥が橋を架けてくれ二人は会うことができた。
しかし七月七日に雨が降ると天の川の水かさが増し
織姫は渡ることができず彦星も又、織姫に会うことができない。
星の逢引であることから七夕には星合いという別名がある。
また、この日に降る雨は催涙雨とも呼ばれる。
催涙雨は織姫と彦星が流す涙といわれている。
「どう? ロマンチックな話だと思わない?」
「そうだね。何だか教訓めいてる気もするけど」
「もう! あなたってホント、クールっていうか夢がないのよね」
君は宇宙服のヘルメット越しでも良く分るくらい口を尖らせた。
「あはは、ごめんごめん。いや、大変ロマンチックでございます」
「もう良いわ、知らない!」
「ごめんごめん」
俺は苦笑いをしながらヘルメットの後ろを掻いた。
「でも・・・そんな話を聴いてから改めて天の川を見ると何か違って見えるよね」
「でしょ、でしょ?」
君はヘルメット越しからでも良く分るくらいとびっきりの笑顔を見せた。
立ち直りの速さで君に敵う者はいないんだと思う。
「ねぇ?」
マジマジと俺を見ると君は訊いた。
「なんだい?」
「もし・・・もしよ。私達が無理やり引き離されたらどうする?」
「どうするって・・・そんなことは有り得ないよ。
俺達はシティの人口管理コンピューターで何百万もの相性の中から選ばれたんだぜ。
相性が合わないなんてことはないからケンカもしないだろ?
だから途中で別れるなんてことは絶対にないし
第一、そんなことはコンピューターは許さないよ。
病気だってもう何百年も昔に淘汰されたから病気にもならない」
「それはそうだけど・・・」
期待していた回答ではなかったのか君は不満そうに呟いた。
「まぁ、確かに人類はまだ寿命だけは克服してはいないけどね」
「だから、もしよ」
「そうは言ってもなぁー あっ!?」
俺は突然、明け方に見た夢を思い出すと
その時見た夢の映像が一瞬脳裏にフラッシュバックをした。
「いや・・・あれは・・・」
「えっ? どうしたの?」
怪訝そうな顔で君が訊き返した。
「あっ・・・い、いや、なんでもない」
「もう変な人ね。何かあるならちゃんと言ってよ」
「いや、ホント・・なんでもないんだ。大丈夫、うん・・・大丈夫」
「ねぇ? そう言えばあなた、今朝も変だったわよ。
起きて来るなり突然抱きついて来たりして。
『良かった』とか何とか言ってたけど何だったの?
あの時もあなたは『なんでもない』って教えてくれなかったけど・・・
何? 悪い夢でも見た?
変ねぇ、そんなプログラムはされていないはずなんだけど」
広い空間が確保されているとはいっても所詮はドームに囲まれた中だ。
いくら昼と夜の空の映像が<それらしく>流されていたとしても
いくら街中の公園に緑がたくさんあったとしても
いくら郊外の林に鳥や小動物がいて人々の癒しになっていたとしても
その半分は人工的に造られた<モノ>だし
いわゆる閉鎖的な空間には違いないので
どうしても人間は感情に変化をきたしやすくなってしまう。
そこでコンピューターは人間の夢をコントロールする<システム>を創り上げた。
その<システム>のおかげで悪い夢などを見ることもなくなり
逆に寝ている時間は脳を休め穏やかな状態を保てるようになった。
これを<リセット>と呼んでいる。
もちろん、夢をリクエストすることも出来た。
見たい夢の入ったカードをシステムに挿入すると
どんな楽しいことでもバーチャルで体験が出来るのだ。
夢なのでもちろん疲れることはないし
それどころか爽快な気分で目覚めることができるのだ。
『夢・・・そうなんだよ。そんな訳がない。
それじゃ、どうしてあんな夢を?』
俺はよほど切羽詰まった顔をしていたのだろうか?
君は俺の顔を覗き込むようにしてマジマジと見つめると言った。
「やっぱり変よ、あなた。体調が悪いのかしら?」
「あっ、いや。大丈夫だよ。変な夢を見ただけ」
「夢を? どんな? だって、悪い夢なんて見るはずがないわ」
「あはは。コンピューターだってたまにはバグるよ。
なんかね、地球ライブラリーにあった映画のゾンビに追っかけられてる夢?
そんな訳はないよね、バカバカしい」
「もう! でも、帰ったら安静器で休みましょ。
昨日、一ケ月ぶりに<仕事>だったから疲れているのかもね」
ドームではみんなが平等な生活を送っている。
<仕事>はコンピューターで割り与えられていて月に一度。
それもバーチャルマスクを着用して流れてくる映像をただ見ているだけ。
何の意味があるのかは誰も知らないし
中には<仕事をすると洗脳される>と噂をする者も稀にいたが
大概は誰も疑問には思わないし文句も言わない。
それで楽な生活が出来ているのだから。
そんな<仕事>で疲れるはずもなかった。
でも、君がそれで納得をしてくれたならそれで良い。
本当に見た夢はそんなのではなかった。
しかも、その夢の話など君に出来るはずもなかった。
君が死んだ夢だったなんて。
「あー、本当にキレイ!
ねぇ、もう織姫と彦星は再会できているかしら?」
無邪気に君はそう言った。
俺も笑いながら答えた。
「あっ、ほらあそこ! 光ってるでしょ? あそこじゃない?」
俺が指差す方向を見ると君は目を輝かせて呟いた。
「どこ? あっ、ホントだ。そうね。きっとそうだわ」
君はウットリとするかのように地球の向こうに見える天の川を眺めていた。
君の死んだ夢がどうしても引っ掛かっていた。
あれは何処だったんだろう?
地球史の教科書で見た<病院>の部屋に似ていた気がしていた。
ただ白いだけの殺風景な部屋の真ん中にベッドがあって
君はそのベッドで白いシーツのような物に全身を覆われて横たわっていた。
顔は見えなかったけど俺はその瞬間確かに君だと確信をしたのだ。
そして誰か解らないけど数人の人達がそのベッドを囲みながら泣いていた。
とてもとても深く悲しい想いがその部屋全体を包んでいた。
その悲しみがやけに重たく今でも俺の心に残っている。
まるで、それが俺自身の体験だったかのように。
「ほらー、又、考えごとをしている。
ゾンビなんか何処にもいないわよ。意外と怖がりだったりして?」
君の言葉に我に返った。
「あはは。そうだねー 君より怖いゾンビなんていないよね?」
「まぁ、ひどい! 今夜はチューブの宇宙食にしちゃうぞ!」
「ごめんごめん。チューブならせめて地球食にしてくれないか?
でも、地球食って言えば久し振りにカレーライスが食べたいな。
チューブじゃないやつでさ」
「もう。けっこう面倒なのよ」
「由美殿の作ったカレーライスが所望したいでござる」
俺はいつか見た地球史の<時代劇>口調でおどけて言った。
「はいはい、健二殿。分ったでござるよ」
君もおどけて答えた。
「でも、『ござる』は女性は言わないはずなんだけど?」
「あれー? なんか変だと思ったわ」
俺達は顔を見合わせて笑った。
『夢で本当に良かった』
俺は心からそう思った。
「おっと、そろそろ帰らなきゃ。酸素が無くなっちゃうよ」
「あっ、ホントだ。大変!
でも、不便よね。こんな宇宙服なんか着ないで散歩が出来たら良いのに」
「仕方ないよ。たまにだけどこうして一緒に出掛けて来られて
そして二人で同じ風景を見て一緒の時間を過ごせるだけで幸せさ」
「そうね。織姫さん、彦星さん、お幸せに。
そしていつか又、一緒に暮らせるようになると良いね」
由美は天の川に向かって大きく両手を振った。
それを聞きながら俺は呟いた。
「あぁ、きっと一緒に暮らせるようになるさ。時間はかかってもね、必ず」