
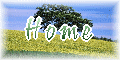
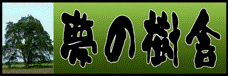
隣のサンタクロース
夜中に他人様の家に入ろうとするなんざ
ドロボーとサンタクロースだけだろうさ。
ただ、その目的は全く真逆だけどね。
奪う者と与える者。
ドロボーは金品だけじゃなく時には人の想い出さえも奪おうとする。
だけど、サンタクロースは与えるんだ。
しかも、サンタクロースが与えるモノは何もオモチャだけじゃない。
世界中の子供達・・・いや、大人達にだって夢を与え続けているのさ。
その違いは服装にも現れているよね。
ドロボーは闇に紛れやすいように黒っぽい服を着る。
だからって訳じゃ無いだろうけど
サンタクロースはドロボーと間違われないように
あえて目立つ赤い服を着ているのさ。
築三十何年かの昭和感満載の二階建ての木造アパート。
来春からの就活を控えて少しでも都心部に近い方が良いかと思って
古いのは承知の上で引っ越しては来たものの
テレビでも付けていなければ隣のヒソヒソ声だって丸聞えだ。
聞こうとして壁際で耳をそばだてたらだけどね。
仕送りとバイト代で何とかやり繰りをしている身としては
家賃が高くても利便性を取るか、
郊外のアパートに甘んじて少しでもやり繰りが楽な生活を取るか。
私が選択を為たのは利便性なのだから、多少の生活の窮屈さくらいは我慢の上だ。
そこに高級マンションのような自由な快適さは求めてはいけないのだ。
当然、風呂は夜の早い時間帯に済ませる。洗濯は土日の日中に済ませる。
夜はなるべく静かに過ごす。それが隣人に迷惑をかけない生活だ。
なので、アパートには極力友達も呼ばないようにしていた。
今の時代は特に若い人が住むアパートやマンションなんかでは
隣の部屋の住人はどんな人なのか知らないでいることの方が多いんだろう。
お互いに余計な詮索はしないという適度な、しかし厳然とした相互の距離感。
田舎の近所付き合いと比べてはいけない。
都会では人間関係も田舎のそれとは全くの別物なのだということをこっちに来てから学んだ。
「やっぱ、田舎に帰って就職をしようかなぁ-。」
何度となく、そんな考えが頭を支配してきたが
現実問題として田舎に戻っても仕事なんかそうはない。
親は「こっちに戻って教員になるか役場にでも入れ」というけど
五年先、十年先の自分の姿が容易に想像出来てしまって、それを良しとはしたくない自分がいた。
とは言え、それじゃこっちに残って何がしたいんだ?
そう問われると、まだ自信を持って「これだ!」と言えるものも見つけられてはいない。
その漠然とした未来は自分の中では天国と地獄ほどの落差でいくつも存在した。
それが若さなんだと自分にいつまで言い聞かせられるのだろう?
いつか「これだ!」というものが自分にも見つけられるのだろうか?
いや、違う。見つけなければならないのだ。
そうじゃなきゃ、今ここにいる意味が嘘になる。
選択肢は排除しない。可能性を探す。大学生活とはその為の四年間なのだ。
「みんな偉いよなぁ-。ちゃんと目的を持って大学に進学している。それに比べて私なんか。」
「そんなの一握りだよ。大学に入ってから方向転換することだってあるし。
焦ることはないって。先は長いんだからこれから、これから!」
親友たちと話すといつもそんな話の堂々巡りになる。
田舎の親には大きな声では聞かせられない話だ。
バイト帰りの夜の駅前通りは十二月になるのを待っていたかのように
ウインドウを飾るイルミネーションも華やかになって一気にクリスマスムード全開になっていた。
「クリスマスかぁ-。」
思わずため息交じりになる。
去年は親友たちとカラオケボックスでパーティをしたが今年はどうなんだろう?
地元での就活で早めに地元に戻ると言っていた友達もいる。
彼氏が出来て初めてのクリスマスを心待ちにしている友達もいる。
「今年は独りかなぁ-。まっ、仕方ないけどさ。」
夜の八時。この時間ならまだ多少の物音は許容されるだろう。
冷蔵庫の中を見渡して冷凍食品といくつかの野菜を取り出して調理を始めた。
朝、炊いておいたご飯を大きめのお皿によそって、その脇にサッと炒めたおかずを並べた。
独りぼっちのワンプレートディナー。
一人暮らしに肝心なのは洗い物を極力減らすこと。
見た目は気にしてはいられない。お腹に入れば同じなのだから。
ご飯を食べ終わって何気にテレビを観ているうちにウトウトしてしまったようだ。
気が付けば時計は十二時を少し回っていた。
「あー、すっかり寝てしまったわ。どうしよ・・・」
今夜はゼミの宿題もないし、いっそもう寝てしまおうかと歯磨きに立ち上がった時だった。
<ギィ-、バタン>
隣の部屋から誰かが出て行く音がした。
「こんな時間にお出かけ?
確か、隣の部屋は空き部屋だったはずだけど、誰か入ったのかな?」
古いアパートだけど、都心部に近いせいか誰かが出てもすぐに次の人が決まると
入居の挨拶に行った時に大家さんが言っていたのを思い出した。
なので、その時もさほど気にも留めなかった。
ところが、その次の夜も夜中の十二時を回った頃にドアを開けて出て行く音が聞えた。
「何をしている人なんだろう? 夜勤の仕事なのかな?」
私は隣人のことが少し気になりはしていたが、他人の私生活をアレコレ詮索するのは良くないと
自分に言い聞かせて努めて気にしないようにしていた。
みんな、それぞれ生活のリズムは違うのだ。特に都会では。
しかしそれが連夜ともなれば話は変わってくる。
その次の夜も。又、次の夜も十二時過ぎになると決まって部屋を出て行く音が聞えるのだ。
気にはしないように努めてはいたが、それが十日も続くとさすがに興味が沸かないはずがない。
「夜勤? まさか、ドロボーとか? いや、まさかね。」
だが或る時、ふと気が付いた。
夜中に部屋を出て行く時のドアを閉める音の他は何も生活音がしないのだ。
テレビの音はもちろん、トイレの水を流す音やちょっとした物音さえも。
もちろん、これが防音もしっかりした鉄筋コンクリートのマンションならそうなのかもしれない。
そんな立派なマンションには住んだことはないけど。
でも、ここはそんなマンションとは対極と言って良いくらいな古い木造のアパートなのだ。
実際、反対側の部屋からはいつも友達が集まっているとみえて
時にはワイワイ煩いくらいの話し声や笑い声、トイレの流す音や洗濯機を回す音も聞えていた。
「それはおかしいですよね。いや、何か怪しい! うん、絶対に怪しい!」
大学の学食。いつものA定食のメンチカツを頬張りながら和樹は言った。
「やっぱ、そうだよね。」
私はご飯茶碗を定食のトレイの手前に置きながら答えた。
「そうですよ、先輩!
夜勤にしてもドロボーにしても出て行く音しかしないってのは明らかにおかしいです。」
「だよねぇ-。」
「でも、先輩。<ドアを閉める音>ってホントに出て行く時の音なんですか?」
「えっ? どういうこと?」
「部屋に帰って来た時の音ってことはないですか?」
「いや、部屋を出て行く時にドアを締めた音だったわ。」
そう言いながら、正直「そうだ」と言える自信はなかったのだがどうしてだろうか?
間違いなく出て行く時の音だと確信めいたものがあったのだ。
「んー、絶対とは言えないかも知れないけど・・・でも、出て行く時の音に聞えたわ。
だって、帰った時の音だったら、その後に何かしら物音ってすると思わない?
夜、部屋に帰ってテレビもラジオもつけないとかトイレにも行かないってある?」
「それはそうですけど・・・」
「自慢じゃ無いけど、古い木造アパートなんだから、
隣に人がいたら何かしらの気配ってするもんじゃない? それがないのよ。」
和樹は箸で味噌汁をかき混ぜながらうつむき加減で何か深く考え込んでいた。
そして、顔を上げるとおもむろにこう言った。
「判りました、先輩。今夜僕、先輩のアパートに行きます。」
突然の申し出に驚いて私は慌てて話の続きを遮ろうとした。
「えっ? ダメよ、そんな。そ、そう! きっと、私の気のせいなんだわ。
ほら、日中は私、大学だし、生活のパターンが違っているだけよ。」
いくら後輩とは言え、夜中に男子と二人っきりはマズいでしょとも言えずに
とにかく私は話をはぐらかそうとした。
「そうかも知れません。でも、何となく面白そうじゃないですか?
二人して正体を確かめましょう!」
意に反して和樹は満面の笑みで答えた。
和樹は一年下のゼミの後輩だ。
私と同じく地方から出てきていて大学近くのワンルームマンションに住んでいると言っていた。
慣れない生活に苦労をしてそうな様子を見ていると一年前の自分を見ているようで
つい何かと声を掛けては世話というほどではなかったろうが面倒を見ていた。
私にとってはここでの弟のような存在だった。
和樹も私のことを姉のように慕ってくれていて、
仕送りに入っていたと言ってはいつも食品のお裾分けを持って来てくれたりしていた。
なので、いつもの気安さでつい和樹に相談をしたのだ。
ともあれかくして、隣人の正体を確かめるべく二人のミッションが始まった。
夜の十一時を過ぎた時、玄関を小さくノックする音がした。
ドアを開けると手にコンビニ袋を提げてニコニコした和樹が立っていた。
「先輩、肉まん買って来ました。バイト先のですけど、案外美味いんですよ。
ほら、腹が減っては戦が出来ぬって言うじゃないですか。」
「お腹が空いてるの? 何か作ろうか?」
「ホントですかぁ-? 嬉しいなぁー でも、時間がないんじゃないですか?
ご馳走は今度の楽しみにいておきますよ。今夜はこれで満たしましょう。」
和樹はそう言うと肉まんにかぶりついた。
和樹のいつもと変わらぬマイペースぶりに
部屋に初めて男子を招き入れることに変にドキドキしていた自分が可笑しくなった。
「えっ? どうかしました?」
「ううん。お茶でも入れるね」
隣に気取られてはいけないと、つい話す声も小声になっていたが
十二時十分前になる頃にはお互いに息を潜めて<その時>を待っていた。
私は居間で隣の部屋の気配を感じ取ろうとしていて
和樹はすぐにダッシュが出来るようにと靴を履いたまま玄関で待機をしていた。
そして十二時。
一分、二分、そして五分が立った時、隣の部屋からドアを開ける音が聞えてきた。
「良し!」
和樹にも聞えたのだろう。和樹は小声で叫ぶとすぐに玄関のドアを開け放った。
「どう?」
私が訊くと玄関先に出た和樹はキョロキョロと周りを見渡していた。
「和樹?」
和樹はこちらを向くと両手を拡げて答えた。
「誰もいません。中は?」
「あっ、そうね。」
私はすぐに居間に戻って隣の壁に耳を寄せて神経を集中させた。
だが、やはり隣の部屋からは何の音も聞えなかった。
「確かに、僕にも部屋を出て行く音に聞えました。でも・・・」
部屋に戻りながら和樹は呟いた。
「でも、外には誰もいなかった?」
「えぇ。」
和樹は腕を組んで考え込んでいるようだった。
だが、どうしても腑に落ちない。
確かにドアを開ける音はした。
でも、あれだけすぐにドアを開けたにも関わらずそこには誰もいなかった。
「なんでだろう?」
キツネにつままれるとはこういうことを言うのだろうか?
次の夜。やはり十一時を過ぎた頃に和樹はやって来た。
「先輩。今夜は作戦を考えて来ました!」
「作戦って?」
「僕がアパートの外で見張ってみます。
十二時を過ぎたら電話を繋いでおいて、隣の部屋から音がしたらすぐに知らせて下さい。
もう見逃しませんよ! ほら、双眼鏡も借りて来ちゃいました。バッチリです!」
「でも、外は寒いよ。」
「平気です。なんせ、こう見えて北海道育ちですから!」
「でも・・・」
「他に何か方法はあります?」
「んー、そう言われると・・・」
「でしょ? 任せて下さい!」
「ホントに大丈夫?」
「もちろん!」
「でも、私のせいで風邪とか引かれたら嫌だよ。」
「平気ですって。僕なんか幼稚園の頃は雪が降っていても半袖半ズボンだったんですよ。」
「それって、家の中じゃないよね?」
「えへへ、バレました?」
「もう!」
「でも、ホント大丈夫です。僕は今燃えていますから!」
そんなこんなしている内に十二時が近づいてきた。
「じゃ、僕は外で待機をしています。何かあったらすぐに呼んで下さい。
僕が下に降りたら携帯で呼び出して下さい。そのまま繋げておきますから。」
夜中の十二時を過ぎた頃、案の定隣の部屋からドアを開ける音がした。
私はすかさず和樹の携帯に向かって叫んだ。
「和樹、今部屋を出たよ!」
「えっ?」
丁度その時、茂みの影から猫が現れて和樹を見ると「ミャア」と鳴いた。
一瞬、その声に気を取られていたせいで和樹はアパートから目を逸らしてしまったのだ。
「すいません。見逃しました。」
「もう、何をやってるのよぉ-。」
部屋に戻った和樹に温かいコーヒーを渡しながら私はついぼやいてしまった。
「すいません・・・」
恐縮している和樹。
「でも、頼んだのは私だもんね。ごめんね、寒い思いをさせちゃって。」
「いや、言い出したのは僕です。でも、あんな時に猫が出てこなくてもなぁ-。」
「仕方ないよ。」
「すみません。明日こそ頑張ります!」
「えっ? まだやるの? 良いよ、もう十分。」
「いや、まだ何も解決していません。このままじゃ・・・」
和樹は何かを言いかけて止めた。
「えっ? 何?」
「いえ、何でも。明日こそは見ていて下さい! 決着をつけてやりましょう!」
そう言うと和樹は隣の部屋に向かってボクサーか空手家のように拳を突き出した。
翌日は雨だった。
「参ったぁー、もうクリスマスも近いってのに、こっちじゃ雨も降るんですねぇー
北海道だったらきっと雪だな。」
十一時過ぎ。
ドアを開けると半ばずぶ濡れになった和樹が手でジャンバーの雨を払いながら言った。
「何よ。ずぶ濡れじゃない? 傘は持ってなかったの?」
「あはは。バイトに行くころは降ってなかったんで。」
「天気予報くらいちゃんと見なよ。」
そう言いながら私は和樹にバスタオルを手渡した。
「はいこれ、風邪引くよ。ちゃんと拭きなよ。」
「あっ、ありがとうございます!」
アパートの窓から外を眺めながら私は言った。
「今夜は止めましょ。さすがに和樹に風邪を引かせる訳にはいかないもの。」
「いや、でも・・・」
「ううん。今夜は休戦よ。今、コーヒーを入れるから飲んだら解散しましょ。」
それから私は和樹を他愛の無い話を続けていた。
隣人のことは二人共すっかり忘れかけていた、その時だった。
<ギィ-、バタン>
「あっ!」
二人同時に声を上げた。
和樹は予想以上に俊敏に立ち上がったかと思うとダッシュで玄関に行きドアを開けた。
和樹は玄関の外で立ちすくんでいた。
「和樹?」
呼びかけると振り返った和樹は困惑した顔で小さく呟いた。
「誰もいません・・・」
その翌日も十一時を過ぎた頃、律儀に和樹はやって来た。
「先輩、おじゃましまーす!」
「昨日は大丈夫だった? 風邪は引いてない?」
「はい、大丈夫です! 丈夫さだけが取り柄ですからね!」
和樹はそう笑顔で答えた。
「悪いわね。晩ご飯は? ちゃんと食べた?」
「はい、もちろんです。」
「もっと早く来てくれたら晩ご飯くらいご馳走するのに。」
「いやでも、バイトがあるもんで。」
「だよね。ごめんね。疲れてるのに付き合わせちゃって。」
「とんでもない! 先輩には日頃お世話になってるんですから、これくらい。」
「そろそろ外で待機してますね。」
時計を見ながら和樹は言った。
今夜も外で待機をして隣の玄関を見張る作戦だ。
「ごめんね。あっ、そうだ! これ。マフラー巻いていって。少しは温かいでしょ?」
私はマフラーを和樹に手渡した。
「これ先輩のですか?」
「そうよ。悪い?」
「いえ、とんでもない。うーん、何か先輩の匂いがします。」
和樹は両手でマフラーを抱えると鼻を近づけて匂いを嗅ぐ仕草をした。
私は急に恥ずかしくなってマフラーを取り上げようとしたが、和樹はそれを察知してかサッと身をかわした。
「ダメですよ。いったん借りたんだから任務が終わるまでは僕のモノです!」
私は思わず苦笑してしまった。
「もう! じゃ、これも持って行って。」
私はステンレスボトルに入れたホットコーヒーを和樹に持たせた。
「おっ、かたじけないっす! これで元気百倍!」
和樹はおどけて言った。
「じゃ、悪いけど頼むわね。」
「はい、任せてください!」
和樹は敬礼をして部屋の外に出て行った。
「うぅ、寒いなぁ。先輩、様子はどうですか?」
「うん、まだ音がしない・・・あっ、待って!」
耳を澄ませると確かに隣の部屋からドアを開ける音が聞えた。
「和樹、今よ!」
「もう、何をやってるのよぉ-。」
戻って来た和樹を迎え入れながら私は言った。
もちろん和樹を責める気持ちは無かったのだが、こうも失敗が続くとついぼやいてみたくなるものだ。
「すみません・・・でも、何でなんだろう? いつも肝心な時に邪魔が入るなんて。
でも、脇見をしていたのなんて、ほんのちょっとですよ。」
申し訳なさそうな顔で和樹は呟いた。
「今回は何だったの?」
「えぇ。僕がアパートの前の茂みに隠れていたら自転車に乗ったお巡りさんが来たんですよ。
あれで見つかったら僕は完全な不審者じゃないですか。
で、ちょっと伏せたんです。でも、ホンの数秒ですよ。」
そう呟いて和樹はフーッとため息を漏らした。
次の夜。例によって十一時過ぎに和樹はやって来た。
ドアを開けると和樹の後ろにもう一人の男性が立っていた。
「先輩! 工学部の友達を連れて来ました!」
「えっ? あー、こんばんは。」
慌てて私が挨拶をすると和樹の後ろにいた男性が前に出て「こんばんは。」と返した。
「和樹、どういうこと?」
私は和樹の腕を取って引き寄せると耳元で囁いた。
すると和樹は自信満々に答えた。
「今度はバッチリですよ。音はする。でも、姿は見えない。不思議ですよねぇ-。
で、実は科学的に解明出来ないかと思って、友達に相談したんですよ。
紹介します。ジャーン、我が大学のアインシュタインこと、玉置祐介です!」
「あっ、どうも・・・ってか、なんかごめんね。変なことに巻き込んじゃって。」
「大丈夫です。和樹が変なのはいつものことですから。」
紹介された祐介はにこやかに答えた。
「おいおい、そりゃないだろ? 今日だって、昼飯をおごったじゃないか?」
「はい、五百円のA定食で釣られてここまでやって来ました。」
「お前、学生にとっちゃ五百円ったら貴重なんだぞ。ありがたく思えよ。」
「へぇへぇ。かしこまりました。一宿一飯の恩義ってやつですね。泊まってないけど。」
「この前、飲み会の後に泊まっただろ?」
「そんな昔のことは覚えちゃおりません。若者にあるのはぁー、今でしょ!」
「って、それ古いべ?」
「テヘッ。」
「はいはい、君たちが漫才が上手なのは良く判りました。
で、私の部屋でもその続きをやるのかしら?」
私は二人のやり取りを聞きながら苦笑した。
「先輩、バカ言っちゃいけません。アインシュタインとガリレオのコンビですよ。
漫才なんて、そんな訳ないじゃないですか?」
「・・・」
私は言葉を失った。
「あれー、嫌だな先輩。ここ突っ込むとこですよぉ-。」
「ごめんね、あいにく私、関西人じゃないから。」
「さてさて、このまま何もしないと追い返されそうだし取りあえず、準備をしようか?」
祐介はそれまでと違った別人の口調で言った。
「おー、そうだった。手伝うよ。先輩も見に来ません? 滅多に見れない代物ですよ。」
アパートの前に一台のライトバンが停まっていた。
見ると後ろの荷台には何個かのジュラルミンのケースが見えた。
「これ、何?」
「見ていたら判りますよ。いや、先輩なら判らないかな?」
和樹はニヤリと笑った。
ここで今までの汚名を挽回するつもりなんだろう。
祐介はライトバンを少し離れたところに移動させると後ろのドアを開けてケースを下ろし始めた。
それから二人でケースを開けるとカメラみたいなものを取り出してパソコンと繋いでいた。
「ねぇ、これ何?」
「ジャーン!」
和樹はちょっともったいを付けてから大仰に両手を開くと説明をした。
「暗視スコープ付きのビデオカメラにサーモセンサーを繋げた特殊カメラです。
もちろん、望遠レンズ付きですよ。これならあの玄関にハエが止まったってバッチリです。
凄いでしょ? これ、外国の軍隊でも使われている奴らしいですよ。
で、これは離れたとこの音を拾う集音器でしょ。解析用のパソコンもほら、この通り!」
「あんたら、何? 覗きのプロ?」
私は半ば呆れて呟いた。
「いやだなぁ-。覗きならこんなとこには来ませんよ。」
「悪かったわね、こんなとこで。」
「いや、そういう意味じゃ。それに僕は覗きなんて趣味じゃありません!」
「ふぅーん、じゃ何? これから戦争でも始めるの?」
「みたいなもんでしょ? 正体不明の奴の正体を暴くんだから。」
和樹は澄まして答えた。
私は部屋の中でドアを開ける音に耳を澄ませていた。
和樹と祐介はアパートの隣の部屋の玄関が見える位置にライトバンを停めて待機をしていた。
時計は十二時を指そうとしていた。
「もうそろそろかも。」
私は待機中の和樹に電話を入れた。
「らじゃ! もうビデオは回してますよ。」
その時、隣の部屋からドアを開ける音がした。
「和樹、今よ!」
私は声を潜めて叫んだ。
「よーし、今度こそ!」
そう言う和樹の声が聞えた。
「和樹、どう?」
私は訊いた。
「・・・」
「ねぇ、和樹。聞えてる?」
耳を澄ませたが和樹の返事は無かった。
私は不安になって外に飛び出してライトバンの方に駆けだした。
ライトバンの中を見ると和樹と祐介はパソコンの画面を見つめたまま固まっていた。
「ねぇ、和樹! 祐介君!」
私がドンドンとライトバンの窓を叩くとどうやら二人は我に返ったようだった。
「どうしたの? 何があったの?」
助手席の窓を開けると青ざめた顔で和樹が言った。
「とりあえず部屋に行きましょう。
何かが映っていたんですけど・・・良く判りません。」
「ドアが開いたようには見えなかったんだけど・・・」
いつも陽気な和樹が呆然とした表情で独り言のように呟いた。
祐介は握った手を顎に当てて何か考え込んでいた。
「アレは何だったんだ?」
もう一度、和樹が言った。
「ねぇ? 何か映っていたの?」
私が訊くと祐介は「えぇ、まぁ。」と歯切れの悪い返事を返した。
「何だろう? 取りあえずもう一度、画像を見直して見ようぜ。」
「あぁ。」
和樹の言葉に祐介はパソコンの動画の再生ボタンを押した。
パソコンに映っている隣の部屋の玄関は私が思ったより鮮明に映っていた。
「この後です。」
和樹も祐介も画面を食い入るように見ていた。
『和樹、今よ!』
私の声だ。そして次の瞬間。
隣の部屋のドアの真ん中付近が一瞬光ったと思うと、その光の中から
何か赤い物体がフッと現れたかと思ったら、すぐに何事も無かったかのようなドアの画像に戻っていた。
「ドア、開いてないよな?」
「あぁ。」
「でも、ドアから光が出て来た・・・」
「あぁ。」
私は言葉が無かった。
「もう一度、今度はスローで見てみよう。」
「あぁ。」
三人はパソコンの画面をさっき以上に食い入るように、まさに凝視をしていた。
光が出てきた場面がスローで再生されていた。
「何だこれは?」
和樹が訊いた。
「判らない。」
祐介は答えた。
「こんなことって・・・。なぁ? 何か外の光が反射したとかある?」
「それはない。もし、そうなら光の中から何かが出てくるように見えることはない。」
「だよな・・・」
「それに。」
「ん? 何?」
「気付いたか? 普通に再生しても、スローにしても光の点滅時間は変わってないんだ。」
「えっ? どういうこと?」
「普通はスロー再生にすると画面の中の動きもスローになるだろ?
光だってそうだ。光った瞬間をスローにしたら光の拡がり方もスローになる。
でも、この光はスローにしても普通の再生と点滅時間が変わらないんだ。
有り得ない・・・」
「お前でも判らないのか?」
「判らない。人間の常識を越えているとしか・・・」
「つまり、俺達が思う時間の概念が通用しないってことか?」
「そう言えるのかもな。」
「集音器の方は?」
和樹が訊いたが祐介は答えなかった。
代わりに集音器の音データを再生し始めた。
しかし、そこには一定のノイズ音しか録音されていなかった。
私は溜まらず二人に訊いた。
「ねぇ? 私に判るように話して。」
「説明出来ることは・・・」
和樹が私を見て呟いた。
「何もありません。」
「あなた達、アインシュタインとガリレオなんでしょ?」
「すみません・・・撤回します。」
和樹はアッサリと敗北を認めた。
祐介はそれでもまだ何かを考えているようだったが何も言わなかった。
「研究室で詳しく分析をしてみるよ。多分、これ以上のことは何も判らないだろうけど。」
「判った。頼むよ。何か判ったら教えてくれ。」
「あぁ。」
私達は簡単に考えていたのだ。
部屋の中で隣人がドアを開ける音が聞えたら外で待機をしている和樹が見てどんな人かを確認をする。
私の部屋は二階だし、部屋を出た通路は外からは丸見えだ。
そこに人がいたら判らないはずがないのだ。
それだけのはずだった。
しかし、最新機器を持って為ても音の正体は判らなかったのだ。
むしろ、不思議な光という新たな謎が増えてしまった。
つまり、確かに何かは存在しているのだ。
十二月も二十日になった。
その後、祐介からは何の報告も無かった。
そんな中で今度、和樹が連れて来たのは学部の同級生で霊感が強いという有希子だった。
科学で判らないことは超常現象に違いないとは和樹の結論だった。
「まさか?」
疑心暗鬼の私に和樹は「可能性の問題ですよ。消去法で行くしかないでしょ?」
そう言って有希子を連れて来たのだ。
「わざわざ、ごめんね。変なことに付き合わせちゃって。
とにかく入って。話はそれからだわ。」
「気にしないで下さい。和樹から話を聞いて、行くって言ったの私なんです。」
「お前がしつこく聞いてくるから・・・」
「あら、間違ってないでしょ?」
有希子は澄まして答えた。
「私、普通の人より霊感は強いと思うけど除霊とかやったことがないから専門家を連れて来たわ。」
「専門家って?」
「こんにちは。」
その涼しげな声に目をやると
有希子の後ろに立っていたのはテレビの心霊番組で良く見る高階礼子だった。
「私の叔母なの。正真正銘の霊媒師よ。多分、日本一ね。ねぇ-?」
「止めてよ。人を化け物みたいに。」
礼子はそういうと苦笑いを浮かべた。
「あー、テレビで良く観てます。いつも凄いですよね。ビックリです。」
私は思わず出会った有名人にドギマギしていた。
有希子は自慢げに続けた。
「でも、本当は叔母さん、あんなもんじゃないんですよ。」
「えっ?」
「透視だとか降霊とか、あんなのはテレビ向けの子供だましです。
ほらっ、テレビで真剣に除霊なんかしたらどうなるか判らないでしょ?
<相手>が強力な力を持っていて、それで失敗したらこっちが祟られるんだから。
下手したら死んじゃうし。
もっとも、叔母さんならどんな<相手>でも除霊しちゃいますけどね。
でも、そんなのを本気でテレビでやったら大変な事になりますよね。
だから、テレビでやっているのは叔母さんの能力のホンの一部なんですよ。
つまりはお手軽な余興みたいなもんです。ねぇ-?」
有希子は礼子に同意を求めた。
礼子はそれには答えずに私に向かって言った。
「それはともかく、霊にも様々なものがいます。
いわゆる、善霊もいれば悪霊もね。
ただ単に成仏出来ずにそこにいるだけの人間には害を与えない者。
強い怨念を持って人に取り憑く者とか祟ろうとする者。
霊の種類も怨念の強さも一概には言えないのは確かです。」
礼子の静かな語り口が逆に凄みを感じさせた。
本当にそんな大袈裟なことになるんだろうか?
私は不安になった。
私の気持ちを読み取ってか礼子は続けた。
「でも、霊は何も怖いだけの存在ではないわ。
守護霊って言葉、聞いたことがあるでしょ?
私達を護ってくれたり、インスピレーションを与えてくれて導いてくれたりもするわ。
だから、霊だからって一概に怖がったり気持ち悪がったりしてはダメよ。
見えたり音が聞えたりするということは精神的にコネクトしている状態なの。
大事なことは絶対に気持ちが弱くなったり逃げようとしたりしないこと。
あらっ、余計に不安にさせちゃったかしら?」
「い、いえ。大丈夫です。」
「そう。良かったわ。」
礼子は部屋に入ると何かを唱えながら部屋の上下左右と隅々まで見て回った。
私達は固唾を呑んでそれを見守っていた。
やがて礼子が私の方を向くとおもむろに訊いた。
「問題の部屋はこっちかしら?」
そう言うと、ズバリと隣の部屋を指さした。
「えぇ。やっぱり何かいるん・・・ですか?」
私の不安は益々高まっていった。
「まだ判りません。一度外に出て玄関を見てみましょう。」
一同は連れだって隣の部屋の玄関前に集まった。
「郵便受けから中を覗けそう。」
好奇心旺盛な有希子が言った。
「その必要はないわ。」
静かに断じるように礼子は言った。
「大丈夫よ。<ここ>には人に危害を加えるようなモノはいないわ。
安心して良いわよ。それに・・・」
礼子はそう言いかけて目を瞑ると隣の部屋にジッと神経を集中させているように見えた。
やがて、フッとひとつ安堵のようなため息をつくと私の方を向いて言った。
「大丈夫。準備が終わったみたいだから今夜からは当面、音は聞えないと思うわ。」
「えっ? いつの間にか除霊したんですか?」
私は恐る恐る訊いてみた。
「除霊? うふふ、まさか。言ったでしょ?
ここには人に危害を加えるようなモノはいないって。」
礼子は微笑みながら答えた。
「でも・・・それじゃ、どういう?」
「そうね。世の中には災いを運ぶモノもあれば幸いを運ぶモノもいるってことかな。」
「えー? 全然、判りません。」
「良いのよ、今はそれで。」
礼子はそう言うと私と和樹の顔をマジマジと見比べて、そして笑顔で言った。
「あなた達、面白いわね。きっと・・・ううん、なんでもないわ。
さっ、有希子。帰りましょ。 メリークリスマス!」
そう言って手を振ると高階礼子は有希子とアパートの階段を降りて帰って行った。
その場に残された私と和樹はポカンとして互いの顔を見合っていた。
結局、隣の住人の正体は分からなかったけど、ひとつだけ判ったことがあった。
頼りないと思っていた和樹が意外にも頼りがいがある奴だったってこと。
そしてクリスマスイブの夜。
玄関のチャイムが鳴ってドアを開けると、そこには満面の笑みを浮かべた和樹が立っていた。
「メリークリスマス! 先輩、お招きにあずかりありがとうございました!。
ケーキを買って来ました。シャンパンは身分不相応なのでシードルで勘弁して下さい。」
それは今日の昼のことだった。
例によって大学の学食でA定食を食べながら和樹は言った。
「あーぁ、クリスマスくらいはA定食じゃくて唐揚げ定食にしとけば良かったかな。」
「そんなことをしたら学食のオバサンが仰天して卒倒しちゃうわ。
『あれま、あの子ったら初めてA定食以外を頼んだわ、どうしましょ!?』なんてね。」
「んな訳ないじゃないですか。それに僕だっていつもA定食ばかりじゃないですよ。」
ちょっと口を尖らせて和樹が言った。
「じゃ、昨日は何を食べた?」
「昨日はたまたま・・・A定食でした。」
「じゃ、一昨日は?」
「A定食だけど・・・でも、あれは先輩に付き合ってですよ。」
「へぇ-、私頼んだっけ?
『あー、やっぱ昼はA定食ですよね』ってA定食のトレイを持ちながら言ったのは誰?」
「もう、良いですよ。はいはい、僕はA定食野郎ですよ、どうせ。」
和樹はちょっと拗ねて横を向いてA定食のメンチカツをがっつき始めた。
それを見て、さすがに私もちょっと意地悪過ぎたかなと思った。
「ねぇ、今夜もバイト?」
「ですけど、何か?」
和樹はまだむくれているようだ。
「何時に終わるの? 早く上がれるんだったら家に来ない?
まだ、この前のお礼もしてないし。何かご馳走するわ。」
それを聞いた途端に和樹の態度が一変した。
「ホントですか? じゃ、今日はバイト休んじゃおうかなぁ-」
「ダメよ。バイトだって責任あるでしょ? 早く上がれたらで良いわよ。」
「上がります! 絶対! 何をおいても! 必ず行きます!」
和樹は立ち上がると高揚してかかなり前のめりで答えた。
「和樹、みんな見てる。」
私は和樹を宥めるように席に座らせた。
周りの人達がこっちを見てクスクス笑っているのが判って私は赤面をした。
「でも、あんまり期待はしないでよ。」
「大丈夫です。僕、お腹だけは丈夫なんで。」
今度は私がむくれる番だ。
「あのねぇ-、やっぱ呼ぶの止めようかな。」
「いや、それは、ちょっと。ま、待って下さい! 行きます、行かせて下さい!」
和樹が本気で慌てふためいているのが可笑しかった。
「ちょっと、先輩! 何を笑ってるんですか? いやだなぁ-、もう。」
「お疲れさま。取りあえず、そこに座ってて。今、用意するから。」
「はい! いつまでも待ってます。」
「いつまでもってね。」
私が苦笑するのも構わず
和樹はテーブルの前に座ると持って来たケーキをかざして言った。
「ケーキ、ここで良いですか?」
「そうね。お願い。」
「らじゃ!」
私は作っていた唐揚げを大皿に山のように載せるとテーブルに運んだ。
「まずは、これね。」
「おー、唐揚げだ! やったね、今日の昼は食べなくて良かったです。」
「だから作ったのよ。
本当ならローストビーフとか、もっと手の込んだのを作りたかったんだけどな。」
「えっ? 先輩、ローストビーフなんか作れるんですか?」
目を輝かせて和樹が言った。
「いや、まぁ-。その気になればね。」
本当はローストビーフなんか作ったことはない。
でも、クリスマスイブの女子のちょっとした見栄も今日くらいは神様もサンタさんも許してくれるだろう。
「いやぁ、先輩。さすが女子力高いですね!」
テンションが高めの和樹に思わず苦笑した。
それからパスタとサラダ。それから帰りにスーパーで買ったサーモンのマリネを並べた。
食事の後片付けも終えてコーヒーを飲みながら今年あった色々なことを時間を忘れて話していた。
時間はもうすぐ十二時になろうとしていた。
その時、和樹がふと呟いた。
「結局、あの音って何だったんでしょうね?」
「そうね。結局判らないままだったわね。」
「ですねぇー」
ちょっと間を空けて和樹は言った。
「色々考えてたんですけどね。高階礼子さんの言葉とか。」
「あぁ、『ここには人に危害を加えるようなモノはいない』って言ってたこと?」
「えぇ。それからこうも言ってましたよね。
『世の中には災いを運ぶモノもあれば幸いを運ぶモノもいるってこと』
アレってどういうことなのかなって。」
「うん。それで?」
「でも、危害を加えるモノはいないんだから、それは災いを運ぶものじゃないですよね?」
「そう・・・かな?」
「ってことは、幸いを運ぶモノはいるって意味じゃないかと思ったんです。」
「なるほど。で?」
「例えばですけどね。」
「うん。」
「隣の部屋のドアって、もしかして違う世界に通じているのかなとかね。」
「違う世界って?」
「そう、例えばサンタクロースの世界。
丁度十二月じゃないですか。色々と子供達の欲しいものとか調査をしてたんじゃないですかね。」
「えー? ファンタジーだわ! 和樹って案外ロマンチストなのね?」
私は可笑しくて笑いながら和樹を見たが和樹はけっこう真剣な顔をしていた。
「えぇ。男はロマンチストなんですよ。でね。
音がしなくなったのは二十日でしたよね。クリスマスを控えて、きっと調査が終わったんですよ。
高階さんも言っていたじゃないですか? 準備が終わったみたいな。」
「うん・・・まぁ。」
私の反応に和樹は意外だという顔をした。
「あれ? 先輩、もしかして突拍子も無い話だと思ってます?」
「思うよ、普通。」
「先輩。先輩には夢がないんですか?」
「えー? 話がそこに行く?」
そんなだめ出しをされてもなぁーと思ったが、取りあえず黙って和樹の説を拝聴することにした。
「ダメですよ。いつまでも夢は持ってなきゃ。
あー、先輩ってもしかして、子供の時もサンタさんを信じてなかったでしょ?」
「そんなことないわよ。」
「僕、実は今でもサンタさんって本当にいるんじゃないかって信じてるんです。」
「えー? 真面目に言ってるの?」
「もちろんです!」
和樹は真顔で答えた。そして言った。
「じゃ、賭けましょうか?」
「何を?」
「僕が勝ったら、先輩は僕の言うことは何でも聞くこと。
今夜はクリスマスイブです。きっと今夜は久しぶりに例の音が聞えるはずです。」
「じゃ、音がしなかったら私の勝ち? その時はどうするの?」
「その時は僕が先輩の言うことを何でも聞きます。」
「へぇー、何でも?」
「えぇ、何でもです。」
「判った。良いわよ。」
和樹は壁の時計を指さして言った。
「僕の説が正しければ・・・ほら、もう十二時を回りました。
もうすぐ音がするはずです。サンタクロースがプレゼントを持って出発する頃ですから。」
和樹が言ったが先か、隣の部屋からドアを開ける音が聞えた。
「えっ!?」
二人同時に声を上げて一斉にドアの方を見た。
その瞬間、和樹は立ち上がるとドアに向かって走り出そうとした。
「待って! 和樹、もう良いよ。」
「でも・・・」
立ち上がったまま和樹はこっちを見た。それでもやっぱり外が気になっているようだ。
「確かめなくて良いんですか?」
「和樹の言う通りかもね。今夜はクリスマスだものサンタさんの邪魔はよしておきましょ。
これで和樹の勝ちね。私は何をしたら良い? 何でも良いわよ。約束だから。」
「ホントに良いんですね?」
「えぇ。」
「何でも?」
いつもの和樹らしくなく真剣な眼差しで和樹は訊き直した。
「えー? 何? 何か怖いんだけど。やっぱ、止めようかな?」
「いや、もうダメです。男の約束ですから。」
「私・・・一応、女なんだけど。」
「それは判ってます。」
今の和樹には冗談も通じない雰囲気だった。
「まぁ・・・判ってるなら、それで・・・」
私はそう言うしかなかった。そして、改めて訊き直した。
「で、何?」
和樹はテーブルの前に座り直すとひとつ咳払いをしてから私に向かって言った。
「先輩、好きです。僕と付き合ってください!」
和樹はそう言って目を瞑ると私の前に勢いよく両手を差し出した。
一秒だけ勿体を付けて、それから私はもちろん、和樹の手を取った。
「ねぇ? これってサンタさんから私へのクリスマスプレゼントなのかな?」
私は並んで座っている和樹の肩に頭をもたせかけながら訊いた。
「違いますよ。これは僕へのプレゼントですよ。」
和樹は当然と言う風に即答をした。
私はもたせかけていた顔を上げて、そして和樹の目を見ると言った。
「あら、私へのプレゼントよ。」
「いや、僕へのです。」
断固として和樹は言った。
「じゃ、私へのプレゼントは?」
私が訊くと和樹はそっと私に顔を近づけて、そして優しくキスをした。