
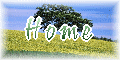
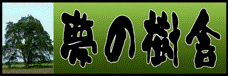
クリスマスなんて大っ嫌い!
楽しみにしているプレゼントや大好きなケーキ。
子供達はクリスマスが大好きですが
でも、中にはそうじゃない子供もいるようです。
何故かって?
それは、この日は親が一年で一番忙しくて
ちっとも相手をしてくれないからです。
例えば、こんな子とか・・・
ノエルが学校から帰ると
リビングのテーブルの上にもみの木の枝で編んだリースと
クリスマスカードを添えて
キレイな色の包装紙に包まれた大きな箱が置いてありました。
「ヤッター! プレゼントだぁー!」
目を輝かせてノエルはもう待ちきれないとばかりに
急いで破るように包装紙を解くと箱の蓋を開けました。
「まぁ!」
先ず箱の中から取りだしたのは
白いファーで縁取りがされた真っ赤なベルベット生地のケープでした。
襟元には先っぽに白いファーの玉が付いた緑色のリボンタイが付いています。
「キレイ!」
ノエルは胸の前で両手を組むと感嘆の声を上げました。
次に取り出したのは
太めの毛糸で編まれた暖かそうな
これまた真っ赤のタートルネックのセーターでした。
それはお母さんがいつも着ているセーターに似ていました。
ノエルは嬉しくてそのセーターをギュッと握り締めました。
それから縁に白いフリンジの入った赤い毛糸のマフラー。
そして赤いブーツと赤い毛糸の帽子が入っていました。
ノエルが暮らす街では女の子が七歳になったクリスマスイブの夜に
もみの木で編んだリースと赤い服を贈る風習がありました。
そしてクリスマスの日はその赤い服を着て教会に行って洗礼を受けます。
女の子にとって7歳のクリスマスは
女の子からレディの仲間入りが出来る晴れの日だったのです。
ノエルは喜びいさんで赤い服に着替えました。
そしてお母さんの部屋の大鏡の前に立つと
確かめるように二度、三度とクルッと回ってみました。
そして大きく頷きました。
「うん!」
ノエルは大好きなお父さんに
真っ先にその姿を見せようと小走りで仕事場に入っていきました。
「ねぇ。お父さん、見て・・・」
「あー。ごめん、ノエル。今ちょっと忙しくて手が離せないんだ」
「でも・・・」
「あぁ、ごめんよ。用事ならお母さんに頼んでごらん」
お父さんはノエルの赤い服に気が付いていないようです。
ガッカリしたノエルはお母さんのいる台所にいきました。
台所でお母さんを見つけるとノエルは後ろからお母さんに抱きつきました。
「お母さん」
驚いたお母さんが振り返ると、そこにはノエルの満面の笑顔がありました。
「ねぇねぇ、お母さん! どう? 似合う?」
「あらっ、ノエル。もう着替えちゃったの?
それは明日着るのよ。さぁさ、汚す前にちゃんと着替えておいで」
「お母さーん」
ノエルは不満そうです。
「なぁに?」
「もういい・・・」
ノエルはお母さんに赤い服が似合うと言って欲しかったのです。
でも、お父さんもお母さんもそうとは気が付きませんでした。
この家にとって今日はそれほど忙しい日だったのですが
七歳の子供にそんな事は判るはずもありません。
「あっ、そうそう!
ねぇ、トラックのおやつをおやつ袋に入れておいてくれる?
あの子ったら、最近はお腹が減ると言う事を聞かないで動かなくなっちゃうのよね。
ノエル。頼んだわよ。おやつは納屋の入り口の棚の所にあるからね」
「もう知らない! クリスマスなんて大っ嫌い!」
ノエルは目から大粒の涙をいっぱい流しながら台所を飛び出しました。
「ノエル! ねぇ、ノエル!」
翔太の家はケーキ屋さんです。
クリスマスの時期は一年の内でも一番忙しい時期です。
今日はクリスマスイブ。
翔太の学校も今日で二学期が終わりです。
一学期の通信簿はほとんど二重丸でしたが三つだけ丸がありました。
その時、大きな手で翔太の頭を撫でながらお父さんは言ったのです。
「翔太。頑張ったな。でも、もう少しで満点だったね」
それから翔太は苦手な科目も一生懸命に頑張りました。
そして二学期の通信簿は全部二重丸になりました。
「ヤッター! これでお父さんに喜んで貰えるぞ!」
意気揚々と翔太は家に帰るとお父さんの仕事場に一目散で駆け入りました。
「お父さん! 見て、見て!」
「うん? おう、お帰り。そんなに慌ててどうした?」
お父さんは翔太の方をチラッと見ただけで作業を続けながら訊きました。
「これ! 見て、全部二重丸だよ!」
翔太は目を輝かせてお父さんの前に通信簿を差し出しました。
「ほう、そうか。凄いな」
お父さんは中も見ないでそう応えました。
「もう! ねぇ、見てよ、これ。僕、頑張ったんだよ!」
「あぁ、分かった。後で見ておくから、
そこのテーブルの所に置いておいてくれないか?」
そう言うと又、お父さんは忙しそうにケーキ作りを続けました。
「良いよ、もう知らない!」
翔太がそう言い放って仕事場を飛び出したのにも
お父さんは気が付いていなかったようです。
翔太はお母さんのいるお店に向かいました。
「ねぇ、お母さん・・・」
お店に入りかけて翔太は足を止めました。
お店ではお母さんも忙しそうに次々と入って来るお客さんの応対をしています。
その様子を見ている内に何でか、翔太の目には大粒の涙が溢れてきました。
翔太は家の方には戻らずに、お店の入り口を目がけて走り出しました。
「あら、翔太。何処に行くの? 翔太!」
翔太の背中越しにお母さんの呼ぶ声が聞えました。
ノエルは雪のしんしんと降る中を当てもなく歩いていました。
通りかかる人にはまるでノエルは見えていないかのように
真っ赤なケープに雪を積もらせて
トボトボ歩いているノエルに声を掛ける人は誰もいませんでした。
「お腹が空いたわ。寒い・・・」
真っ赤な手袋をこすり合わせながらノエルは呟きました。
やがて、甘い匂いに誘われるようにノエルは一件のケーキ屋の前に来ました。
クリスマスの飾りとポップがいっぱい貼られた店の硝子越しに中を覗くと
たくさんの買い物客が溢れかえっていました。
どうやらこの辺でもかなり評判のケーキ屋のようです。
その店の前に立って中を覗いていると
急にドアが開いて男の子が外に飛び出して来ました。
「キャッ!」
ビックリしたノエルは雪の歩道の上に尻もちをつきました。
「あっ、ごめん。大丈夫?」
翔太は立ち止まってノエルに声を掛けました。
「翔太!」
店の中からはお母さんの呼ぶ声がしました。
「行こう!」
そう言うと翔太はとっさにノエルの手を取ると雪の中を走り出しました。
「はぁはぁ、私もうダメ・・・走れない・・・」
どれくらい走ったでしょう。
ノエルの声にふと我に返ると翔太には見覚えのない街並みの通りに出ていました。
何かの時にテレビででも観た、そうまるで外国の街並みのようにも見えました。
「ここは何処だろう?」
辺りを見渡しながら翔太は呟きました。
「はぁはぁ・・・」
雪の上にへたり込むように座っているノエルに気が付くと翔太は優しく声を掛けました。
「ごめん。何か、巻き込んじゃったね。お父さんもお母さんも心配してるよね?」
「ううん。心配なんかしてないわ。
お父さんもお母さんも仕事の事で頭がいっぱいなの。
私の事なんかどうでもいいんだわ」
「そっか・・・うちの一緒さ。僕の事なんかどうでもいいんだ・・・」
翔太はノエルの隣に腰を下ろしました。
雪はいつ止むとも知れずに降りしきっています。
「寒いね。何処か雪の当たらない所を探そう」
雪の落ちてくる空を見上げながら翔太は言いました。
「うん」
ノエルは笑顔で答えました。
でも、ノエルが寒さに凍えそうになっているのは翔太の目にも明らかでした。
「急がなきゃ」
それから二人は手を繋いで又、歩き出しました。
しばらく歩くとドアが少し開きかけた家が見えました。
「誰かいますか?」
そう良いながら翔太は恐る恐るそのドアをゆっくり開けました。
中を覗き込んでも誰もいませんでした。
「取りあえず中に入れてもらおう」
「うん・・・でも、大丈夫?」
「家の人が戻ってきたら訳を話せば大丈夫だよ、きっと」
「ホント?」
「うん・・・きっとね」
翔太は内心自信なさげでしたが、今はそんな心配をしている場合ではありません。
開き掛けたドアのせいで入り口付近には少し雪が吹き込んではいましたが
中には大きなカーペットが敷いてあって、少なくとも外よりははるかに暖かそうです。
二人は入り口で頭や肩に積もった雪を払い落とすとカーペットに並んで座りました。
「そうだ。まだ名前も言ってなかったよね? 僕、翔太。君は?」
「私はノエル」
「ノエルか。可愛い名前だね? 外国の人?」
「外国? 分からない・・・」
「ノエル、学校は? この近く?」
「分からない・・・たぶん、ずっと遠い所かも」
「そうなんだ。やっぱり外国の人なんだね?
そう言えば、外国の人ってクリスマスのお休みがたくさん有るって聞いた事があるよ。
でもさ。そしたら余計にお父さんやお母さんが心配してるんじゃない?
一緒に来てるんでしょ? もしかして迷子・・・かな?」
「迷子じゃない・・・家を飛び出してきたの」
「えー? そうなの? 実は僕もさ!」
「私、クリスマスなんて大っ嫌い」
ノエルは目にいっぱい涙を溜ながら言いました。
「僕もさ。大っ嫌いだ!」
翔太は拳を強く握り締めながらそう答えました。
その手は震えているようにも見えました。
それから翔太は気持ちを落ち着けるとノエルに話しかけました。
いくら家の中とは言っても暖房も入ってはいません。
じっとしていると、それだけで凍えてしまいそうでした。
「ねぇ、お父さんは何をやっている人なの?」
「お父さん? 荷物を届けているわ」
「トラックの運転手とか?」
「うんてんしゅ? うーん、良く判らない。
でも、トラックはいるわ。相棒だって言ってた」
「やっぱりトラックの運転手なんだね。そっか、かっこいいな」
「良くない。今日は一年で一番忙しいんだって。遊んでもくれないのよ」
「仕事なら仕方ないよ」
「でも・・・」
「うちもそうさ。一年で一番忙しいんだって。なんか似てるね」
「翔太クンも構ってもらえなかったの?」
「よせやい。構って欲しい歳でもないよ。
たださ、勉強を頑張って今まで一番良い通信簿だったのに
お父さんなんか見てもくれなかった。あんなに頑張ったのに・・・」
「そうなんだ・・・なんか似てるね。
でも、翔太クンの家ってあのケーキ屋さんでしょ?
なら、仕方ないよ」
「そんなのは分かってるよ」
翔太は少しムッとして答えました。
「でもさ、少しくらいは子供の事にも気を遣えよってね」
「そうだ、そうだ!」
ノエルも右手を突き上げて同意しました。
「大人はすぐ仕事、仕事ってさ。子供には関係ないよ」
我が意を得たりという感じで翔太の意気はますます盛んになりました。
「そうだ、そうだ! 大賛成ー!」
ノエルも嬉しそうにもう一度大きく右手を振り上げました。
話が解り合える相手が居て気持ちも高まったからでしょうか。
それとも大きな声を出したからでしょうか。
少しだけ身体も温まってきた気がしました。
「でも、なんか可笑しいね、なんか不思議」
翔太はノエルの顔を改めて見ると笑いながら言いました。
「不思議?」
ノエルは翔太の顔を見てそう訊き返しました。
「だって、さっき初めて会ったのに今はこうして同志みたいになってる」
「どうし? <どうし>って?」
「うーん、仲間とかさ。大事な人っていうか・・・そんな感じ」
「ふーん、<どうし>なんだ。なんか嬉しい言葉だね」
その時突然、ドアが開くと大きな男の人が入ってきました。
翔太には薄暗くて良く見えませんでしたが
雪明かりに照らされたその男の人の格好は何処かで見た事があるような赤い服でした。
「ノエル! なんだ、ここに居たのかい? ずいぶん心配したよ。
寒かったろう? さぁ、家に帰ろう。お母さんも心配をして待っているよ」
ノエルは少し拗ねるように訊きました。
「もう、お仕事は終わったの?」
その男の人は優しく微笑みかけながら答えました。
どうやらノエルのお父さんのようです。
「あぁ、大丈夫だよ。残りはおじいちゃんがやってくれるってさ」
そう言うとお父さんはウインクをして、それからノエルをギュッと抱き締めました。
それから翔太の方を向くと言いました。
「君は?」
ノエルが代わりに答えました。
「翔太君よ。私達、<どうし>なの」
お父さんは怪訝そうに訊きました。
「<どうし>?」
「そうよ。ねぇ-? 私達、大切な仲間なの。」
ノエルは嬉しそうに答えました。
「なるほど。その同志ね? 翔太クン、娘を守ってくれてありがとう」
ノエルのお父さんは翔太の冷たくなっていた手を握ると丁寧にお礼を言いました。
「おや、手も冷たくなってるね? それじゃ急いで家に帰ろう。
そうだ! はい、これ。勇敢な同志クンにオジサンからプレゼントだよ」
ノエルのお父さんは何処から出したのか?
キレイに包装された大きな箱を翔太に手渡しました。
「じゃ、君も一緒に送って行くよ。君の家は分かってる」
夜の九時も過ぎて、やっとお店を閉めると、
奥の作業場からお父さんが店に入って来ました。
「やれやれ、やっと終わったね。あー、疲れたー!」
お父さんは大きな伸びをしながら言いました。
「そうね。お疲れ様でした。
私、まだ少し片付けがあるから先に居間に戻っていてくれる?
すぐにご飯にするけど、ひとまずコーヒーでも入れておいてくれると嬉しいな」
「はいよ、了解!
そういや、居間の電気が消えているようだけどけど翔太はもう寝たのかい?」
「あらっ、そう言えば・・・。ねぇ、ちょっと見てきてくれる?」
お母さんはお父さんの言葉に胸騒ぎがしました。
怒られた時とか、お母さんとケンカになった時とか
翔太が店を飛び出すのはしょっちゅうでした。
そんな時でも、翔太が裏口の家の玄関からこっそり戻って
自分の部屋でよくふて寝をしていたのです。
なので、さっき店を飛び出した時も、
忙しかったのもあって追いかけませんでした。
お母さんも気になって、お父さんの後を追うように居間に戻りました。
「ねぇ?」
「しー」
お母さんが翔太の部屋を覗いているお父さんに声を掛けると
お父さんは口の前で『静かに』と合図を送ると部屋の中を指さしました。
お母さんが中を見ると翔太は布団でスヤスヤと寝ていました。
「そっか、そんな事があったのか」
ご飯を食べながら、
お父さんはお母さんから翔太が店を飛び出した話を聞いていました。
「そうなの。でも、私が忙しかったから構えないでいたらね」
「俺も忙しくて翔太の話をろくに聞いてやれなかったからなぁー
悪いことをしたな。そういや、通信簿がどうとか言ってたな」
「これでしょ? そこに投げてあった」
お母さんは苦笑いをしながら、お父さんに手渡しました。
お父さんは翔太の通信簿を受け取ると中を見ながら言いました。
「ほぉ、頑張ったじゃないか。全部二重丸になってる。
そっか、これを翔太は言ってたんだな」
昼間の事を思い出してお父さんは困ったなという風で頭を掻きました。
「まぁ、今夜はしょうがないわよ。翔太もきっと分かってくれてると思うけど」
「だと、良いけどな」
「大丈夫よ。あたなの息子だもん。明日になったらすっかり忘れているわよ」
「おいおい、それってどういう意味だよ!」
お父さんは口を尖らせましたがお母さんは我関せずとご飯を口にしました。
お父さんはしみじみと話を続けました。
「俺はオヤジの作ったケーキが大好きだったけどクリスマスだけは嫌いだったな。
クリスマスの一週間くらい前からずっと放ったらかしにされていてさ。
遊んでもらうどころか全然構ってももらえなかった。
だから、翔太の気持ちも良く判るよ。
いつだったかな。
オヤジが亡くなった後で母さんに聞いたんだけど
オヤジは新しいケーキを作ると真っ先に俺に食べさせてくれていたんだ。
そして俺が美味しいと言ったケーキだけを店に並べていなんだって。
バカなオヤジだよな。
こんな子供の言葉だけで店に出す出さないを決めていたなんてさ」
「あら、初めて聞いたわ。良い話ね」
お母さんはニッコリと笑いました。
お父さんとお母さんがもう一度翔太の部屋を覗くと
ベッドでは相変わらず翔太がスヤスヤと寝息を立てていました。
よく見るとベッドの枕元には大きな包みのプレゼントが置いてありました。
「あら、あんな大きなプレゼント。お父さんが用意をしてくれていたの?」
「えっ? 知らないよ。お前が置いたんじゃないのか?」
「ううん。知らないわ。
第一これは近所のおもちゃ屋やデパートの包装紙じゃないし」
「えっ? そしたら誰が?」
お父さんとお母さんは顔を見合わせました。
お母さんはお父さんが買っておいてくれたと思っていました。
照れ屋のお父さんです。
子供のプレゼントを買ったなんて
恥ずかしく言いそうにもないと思っていたのです。
お父さんはお母さんが買ってくれていたんだと思っていました。
忙しくてお父さんが何もかまってやれない事をいつも心苦しく思っていると
ちゃんと理解をしてくれている優しいお母さんです。
お父さんに花を持たせてくれているんだとお父さんは思っていたのです。
そんな事があってから十何年かが経ちました。
翔太はヘルシンキの空港に降り立つと何本か列車を乗り換えて
とある小さな街にやって来ました。
「なぁ、翔太。卒業をしたらどうするんだ?
オヤジさんの店を継ぐのかい?」
「いや、それはまだないよ。
いつかは一緒にやらせてもらいたいとは思ってるけどね。
俺さ、留学をしようと思ってるんだ」
翔太は高校を卒業するとパテシェの専門学校に進みました。
卒業を来春に控えた或る日、
近くのカフェでお茶を飲みながら友人が翔太に訊きました。
「留学? そっか、お前の腕なら何処でもやっていけるよな。
で、やっぱりフランスとかイタリアかい?」
「いや、フィンランドに行こうと思ってる」
翔太は答えました。
「フィンランド? フィンランドのお菓子とかケーキって習ったっけ?」
「いや、前に雑誌で見たんだ。
濃厚なチョコレートケーキとか、けっこう色々あるらしいよ。
そうそう、フィンランドのクリスマスでは、
ヨウルトルットゥという星形のパイを食べるんだって。
パイ生地に切り込みを入れて、真ん中にプラムなどのジャムを乗せて焼いて
出来上がったら粉砂糖をふりかけるというシンプルなものなんだけどね。
なんかさ、そういうのって良くない?
シンプルだけど、奥が深いみたいなさ。
そういうのって、きっとそこの空気とか風土とかさ。
何か有るじゃん。そんなのが知りたいんだよね」
「ふぅーん。お前らしいというか、何というか・・・だね。
まぁ、フランスとかイタリアってみんな行ってるし、
超有名なパティシエとかいっぱいいるもんな。
フィンランドってけっこう穴場かもな」
「まぁ、それだけじゃないけどね」
「何だよ? 他に何かあるのかい?」
「いや、具体的にって訳じゃないけど。何か行くならそこかなってさ」
フィンランド、クリスマス、サンタクロース。
いつからか翔太にとっては三点セットみたいな感じのそんな想いがあって
それが歳を経るごとにますます強くなっていましたが
そんな子供じみた事は恥ずかしくって友人にも言えなくて
何となく言葉を濁したのでした。
「ふぅーん。やっぱ、お前らしいわ」
「何だよ、お前らしいって」
そんなやり取りを思い出しながら翔太は
フィンランドの北にある小さな街を地図を頼りに歩き始めました。
「フィンランド?」
「えぇ、フィンランドです。何処か伝手のある店はありませんか?
そんな有名店じゃなくて良いんです。
出来れば昔ながらのお菓子とかケーキを作っているような」
「うーん、どうだろ? 誰かいたかな? ちょっと訊いてみよう」
「ありがとうございます!」
「それにしても君は変わってね。みんなフランスとかイタリアに行きたがるのに」
専門学校の講師にそんな相談をしていたのですが
それから二週間くらい経った或る日、翔太は講師室に呼ばれました。
「先生、決まったんですか?」
講師室のドアを開けるなり翔太は声を上げました。
「まぁまぁ、そんな慌てないで」
講師は苦笑しました。
「まぁ、そこに掛けたまえ」
講師は翔太をソファに促すと言いました。
「苦労したよ」
「すみません」
翔太は神妙な面持ちで深々と頭を下げました。
「伝手と言っても、伝手の伝手の伝手みたいな感じでね。
君の希望に合うかどうかは私にも分からないんだ」
「かまいません。どんな店ですか?」
「うん。フィンランドの北の方にある小さな街でね。
ほら、サンタクロースの故郷みたいに言われているらしいんだが
果たして、それが本当なのか・・・」
「良いです、良いです! ぜひ、お願いします!」
翔太は目を輝かせてお礼を言うと立ち上がって又、大きく頭を下げました。
「取りあえず、古い店でね。伝統菓子とかあるらしい。
だが、新しい事を吸収出来るかどうか・・・
けっこう、オヤジさんが頑固者らしくてね」
「かえって、ありがたいです」
「そうか、君は変わってるね」
「いやぁ・・・」
翔太は照れながら頭を掻きました。
「さぁ、ここが今日から俺の住む街だ! よーし、頑張るぞー!」
翔太は気合いを入れ直すと又、地図を見ながら街を歩き出しました。
その街は古い街並みでしたが、とてもキレイな印象でした。
そして、初めての街のはずなのに
何故か翔太には何処か懐かしい感じがしていました。
「この景色、何処かで見た事が・・・
テレビ? 雑誌かな? まぁ、気のせいかもな」
気を取り直して、それから十分ほど歩くと一件のケーキ屋がありました。
「ここ・・・かな?」
地図を見直しながら翔太は呟きました。
店の外から中を覗くと、店の中には五~六人のお客さんがいて
恰幅の良さそうな女将さんらしき女性が
あっちにこっちに動きながらお客さんの相手をしていました。
翔太は意を決して店のドアを開けました。
「ヒュヴァーパイヴァー(こんにちは)」
翔太が片言のフィンランド語で話しかけると、
女将さんは手を止めて翔太の前に歩み寄りました。
そして、翔太の手を取ると笑顔で言いました。
「パイヴァー。あぁ、ショータかい?」
「はい、翔太です。今日からお世話になります!」
翔太が改めて挨拶をしようとするのを遮って言いました。
「良いよ良いよ。うちはそんな堅苦しい店じゃないんだ。
亭主は堅苦しい頑固者だけどね」
そういうと、女将さんは豪快に笑いました。
「ヤパニ(日本)からだったね。さぁさ、長旅で疲れただろ?
ここは遠いし寒かっただろうからね。
先ずはこっちに来て一休みしておくれ。後でみんなに紹介するから」
そう言って翔太を手招きし
それから、店の奥に向かって大きく声を掛けました。
「ノエル! ショータが着いたよ。部屋に案内しておくれ」
「はーい、今、行くわ」
店の奥の二階から明るい女性の声が返ってきました。
弾むようなリズムで階段を駆け下りてくる足音と共に。